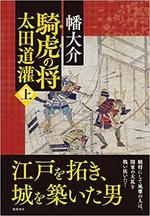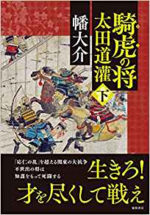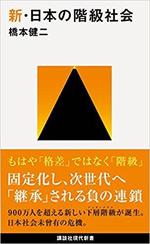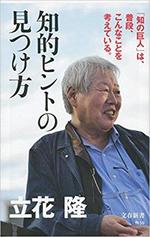 「文藝春秋」の2014年8月号以降の巻頭随筆と、その他の特集記事「最先端技術と10年後の『日本』」「ノーベル賞興国論」の2本。ずっと立花隆さんの本を読んできたが、正確さ、緻密さ、深さ、加えて真摯さや境地を感じさせるものとしてスッと心に入ってくる。日本人を励ましてくれているかのようだ。
「文藝春秋」の2014年8月号以降の巻頭随筆と、その他の特集記事「最先端技術と10年後の『日本』」「ノーベル賞興国論」の2本。ずっと立花隆さんの本を読んできたが、正確さ、緻密さ、深さ、加えて真摯さや境地を感じさせるものとしてスッと心に入ってくる。日本人を励ましてくれているかのようだ。
「日本が抱える最大の弱点とは何か。3つに要約できる。人口減、高齢化、そして夢のない社会。いいかえれば日本が"悲観社会"になっていることだ」といい、「乗り越えることができる」と具体的に例示。「この世の中は、悲観論者は自分の予測通り失敗して没落し、楽観論者は自分の予測通り成功していくものです。楽観主義でいきましょう」と結んでいる。
その時々の発言は、行動して探り深めた「知」に満ちている。「生と死に学ぶ」「歴史と語らう」「科学を究める」「戦争から考える」「政治と対峙する」「未来を描く」にまとめられているが、政治の情なさと科学技術の探求・進展への指摘は際立っている。
室町時代後期の武将、武蔵守護代・扇谷上杉家の家宰である太田道灌(1432年~1486年)。江戸城を築き、山吹伝説など歌人として名高いが、応仁の乱等の混乱のなかでの15世紀後半、動乱の続く関東での武将の姿が描かれる。
関東公方・足利持氏と確執していた6代将軍・足利義教は、関東管領方の上杉一門を支援し、持氏を討つ。関東管領上杉氏は山内上杉家・犬懸上杉家・宅間上杉家・扇谷上杉家に分かれていたが、上杉禅秀の乱で犬懸家が没落、山内家とそれを支える扇谷家の両上杉家が関東管領職を担う。太田道灌は扇谷上杉家の家宰となって動乱を戦い抜くことになる。持氏が討たれた後、関東の諸家が分裂するが、次第に持氏の遺児足利成氏が「古河公方」を立て、利根川をはさんで「古河公方陣営vs山内・扇谷の両上杉家を中心とする管領方陣営」が断続的に戦闘を続ける。
太田道灌はドライな徹底したリアリストの幼少期から次第に幅広い軍略家として成長するとともに、利根川の河口(江戸)の要衝地を押さえる江戸城を築き、物流拠点として浅草と品川を押える。荘園の警備役であった武士が、所領と戦さに欠かせない米を押さえることによって確立されていく先駆役でもあった。めまぐるしい戦乱を知謀をもってくぐり抜けた道灌は謀殺されるが、本書の最後に伊勢新九郎(北条早雲)が登場し、時代は16世紀、戦国時代、武士の時代を迎えることになる。"騎虎の将"と呼ばれた太田道灌の戦いの地は、まさに今の首都圏。今の地名の根源を知るのも興味深い。
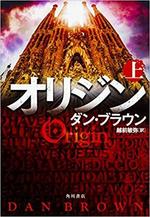
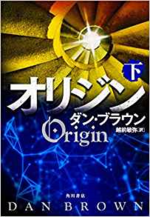
あの「ダ・ヴィンチ・コード」のダン・ブラウンのラングドン・シリーズ第5作。スケールが大きく、時空を深く掘り下げていく緊迫の書。一気に終章まで誘う。
「われわれはどこから来たのか」「われわれはどこに行くのか」――。人類の根源に迫る問いかけ。宗教象徴学者ロバート・ラングドンの教え子のエドモンド・カーシュが、それを解き明かす衝撃的な発表をするという。2億人を超える世界の人がインターネットで注目するなか、カーシュは凶弾に倒れる。しかし、カーシュはその前に、宗教各派の中心者3名にその中身を知らしていた。
宗教を根底から覆す恐怖に襲われたのではないか。人類の未来はAIと結びついた"新たな人間"に支配される恐るべき社会になるのではないか。きわめて根源的な問いかけは緊迫と恐怖をもたらす。カーシュの発表する内容の謎。暗殺者の謎。宗教界やスペイン王宮の深淵・・・・・・。欧米における神や教会と異端、そして王宮の存在が日本とは画然と差異があることをまざまざと見せつける。
ラングドンと美術館館長でフリアン・スペイン国王太子の婚約者アンブラ・ビダルは逃亡しながら謎の解明に走る。そこに登場する人工知能ウィンストン。AIの未来と人間、科学と宗教、進化論と神・・・・・・。対立か共存か。はたして"暗き宗教は息絶え、かぐわしき科学が治する"のか。AIの急進展のなかで根源的問題を突きつける。テンポのいい越前氏の訳も秀逸。
日本が「格差社会」から「新しい階級社会」になったことを、社会学者の研究グループが10年ごとに行う「社会階層と社会移動全国調査(SSM調査)(最新は2015年)」と「2016年首都圏調査データ(橋本氏中心の研究グループ)」等で分析、解説する。日本社会は、資本家階級・新中間階級・労働者階級と旧中間階級の4階級構造から成り立っていたが、労働者階級の内部に巨大な分断線が入り、900万人を超える「アンダークラス」という「新しい階級」を含む5階級構造へと転換したという。正規労働者・非正規労働者の深刻な分断線だ。
「分解した"中流"」「現代日本の階級構造」「アンダークラスと新しい階級社会」「階級は固定化しているか」「女たちの階級社会」「格差をめぐる対立の構図」等を調査データに基づいて分析する。そして格差縮小のためには、「格差拡大の事実認識」「自己責任論の打破」「所得再分配の支持」の重要性を説く。5つの階級のなかで最も貧困等の窮状にあるアンダークラスを救い、格差社会の克服に注力せよという。
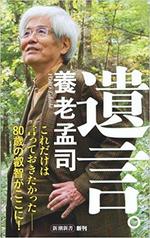 「感覚所与と意識の対立」「意識と感覚の衝突」「感覚所与を意味のあるものに限定し、いわば最小限にして、世界を意味で満たす。それがヒトの世界、文明世界、都市社会である。・・・・・・意味は与えられた感覚所与から、あらためて脳の中で作られる」「科学とは、我々の内部での感覚所与と意識との乖離を調整する行為である」「動物の意識には『同じ』というはたらきがほとんどない」「ヒトの意識の特徴が『同じだとするはたらき』であり、それで言葉が説明でき、お金が説明でき、民主主義社会の平等が説明できる」・・・・・・。社会と人間存在そのものを「意識(同じにする)と感覚(違う)」から、"意識"して問いかけたらどうか、と語る。「ここまで都市化、つまり意識化が進んできた社会では、もはや意識をタブーにしておくわけにはいかない。そのタブーを解放しよう」という。きわめて根源的で本質的な"遺言"で、随所に立ち止まって考えさせられた。
「感覚所与と意識の対立」「意識と感覚の衝突」「感覚所与を意味のあるものに限定し、いわば最小限にして、世界を意味で満たす。それがヒトの世界、文明世界、都市社会である。・・・・・・意味は与えられた感覚所与から、あらためて脳の中で作られる」「科学とは、我々の内部での感覚所与と意識との乖離を調整する行為である」「動物の意識には『同じ』というはたらきがほとんどない」「ヒトの意識の特徴が『同じだとするはたらき』であり、それで言葉が説明でき、お金が説明でき、民主主義社会の平等が説明できる」・・・・・・。社会と人間存在そのものを「意識(同じにする)と感覚(違う)」から、"意識"して問いかけたらどうか、と語る。「ここまで都市化、つまり意識化が進んできた社会では、もはや意識をタブーにしておくわけにはいかない。そのタブーを解放しよう」という。きわめて根源的で本質的な"遺言"で、随所に立ち止まって考えさせられた。
これからIoT、AIの急進展がある。「生命倫理」「遺伝子操作、ヒトの改造とシンギュラリティー」「人間とは何か」が問われる時代が来る。コンピュータにできるようなことしか人間がやらなければ、人間の社会ではなくなる。
「ヒトは、意識に『同じにする』という機能が生じたことで、感覚優位の動物の世界から離陸をした」が、意識と感覚の対立は、ともすると「意識が感覚より上位」だという近代化と呼ぶ社会的システムに傾斜する危険性をもつ。「都市は意識の世界」であり、「意識は自然を排除」する。
そして「実生活の中で感覚を復元する。これもむずかしい世の中になった。効率や経済、つまり便宜やお金で計れば、感覚は下位に置かれる」という。デジタル、ロボットには生老病死はない。人間と社会のその根源的仕組みを問いかける叡智の"遺言"。