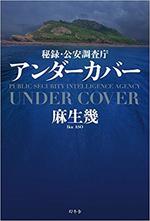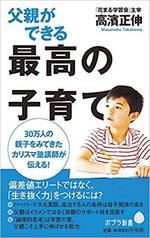 テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
テレビで講演を聞いたこと、さらに「読解力」「意味を考える力」をどう獲得するかを考えていたこともあって、高濱さんの本を読んだ。2050年以降も「生きる」今の子どもが「生き抜く力」を身につけるにはどうしたらよいか。父親の役割は大きいようだ。
まずは、「家庭での父親の第一義的仕事はあくまで『妻を笑顔にすること』、そして『母親が安心して育児に取り組めるように支えてあげること』」という。子どもの心身の成長、学力の伸びは、妻の笑顔からということだ。とくに父親は「正しい会話、意味のある会話を日常的に心がけること、論理的思考を伸ばすこと」に努めることだ。言葉の厳密さは学力に比例し、言語感覚は日常会話でしか培われない、という。
妻からの相談ごと、会話には、「解決してあげる」と思わないで「寄り添う」「共感」「聞くこと」にこそ価値がある。そして、「子どもに何かひとつ自信をもたせること」を養うことが大切であり、「子どもの自信、生き抜く力は、親が養ってあげるもの。照れずに本音でぶつかること、取り組むこと」を示す。
 池袋ウエストゲートパークⅧ。池袋Gボーイズのタカシとマコトが、闇にうごめく悪から純朴な庶民、親子を救い出す。池袋も西口公園も滝野川、上池袋、大塚、板橋もなじみだけに、これまでの作品以上に臨場感をもつ。
池袋ウエストゲートパークⅧ。池袋Gボーイズのタカシとマコトが、闇にうごめく悪から純朴な庶民、親子を救い出す。池袋も西口公園も滝野川、上池袋、大塚、板橋もなじみだけに、これまでの作品以上に臨場感をもつ。
ネット社会での残酷な攻撃。真面目な宅配ドライバーの別れた息子が虐待されていた事件(「滝野川炎上ドライバー」)。母親が覚醒剤を扱う悪い男にハマって娘の中学生にまで魔手が及ぼうとした事件(「上池袋ドラッグマザー」)。ITと心理詐欺の話(「東池袋スピリチュアル」)。スペインの銀行にまでつながる偽造カード事件(「裏切りのホワイトカード」)。
IT社会の光と陰と闇のなか、池袋の"トラブルシュータ―"マコトとタカシの面目躍如。痛快。
 「『所有者不明化』と相続、空き家、制度のゆくえ」が副題。所有者不明の土地が全国で増加している。なんと日本の私有地の約20%、九州を上回る規模になっている。これまでは地方、農林業関係者の間で、過疎化・相続増加にともなって相続人把握の難しさが指摘されてきたが、今は震災復興や耕作放棄地、空き家対策で都市部も含めて顕著となっている。国として対策に乗り出し始めた段階だが、ことは人口減少・高齢社会と経済成長を前提とした土地制度との乖離という構造的問題だけに、政府あげての総合的取り組みが不可欠だ。いらない土地がふえている、ということだ。
「『所有者不明化』と相続、空き家、制度のゆくえ」が副題。所有者不明の土地が全国で増加している。なんと日本の私有地の約20%、九州を上回る規模になっている。これまでは地方、農林業関係者の間で、過疎化・相続増加にともなって相続人把握の難しさが指摘されてきたが、今は震災復興や耕作放棄地、空き家対策で都市部も含めて顕著となっている。国として対策に乗り出し始めた段階だが、ことは人口減少・高齢社会と経済成長を前提とした土地制度との乖離という構造的問題だけに、政府あげての総合的取り組みが不可欠だ。いらない土地がふえている、ということだ。
「問題の根源――相続未登記の広がり(相続登記は義務でなく任意である)」「登記が行われた年が50年以上も前が19.8%も」「わずか192㎡の土地の相続人が150名にも」「全農地面積の約20%が相続未登記」「土地情報基盤の未整備(不動産登記簿、固定資産税台帳、農地台帳、国土利用計画法に基づく売買届出)」「地元を離れる不在地主の増加」「死亡者課税が200万人以上にも」「増える相続放棄の申し立て」・・・・・・。こうした現状には「地籍調査(現在52%)の遅れと原因」「不動産登記制度の限界」「強い所有権と"土地神話"の問題」「権利関係の調整難航」「費用や時間のかかり増し」があることが指摘される。
そして、解決の糸口として①相続登記のあり方②「受け皿」づくり③土地情報基盤のあり方――の3つの論点とその改善策が示される。
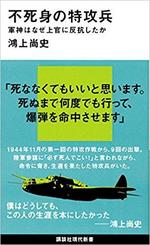 「軍神はなぜ上官に反抗したか」が副題。9回出撃して9回生還した特攻隊員の佐々木友次さん。「臆病者」「なぜ死なないのだ」「なんで貴様ら、帰ってきたんだ。貴様らは人間のクズだ」と罵られ、「処刑飛行」までされた佐々木さんは答える。「私は必中攻撃でも死ななくてもいいと思います。その代わり、死ぬまで何度でも行って爆弾を命中させます」・・・・・・。
「軍神はなぜ上官に反抗したか」が副題。9回出撃して9回生還した特攻隊員の佐々木友次さん。「臆病者」「なぜ死なないのだ」「なんで貴様ら、帰ってきたんだ。貴様らは人間のクズだ」と罵られ、「処刑飛行」までされた佐々木さんは答える。「私は必中攻撃でも死ななくてもいいと思います。その代わり、死ぬまで何度でも行って爆弾を命中させます」・・・・・・。
神風特攻隊については、幾多もの本が出版され、「悠久の大義に殉ずる」などの一言ではとても表わせない言語絶する世界の苦悶・沈黙が知られるようになっている。本書がド迫力で迫ってくるのは、「命令された側」の生の証言であることとともに、「特攻隊とは何であったのか」「なぜ愚かな特攻を続けるに至ったか」を、支配・被支配、戦争という異常時における組織と人間、国民・マスコミの熱狂、過剰な精神主義とリアリズム、「異常」への責任回避・転嫁、日本における「世間」と「社会」、思考の放棄と「集団我」、「当事者」の沈黙と「傍観者」の饒舌、日本文化と戦争など・・・・・・。まさに構造的に深く広く剔抉しているからである。それゆえに佐々木さんの「寿命ですよ」という言葉、岩本益臣隊長や美濃部正少佐等の勇気と存在が心に響く。現在の社会・組織と人間の問題を考えさせられる。