 桶狭間から大坂の陣までの戦国の世――。織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣秀頼の6人を描く。「決戦!関ヶ原」などの決戦シリーズで冲方丁氏が挑んだものだが、時系列に並べてみると、より人物が浮き上がってくる。「世は、秀頼が望んだ騒がしさを失い、かつてどの武将達も大義名分とした、全国静謐の泰平へと移り変わっていった。織田・豊臣が直面した戦なき世が訪れ、そこでは上杉が磨いた兵法も机上のものに過ぎなくなった。明智のような主君殺しは忌み嫌われ、五畿七道を、八道、九道とせんとする野心は誰の心からも消え去った。・・・・・・下克上の世が残したおびただしい道を通るのは、兵ではなく、人と物、銭と思想であった」――。
桶狭間から大坂の陣までの戦国の世――。織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣秀頼の6人を描く。「決戦!関ヶ原」などの決戦シリーズで冲方丁氏が挑んだものだが、時系列に並べてみると、より人物が浮き上がってくる。「世は、秀頼が望んだ騒がしさを失い、かつてどの武将達も大義名分とした、全国静謐の泰平へと移り変わっていった。織田・豊臣が直面した戦なき世が訪れ、そこでは上杉が磨いた兵法も机上のものに過ぎなくなった。明智のような主君殺しは忌み嫌われ、五畿七道を、八道、九道とせんとする野心は誰の心からも消え去った。・・・・・・下克上の世が残したおびただしい道を通るのは、兵ではなく、人と物、銭と思想であった」――。
「人間、五十年・・・・・・。六欲天の魔王。人心掌握の神算鬼謀」「炯眼の持ち主(虎視の眼)」「我、鬼札として天下を取れり」「人望厚く、中庸をなし、国を富み栄えさせること能う逸材(家康の吉継評)」「秀吉と豊臣家と文官に対する深い失望(吉継がはなから信じていなかった秀秋の心中)」「神生(な)りて下克上巳む」――。いずれも途方もない能力をもち、人心掌握に長け、宿命的立場に立たされた者の激烈な人生とその勝負の決断。異常な戦国の事態が異能の"神がかる人"を"神そのもの"と押し上げる姿が描かれる。
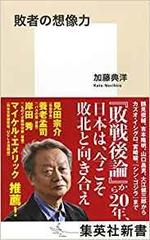 「敗戦後論」から20年。「戦争の敗北」「占領」を真正面から受け止め、血肉化、思想化していない日本の現状を、山口昌男、大江健三郎、鶴見俊輔、吉本隆明、カズオ・イシグロ(ノーベル賞受賞前に本書は書かれている)、宮崎駿、そして「シン・ゴジラ」等を通じて語っている。なぜそうなったのか。深まらないのは残念なことなのだ。
「敗戦後論」から20年。「戦争の敗北」「占領」を真正面から受け止め、血肉化、思想化していない日本の現状を、山口昌男、大江健三郎、鶴見俊輔、吉本隆明、カズオ・イシグロ(ノーベル賞受賞前に本書は書かれている)、宮崎駿、そして「シン・ゴジラ」等を通じて語っている。なぜそうなったのか。深まらないのは残念なことなのだ。
「敗者の想像力とは、敗者が敗者であり続けているうちに、彼のなかに生まれてくるだろう想像力のことである」「日本の敗戦国としての70余年の経験が育んだ感性、感受性、考え方――それを総称して敗者の想像力と呼ぶ。しかしそれは、敗者に限らない、人間の想像力の深い現れでもある」「敗れることの経験の深さ」「自分たちが敗者である。その自覚の底に下りていく。そこから世界をもう一度見上げてみる。見下ろす想像力と見上げる想像力。想像力にも天地がある」「第二次世界大戦の敗戦国の特異さ――壊滅的な物質的・倫理的敗北によって"敗戦国"としての自意識が残らないほど徹底的に打ちのめされた点にある......かくも従順に、抵抗もせずに、不当なことを受け止める......運命として受け止める」「日本という国には、現在、敗者の想像力が足りない。圧倒的に足りない。......なぜか大江健三郎の初期作品が、意味深い例外的な位置を占めている」「敗者の想像力とゴジラ」「原発事故とシン・ゴジラ」「文明の逆襲と冷温停止」「これからの時代、低エントロピー社会を射程に置く。そのモデルとして"勝ち派"のスタイルではなく、"負け派"のスタイル、せり下げの非・上昇志向」「近代日本は、明治以来"(上昇)文明のハシゴ段"を登ってきたが、この強迫観念からどう自由になるかが、戦後の課題になる(鶴見)」「(マルクス主義など)輸入思想を金科玉条的に信念貫徹してきただけでは、思想的な価値はみじんもない」「ぼろぼろな戦後に殉じる、矛盾を生きる」「戦後民主主義という時代遅れの"時代の精神"に、いまこそ自分が殉死しよう」......。まさに「下り坂での戦い」の「負けることを最後までやりとげる戦い」ということを考える。
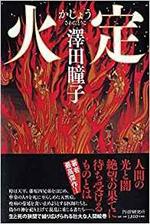 飛鳥から寧楽(なら)に都が移されて27年後。史実には、「737年(天平9年)、奈良に天然痘が流行し、左大臣藤原武智麻呂ら藤原4兄弟をはじめ多数が死亡する」とある。その凄まじいパンデミックのなか、食い止めようとする医師、それに乗じて混乱を起こし私欲に走る者、権力でのし上がろうとする者、陰謀と罠・・・・・・。光明皇后が発意した貧しい病人のための施薬院や悲田院なども舞台となる。
飛鳥から寧楽(なら)に都が移されて27年後。史実には、「737年(天平9年)、奈良に天然痘が流行し、左大臣藤原武智麻呂ら藤原4兄弟をはじめ多数が死亡する」とある。その凄まじいパンデミックのなか、食い止めようとする医師、それに乗じて混乱を起こし私欲に走る者、権力でのし上がろうとする者、陰謀と罠・・・・・・。光明皇后が発意した貧しい病人のための施薬院や悲田院なども舞台となる。
飢饉・疫病、この世の業火のパンデミックが、あの時代いかに凄まじいものであったか。次から次へと嵐の如く襲いかかるその様子が、ものすごい迫力で描かれる。屍累々のなかで、「生きる」「1つの命の輝き」が、浮かび上がる。施薬院の峰田名代が夢中で走る。そして「綱手の苦しみが、諸男の憎しみが――それでもなお、人を救い、癒す彼らの哀れなまでの志が胸を打ち、やがて激しい震えとなって心を揺さぶった」――。力作。
 「他人を引きずり下ろす快感」が副題。「シャーデンフロイデとは、誰かが失敗した時に、思わず湧き起こってしまう喜びの感情」だ。この感情は"愛情ホルモン""幸せホルモン"などと俗に呼ばれる「オキシトシン」という物質と深い関わりがあり、これらの効果と同時に"妬み"感情も強めてしまう働きをもつことがわかってきた。そしてオキシトシンは、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質に影響を与える。
「他人を引きずり下ろす快感」が副題。「シャーデンフロイデとは、誰かが失敗した時に、思わず湧き起こってしまう喜びの感情」だ。この感情は"愛情ホルモン""幸せホルモン"などと俗に呼ばれる「オキシトシン」という物質と深い関わりがあり、これらの効果と同時に"妬み"感情も強めてしまう働きをもつことがわかってきた。そしてオキシトシンは、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質に影響を与える。
オキシトシンの働きは「安らぎと癒し」「愛と絆」。「愛着を形成する」ものであるだけに、逆に人と人とのつながりが切れてしまいそうになるとき、オキシトシンはそれを阻止しようとする行動を促進する。「私から離れないで」「私たちの共同体を壊さないで」「絆を断ち切ろうとすることは、許さない」――。
こうした脳の働きから、「加速する『不謹慎』」「標的を"発見"するのは妬み感情」「相手の不正を許さないのは協調性の高い人」「集団を支配する『倫理』」「承認欲求ジャンキー」「"自分こそが正しい"正義バブルの時代」「『愛と正義』のために殺し合うヒト」「宗教戦争はなぜ起きるか」「愛が抱える矛盾」などを詳述する。
「よかれと思って」という気持ちとその帰結。「東に向かって全力疾走しているつもりが、西に向かって暴走していた」・・・・・・。愛の情動の裏にある闇を、脳内物質「オキシトシン」から剔抉する。


