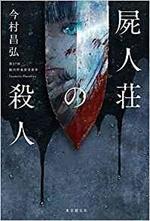新しい画風に挑みながらも、不遇のうちに自らに銃弾を放った画家フィンセント・ファン・ゴッホ。それを献身的に支え続けた弟テオドルス・ファン・ゴッホ(テオ)――。その互いの思いやりが、それぞれの半身ともいうべき深い運命的つながりに起因することが激しく伝わってくる。そしてその同時期1880年代のパリに2人の日本人がいた。花のパリの美術界に東大を中退してまで乗り込み、大ブームとなった浮世絵など日本美術を紹介し売り込んだ林忠正と、その助手・加納重吉。この「史実をもとにしたフィクション」は感動的だ。
新しい画風に挑みながらも、不遇のうちに自らに銃弾を放った画家フィンセント・ファン・ゴッホ。それを献身的に支え続けた弟テオドルス・ファン・ゴッホ(テオ)――。その互いの思いやりが、それぞれの半身ともいうべき深い運命的つながりに起因することが激しく伝わってくる。そしてその同時期1880年代のパリに2人の日本人がいた。花のパリの美術界に東大を中退してまで乗り込み、大ブームとなった浮世絵など日本美術を紹介し売り込んだ林忠正と、その助手・加納重吉。この「史実をもとにしたフィクション」は感動的だ。
19世紀後半のパリの美術界は「アカデミー」全盛から新興の「印象派」台頭のせめぎあいの時。これに、日本の浮世絵が鮮烈な影響を与えた。
「たゆたえども沈まず」――。「パリは、いかなる苦境(洪水等の)に追い込まれようと、たゆたいこそすれ、決して沈まない。まるでセーヌの中心に浮かんでいるシテ島のように」「どんなときであれ、何度でも、流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる。そんな街。それこそが、パリなのだ」。そして、茶碗の包み紙に過ぎなかった浮世絵も、その光明を受けて夢に突き進んだゴッホも、印象派も、それを支えた人々も、いつか世に認められる陽光の時が来た訳だが、そこは本書にはあえて書かれていない。
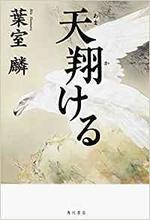 葉室麟の遺作となった。「(国を守ろうと思った西郷・橋本左内の志)それは天を翔けるような志であったに違いない。春嶽もそんな志を持った。・・・・・・しかし西郷は志を捨てぬまま世を去ったのだ。そう思うと春嶽の目から涙があふれた。・・・・・・明治23年、松平春嶽逝去、享年63」・・・・・・。本書はそう締められているが、葉室麟の死を思った。幕末から明治新政府、ずっと要職に就いて苦難を生きてきた松平春嶽。「破私立公」の人であるか否か。救国の思い、大きな志をもった男か「私」に立つ人か。春嶽はその観点から真の友を選び友を得た。見識と謹直と温和、絶妙のバランス感覚をもつ春嶽だからこそ、激震の時代の中枢にいる人の信頼を得た。阿部正弘も、水戸の徳川斉昭も、島津斉彬も、熟友の山内容堂も、そして横井小楠、勝海舟、坂本龍馬、西郷隆盛も春嶽に信頼を寄せたが、彼は徳川慶喜らに危うさを観た。
葉室麟の遺作となった。「(国を守ろうと思った西郷・橋本左内の志)それは天を翔けるような志であったに違いない。春嶽もそんな志を持った。・・・・・・しかし西郷は志を捨てぬまま世を去ったのだ。そう思うと春嶽の目から涙があふれた。・・・・・・明治23年、松平春嶽逝去、享年63」・・・・・・。本書はそう締められているが、葉室麟の死を思った。幕末から明治新政府、ずっと要職に就いて苦難を生きてきた松平春嶽。「破私立公」の人であるか否か。救国の思い、大きな志をもった男か「私」に立つ人か。春嶽はその観点から真の友を選び友を得た。見識と謹直と温和、絶妙のバランス感覚をもつ春嶽だからこそ、激震の時代の中枢にいる人の信頼を得た。阿部正弘も、水戸の徳川斉昭も、島津斉彬も、熟友の山内容堂も、そして横井小楠、勝海舟、坂本龍馬、西郷隆盛も春嶽に信頼を寄せたが、彼は徳川慶喜らに危うさを観た。
春嶽は大政奉還を早くから構想した。「徳川家の私政から脱却させ、公の政を行う」「安政の大獄で冷え切った朝廷との関係を修復し、公武合体によって国難に立ち向かう」「開国派と尊攘派が手を携えて国難にあたる挙国一致体制をつくる」――。常に変わらぬ一念が幕末の混乱のなかでも貫かれた。
しかし、「大政奉還、王政復古にいたる流れでは、実権は島津久光を始めとする春嶽や容堂らいわゆる賢候にあったが、新政府成立後、志士上がりの官僚たちが、すべては自分たちの功績であったかのように主張していく」「いずれにしても明治初年に尊攘派以外の政府要人はしだいに遠ざけられ、その後、明治維新は尊攘派による革命であったかのように喧伝されていく」のである。
激震の幕末を、その中枢にあった松平春嶽から描く思いの込められた歴史小説。幕末の四賢候とは、松平春嶽、山内容堂、島津斉彬と宇和島の伊達宗城。
 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」――。最も厳しい状況のなか、心が本当に通った関係だったことが、あふれている。
平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」――。最も厳しい状況のなか、心が本当に通った関係だったことが、あふれている。
表紙にラグビーボールを共にもった写真が出ている。「人生はラグビーボールと同じ。楕円形のボールはどこに転がっていくかわからない。しょうがないやないか」「世の中には理不尽なことがたくさんある、というのが僕の持論」「ラグビーボールが今も楕円形なのは、世の中というものが予測不可能で理不尽なものだから、その現実を受け入れ、そのなかに面白みや希望を見出し・・・・・・」と平尾さんは語り、「しゃあない、こんなこともある。でもなんとかなるわ」と理不尽な経験をポジティブにとらえる。二人の友情と対話。互いに全身で刺激し、支え合い、共鳴盤を打ち鳴らした強くすがすがしい世界が描かれる。
「技術革新と倫理観」では、技術革新とともに、「その時、暴走をコントロールするために必要なのが人間の倫理観というか、本当の意味での人間の力なのではないか」という。
ナイスガイの二人。波長があい噛み合った二人。素晴らしい。
 安倍内閣が最も力を入れている「働き方改革」――。「同一労働同一賃金」「残業時間の上限規制」「"非正規労働"という言葉を国内から一掃」などが今、いかに喫緊の課題であり、重要か。日本社会全般にわたる大きな課題をガッチリと、しかもコンパクトにまとめて提示している。
安倍内閣が最も力を入れている「働き方改革」――。「同一労働同一賃金」「残業時間の上限規制」「"非正規労働"という言葉を国内から一掃」などが今、いかに喫緊の課題であり、重要か。日本社会全般にわたる大きな課題をガッチリと、しかもコンパクトにまとめて提示している。
GDPは資本と生産性と労働力の3つの要素からなる。「全要素生産性上昇率は、経済全体の資本や労働力の配分効率であり、これを高めるには、雇用の流動性を制約している要因を取り除く必要がある」ということだ。日本の経済成長を支えてきた独特の働き方、「終身雇用」「年功賃金」「定年退職」などを変える「労働市場改革」が急務となる。成功体験が労働市場改革を阻んでいる。
日本の労働市場の構造変化は激しい。「高度成長の終焉」「各職場、役職も増えない」「若者は少なく、高齢化が進む社会」「正社員・非正規社員問題」「AI・ICT社会の進展」「女性の活躍」「共働きの増加、両立支援」「転勤問題」「ストレス社会と健康・休暇」「長時間労働規制と残業問題」「転職リスク」「人手不足問題」・・・・・・。「同一労働同一賃金」は、これらの働き方の枠組みを抜本的に変えてこそ実現するものだ。
本書はこれらの全貌を剔抉している。「日本の労働市場の構造変化」「解雇の金銭解決ルールはなぜ必要か」「竜頭蛇尾の同一労働同一賃金改革」「残業依存の働き方の改革」「年齢差別としての定年退職制度」「女性の活用はなぜ進まないか」「人事制度改革の方向」――。これら各章は互いにリンクしている。副題は「少子高齢化社会の人事管理」。「同一労働同一賃金」「人事管理のあり方」が改革の本丸だとの思いが募る。