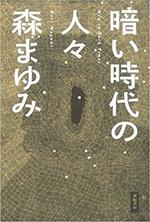 大正デモクラシーから昭和の戦前・戦中に生き抜いた人々。とくに最も精神の抑圧された1930年~45年の「暗い時代」に「精神の自由」を掲げて戦った人々を描いたという。それは「良心的な文化運動なども圧迫されがちで、軍国主義的色彩は強くなるばかりの時代」「『人権の尊重』『言論の自由』などと説くと、危険思想と言われた暗い時代」「窮屈で、貧しく人が死んでいく時代」であった。
大正デモクラシーから昭和の戦前・戦中に生き抜いた人々。とくに最も精神の抑圧された1930年~45年の「暗い時代」に「精神の自由」を掲げて戦った人々を描いたという。それは「良心的な文化運動なども圧迫されがちで、軍国主義的色彩は強くなるばかりの時代」「『人権の尊重』『言論の自由』などと説くと、危険思想と言われた暗い時代」「窮屈で、貧しく人が死んでいく時代」であった。
日本人9人の生涯が描かれる。「粛軍演説」「反軍演説」の斎藤隆夫、社会主義運動と女性運動に奔走した山川菊栄、生物学者をめざし、社会運動家として活躍した山本宣治(山宣)、アメリカで恐慌をベルリンでナチスの台頭を見た竹下夢二、日本で初めての婦人の社会主義団体・赤瀾会の創立メンバーで産児制限運動と労働運動に奔走した九津見房子、京都で反ファシズム雑誌を作り支えた斎藤雷太郎と立野正一、マルクス主義哲学者・古在由重、終生のわがまま者にしてリベルタン・西村伊作だ。
世界史の激流と思想の激突、社会の底で苦悶する民衆、女性と権力の弾圧・・・・・・。短編であるがゆえに血がにじみ鮮烈だ。
 最近までの産経新聞連載をまとめたもの。短いエッセイだが、納得するし何か身体がすっと楽になる。鍛えられた人間の基本、人生哲学。心に刺さるというより、抱えられる。
最近までの産経新聞連載をまとめたもの。短いエッセイだが、納得するし何か身体がすっと楽になる。鍛えられた人間の基本、人生哲学。心に刺さるというより、抱えられる。
「求められる『才覚』と『優しさ』」「自立した生活こそ最高の健康法」「人生は何とかなるという魂の強さ」「日本人、ことにマスコミや進歩的文化人や学者は、最近すぐに他人に対して『謝れ』と言うようになった。しかし多くの日本人は、他人に強いて謝らせるという行為の虚しさと思い上がりの醜悪さとを知っていると思う」「悪い言葉だけを禁じても犯罪は防げない。・・・・・・表現力がない人に、人間相手の仕事はできない」「私が最近の日本人について感じるのは、『自分の身は自分で守る』という本能の欠如である」「緊急時に1番に頼れる存在は自分自身なのだ(1番遠い存在である国家に頼るようになった)」「しかし何より大切なのは、他者の不幸をわが身のことのように感じる『同情』の能力なのだ」「不運も不幸もまた一種の財産だ。人間は、涙の中から覚り、知ることがある」「成熟した大人は、分裂した現実に耐え、普通は対立した陰の心理を感じ生きている。しかし日本人には、ひたすらまっすぐ正論を掲げてその道を行けば、必ずゴールに達することができる、と信じている"善意の大人"群が実に多い」「人生で一人も殺さず、自分も自殺しなければ、それだけで大成功だ」「私は、人間は生きている限り、できるだけ働いて当然だ、と思っている」「(閣僚に任命するときに)いざという時の攻め方と耐え方、私生活上の清廉潔白さ、表現力の豊かさなどの上で、何より賢さや徳の有無を見抜け」「最近のマスコミは、自分が人権を守っている人道主義者だということを、幼稚に示すことに熱心である。自分が正しいことを示すために、人を糾弾することも好きだ(「善」だけしか認めない息苦しさ)」「その手の"人道的""弱者に優しい"番組さえ作ればマスコミの世界で非難されることはないのだ」「追及ばかりで議会空転ならお金のムダだ」「"おきれいごと"に愛想を尽かした人たち」「戦争には必ず敵がいるという現実だ・・・・・・その敵にどう対処するかを教えない心情的平和など、まず力を持たない」「安全優先と国際貢献との葛藤」「私は現実を正視する勇気のある人には希望を繋ぐ」「正義、平等、人道主義、反権力などを、はずかしげもなく前面に出して振りかざすのが言論人だと言っている人たちへの対処」・・・・・・。
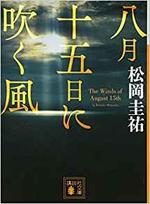 日本の敗色が濃くなっていった1943年夏――北の最果て、アリューシャン列島西部にある鳴神島=キスカ島で、孤立状態にあった日本兵5200名が奇跡的に無血で救出された。しかもその直前、隣の島・熱田島=アッツ島では日本軍は全滅、玉砕していた。
日本の敗色が濃くなっていった1943年夏――北の最果て、アリューシャン列島西部にある鳴神島=キスカ島で、孤立状態にあった日本兵5200名が奇跡的に無血で救出された。しかもその直前、隣の島・熱田島=アッツ島では日本軍は全滅、玉砕していた。
人の命は一度失ったら取り返せない。命の尊さ、戦時下における指導者のゆるぎなき人道の魂の重要さ。その無血の大救出劇は、「一億玉砕、一億総特攻、人命を軽んじ野蛮で好戦的で、狂信的な危険きわまりない日本人」という米国の見方を大きく変えることにもなった。海軍少将・木村昌福、陸軍中将・樋口季一郎、気象専門士官・橋本恭一少尉、同盟通信社の菊池雄介、そして日本人観を覆した米軍諜報部員・ロナルド・リーン(ドナルド・キーン)・・・・・・。「この小説は史実に基づく 登場人物は全員実在する(一部仮名を含む)」と書かれている。重い感動作。
 「自分の『強み』を見つけるには」が副題。ハイエクは「誰がいちばん優れているか、誰がいちばん私たちの要求に応えてくれるか、あらかじめわからない場合、それを見つけ出すための装置としての役割が競争にはある」ととらえた。激しい競争に身を置けば自分の強みを発見できる可能性が高まる。これからの日本を考えると、日本経済の構造問題として、生産性、高齢化、労働市場等の問題に突き当たる。大竹さんは、「難問から目をそむけるな。存在しない単純な解決策を求めてはならない」と言い、「経済制度や政策を工夫すれば、日本経済の効率性は上がり、生産性は上昇する効果はあるはずだ。・・・・・・低成長や高齢化を前提に、日本の経済社会制度をつくり直すという難問にすぐ向き合わないと、難問の解決には間に合わない」と警鐘をならす。
「自分の『強み』を見つけるには」が副題。ハイエクは「誰がいちばん優れているか、誰がいちばん私たちの要求に応えてくれるか、あらかじめわからない場合、それを見つけ出すための装置としての役割が競争にはある」ととらえた。激しい競争に身を置けば自分の強みを発見できる可能性が高まる。これからの日本を考えると、日本経済の構造問題として、生産性、高齢化、労働市場等の問題に突き当たる。大竹さんは、「難問から目をそむけるな。存在しない単純な解決策を求めてはならない」と言い、「経済制度や政策を工夫すれば、日本経済の効率性は上がり、生産性は上昇する効果はあるはずだ。・・・・・・低成長や高齢化を前提に、日本の経済社会制度をつくり直すという難問にすぐ向き合わないと、難問の解決には間に合わない」と警鐘をならす。
取り上げた実例は広範で身近な問題で、経済の視点でリアルに把えて面白い。「チケット転売問題について音楽関係者側と業者側の言い分を行動経済学で考える」「他店対抗広告の狙い」「くまモンの普及戦略と二部料金制」「落語の"千両みかん"から考える価格と価値」「納税は国民の義務か、課税が国の権利か」「感情とリスク、感情と謝罪」「プロゴルファーの損失回避」「行動経済学による現実的研究」「平等主義で反競争的な教育が、逆に、教育における競争を激化させた皮肉」「三多摩地域のコレラ騒動と外部性(外部性の内部化)」「お金持ちは所得再分配が嫌いか」・・・・・・。
身近な問題から大きな問題まで、経済学的思考と行動経済学で、先入観から解き放ち、怜悧に整理してくれる。
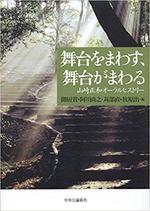 まさに「知の巨人」。戦後日本の深層を自らの歩みから語る感動的、圧巻の書となっている。御厨貴さんら4人が、山崎正和さんへのロングインタビューを行ったものだ。これまで大事な時に山崎さんに話をうかがい、また著作にふれてきた私だが、そのインタビューの場に同席させてもらったような感動を覚えた。
まさに「知の巨人」。戦後日本の深層を自らの歩みから語る感動的、圧巻の書となっている。御厨貴さんら4人が、山崎正和さんへのロングインタビューを行ったものだ。これまで大事な時に山崎さんに話をうかがい、また著作にふれてきた私だが、そのインタビューの場に同席させてもらったような感動を覚えた。
まず感ずるのは、日本の時代と社会と人など直面する課題への関わり方の厚みだ。満州での少年期・終戦体験、戦後の左翼に傾斜する知識人への対処、共産党活動からの離脱、「世阿彌」の執筆、米国での自作の戯曲上演・・・・・・。20代、30代での仕事があまりにも濃密、あの碩学との対談「対談天皇日本史」刊行も40歳の時だ。「鷗外 戦う家長」「不機嫌の時代」「柔らかい個人主義の誕生」など、時代・社会の微妙な変化の"気分"を察知する洞察が、いかに哲学・思想の深みから発したものかを、本書は生々しく示している。サントリー文化財団設立、大阪大学への異動と演劇学講座創設、政治との関わりや内閣官房からの要請、中央教育審議会の会長就任・・・・・・。いずれも政権中枢や大阪など地方の難題に真正面から取り組んできたものだ。それは、時代の直面する課題を、より根底的にとらえる正視眼の姿勢、毅然たる山崎さんの姿勢を頼りにし求めているからだと思う。そして、組織の硬直的な権威主義や、いわゆる"左翼"と戦うなか自ら切り拓いてきた姿勢が凄い。「舞台をまわす」だ。
急激な大衆化のなかで、浅薄で煽動に乗りやすい体質がつくられ、ポピュリズムとナショナリズムに翻弄されがちな社会のなかで「常に問題解決の方途を示す中道の精神」「偏ることなく全体を如実知見する中道の精神」「道に中(あた)る中道の精神」を感じた。

