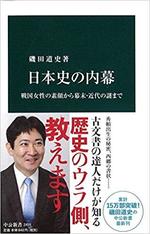 日本史にはたくさんの謎が潜んでいるし、勝者の歴史となっていることは否めない。磯田さんは、「日本史の内幕を知りたい。そう思うなら、古文書を読むしかない」と、15歳の頃からずっと古文書を見つけ、解読してきた。きわめて面白い。
日本史にはたくさんの謎が潜んでいるし、勝者の歴史となっていることは否めない。磯田さんは、「日本史の内幕を知りたい。そう思うなら、古文書を読むしかない」と、15歳の頃からずっと古文書を見つけ、解読してきた。きわめて面白い。
「沼津市にある高尾山古墳は卑弥呼と全く同世代の"初期古墳"(初期古墳を護れ)」は、国交大臣の時の話で私もかかわった。「秀吉の天下統一に本願寺が協力」「『殿、利息でござる!』の浅野屋甚内と穀田屋十三郎の感動的な"慎み"」「三方ヶ原の戦いでの織田援軍の人数」「豊臣の金銀の行方」「水戸は"敗者復活"藩」「築山殿と家康の関係」「井伊家と松下嘉兵衛と秀吉」「秀吉は秀頼の実父は疑わしい」「庶民が実学を学んだ"寺子屋"文化の財産」「我々は『本が作った国』に生きている」「龍馬の書状発見」「"民あっての国"山田方谷(総じて天下のことを制するものは、事の外に立って事の内に屈してはならない)」「日本の人口が世界シェアの最高になったのは綱吉の時代(6億人中3000万人)」「中根東里と司馬遼太郎」、そして「災害と日本人」・・・・・・。いずれも興味深く、「日本人と歴史」の重さがじわっと突き上げてくる。
 人口減少・少子高齢社会、人生100年時代に本格的に進む今、日本の社会保障制度は大きな曲がり角に差し掛かっている。社会保障は「民生の安定」と「経済の成長」の両面を担う。安心社会の基盤となり、社会経済の変化に柔軟に対応し、社会の発展・経済の成長に寄与できる社会保障制度をどう構築するか。
人口減少・少子高齢社会、人生100年時代に本格的に進む今、日本の社会保障制度は大きな曲がり角に差し掛かっている。社会保障は「民生の安定」と「経済の成長」の両面を担う。安心社会の基盤となり、社会経済の変化に柔軟に対応し、社会の発展・経済の成長に寄与できる社会保障制度をどう構築するか。
内閣と厚労省で直接、この問題と格闘してきた香取さんが、きわめて丁寧に、幅広く、そして歴史・理念・哲学をも踏まえて「人口減少社会を乗り切る持続可能な安心社会」のための社会保障制度の方向性を示す。「一億総活躍」「働き方改革」「全世代型社会保障」など、安倍内閣・自公政権の行っていることの意味が、より鮮明に浮かび上がってくる。
「系譜、理念、制度の体系――ギルドの互助制度を基本としたビスマルク」「基本哲学――共助やセーフティーネットが社会を発展させた」「日本の社会保障――『皆保険』という奇跡」「変調する社会・経済――人口減少・少子化・高齢化で『安心』が揺らぐ」「産業としての社会保障――GDPの5分の1の巨大市場」「国家財政の危機――次世代ツケまわしの限界」「目指すべき国家像――社会を覆う"不安"の払拭」「新たな発展モデル――知識産業社会と労働、安心と成長の両立」「改革の方向性――安心社会への改革」・・・・・・。現在の最大の課題、経済、財政、社会保障の位置と役割がよくわかる。
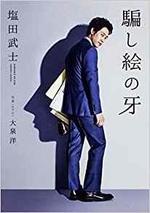 激変する社会のなかで変化を迫られる出版業界。しかし、編集作業、編集する頭脳は人間のなかでも根源的ともいえる最重要のものだ――。「自分は何のために編集者になったのか」「昨今の出版業界の移り変わりを前に『このまま何もせずにいていいのだろうか』『現在この業界に本当に必要な存在とは何か』との問い」「思考を続ける人間には、真贋を見極める目が備わっている。本物を、上質を選ぶ慧眼を身につけることが、情報の波にさらわれない唯一の対抗策だ。思考の源は言語だ。言葉を探し、文化を育み続けることこそ、出版人の使命だ」――。
激変する社会のなかで変化を迫られる出版業界。しかし、編集作業、編集する頭脳は人間のなかでも根源的ともいえる最重要のものだ――。「自分は何のために編集者になったのか」「昨今の出版業界の移り変わりを前に『このまま何もせずにいていいのだろうか』『現在この業界に本当に必要な存在とは何か』との問い」「思考を続ける人間には、真贋を見極める目が備わっている。本物を、上質を選ぶ慧眼を身につけることが、情報の波にさらわれない唯一の対抗策だ。思考の源は言語だ。言葉を探し、文化を育み続けることこそ、出版人の使命だ」――。
読者の活字離れ、激震の出版業界のなかで生き抜くことを迫られる雑誌の編集長・速水輝也。軽妙な会話、人を惹きつける力、心を通わせての信頼の獲得、好感度抜群、やり手の速水は、懸命に雑誌を守ろうと奔走する。しかし、社内の軋轢も加わって社を去ってゆくことになる。
しかし、やられっ放しと思いきや大逆転が待っていた。はたして速水の本性はどこにあり、その牙ともいえる執念は何によって築かれてきたのか。情報社会の急進展、変化を余儀なくされ、もがく出版業界のなかで、出版や編集の意味や人間の文化を問いかける。そのなか人間の泥臭さを交えて描く傑作。大泉洋を写真で使い、小説に映像を組み込んだ新しい試みまである。
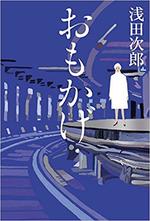 商社のエリート社員・竹脇正一。定年となったその日に、地下鉄で倒れ意識を失う。65歳。彼をこの世に生み出した母親と思しき人、彼を支えた家族・友人が次々に「おもかげ」として出てくる。彼は親を知らない、孤児となったいきさつも知らない。残酷な真実を胸の奥に蔵(しま)い続けて生きてきた。真っ白な戸籍。被い隠した劣等感の源でもあった。周りも同じような境遇の人が集う。親子の絆が切られていた妻・節子。両親が交通事故死して同じ養護施設で育った幼なじみの永山徹(親方)、両親の愛を全身に受けて育った娘・竹脇茜、その結婚相手で保護観察付きで親方に拾われた大野武志、そして集中治療室の隣のベッドの榊原勝男(戦災孤児)とそのマドンナ的存在であった峰子・・・・・・。
商社のエリート社員・竹脇正一。定年となったその日に、地下鉄で倒れ意識を失う。65歳。彼をこの世に生み出した母親と思しき人、彼を支えた家族・友人が次々に「おもかげ」として出てくる。彼は親を知らない、孤児となったいきさつも知らない。残酷な真実を胸の奥に蔵(しま)い続けて生きてきた。真っ白な戸籍。被い隠した劣等感の源でもあった。周りも同じような境遇の人が集う。親子の絆が切られていた妻・節子。両親が交通事故死して同じ養護施設で育った幼なじみの永山徹(親方)、両親の愛を全身に受けて育った娘・竹脇茜、その結婚相手で保護観察付きで親方に拾われた大野武志、そして集中治療室の隣のベッドの榊原勝男(戦災孤児)とそのマドンナ的存在であった峰子・・・・・・。
「無言の人生が詰まっている」静寂の集中治療室の中での回想は、「親を知らない」「子を棄てる」という究極の闇の深さを突きつける。「孤児にとって最大のハンディキャップは、愛の欠落ではない。むしろ、自分の人生の芯や核になりうるもの、あらゆる行為や道徳の基準となるものの欠如が問題だった」・・・・・・。それらをきわめて透明感をもった人間愛の世界に誘い描き切る。重苦しさがないのは「皆、貧しかったから」、そして右肩上がりの昭和の時代を生きたから、そして「あんたの人生、できすぎだぜ」との思いからだろう。深い感動作。
 「政軍関係を考える」がメーンテーマ。何度も繰り返し述べられているのは、「政軍関係の概念」は「専門家集団である軍隊の国家機構の中における明確な位置付け、専門職としての軍隊と軍隊が守るべき国民との一体感、政治指導者と軍隊の指揮官の間の相互理解、政策決定過程における政治指導者と軍隊の指揮官の率直な意見交換、政治指導者による最終的な政策決定に対する軍隊の指揮官の徹底的な服従及び政策決定の過程と結果についての国民に対する説明責任――その全てを包含するダイナミックな相互関係」であり、「我が国においては、政治、自衛隊及び国民の三者の間で、この政軍関係の理解は著しく遅れている」ということだ。また民主主義国家における軍隊の在り方に関する4つの原則として「軍事専門性の追求」「政治目的と作戦目的の合致(そのための真摯な努力)」「政治決定に対する軍隊の絶対的な服従」「軍隊の政治的な中立性」をあげている。
「政軍関係を考える」がメーンテーマ。何度も繰り返し述べられているのは、「政軍関係の概念」は「専門家集団である軍隊の国家機構の中における明確な位置付け、専門職としての軍隊と軍隊が守るべき国民との一体感、政治指導者と軍隊の指揮官の間の相互理解、政策決定過程における政治指導者と軍隊の指揮官の率直な意見交換、政治指導者による最終的な政策決定に対する軍隊の指揮官の徹底的な服従及び政策決定の過程と結果についての国民に対する説明責任――その全てを包含するダイナミックな相互関係」であり、「我が国においては、政治、自衛隊及び国民の三者の間で、この政軍関係の理解は著しく遅れている」ということだ。また民主主義国家における軍隊の在り方に関する4つの原則として「軍事専門性の追求」「政治目的と作戦目的の合致(そのための真摯な努力)」「政治決定に対する軍隊の絶対的な服従」「軍隊の政治的な中立性」をあげている。
こうしたテーマを米英、とくに米国の現在までの適切な政軍関係への葛藤と模索と構築課程を探り開示する。「何故、ジョージ・マーシャル元帥が米軍人から最も尊敬されているのか」「何故、ダグラス・マッカーサー元帥は米軍人から尊敬されていないのか」「湾岸戦争におけるコリン・パウエル統合参謀本部議長の判断は果たして正しかったか」「苦悩し続けたマイケル・マレン統合参謀本部議長は、何故、尊敬されているのか」を政軍関係から剔抉する。そして、民主主義国家日本が取り組むべき政軍関係の課題を提起している。

