 ギリシャ美術から印象派に至るまでの西洋美術の変化には、西欧の歴史、政治・社会、文化、価値観の変遷が投影されている。とくに、信仰や権力者の意図もあって、一定のメッセージを伝える手段でもあっただけに、「読み解く」ことが重要でもある。これまで中野京子さんの一連の「読み解くシリーズ」や原田マハさんの幾つもの小説等を興味深く読んできただけに、本書は掛け足する俯瞰の良さをもつ。
ギリシャ美術から印象派に至るまでの西洋美術の変化には、西欧の歴史、政治・社会、文化、価値観の変遷が投影されている。とくに、信仰や権力者の意図もあって、一定のメッセージを伝える手段でもあっただけに、「読み解く」ことが重要でもある。これまで中野京子さんの一連の「読み解くシリーズ」や原田マハさんの幾つもの小説等を興味深く読んできただけに、本書は掛け足する俯瞰の良さをもつ。
「なぜ、古代の彫像は『裸』だったのか(男性美を追求したギリシャの価値観)」「ローマの大規模建築」「修道院の隆盛によるロマネスク」「巡礼ブーム・都市化とゴシック美術(神と光)」「ルネサンス」「15世紀の北方ルネサンス・ネーデルラント絵画」「16世紀ヴェネツィア絵画の自由と享楽」「カトリックvs.プロテスタントが生み出した新たな宗教美術・バロック絵画(ルーベンス、ベラスケス)」「17世紀オランダ美術の別格レンブラント」「かつての美術後進国フランスに設立された王立絵画彫刻アカデミー(明晰な精神と理性のプッサン芸術とフランス古典主義)」「ルイ14世死去(1715年)から生まれた繊細で華やかなロココ文化(貴族の時代)」「フランス革命と新古典主義の幕開け」「新古典主義と対立したロマン主義」「産業革命・都市の発展のなかで"現実"をそのまま描いたクールベがこじ開けた近代美術の扉」「さらに一層押し開いた近代絵画の父マネ」「文化的後進国イギリスの反撃」「身近な自然や田園風景を描いたバルビゾン派(ルソー、コロー、ミレー)」「印象派の画家とアメリカ」・・・・・。
 最近、目黒区内で発生した児童虐待事件をはじめとして、児童の「虐待事件」「餓死事件」「置き去り死事件」「遺体放置事件」が続いている。児童虐待は10万件を越え、増え続けている。本書は「児童虐待を考える」ではなく、「児童虐待から何が見えてくるか」「社会は家族に何を強いてきたか」を現場の実態から問いかけている。
最近、目黒区内で発生した児童虐待事件をはじめとして、児童の「虐待事件」「餓死事件」「置き去り死事件」「遺体放置事件」が続いている。児童虐待は10万件を越え、増え続けている。本書は「児童虐待を考える」ではなく、「児童虐待から何が見えてくるか」「社会は家族に何を強いてきたか」を現場の実態から問いかけている。
現場を歩いているだけに、表面的に言われている話とは随分違う。「作られた"残酷な父親"像」「親としての過剰な『生真面目さ』」「育てる力が乏しい親、それを支えない社会」「助けを求めることを知らない親たち」「社会に不信感を抱きつつ、その規範に過剰に従う」「完璧な母であれ」「社会につながれない"ニューカマー"たち」「子育てには家族という器がいる。しかし家族の凝集力が失われている現代」「母子家庭の貧困の根深さ。とくにニューカマー(例えばフィリピン人女性たち)」「育児は母親だけの義務か? 母性から降りる、共同体で支援する」・・・・・・。
そして、現場を歩くと、10年間で高度成長期につくられた近代家族の変容が見えてくる。「子どもを連れての住居移動」「母子家庭の増加」「性行動の活発化と離婚の増加」「安定した就労の困難」「性産業への一般女性が参入する敷居の低下」「ネット、SNS等メディアの進化」「虐待が脳を損傷させるなどの研究の進歩」「人の孤立化の進行」などだ。
新しい子育て社会をどうつくるか。厚労省の出した新しい社会的養育ビジョンにどう現実的魂を入れるか。児相など各部署での職員の力量アップ。親のキャパシティをどうバックアップするか。地に足をつけた問題提起がされている。
 日露戦争前の帝政ロシアのウラジオストク。明治初期の1871年、函館の大火で孤児となったところを寄港していたイリーナ号の由松に拾われてウラジオストクにやって来た「お吟」。ペトロフ家に入って2か月後、彼女を引き取った夫婦は、やがてお吟を娼妓「浦潮吟」としてこき使う。20歳の1887年、ウラジオストクに商会を構えるグリゴーリィ・ペトロフに再び養女として迎えられ、令嬢として活躍する。波乱万丈の苦難のなか育ったお吟は賢く、度胸も知恵もたくましさもあり、凛として生きる。小型拳銃も持ち、修羅場を切り拓く鉄火場の女でもある。
日露戦争前の帝政ロシアのウラジオストク。明治初期の1871年、函館の大火で孤児となったところを寄港していたイリーナ号の由松に拾われてウラジオストクにやって来た「お吟」。ペトロフ家に入って2か月後、彼女を引き取った夫婦は、やがてお吟を娼妓「浦潮吟」としてこき使う。20歳の1887年、ウラジオストクに商会を構えるグリゴーリィ・ペトロフに再び養女として迎えられ、令嬢として活躍する。波乱万丈の苦難のなか育ったお吟は賢く、度胸も知恵もたくましさもあり、凛として生きる。小型拳銃も持ち、修羅場を切り拓く鉄火場の女でもある。
戦乱への序曲、民族間の確執・策謀・文化的差異、シベリア鉄道開発、捕鯨や漁業、鉱山開発、荒くれの人夫、遊郭、流血の抗争・・・・・・。多民族が入り乱れる陰謀渦巻く時代状況、そしてロシアにとって重要な極東の港・ウラジオストクにはそうした矛盾が集約される。スラム街・ミリオンカには、その闇が集結する。
激しく厳しい事件の連続だが、美しい坂の港町である函館とウラジオストク。厳しい環境のなか心を通わせ合う人々の絆、四季折々の花がバクコーラスのように奏でられる。
 「10才の章子へ こんにちは、章子。わたしは20年後のあなた、30才の章子です。・・・・・・」。大好きなパパ(佐伯良太)を亡くしたばかりの章子に、突然不思議な一通の手紙が届く。"人"になったり"人形"になったり、体も精神的にも弱いママ(文乃)と2人で暮らしていくことになる章子。ママはいつから、どうしてこのようになったのだろう。そのママと樋口の名も故郷を捨てて、パパはなぜ結婚したのだろう。学校では、優秀だが、イジメにもあっている章子。新しく父親的存在になる男からの暴力・・・・・・。章子が交差する数少ない友人・知人のなかで次々起きるいじめ、虐待、自殺、放火・・・・・・。
「10才の章子へ こんにちは、章子。わたしは20年後のあなた、30才の章子です。・・・・・・」。大好きなパパ(佐伯良太)を亡くしたばかりの章子に、突然不思議な一通の手紙が届く。"人"になったり"人形"になったり、体も精神的にも弱いママ(文乃)と2人で暮らしていくことになる章子。ママはいつから、どうしてこのようになったのだろう。そのママと樋口の名も故郷を捨てて、パパはなぜ結婚したのだろう。学校では、優秀だが、イジメにもあっている章子。新しく父親的存在になる男からの暴力・・・・・・。章子が交差する数少ない友人・知人のなかで次々起きるいじめ、虐待、自殺、放火・・・・・・。
とにかく最後までつらい。とくに出てくる女性がいずれも皆、酷い目にあい、想像を絶するどん底の闇に落される。"人形"という病に化して遮断しなければ生きられない究極の絶望。そのなかでパパ、ママ、章子の揺るぎない愛情。その中心軸が、時間のなかに細くも芯の通った生命線として貫かれる。ママの心をこそのぞきたくなるが、それこそ読者が感じ取るものなのか。
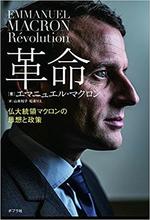 仏大統領マクロンが、自らの生いたち、仏の再興戦略、難民・移民とテロ、EUの政治・経済の展望等を率直に語る。解説する池上彰氏は「通底する思想は、一言で言えば『アンガージュマン』。人々の政治参加による新たな『フランス革命』なのだ」といい、増田ユリア氏は「右でも、左でもない。前へ!(自由・平等・友愛の精神は前進あるのみ)」という。
仏大統領マクロンが、自らの生いたち、仏の再興戦略、難民・移民とテロ、EUの政治・経済の展望等を率直に語る。解説する池上彰氏は「通底する思想は、一言で言えば『アンガージュマン』。人々の政治参加による新たな『フランス革命』なのだ」といい、増田ユリア氏は「右でも、左でもない。前へ!(自由・平等・友愛の精神は前進あるのみ)」という。
感ずるのは、「仏・EUの再建への意欲」「左右ではなく、上下。下からの改革」「難民・移民やテロ等に対する冷静かつ真剣な姿勢」「仏と欧州に蓄積してきた歴史・文化を踏まえた思想と戦略」等々だ。遭遇している困難さは、日本と同種の経済・社会保障・働き方・教育等の問題もあるが、外交・安全保障・EUとその周辺諸国関係等は明らかに違う。
マクロンの主張はかなりシンプルに凝縮される。例えば対テロ。「分裂や憎悪の言葉にはけっして屈せず、自由のために全力を尽くすこと。イスラム教がフランスのなかに真の居場所を持つことができるよう手助けをすること。ただし、フランスの理念についてはけっして譲らず、自分たちは例外だとするあらゆる共同体主義と闘うべきである」。また例えばユーロ圏。「十年かけて税制、社会対策、エネルギー問題の一律化を達成しなければならない。これはユーロ圏の核となる政策になるだろう。さもなければユーロ圏は空中分解してしまう。それには、2年以内に真の政治的決断が前提となる。・・・・・・共通の予算と迅速に実行されるべき投資力を中心に経済格差を縮めていくことにある」・・・・・・。

