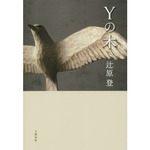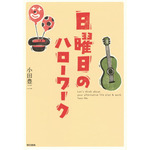 こんな職業があったのか、そう思う。「歌うセールスマン」「縁日の露天商」「大相撲のタニマチ」「聞き書き作家」「金魚チャンピオン」「クラウン(パフォーマー)」「コンビニアイス評論家」「銭湯絵師」「宝くじの販売」「農家民宿主人」「フラメンコ・ダンサー」「モデラー(ジオラマ作家)」「屋形船の船頭」――。
こんな職業があったのか、そう思う。「歌うセールスマン」「縁日の露天商」「大相撲のタニマチ」「聞き書き作家」「金魚チャンピオン」「クラウン(パフォーマー)」「コンビニアイス評論家」「銭湯絵師」「宝くじの販売」「農家民宿主人」「フラメンコ・ダンサー」「モデラー(ジオラマ作家)」「屋形船の船頭」――。
「二足のわらじ」を履いているが、いずれも本気で、プロだ。「サイドビジネス」や「小遣い稼ぎ」や「副業」といった生活の臭いのするものではなく、「個人的な"夢"や"理想"、さらにはその人がその人であることを証明する『尊厳』に近いものだ」という。本気と一生懸命で素人を突き抜けた楽しさが伝わってくる。
最後の「今日という日は、残りの人生の最初の日だ」(チャールズ・ディードリッヒ)という言葉が、"体操の見事な着地"のようにビシッと響く。
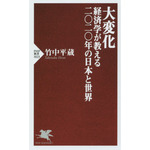 「決められない政治」「短命内閣」が続いてきたが、安倍内閣の3年は、茨の道が続いてはいるが、「未来を構築する政治」「前に進む政治」が始まったと思う。今、世界は、社会は大きく変化している。「経済学が教える2020年の日本と世界」と副題にあるが、「『どうなる』ではなく『どうする』かだ」「2020年東京五輪は、日本にとって最大かつ最後のチャンス」という。同感だ。
「決められない政治」「短命内閣」が続いてきたが、安倍内閣の3年は、茨の道が続いてはいるが、「未来を構築する政治」「前に進む政治」が始まったと思う。今、世界は、社会は大きく変化している。「経済学が教える2020年の日本と世界」と副題にあるが、「『どうなる』ではなく『どうする』かだ」「2020年東京五輪は、日本にとって最大かつ最後のチャンス」という。同感だ。
時代の「大きな流れ」が提示されるが、結論は「課題も多いが日本の未来は明るい」ということ。いや「明るくしよう」ということだ。「改革のモメンタムが到来する」「アジアの中間所得層はあと数年で3.5倍に膨張する」「グローバリゼーションは選択ではなく、事実としてある」「"仲間"と"英語"で生き残れ」「2027年、リニア新幹線で世界最大のメガリージョンが生まれる」「"正社員"より"自由な働き方"をめざす時代」「終身雇用・年功序列の強要は時代不適合」「同一労働、同一条件の実現に向けて」「雇用で重要なのは多様性と柔軟性」「2020年の日本の姿」「日本の農業の未来はオランダ式、土地の広さではない」「突破口となる国家戦略特区」「空港のコンセッションで地域活性化」「"日本版DMO"を外国人観光客誘致のテコに」「社会保障の主役を若者に」「やるべきことをやれば財政問題は解決できる」「世界経済、変化する者だけが生き残る」・・・・・・。
「どうするか」を考える「未来予想図」が提示される。
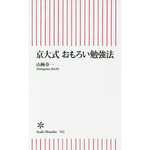 京大総長になっているのが、世界的なゴリラの研究者ということ自体が面白い。これは"勉強法"ではなく、人間学、人間論だ。サル、ゴリラ、人間――。ゴリラを通して人類の由来や人間とはどんな動物であるかが浮き彫りにされる。それに、アフリカの人たちとの付き合い、フィールドワークが付加され、対話や対人関係の術がいかに大事かを学ぶことができる。
京大総長になっているのが、世界的なゴリラの研究者ということ自体が面白い。これは"勉強法"ではなく、人間学、人間論だ。サル、ゴリラ、人間――。ゴリラを通して人類の由来や人間とはどんな動物であるかが浮き彫りにされる。それに、アフリカの人たちとの付き合い、フィールドワークが付加され、対話や対人関係の術がいかに大事かを学ぶことができる。
「"時間を切断してしまう"文明の利器」「"共にいる"関係を実らせてこそ幸福感」「ニホンザルとゴリラの目の合わせ方」「食事や会話は、対面を持続させる」「ゴシップが道徳をつくった(生の会話、うわさ話、雑談が大事で、文字情報だけで世界を判断しない)」「言葉より"構え"を磨け」「"分かち合って"食べる、飲む」「同調するなら、酒を飲め」「酒は"ケ"から"ハレ"へのスイッチ」「恋と動物」・・・・・・。
きわめてすぐれた人間学、人間論が自身の蓄積のなかで語られる。
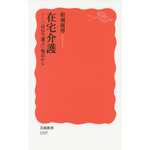 団塊の世代が75歳以上となる2025年問題。私はそれが80歳以上となる2030年問題がより深刻だと思うが、介護の問題は切羽詰まった段階に来ている。
団塊の世代が75歳以上となる2025年問題。私はそれが80歳以上となる2030年問題がより深刻だと思うが、介護の問題は切羽詰まった段階に来ている。
副題に「『自分で選ぶ』視点から」とあるように、介護の実態をわかりやすく説明している。「施設介護から在宅介護へ」は政府の大方針だが、施設も在宅介護も困難に直面している。「在宅介護の困難さ」「サ高住」「介護離職者10万人」「パラサイトシングル介護者の増加」「認知症高齢者の急増」「地域包括ケアシステム」「施設あっての在宅介護」「看護と介護(医療と介護の表裏一体)」「介護士不足」「介護保険制度の改正がもたらしているもの」「あるべき在宅介護と財源論」・・・・・・。
「介護」については、たしかにキメ細かく体制をとってきた。しかし、高齢者急増の大波に応える体制が財源的にも整えられない。医療も含めて"担い手"の不足がより深刻化している。さらにそもそも高齢者はどう生きていくか、生活していくか、という根源の問題が重くのしかかっていて厳しさを増している。裕福で人にも恵まれている高齢者は少ない。本書は現場の実態と「介護のあり方」の道筋を冷静に示している。