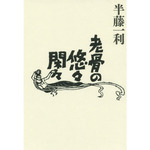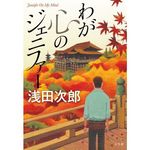 ニューヨーク育ち、父母の離婚で米海軍大将の祖父に厳しく育てられた青年・ローレンス・クラーク。恋人のジェニファー・テーラーに告白しようとしたところ、日本びいきの彼女は「プロポーズの前に、日本を見てきてほしい。ひとりでゆっくりと」という。
ニューヨーク育ち、父母の離婚で米海軍大将の祖父に厳しく育てられた青年・ローレンス・クラーク。恋人のジェニファー・テーラーに告白しようとしたところ、日本びいきの彼女は「プロポーズの前に、日本を見てきてほしい。ひとりでゆっくりと」という。
成田に降り立った瞬間から、見るのと聞くとは大違い。「日本はハワイの先にあるのではなく、固有の文明を持つ遥かな異国だった」と、カルチャーショックを受けるとともに、父母と離れて育った人生をも振り返り思考する時間をもつ。現在急増しているインバウンドの日本再発見小説ともなっている。東京、京都、大阪、別府、そして銀座から丹頂鶴の舞う釧路へ・・・・・・。
アメリカ人のいう「ネバー・ルック・バック ゴー・アヘッド(けっして振り返るな、前へ進め)」。しかし祖父はいう。「ブリッジに立っていても、船がまっすぐ進んでいるかどうかはわからない。常に航跡を振り返れ」と。そして、彼がなぜ日本に共感するのか。心奥に日本の社会と文化の共鳴盤をもつ出生の秘密にたどりつく。そして絶滅寸前であった丹頂鶴を100年間にわたって育て続けてきた善行の背後に「自然は目に見える神だということ。施すのではなく、仕えるのだということ。過不足のない平等、それこそが真実の愛」という依正不二の生命観の世界があることを静かに示す。
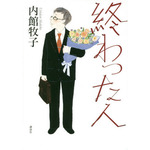 定年後の人生は長い。「悠々自適」「好きなことに時間をかける。趣味に、旅行に」「ゆっくり夫婦で」などというのは恐らく3カ月だけ。多くの人は「やり切った。会社人生に思い残すことはない」などという感覚をおそらくもたない。内館さんは「成仏してない」という。もう一回挑戦したいと思っても、社会は「終わった人」と見る。着地点に至るまでの人生が恵まれていても「かえって"横一列"を受け入れられない不幸もある」のだ。
定年後の人生は長い。「悠々自適」「好きなことに時間をかける。趣味に、旅行に」「ゆっくり夫婦で」などというのは恐らく3カ月だけ。多くの人は「やり切った。会社人生に思い残すことはない」などという感覚をおそらくもたない。内館さんは「成仏してない」という。もう一回挑戦したいと思っても、社会は「終わった人」と見る。着地点に至るまでの人生が恵まれていても「かえって"横一列"を受け入れられない不幸もある」のだ。
「年齢や能力の衰えを泰然と受け入れることこそ人間の品格」「重要なのは品格のある衰退(坂本義和)」というが、人生も街づくり(コンパクトシティ)も「上手に縮む」のは簡単ではない。「思い出と戦っても勝てねンだよ」とはプロレスラーの武藤敬司さんの名言で、本書でも何度も出てくる。たしかに定年後、美化された思い出ばかりと格闘しがちになろう。
「介護」「認知症」「下流老人」・・・・・・。これも深刻だが、元気な高齢者の居場所、孤独、暴走老人も大きな問題だ。全ての人に定年が来る。秋が来る。そして今やなかなか死が来ない。そして生老病死の人生の着地点は大差がないものだ。内館さんのこの小説で、様々なことを360度にわたって考えさせられた。
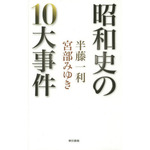 異色の対談だが、いい語らいが続く。驚愕の事件そのものを取り上げているというより、その事件を生み出した社会的背景を述べている。生の言葉で語られるがゆえに、説得力をもつ。
異色の対談だが、いい語らいが続く。驚愕の事件そのものを取り上げているというより、その事件を生み出した社会的背景を述べている。生の言葉で語られるがゆえに、説得力をもつ。
10大事件は「昭和金融恐慌」「2.26事件」「大政翼賛会と三国同盟」「東京裁判と戦後改革」「憲法第9条」「日本初のヌードショー」「金閣寺焼失とヘルシンキ・オリンピック挑戦」「第五福竜丸事件と『ゴジラ』」「高度経済成長と事件――公害問題・安保騒動・新幹線開業」「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(宮崎勤事件)」だ。昭和の時代は戦争が傷となり、トラウマとなり、その記憶は癒えず、体験を引きずっている。20年代終わりからは私も明確に覚えている。
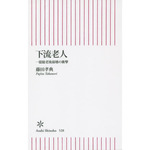 「一億総老後崩壊の衝撃」と副題にある。今後さらに下流老人(生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびその恐れがある高齢者)が大量に生まれ、日本社会に衝撃を与えるが、現在の若者の多くは下流老人と化す。
「一億総老後崩壊の衝撃」と副題にある。今後さらに下流老人(生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびその恐れがある高齢者)が大量に生まれ、日本社会に衝撃を与えるが、現在の若者の多くは下流老人と化す。
貧困の問題というと「絶対的貧困」とか「最貧困女子」などが取り上げられるが、「下流老人の問題は、絶対的貧困も含むが、相対的貧困が主体であるため、貧困が見えにくい。相対的貧困は、共同体の大多数と比べて著しく生活水準が低く、必要なものが足りないということだ」といい、この問題を安易に捉えてはならないと指摘する。
下流老人は3つのない――収入が著しく少「ない」、十分な財蓄が「ない」、頼れる人間がい「ない」(社会的孤立)――が特徴だが、「あらゆるセーフティネットを失った状態」と言う。ごく普通のサラリーマンであった人が65歳の時点で「資産(貯金+退職金)」「年金」で暮らそうと思っても、80歳を過ぎるとその資産が底をつく。途中、「病気」になった時(誰しもだが)、その結果は明らかだ。2025年問題というが、団塊の世代が80歳を超えた2030年問題への備えをどうするか。本書は、個人も国も今何をすべきかを、かなりストレートに具体的に踏み込む。