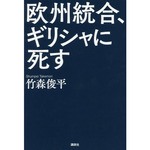 ギリシャ問題の解決は難しい「終わらない危機」だ。まずギリシャという国が、歴史的にも地政学的にも重要であるとともに、1820年から今年2015年までの195年間のうち90年以上が「債務不履行期間」に当たる"常習犯"であるということだ。そして今もチプラス政権の迷走、支離滅裂な行動は続いている。そして「ユーロという仕組みは"矛盾"を内包した仕組みです。そこにはドイツとフランスという二つのリーダー国の根本的な思想の違いに起因する"矛盾"が存在する」「欧州統合は、フランスにとっては文化的な"夢"であり、ドイツにとっては経済的な"現実"であり、ユーロ加盟国に厳格なルールを導入しようとしている(欧州統合の夢か、ゲルマン・エリート・クラブか)」という根本矛盾が背景にあると指摘する。
ギリシャ問題の解決は難しい「終わらない危機」だ。まずギリシャという国が、歴史的にも地政学的にも重要であるとともに、1820年から今年2015年までの195年間のうち90年以上が「債務不履行期間」に当たる"常習犯"であるということだ。そして今もチプラス政権の迷走、支離滅裂な行動は続いている。そして「ユーロという仕組みは"矛盾"を内包した仕組みです。そこにはドイツとフランスという二つのリーダー国の根本的な思想の違いに起因する"矛盾"が存在する」「欧州統合は、フランスにとっては文化的な"夢"であり、ドイツにとっては経済的な"現実"であり、ユーロ加盟国に厳格なルールを導入しようとしている(欧州統合の夢か、ゲルマン・エリート・クラブか)」という根本矛盾が背景にあると指摘する。
ギリシャは今、極端な緊縮財政がとられ、GDPは2008年から1/4ほど消滅し、失業率は25%と大恐慌時のアメリカ並み、若年者の失業率は50%以上、今後さらに第三次支援策の下でも強引な緊縮策が予定される。
ギリシャの危機は、ギリシャを超えて「ユーロ自体の存続の問題」にまで拡大しているが、竹森さんは一つの解決法としてドイツ、フランスが交わりようのないそれぞれの考えのなかで、「ギリシャは特例だ」という認識をもち、「一番無理のない方法でいずれにしても必要な"債務の減免"を実行する」ことだと提起する。今年のギリシャ、独仏、IMF等の動きを丁寧に分析し、その構造を解説している。
増田さんの「地方消滅――東京一極集中が招く人口急減」と、冨山さんの「なぜローカル経済から日本は甦るのか――GとLの経済成長戦略(通称GL本)」の両著は昨年、すぐれたというだけでなく、地方創生戦略に大きな影響を与えた。私も国交省の「国土のグランドデザイン2050」と「インフラ・ストック効果」の2つを交えて、増田さん、冨山さんとそれぞれ対談を行った。
時代、社会は動いている。変化している。東京も地方も、そして日本も、「人口減少」「高齢化」「迫る大災害」「グローバリゼーションのなかでの都市間競争の激化」「進むICT」等々を凝視し、今、戦略的に対応しないと生き残れない。「GとLは違う」「地方で人出不足の時代が来ている」「生産性を向上できれば、賃金が増え、夫婦で500万の年収が得られるようにできる」「その生産性向上の余地があるのは圧倒的にローカル経済圏だ」「データに基づいて考えよ。デマに惑わされるな」「企業の生産性向上は安い賃金の雇用や失業によっての時代とは異なる。人出不足の時代の生産性向上、地方発のイノベーションの時代だ」「地方創生は中央創生」・・・・・・。3人で活発に対談しているかのように読んだ。
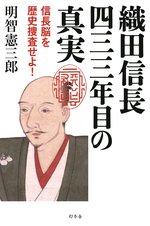 天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変とは何であったか――信長とは、光秀とは・・・・・・。前著「本能寺の変 431年目の真実」に続いての書。前著は光秀を中心にして科学的、論理的、文献の証拠をあげての徹底解明だが、本書は信長の思考と戦略に迫る。副題の「信長脳を歴史捜査せよ!」だ。
天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変とは何であったか――信長とは、光秀とは・・・・・・。前著「本能寺の変 431年目の真実」に続いての書。前著は光秀を中心にして科学的、論理的、文献の証拠をあげての徹底解明だが、本書は信長の思考と戦略に迫る。副題の「信長脳を歴史捜査せよ!」だ。
「生存合理性を追求した武将が"無策・無謀"で謀反に飛躍することはあり得ない」「信長への恨みなどから1人で謀反を決意したという怨恨説・野望説は誤り」「秀吉が後に家臣に書かせた『惟任退治記』や『甫庵信長記』は創作話だ」「長曽我部征伐が不可避であることを知って、光秀は謀反を最終決断した」「密室で信長と光秀の2人で家康討ちを打合せている。備中出陣そのものが家康討ちのための偽装工作だった」「家康が謀反を起こして自分を殺そうとしたので返り討ちにしたという理由付けを信長は考え、本能寺に入り、舞台をつくった(無警戒で本能寺にいたのではない)。しかし、光秀の謀反を見抜けなかった」・・・・・・。
そして信長、秀吉の「唐入り」が問題の底流を形成した。つまり「(秀吉は)諸国の領主を籠絡し服従させた後には、彼らをシナ征服という企てに駆り立てようとした。・・・・・・唐入りに対する恐怖が国中に広まり、唐入りを止めるために謀反が起きるであろうと、人々は考えていた。・・・・・・秀頼が生まれる1年4カ月も前に秀吉は関白秀次の明への放逐を考えた」「信長は唐入りの着想をどこから得たのか。・・・・・・スペインの海外征服の知識を信長に与えたのはイエズス会である」――。近くを、そして国内を身内で固め、遠くに武将を置こうとしたのだ、という。
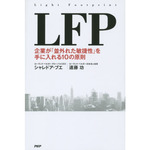 時代の経営環境は大きく変わり、乱気流の様相を呈している。しかしそれが常態化し、いつか安定飛行に戻るという甘い考えは通用しない。そうした未知なる経営環境は「VUCA(ブカ)」と呼ばれる。不安定で不確実性が高く、複雑で不明確・不透明な環境ということだ。
時代の経営環境は大きく変わり、乱気流の様相を呈している。しかしそれが常態化し、いつか安定飛行に戻るという甘い考えは通用しない。そうした未知なる経営環境は「VUCA(ブカ)」と呼ばれる。不安定で不確実性が高く、複雑で不明確・不透明な環境ということだ。
その乱気流の時代に勝ち残る経営は「LFP(ライト・フットプリント)=足跡が残らないほど、敏捷で変化に柔軟な経営」でなくてはならない。それも並外れた敏捷性、並外れた柔軟性、並外れた創造性をもつことだ。伝統の大企業・組織にありがちな「遅い」は致命傷だ。それを確立するためには(1)中央集権と自己分散の両立(現場に大きな権限)(2)協働協創(3)相互信頼(4)隠密潜行――が重要だという。
その変革の実例、取り組みとして「グーグル」「ウーバー」等をあげつつ、(1)本社主導から現場主導(現場力こそ最先端の経営)(2)体格一辺倒から体質重視(3)戦略至上から戦術重視(4)革新から改善重視(5)個人依存からチーム重視――などをあげる。そして、これらに挑戦している「シュナイダーエレクトリック」「ZARA」「BMW」「東レ」「セブン&アイ・ホールディングス」「トヨタ」の6社をあげている。「体内時計を入れ替えよ」「ダイナミックに"時間"を買え」「常に現場」「初にこだわる」「タスクフォースを編成せよ」――まさにその通りだ。経営資源は「ヒト・モノ・カネ」に情報が加わったが、今はそれに「時間(スピード)」が第5の経営資源になった。だからLFPだとの主張はその通りだ。
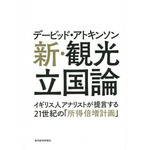 外国人観光客が一気に増え、本年は1900万人台後半になる見通しだ。経済成長は最重要で、生産性向上が不可欠だが、「効率性向上は、人口減少を吸収するくらいの力はあっても、GDPを成長させるほどの力はない。GDPは主に人口によって決まる。ならば、外国人観光客をたくさん呼んで、お金を落としてもらえばいい」「日本は世界有数の観光大国になれる潜在力がある。しかし、日本はそれと、ほど遠い観光後進国だ」「日本は観光立国の4条件『気候・自然・文化・食事』を満たす稀有な国だ」「観光は世界的に発展・増大している。観光を一大産業と自覚し、"観光鎖国・ニッポン""自画自賛・思い込み・勘違い"を排し、相手のニーズとビジネスの視点、"お金を落としてもらう"という発想に立て」・・・・・・。きわめて示唆に富む提案が続く。
外国人観光客が一気に増え、本年は1900万人台後半になる見通しだ。経済成長は最重要で、生産性向上が不可欠だが、「効率性向上は、人口減少を吸収するくらいの力はあっても、GDPを成長させるほどの力はない。GDPは主に人口によって決まる。ならば、外国人観光客をたくさん呼んで、お金を落としてもらえばいい」「日本は世界有数の観光大国になれる潜在力がある。しかし、日本はそれと、ほど遠い観光後進国だ」「日本は観光立国の4条件『気候・自然・文化・食事』を満たす稀有な国だ」「観光は世界的に発展・増大している。観光を一大産業と自覚し、"観光鎖国・ニッポン""自画自賛・思い込み・勘違い"を排し、相手のニーズとビジネスの視点、"お金を落としてもらう"という発想に立て」・・・・・・。きわめて示唆に富む提案が続く。
そして、「上客を呼ぶ」「文化財を活用し"稼ぐ文化財"に」「観光戦略は滞在日数から逆算せよ」等々、具体例を示しつつ、「2030年までに8200万人を招致することも不可能ではない」という。いずれにしても観光は、新たな段階に突入しており、国も自治体も観光地も新たな戦略で挑む時が来た。

