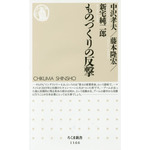 「我々3人は、バブル経済時にも、その後の不況期にも、金融危機時にも、円高で日本産業空洞化が叫ばれた時期にも、リーマンショック時も大震災の時も、良い現場を作り、(良い現場を)日本に残せと一貫して言い続けた。しかし今、ポスト冷戦期の低賃金国優位の局面が一段落し、グローバル能力構築競争の時代が来つつある中で我々は、日本を起点として"世界中に良い職場を残せ"と呼びかける時代になってきたと感じる」という。冷戦終結後のグローバル競争のなかで、最も激戦地であった貿易財の領域で、賃金20分の1の中国の登場をはじめ、数々のハンディを背負いながら、逆境に耐え、鍛え、強くなり、持続してきたのが、今の日本の貿易財現場だ。産業空洞化論を言っていた論者が、今度は国内回帰論を言ったりしているが、どちらも本質論から外れ、右往左往しているだけだ。国内には鍛え上げられた「良い現場」がある。国内と海外の同時強化が大きな流れだ。ずっと中小企業の現場を見続けてきた人の指摘であり、説得力がある。
「我々3人は、バブル経済時にも、その後の不況期にも、金融危機時にも、円高で日本産業空洞化が叫ばれた時期にも、リーマンショック時も大震災の時も、良い現場を作り、(良い現場を)日本に残せと一貫して言い続けた。しかし今、ポスト冷戦期の低賃金国優位の局面が一段落し、グローバル能力構築競争の時代が来つつある中で我々は、日本を起点として"世界中に良い職場を残せ"と呼びかける時代になってきたと感じる」という。冷戦終結後のグローバル競争のなかで、最も激戦地であった貿易財の領域で、賃金20分の1の中国の登場をはじめ、数々のハンディを背負いながら、逆境に耐え、鍛え、強くなり、持続してきたのが、今の日本の貿易財現場だ。産業空洞化論を言っていた論者が、今度は国内回帰論を言ったりしているが、どちらも本質論から外れ、右往左往しているだけだ。国内には鍛え上げられた「良い現場」がある。国内と海外の同時強化が大きな流れだ。ずっと中小企業の現場を見続けてきた人の指摘であり、説得力がある。
アメリカ型の「IoT」のイノベーションは、上空のICTの世界から降ってくるタイプだが、それに対して製造業の現場という下界から反攻するというのがドイツの「インダストリー4.0」の言い分だろうが、それは中間あたりというべきもので、結局、地上の現場でのFAの改善を一番やっているのは日本だ、という。
「オタオタして自己否定するな」――苦境の25年を生き延びた日本の優良現場の粘りは大したものだ。それを直視して日本は戦略的に取り組むことが大事だという。きわめて論理的、かつ感動的でさえある。
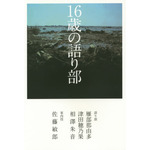 東日本大震災から5年、あの日小学5年生だった3人は今、高校生。3人が「16歳の語り部」として語ってくれた、「あの日」「その後」そして「今と未来」――。
東日本大震災から5年、あの日小学5年生だった3人は今、高校生。3人が「16歳の語り部」として語ってくれた、「あの日」「その後」そして「今と未来」――。
「"被災者に寄り添う"とはどういうことか」「心の復興とはどういうことか」「復興とは政治がやるなどというものではなく、被災した人たちが、苦しみをかかえながらも、普通に生きるようになること」など、さまざま考えながら声を聞いた。
「親に心配をかけたくない。気持ちを吐き出すことのない子どもが求めたものとは」「立ち直るということ。私生きていても大丈夫じゃん。・・・・・・強く・・・・・・とは言えないけど、生きていこう」「大人たちは、子どもたちのことをそっと見守ってあげていてください」「"もっと話をしておけばよかった"といっても失ったものは戻ってきません。これまで僕は、大切なことをずっとないがしろにしていたんだな・・・・・・。いちばん大切なのは、1日1日を大切に生きていくこと。そう思って僕は、16歳の今を過ごしています」「記録することも大切だけど、もっと生の実際の人と人との関わりを、本当に大切にしていってほしい。・・・・・・私は、ちゃんと相手のことを、目や耳や胸に焼きつけながら生きていきたい」・・・・・・。
3人に接した東京の高校生・山城未裕さんに「やっぱり、無為に過ごしていたんです。・・・・・・1回しかない人生なのに、スカスカの日常で終わるなんて、絶対に『あり得ない!』と今は思ってます」とまでいわせた「語り部」の力。解説・評論を越えた世界を拓いてくれている。
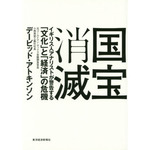 「イギリス人アナリストが警告する『文化』と『経済』の危機」と副題にある。労働人口や国内市場が縮小し、社会保障財源が厳しくなるなかで、観光立国が日本経済の重要な柱となる。話題を呼んだ「新・観光立国論」に続いての観光立国推進への第2弾が本書。
「イギリス人アナリストが警告する『文化』と『経済』の危機」と副題にある。労働人口や国内市場が縮小し、社会保障財源が厳しくなるなかで、観光立国が日本経済の重要な柱となる。話題を呼んだ「新・観光立国論」に続いての観光立国推進への第2弾が本書。
「観光立国実現のためには、国宝をはじめとする文化財が大きなハードルとなっている」「外国人観光客は、文化財観光に魅力を感じている。しかし、日本は観光戦略を重視してこなかったし、文化財が観光資源として整備されていない」「日本の文化行政は、明治以来、『優れたものを選定し、税金(補助金)を投入して手厚く守る』という考え方が根強い」「日本社会から伝統的な日本文化が消滅しつつある。観光客にお金を出してもらって文化財維持に貢献してもらうことだ」「保護ではなく、観光資源化。文化財行政の大転換が迫られている」・・・・・・。
そうした問題提起は、どんどん現実に踏み込み、具体的に矛盾や歪みを剔抉する。「建物見物から文化の実感へ」「判断するのは客」「文化財専門家の功罪」「文化財指定の"幅"が狭い」「文化財指定に観光の視点を」「安い拝観料を誰のため?一見消費者主義に見えるが、実は供給主義的考え方だ」「本当に職人はいないのか」「京漆器は日本産なのか」「補助金で支えるのは職人か社長か」「営業や情報発信の発想があまりに少ない」「職人文化を育てるためには生活保護的サポートでなく豊富な仕事量を」・・・・・・。1つ1つきわめて的確。観光立国、文化財行政の大転換の時はまさに今だ。
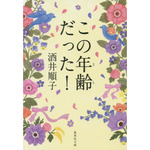 27人の有名な女性の「人生における転機」となった年齢にスポットを当てる。よくある武将の列伝や近代日本を創った経営者の列伝は大体常だが、女性を描いて面白い。「多くの女性達の転機を見ていると、彼女達は皆、転機を利用することが上手」「荒波に呑み込まれたとしても、彼女達は必ず浮かび上がってくる」「荒波に呑み込まれたからこそ、そこで浮かび上がる術を覚えた、と言いましょうか」と酒井さんは言う。
27人の有名な女性の「人生における転機」となった年齢にスポットを当てる。よくある武将の列伝や近代日本を創った経営者の列伝は大体常だが、女性を描いて面白い。「多くの女性達の転機を見ていると、彼女達は皆、転機を利用することが上手」「荒波に呑み込まれたとしても、彼女達は必ず浮かび上がってくる」「荒波に呑み込まれたからこそ、そこで浮かび上がる術を覚えた、と言いましょうか」と酒井さんは言う。
27人に共通項があるかと思えば、そうでもない。宇野千代のように健康で、明朗。「人でも着物でも文学でも『好き』だと思ったら、一気にそちらに駆けていく」「『好き力』とでも言う力が、人並み外れて強い人」もいれば、オードリー・ヘップバーンのように「彼女は常に自信のなさを抱えていた。容貌にも・・・・・・」「人前に出るとどうしようもなく緊張してしまうという性分は一生変わらなかったようです」という人もいる。山口百恵のように「鮮やかな引き際で、1人の女房として意志を貫く人」もいれば、「あれもこれも貪欲に手をいれ、むしろ結婚後に女を上げ、そこまで頑張る聖子ちゃんは偉いとファンに言わしめる人」もいる。
同時代を生きる清少納言と紫式部、早く逝った金子みすゞと樋口一葉、マドンナとレディー・ガガ、マザー・テレサとマーガレット・サッチャー・・・・・・。27人の女性偉人が並ぶと1人1人が対比のなかでも鮮やかに増幅する。真摯に人生に向かいあった様々な生き方、生き様はまさに偉人だ。
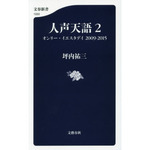 オンリー・イエスタデイ 2009-2015。政権交代の2009年から昨年までの6年間、坪内さんの「文藝春秋」連載コラムを集めたもの。「中川昭一財務・金融大臣の記者会見事件」「鳩山・菅らの団塊の世代内閣誕生」「3・11と石原慎太郎の『天罰』発言」「浅草から映画館が消える時」「テレビのワイドショーはますますひどくなってゆく」「井の頭線には何の罪もないのに」「私もまた『あまちゃん』にはまっている」「2020年の東京オリンピックに私が反対する理由」「私の住む町からCDショップが消えた」「ポール・マッカートニーのコンサートは素晴らしかった」「常盤(新平)さんも山口(昌男)さんもいない新たな年」「増税と『笑っていいとも!』の終了が重なった春」「名画座はもはや滅び行く空間なのだろうか」「かつての予備校――代ゼミや駿台はまるで旧制高校のような場所だった」「マイフェーバリット"健さん"はどの作品だろう」「国立西洋美術館は気持ち悪い」・・・・・・。心に残る多くの方が次々とこの世を去っていく。生活に最も近い文化・芸術・芸能・音楽・映画・テレビなどがどんどん動いていく。大相撲の話題がとても多く取り上げられている。その時の白鵬、その時の魁皇、その時の稀勢の里、優勝した旭天鵬、そして雅山、北の湖、遠藤・・・・・・。くっきりと思い出す。
オンリー・イエスタデイ 2009-2015。政権交代の2009年から昨年までの6年間、坪内さんの「文藝春秋」連載コラムを集めたもの。「中川昭一財務・金融大臣の記者会見事件」「鳩山・菅らの団塊の世代内閣誕生」「3・11と石原慎太郎の『天罰』発言」「浅草から映画館が消える時」「テレビのワイドショーはますますひどくなってゆく」「井の頭線には何の罪もないのに」「私もまた『あまちゃん』にはまっている」「2020年の東京オリンピックに私が反対する理由」「私の住む町からCDショップが消えた」「ポール・マッカートニーのコンサートは素晴らしかった」「常盤(新平)さんも山口(昌男)さんもいない新たな年」「増税と『笑っていいとも!』の終了が重なった春」「名画座はもはや滅び行く空間なのだろうか」「かつての予備校――代ゼミや駿台はまるで旧制高校のような場所だった」「マイフェーバリット"健さん"はどの作品だろう」「国立西洋美術館は気持ち悪い」・・・・・・。心に残る多くの方が次々とこの世を去っていく。生活に最も近い文化・芸術・芸能・音楽・映画・テレビなどがどんどん動いていく。大相撲の話題がとても多く取り上げられている。その時の白鵬、その時の魁皇、その時の稀勢の里、優勝した旭天鵬、そして雅山、北の湖、遠藤・・・・・・。くっきりと思い出す。
時代と社会と人間性の変容、とくに「東京」社会の心象風景が浮き彫りにされる。

