 「恐慌を突破する逆転の発想」と副題にある。主流派経済学者たちのいう「価格が需要と供給を一致させる市場メカニズムを安定させる」のではない。「資本主義は本質的に不安定なもので、それゆえに金融危機は必ず生じる」と主張したハイマン・ミンスキーの理論、そして米国の世界恐慌脱出におけるマリナー・エクルズの理論を紹介する。
「恐慌を突破する逆転の発想」と副題にある。主流派経済学者たちのいう「価格が需要と供給を一致させる市場メカニズムを安定させる」のではない。「資本主義は本質的に不安定なもので、それゆえに金融危機は必ず生じる」と主張したハイマン・ミンスキーの理論、そして米国の世界恐慌脱出におけるマリナー・エクルズの理論を紹介する。
今の日本、このような閉塞感のなかにあるのは、改革が進んでいないからではなく、「デフレ・レジーム」に制約されて、そこから抜け出せないからだ。
デフレが20年も続いているのに、インフレの時に行うべき「デフレ・レジーム」をなぜ続けるのか。栄養不足で体調が悪い時に、なぜ「ダイエットが良い」などといっているのだ。デフレから脱却するための「インフレ・レジーム」へと、ありとあらゆる経済政策の向きを一斉に反転させよ。
インフレ・ターゲティングにも限界がある。あらゆる経済政策を総動員することだ。デフレは、投資や消費を減退させ、需要は不足し、供給は過剰になるが、市場は底を打たせることはない。底なしだ。金融危機(バブルは必ず崩壊するが、金融資本主義は必ず金融危機を招く)、グローバリゼーション、労働市場の流動化、成熟国家の実態経済に内在するデフレ圧力、そして財政均衡論の高まりと消費増税、公共事業悪玉論(非生産性部門の退出)・・・・・・。
全て今の世界はデフレ圧力に満ち満ち、デフレ・レジームから脱出できないでいる。
中野さんは「大それた試み」と思いつつも、国民全体に訴えたいと本書を出版したという。
 欧州の金融危機は、米国より深刻だった。ユーロの構造的要因が、経常赤字国を追い詰め、欧州金融市場はヘッジファンドの思いのままだ。最終的標的はイタリア、スペインだ。その危機は、財政危機と金融危機の複合危機だ。中原さんはヘッジファンドは「国家の債務+金融機関の債務」を見ているが、次の標的は米国となる。しかし米が、共和党になって財政再建に入ると、次のターゲットは日本になると言う。経常収支が赤字になった時、またモタモタと財政再建に何の手も打たなければ、日本攻撃が始まり、国債は暴落する。
欧州の金融危機は、米国より深刻だった。ユーロの構造的要因が、経常赤字国を追い詰め、欧州金融市場はヘッジファンドの思いのままだ。最終的標的はイタリア、スペインだ。その危機は、財政危機と金融危機の複合危機だ。中原さんはヘッジファンドは「国家の債務+金融機関の債務」を見ているが、次の標的は米国となる。しかし米が、共和党になって財政再建に入ると、次のターゲットは日本になると言う。経常収支が赤字になった時、またモタモタと財政再建に何の手も打たなければ、日本攻撃が始まり、国債は暴落する。
逆説的に言えば、日本が5年も10年も財政再建を放置するなら、ヘッジファンドが早く日本に気付かせてくれる方がよい。ヘッジファンドが日本を救う。日本のやることは明らかだ。大増税と歳出削減(社会保障)をやれば、財政破綻はしない。消費税20%、法人税は20%に下げる。年金は支給年齢を遅らせるだけでなく、税でやれ。景気回復してから財政再建などというが、景気は回復しないからムリな話だ。アイルランドなど、耐えて耐えて、財政再建しているではないか――中原さんは、政治家よ目をさませとガンガン主張している。
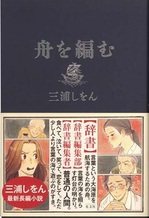 「辞書は、言葉の海を渡る舟だ」「海に渡るにふさわしい舟を編む」――新しい辞書「大渡海」づくりにかけた者たち。松本先生、荒木、馬締(まじめ)、そして西岡、佐々木、岸辺・・・・・・。空恐ろしいほどの熱意、世間でいえば"変人"の馬締が主人公だ。
「辞書は、言葉の海を渡る舟だ」「海に渡るにふさわしい舟を編む」――新しい辞書「大渡海」づくりにかけた者たち。松本先生、荒木、馬締(まじめ)、そして西岡、佐々木、岸辺・・・・・・。空恐ろしいほどの熱意、世間でいえば"変人"の馬締が主人公だ。
言葉の持つ力。言葉の重要性。「記憶とは言葉だ。香りや味や音をきっかけに、古い記憶が呼び起こされることがあるが、それはすなわち、曖昧なまま眠っていたものを言語化するということだ」「玄奘三蔵が大部の経典を中国語訳する偉業を成し遂げたように。禅海和尚がこつこつと岩を掘り抜き、30年かけて断崖にトンネルを通したように。辞書もまた、言葉の集積した書物という意味だけでなく、・・・・・・ひとの叡智の結晶だ」「言葉があるからこそ一番大事なものが俺たちの心のなかに残った。先生のたたずまい、先生の言動。それらを語りあい、記憶をわけあい伝えていくためには、絶対に言葉が必要だ」――。
辞書づくりという思いもよらない世界を、ここまで書き上げた三浦しをんさん。丁寧に、しかも一気に読ませる2012年本屋大賞受賞作。
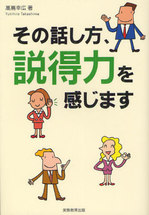 「説得力」は重要。仕事におけるプレゼンテーションでも、日常の対話においても。しかし、簡単なことではない。問題の急所を、わかり易く語るには、当然、勉強量の蓄積は欠かせない。問題の所在が蓄積されていなければ、相手にもされない。
「説得力」は重要。仕事におけるプレゼンテーションでも、日常の対話においても。しかし、簡単なことではない。問題の急所を、わかり易く語るには、当然、勉強量の蓄積は欠かせない。問題の所在が蓄積されていなければ、相手にもされない。
そのうえでの技術――高嶌さんは「人間的な魅力」「説明する能力」「納得させる能力」をあげる。そして、いきなり重大な頼みごとをせずに抵抗感を和らげておいて説得に入る「フット・イン・ザ・ドア・テクニック」や、その逆の「ドア・イン・ザ・フェイス・テクニック」、そして、相手が受け入れやすい頼みごとをして承諾してもらった後にオプションを増やす「ロー・ボール・テクニック」、勝ち馬に乗りたい同調心理をくすぐる「バンドワゴン効果」などを紹介する。
この社会で生きていく以上、説得力は不可欠――しかし演説と、会議などの説得力は異なると思う。
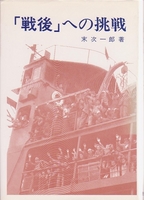 昨年は末次一郎氏没後10年の「学ぶ会」が行われ、最近は野田総理が初の沖縄訪問で胸像を訪ねている。現代社会の不安と閉塞感、破壊衝動の風潮とポピュリズム――そんななかで昭和56年に発刊された本書を読んだ。思うことは、イデオロギーに流されずに働く「奔走」ということだ。生きざま、国(民)を担うということ、実践ということだ。
昨年は末次一郎氏没後10年の「学ぶ会」が行われ、最近は野田総理が初の沖縄訪問で胸像を訪ねている。現代社会の不安と閉塞感、破壊衝動の風潮とポピュリズム――そんななかで昭和56年に発刊された本書を読んだ。思うことは、イデオロギーに流されずに働く「奔走」ということだ。生きざま、国(民)を担うということ、実践ということだ。
「大陸に残された同胞の救出や支援(引揚援護活動)」
「戦争受刑者の釈放」
「核抜き、本土並み、72年返還への沖縄返還」
「四島一括を求める北方領土返還」・・・・・・。
とくにあくまで実践者、運動家として、いつも初めは小さく、そしてうねりが大きく展開されていく。健青クラブ、日本健青会も、沖縄に国旗「日の丸」を贈ることも。「評論ではなく、動きをつくる人」「破壊ではなく、汗を流して創る人」が大事であることは、時代を超える。

