 著者はスタンフォード大学ビジネススクール教授。
著者はスタンフォード大学ビジネススクール教授。
「権力なんてほしくない、上に行こうとあくせくするのはみっともない――と迷う人がいるが、権力や地位はあった方がよい。イギリスの中央官庁で働く公務員を対象とした研究では、ヒエラルキーの底辺にいる人は、頂点にいる人と比べ、死亡率が4倍も高い」「権力はリーダーシップの一部であり、何かを成し遂げるためには欠かせない」――。
「権力」を手にするためには7つの資質がいる。
「何としてもやりとげるという確固たる決意」
「周りにも伝染する死にものぐるいのエネルギー」
「目標達成に欠かせない業務への集中」
「学習や成長に不可欠な自己省察」
「自信」
「親身になれる(他人の考えや感情を正確に読みとれる)共感力」
「体内に活火山をもつ闘争心」
――を紹介する。
限りなく多くの人を具体的に調査・研究し、いかにも米社会らしく自由自在にその成果を述べている。
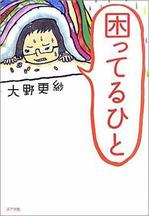 上智大学大学院に進学した2008年、自己免疫疾患系の難病を発病した優秀で行動的・活発な大野さん。免疫のシステムが暴走、全身に炎症を起こす。24時間、途切れることなく、痛み、発病、倦怠感、生き検査地獄1年、9か月の入院治療、絶叫、瀕死、死にたい、死ねない。いや生きたいかも......。
上智大学大学院に進学した2008年、自己免疫疾患系の難病を発病した優秀で行動的・活発な大野さん。免疫のシステムが暴走、全身に炎症を起こす。24時間、途切れることなく、痛み、発病、倦怠感、生き検査地獄1年、9か月の入院治療、絶叫、瀕死、死にたい、死ねない。いや生きたいかも......。
今、どうしているだろうと思う。ブログなどを見るが、作家&大学院生とあり、連載などもかかえている。しかし、この本にあるような生の声は伝わってこない。
「なにがあっても、悲観も、楽観もしない。ただ、絶望は、しない」
「生涯崖っぷちの難病患者は"制度の谷間"に落ち込む。福祉から見捨てられた存在だった」
「人間とは、きわめて経験的な生き物だ。......それぞれには、それぞれの苦労と言い分というものがある」
「医学については、スペシャリストでも、今日の複雑かつ急展開な人類の生態系については疎いのではないか。......ひとは誰しも、自分が"主人公"だ」
とにかく痛みが少しでも軽い大野さんの今日をと祈る。
 「福祉は天から降ってくるものではなく、外国から与えられるものでもない。日本人自身が、自らのバイタリティーをもって経済を発展させ、その経済力によって築きあげるほかに必要な資金の出所はない」「我々はこの日本の国土を、祖先から受けて、子孫に伝える。鴎外が生まれたままの顔をもって死ぬのは恥だ、といったと同じように、吾々もこの国土を吾々が受け取ったままのものとして子孫に遺すのは、恥じなければならぬ」――。先人の厳たる言葉だ。
「福祉は天から降ってくるものではなく、外国から与えられるものでもない。日本人自身が、自らのバイタリティーをもって経済を発展させ、その経済力によって築きあげるほかに必要な資金の出所はない」「我々はこの日本の国土を、祖先から受けて、子孫に伝える。鴎外が生まれたままの顔をもって死ぬのは恥だ、といったと同じように、吾々もこの国土を吾々が受け取ったままのものとして子孫に遺すのは、恥じなければならぬ」――。先人の厳たる言葉だ。
本書は、日本が世界に類をみない脆弱国土であることを示す。そして明治以来(いや有史以来も)から戦後復興、経済成長時代に至るまでの国土造りを、具体的に「全総」に携わった経験も含めて俯瞰する。
そして今後のことだ。公共事業のあり方、経済との関連、インフラ・社会資本整備とは何かを説きつつこれからの国土造りに論及する。資料も豊富。世界の中でわが国土を見る眼には哲学があってゆるぎない。心持よいほど明快だ。
政治への怒りやあきれるほどの"公共事業悪玉論"、このまま荒廃させて、わが国はわが世代はいいのかという責任感が一本の筋として通っているが、時には抑制的に表現されていることを、同じ感覚をもっている私には感じられる。国土と日本人――この重大なテーマの第一人者の言に、耳を傾けるべきだ。とくに政治にかかわる者は。
 はじめにまず"志"ありき、と副題にある。
はじめにまず"志"ありき、と副題にある。
渋沢栄一、前島密、岩崎弥太郎、安田善次郎、浅野総一郎、大倉喜八郎、田中久重、早矢仕有的、鮎川義介、小林一三、早川徳次、松下幸之助の12人。いずれも、明治、大正、昭和と、まさに日本を創ってきた人々だ。
浅野セメントの浅野総一郎の"九転び十起き"、シャープの早川徳次の悲惨に現れているように艱難辛苦を乗り越え、けっして挫けることなく、新しい挑戦をし続けた人々が、日本を創った。共通するのは人並みはずれた"忍耐力"、そして私欲でなく国の為、社会の為という理念・目的が厳としていること、そしてその真摯な姿勢に共感して助ける力ある仲間のいることだ。
短編であるがゆえに、人物像が鮮明だ。また、ビジネスにモラルを求め、企業に社会性を求める日本の伝統が浮き彫りにされる。北さんが注ぐ眼も温かい。人物にも、この国難に直面している日本という国にも。
 政治家の劣化がいわれ、倫理的資質の低下、哲学の欠如が指摘される。哲学不在は政治家のみではなく、社会そのものの浅さでもある。メディア社会も選挙制度の問題もある。
政治家の劣化がいわれ、倫理的資質の低下、哲学の欠如が指摘される。哲学不在は政治家のみではなく、社会そのものの浅さでもある。メディア社会も選挙制度の問題もある。
孔子、孟子、荀子、そしてソクラテス、プラトン、アリストテレス、そして内村鑑三の「代表的日本人」でも紹介されている西郷隆盛、上杉鷹山、日蓮の言葉など。さらにゲーテ、カーライル、セネカ、シラー、ルソーなどの123の政治に関する格言・名言。
森田実さんが、自らの言として心にとどめ、政治評論活動のなかで、指摘してきたものだ。
「一隅を照らす」「政の興る所は民の心に従うに在り」「上善は水の如し」――など、森田実さんの姿勢自体に感動をおぼえる。
政治家必読の著。

