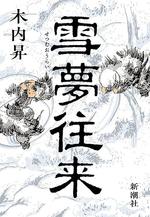 越後国魚沼郡の南端にある塩沢村の縮仲買商・鈴木牧之。19歳の時、行商に訪れた江戸で、ふるさと越後の雪の多さなどが、まるで知られていないことに驚き、雪を主題とした随筆で、雪国越後を紹介しようと決意する。やがて彼の書いた「雪話」は、人気戯作者の山東京伝の目に止まり、出版へと動き始める。しかし山東京伝も本気で取り合ってくれず、版元からの金銭要求や仲介者の死去等もあり、事態は暗礁に乗り上げ、年月のみが経過する。
越後国魚沼郡の南端にある塩沢村の縮仲買商・鈴木牧之。19歳の時、行商に訪れた江戸で、ふるさと越後の雪の多さなどが、まるで知られていないことに驚き、雪を主題とした随筆で、雪国越後を紹介しようと決意する。やがて彼の書いた「雪話」は、人気戯作者の山東京伝の目に止まり、出版へと動き始める。しかし山東京伝も本気で取り合ってくれず、版元からの金銭要求や仲介者の死去等もあり、事態は暗礁に乗り上げ、年月のみが経過する。
やがて、原稿は山東京伝への敵対意識に燃える曲亭馬琴の手に渡る。馬琴は12年間も本気で板元を探すでもなくほったらかしにした上、牧之の催促に腹を立て、送った膨大な原稿を捨てたとまで言う。牧之は虚々実々の江戸出版界に翻弄され、何十年も放置されたのだ。特に馬琴の狷介、固陋、京伝への敵対心はあまりにもひどいもので、牧之の人生をかけた願いを踏みにじり続けた。
ようやく山東京伝の弟・山東京山が乗り出してくれる。「やはり会って話さねばなるまい。牧之さんが越後の話を書こうと思った経緯を。なにゆえ何十年にもわたり、ひとつの事柄を紡ぎ続けたのか」と越後に訪ねてくる。そして天保8年(1837)に「北越雪譜」が刊行される。実に山東京伝に依頼してから40年が経っていた。67歳になっていた。
京山は「私には戯作者としての抜きん出た才はないかもしれぬ。兄ほど評判の作も書けぬ。そういう者が秀でるにはいかにすればよいと思う。それは、ひたすら実直に書き続けることさ。手を抜かず、欲を張らず、多くを望まず、ただただ生一本に書いていくことだ」と言う。牧之もそうだろう。また京伝は京山にこう言ったという。「戯作においては、何でもかんでもつまびらかにせずともよいのだ。正体がわかれば、胸のつかえは下りるだろうが、この世の中は、正体の知れねぇものばかりなのだ。俺にしたって、お前にしたって、一見しただけじゃあわからねぇものを、密かに抱えているだろう。いかに戯作といっても、何でもかんでも白日のもとにさらすのは、野暮でしかねぇのだ。不可解な事は、不可解なままに描くのが一番なのよ。わっちら戯作者は神じゃねぇんだからさ。神どころか、世の底の底を這いずってねぇと、ろくなものは書けねぇんだぜ――」・・・・・・。
「越後の鈴木牧之、その諦めない人生」というが、刊行40年。名著「北越雪譜」はけたはずれだ。

