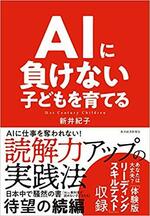 待望の「AI vs.教科書を読めない子どもたち」の続編。前著はAIの限界、AI時代の迷妄を打ち破るとともに、日本の教育の本質に迫る衝撃的著作だったが、本書は具体的、実践的で抜群に面白く、重要だ。「読解力が人生を左右する。とくにAI時代は」「『教育のための科学研究所』(新井紀子代表理事・所長主催)は日本全国の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のホームページを無償で提供する」と覚悟を示す。
待望の「AI vs.教科書を読めない子どもたち」の続編。前著はAIの限界、AI時代の迷妄を打ち破るとともに、日本の教育の本質に迫る衝撃的著作だったが、本書は具体的、実践的で抜群に面白く、重要だ。「読解力が人生を左右する。とくにAI時代は」「『教育のための科学研究所』(新井紀子代表理事・所長主催)は日本全国の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校のホームページを無償で提供する」と覚悟を示す。
「AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか」――。徹底して作り上げてきたRST(リーディングスキルテスト)を実際に示し、「係り受け解析」「照応解決」「同義文判定」「推論」「イメージ同定」「具体例同定」の6つの構成を提示する。RSTがいかに信頼性を獲得してきたか、努力には感服する。しかし、RSTはあくまで、視力検査と同様、「診断のツール」で達成度テストではない。そのうえで「読解力を培う授業」「意味がわかって読む子どもを育てるため」にどのようにしたらいいのか。実例を積み重ねながらの挑戦の課程が示される。
加えて本書には「体験版リーディングスキルテスト」が収録されている。やってみると「よく読む」という作業は結構、エネルギーを使うものだ。前著とともに面白く必読の書。
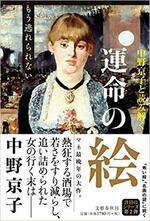 絵画から歴史、神話、感情・思い、流転、栄枯盛衰があふれ出ている。絵画が小さいのは残念だが、中野京子さんの解読はダイナミックで伝わる鼓動は生々しい。「もう逃げられない運命の絵」を感じさせてくれる。
絵画から歴史、神話、感情・思い、流転、栄枯盛衰があふれ出ている。絵画が小さいのは残念だが、中野京子さんの解読はダイナミックで伝わる鼓動は生々しい。「もう逃げられない運命の絵」を感じさせてくれる。
アントワーヌ=ジャン・グロの『アルコレ橋のナポレオン』――風に長髪をなびかせたナポレオンは「小柄、貧弱、惹きつけるものがない」どころか、魅力にあふれている。さらにグロが描く『ヤッファのペスト患者を見舞うナポレオン』は絶頂期のナポレオンだ。ウィリアム・ターナーの『戦艦テメレール号』――。1805年、ネルソン提督率いるイギリス艦隊とヴィルヌーブ提督指揮下のフランス・スペイン連合船隊が激突したトラファルガー海戦。先陣を切るネルソンの旗艦ヴィクトリー号が攻撃され、あわやという時、援護に入って撃退したのがテメレール号。その後の海戦でも何度も出陣、しだいに満身創痍のテメレールは解体のために蒸気船に曳航される。哀愁漂うその姿を描いたこの作品を、中野さんは"老兵はただ消え去るのみ"という。
エドゥアール・マネ最晩年の大作『フォリー・ベルジェールのバー』――。1882年、パリのミュージックホール、猥雑きわまりないフォリー・ベルジェール。「金髪の売り子嬢はまっすぐ正面を向いている。・・・・・・官能的な唇、だが表情は虚ろだ。ほんの一瞬、孤独が木枯らしのようによぎったとでもいうように」と中野さんは語る。ウィンスロウ・ホーマーの『メキシコ湾流』(1899年)、テオドール・ジェリコーの『メデュース号の筏』(1818~19年)――。生還できるか、まるで映画のワンシーン。
ベラスケスの『ブレダ開城』――。1635年、凋落するスペイン。戦火と貧困、ネーデルラント北部(オランダ)の独立運動に喘いだスペインのフェリペ四世は、志気を鼓舞する戦勝記念連作絵画12点を宮廷画家に制作させた。名将スピノラ将軍のスペイン的騎士道精神の高潔さを描いたもの。
ヴェルネの『レノーレのバラード』、シェフェールの『レノーレ――死者は駆けるのが速い』――。絶対王政がゆるみをみせ、ヨーロッパ中が不穏な気配に覆われだした18世紀後半、ドイツの詩人、ビュルガーが『レノーレ』を発表する。7年戦争(1756年~1763年)で死んだ恋人が若き女性レノーレを連れ去る物語。「死人とは駆けるのが速い」――すさまじい絵画。
時代と渦中の人間の流転が、身震いするように迫ってくる。
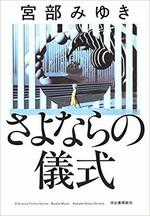 面白いが恐ろしい。8つのSF短篇集だが、AI・ロボット、科学技術の急進展によって、描かれた世界が「ありうるもの」と感じられるから恐ろしいのだ。社会の変質がいつの間にか始まっている。宮部みゆきの全方位的な想像力に凄みがある。
面白いが恐ろしい。8つのSF短篇集だが、AI・ロボット、科学技術の急進展によって、描かれた世界が「ありうるもの」と感じられるから恐ろしいのだ。社会の変質がいつの間にか始まっている。宮部みゆきの全方位的な想像力に凄みがある。
「母の法律」――被虐待児とその親の保護と育成のために「マザー法」ができる。親子のつながりに国が介入。とくに"社会で育てる"大義から記憶を消す「記憶沈殿化措置」がとられる。「戦闘員」――定年退職した孤独な老人。ルーティン化した散歩。街には防犯カメラがいつの間にか増え監視されているが、どうもそのカメラに侵入しているモノがある。「わたしとワタシ」――45歳の"わたし"の前に、女子中学生の"ワタシ"が現われタイムスリップ。自動販売機もスマホも、身近な所で日常のアイテムも大変化していることを実感する。
「さよならの儀式」――汎用作業ロボットが各家庭で使われ家族のようになったとき、それを廃棄する時の感情移入や別れの辛さ、廃棄業者の現実。「星に願いを」――隕石が近くに落ちてから妹がどうもおかしい。宇宙からの外来者がカラダを借りたらしい。
「聖痕」――調査事務所に持ち込まれた相談。社会を騒がせた事件の元<少年A>が、ネット上ですでに死んでいて「人間を超えた存在」になっているという。ネット社会、フェイクの暴走にどう対応するか。ネット上で生まれる"新しい神"の恐ろしさ。「海神の裔」――小さな漁村にやってきた「屍者」が村を救うが、昔からある「屍者」とは・・・・・・。「保安官の明日」――人口わずか823人の平和な町(ザ・タウン)での保安官の周りの事件。「世界は変わった。人造擬体は、今じゃ珍しいものではない」「世界は人間のものだ。人造擬体のものじゃない!」・・・・・・。
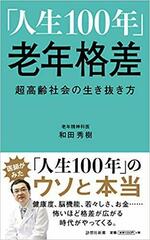 「超高齢社会の生き抜き方」が副題。「人生100年時代」といっても、若返るからなのではなく、"死ななくなる(病気の克服)"から100歳近くまで寿命は延びる。「老いと闘うことは悪くはないが、それには限界があり、ある時期から老いを受け入れ、老いとともに生きることが必要」「子どもの頃なら足が速い遅いといっても大差ないが、高齢者は知的能力も体力も経済力も社会的地位もものすごい格差がある」「その格差を許容するのではなく、いかに緩和できるかが大切」という。
「超高齢社会の生き抜き方」が副題。「人生100年時代」といっても、若返るからなのではなく、"死ななくなる(病気の克服)"から100歳近くまで寿命は延びる。「老いと闘うことは悪くはないが、それには限界があり、ある時期から老いを受け入れ、老いとともに生きることが必要」「子どもの頃なら足が速い遅いといっても大差ないが、高齢者は知的能力も体力も経済力も社会的地位もものすごい格差がある」「その格差を許容するのではなく、いかに緩和できるかが大切」という。
まず、「人生100年時代とは"健康格差社会"の到来」――。「80代まで働く必要のある社会がやってくるというが、実現性の乏しい未来像。iPS細胞でさまざまな臓器が若返っても、脳だけは必ず衰える。85歳であれば、4~5割は認知症になる(脳の萎縮が進む)(脳も使わないとボケる)」「身体と脳の機能維持は使い続けること」「最も大切なのは"意欲"を保ち続けること」という。そこで"意欲"を保つためには2つを活性化する。「前頭葉機能」と「男性ホルモン(人づき合い全般に意欲的)」だ。「人生100年時代には世代間の対立が激化する」「相続税を100%徴収せよ(60代のこどもに相続させても貯蓄に回るだけ)」「メタボ健診というが、やせ形の人の方が平均より6~8年早く死ぬ」・・・・・・。
「いまから始める!人生100年時代に備えた生き方」――。「健康診断の結果と健康状態はリンクしない(コレステロールを下げる食事制限は身体的にも脳機能的にも免疫力を下げ老化を進める)」「健康診断ではなく、心臓ドック、脳ドックを受けよ」「偉い人やマスコミのいうことを疑え。聞いているだけだと前頭葉は刺激されず、どんどん老化する」「ムダな節制などやめて生きる(神経質になるな)」「運転免許は返すな。ペダルの踏み間違いは、慌てるとか注意力の欠如で、認知症ではない」・・・・・・。
「『人生100年ゲーム』にだまされるな」――。「60歳過ぎたら知識習得の勉強は前頭葉の老化を遅らせることにならない。今までの習得知識をどうアウトプットするかに頭を使え」「依存症は病気であって意志の力とは関係ない」「60代は前頭葉の萎縮とセロトニンの減少が進み、感情のコントロールがより難しくなる。70代男性は前頭葉の萎縮と本格的な男性ホルモンの減少で行動意欲がさらに低下する。活動的になれるかどうかだ」「老け込むスピードを遅らせ、運動機能や脳機能を若々しく保つためには意欲を維持することが大切。前頭葉の萎縮は相手の気持ちの推量、共感、感動などの感情の低下をもたらす。外の世界にも無関心となる」「不測の事態に対処する時は活性化するから、変化のない生活をやめる。別の見方を考える。店も行きつけの店を変える」「男性ホルモンを保つには、原料はコレステロールなので、肉食を取り入れる。元気のない老人になるな」「知識を加工し、独特の解釈や見識、ユニークな視点を提示できること。モノ知りではなく、"頭のいい人""面白い人"になること」・・・・・・。皆、認知症になる。人間関係をもって"面白く"生きることの大切さが提示される。
 江藤淳(本名・江頭淳夫)没後20年。 江藤淳の自殺の数時間前に、本人から直接原稿を受け取った縁深き平山周吉氏の渾身の作、1600枚。「漱石とその時代」「小林秀雄」「成熟と喪失」「海舟余波」「閉ざされた言語空間」「完本 南洲残影」をはじめとする膨大な著作や折りおりの発言も含めて、その知見、思想、喪失感、怒り、悲しみを評伝としてまとめたもの。当然、小林秀雄、大岡昇平、丸山真男、三島由紀夫、埴谷雄高、大江健三郎、吉本隆明・・・・・・。ありとあらゆるといってもよい文人、思想家、評論家との切り結び合いは激烈だ。"行動する知性"の刃は相手を正面から打ち砕こうとした。"友"が次々と去るのも宿業ともいうべきものであった。
江藤淳(本名・江頭淳夫)没後20年。 江藤淳の自殺の数時間前に、本人から直接原稿を受け取った縁深き平山周吉氏の渾身の作、1600枚。「漱石とその時代」「小林秀雄」「成熟と喪失」「海舟余波」「閉ざされた言語空間」「完本 南洲残影」をはじめとする膨大な著作や折りおりの発言も含めて、その知見、思想、喪失感、怒り、悲しみを評伝としてまとめたもの。当然、小林秀雄、大岡昇平、丸山真男、三島由紀夫、埴谷雄高、大江健三郎、吉本隆明・・・・・・。ありとあらゆるといってもよい文人、思想家、評論家との切り結び合いは激烈だ。"行動する知性"の刃は相手を正面から打ち砕こうとした。"友"が次々と去るのも宿業ともいうべきものであった。
明治以来の近代日本。"近代なるもの"は各文人にとって耐えられないものとして憤りや喪失を生起した。進歩史観のなかに生ずる「亀裂」と「喪失」。江藤の内部に巣食う幼き頃よりの「母」と「故郷」の喪失が悲しみの基調音となり、"戦後民主主義""反体制の知識人"への激しい断罪が繰り返される。我々の世代にまで受け継がれたラジカルな思想空間の時代を牽引した一人がまぎれもなく江藤淳であった。「時流に流されず、根源的に問う」「浅きを去って深くに就く」「思考の粘着力によって哲学不在の時代を打砕く」・・・・・・。私自身が学生時代、私流の角度でのめり込んだ思想闘争にはエネルギーが満ちていた。
「思想の拠点をどこに置くのか」――。我々が常に問いかけ意識したことだ。江藤淳は芥川、太宰、三島、川端、小林美代子、金鶴泳等々と同じ自殺を選んだ。江藤は自殺について「処女作のころから、金鶴泳の文学は、生と死とのあやうい均衡の上に成立する静かな諦念をにじませていた。おそらくこの均衡の針が、ほんの一目盛だけ死の方に傾いたのだったに違いない」と言っている。その生死の世界として江藤は「老子の玄の世界」にしばしば論及しているが、それは有無中道の境地といえようか。ならば江藤を"保守の論客"などと言う前に、東洋思想、パトリオティズムの基盤が堅固であったことを取り上げるべきではないだろうか。
考えてみれば"批評"は難しい。しかもそれを生業とするからには、抜き身で相手の心中に入り、再び距離感を置いて相手を切り刻むという業火にまみれることを余儀なくされる。一撃で仕留めなければ自らがやられる。成熟という名の空虚を生む近代社会。江藤淳が対象とした人物は西郷も海舟も漱石も小林(秀雄)も三島も引き裂かれながら自立して生きようと戦ってきた"時代の戦さ人"たちであった。江藤自身が批評というシビアな形で血まみれに戦ってきたことを本書は示している。その根源を問い、道を志向する闘争姿勢を「甦る(甦れ)」と言っているのではないか。

