 「『異国の眼』で見た真実の歴史」が副題。日本の古代からの歴史を通じ、「日本とは何か」「日本人とは何か」「外国人から見た日本」を探ることによって、「自国の能力を客観視」することに役立てる意欲的取り組みがされる。膨大な文書の急所が示されている。「戦略――日本人の器用さと思考力」「風土と日本人」「古代――日本人の起源を考える」「平安時代――大和魂の誕生」「鎌倉時代――武家支配の始まり」「戦国時代」「徳川幕府の政治」「倒幕と明治政府樹立」「明治の社会と文化」「日米開戦への道」「米軍による占領時代」の各章がある。面白い。
「『異国の眼』で見た真実の歴史」が副題。日本の古代からの歴史を通じ、「日本とは何か」「日本人とは何か」「外国人から見た日本」を探ることによって、「自国の能力を客観視」することに役立てる意欲的取り組みがされる。膨大な文書の急所が示されている。「戦略――日本人の器用さと思考力」「風土と日本人」「古代――日本人の起源を考える」「平安時代――大和魂の誕生」「鎌倉時代――武家支配の始まり」「戦国時代」「徳川幕府の政治」「倒幕と明治政府樹立」「明治の社会と文化」「日米開戦への道」「米軍による占領時代」の各章がある。面白い。
全体を見ると一つの大きな流れが見えてくる。諸外国との接し方や衝突は、近年を別とすれば島国であったこともあり、そう多くはない。「白村江の戦い」「遣唐使」「元寇」「秀吉の朝鮮出兵、文禄・慶長の役」「鎖国、そして幕末」「近代国家建設への明治」「日米開戦」「戦後とGHQ」――。対応はいかにも稚拙で日本(人)と諸外国とのズレは大きい。孫崎さんの指摘することは、この意識とズレの正体を探ること、いつも戦略的でなく戦術的な対応で見誤り、遅れをとっているということではないか。
気付くことはさまざまある。「戦国時代の日本は、人口・文化で世界の頂点にあったこと(16世紀の日本の人口2500万人、フランス1600万人、スペイン700万人。文化は故国イタリアより高いとの言説)」「文禄・慶長の役は朝鮮を支援した明を消耗させ、満州族に滅ぼされる要因となった」「明治の維新と政府の真の立役者は、お雇い外国人たち」「明治期の外国人が見た日本人、日本文化への驚き」「トルストイの日露戦争論、安重根の対日観、夏目漱石の欧米観」「米国は日露戦争後、日本をターゲットに戦争を準備していた」「"日本は侵略者"――欧米の見た満洲事変」「日本はなぜ占領者を受入れたか――国民の安堵と軍部への嫌悪、生きるのに必死、GHQの日本国民への"公正"戦略」・・・・・・。いずれも重い歴史だ。
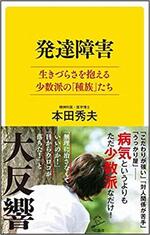 副題は「生きづらさを抱える少数派の『種族』たち」。本田秀夫氏は、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長。東大医学部を卒業、長きにわたって発達障害の臨床と研究に従事し学術論文も多数、日本自閉症スペクトラム学会常任理事。
副題は「生きづらさを抱える少数派の『種族』たち」。本田秀夫氏は、信州大学医学部子どものこころの発達医学教室教授・同附属病院子どものこころ診療部部長。東大医学部を卒業、長きにわたって発達障害の臨床と研究に従事し学術論文も多数、日本自閉症スペクトラム学会常任理事。
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)――。発達障害はこれらなど数種類の障害をまとめた総称だが、じつはそれらの種類のいくつかが重複している人がかなり多い。重複すると複雑な現れ方をして十分に理解されなくなってしまう、という。ASDには「対人関係が苦手」で「こだわりが強い」という特徴があり、ADHDは「うっかりミスが多い」「落ち着きがない」という特徴があるが、「障害(D)」とまではいかず、「AS+ADH」な人たちがかなりいる。「特性は0.5+0.5」「だけど悩みは2以上になる」と理解されないで苦しんでいる人がいるという訳だ。
「発達障害には強弱がある。特性自体は必ずしも障害となるものではないが、生活のさまざまなバランスのなかで支障となったときは、ASDやADHDの特徴として現われてくる」「"オタク"とASはどう違うか。ASの特性がある人は、こだわりと対人関係を天秤にかけた時、こだわりを優先する。オタクの人はこだわりと対人関係を天秤にかけて調整できる(世の中には社交上手なオタクもいる)(映画を見てもケーキを共に食べてもASの人は知識をとことん追究し、内容重視の会話をし、交流重視ではない)」「"うっかり屋"とADHの不注意は違うのか――ミスの多い状態を、本人やまわりの人が『まあいいか』と思える程度であればADHDに該当しない(理解されていくか、"きわめて深刻な問題"として理解されていくか、帳尻が合うかどうか)」・・・・・・。そして自分の「発達の特性」を知っておこうと、11項目を提示する。「ASの①臨機応変の対人関係が苦手②こだわりが強い」「ADHの不注意、多動性・衝動性」「LDの読む、書く、計算が苦手」「DCDの運動、手作業が苦手」「チック、知的発達が遅い」だ。それに対して「生活環境を整える環境調整をする。本人も周りも」「自分の『やりたいこと』を優先する、やりすぎて無理をすることもあるが、"やりたいこと"と"やるべきこと"を分け、調整する」など、11項目についての「環境調整」を具体的に提示している。
更に、「発達の特性を『~が苦手』という形で、なんらかの機能の欠損(病気)としてとらえるのではなく、『~よりも~を優先する』という『選好性の偏り』としてとらえた方が自然」「発達の特性と"ふつう"の間に優劣はない。あるのは多数か少数かという割合だけ」「多数派向けに組み立てられている生活を少数派向けに調整すれば、生きづらさは軽減する」とし、本人や家族や友人・関係者の生活環境の調整を求めている。なにかができない"障害者"というより、独特のスタイルをもつ「種族」のようなものとしての理解を、と結んでいる。
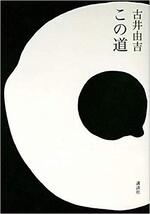 80歳を越えた古井由吉氏の最新小説。2017年8月から18年10月まで、2か月ごとに書いた8篇。その時期の"つれづれ随想"的だが、戦争や戦後の恐怖や「生きる」に精一杯であった時のこと、東日本大震災などの大地震、執筆時の九州北部豪雨や西日本豪雨、昔と今の「季節」「街の変化」の感じ方の相違等々にふれつつ、「生老病死」の老いの実存と境地から描く。「個の記憶を超え、言葉の淵源から見晴るかす、前人未踏の境。」と帯にあるが、深い思索と観識眼とその境地はうなるほどだ。
80歳を越えた古井由吉氏の最新小説。2017年8月から18年10月まで、2か月ごとに書いた8篇。その時期の"つれづれ随想"的だが、戦争や戦後の恐怖や「生きる」に精一杯であった時のこと、東日本大震災などの大地震、執筆時の九州北部豪雨や西日本豪雨、昔と今の「季節」「街の変化」の感じ方の相違等々にふれつつ、「生老病死」の老いの実存と境地から描く。「個の記憶を超え、言葉の淵源から見晴るかす、前人未踏の境。」と帯にあるが、深い思索と観識眼とその境地はうなるほどだ。
老いは喪失、諦念、自愛の組み合わせだろう。諦(あきらめる)とは明らかに観ることだ。「老年に至って振り返ればこれでもさまざま、何事かを為したにつけ為さなかったにつけ、すこしずつおのれを捨てて、置き去りにしてきたことだ。なしくずしの自己犠牲、なしくずしの自愛である。最後の運命の定めるところと受け止めて、これに順う。従容とまではおのれをたのめなくても、その諦念にわずかな自由を見る」という。今の社会は昔に比べ静謐が消え、季節が消え、むき出しの貧病が消え、人と人の生死につながる絆が消えていく。昭和12年生まれの古井さんと、20年生まれの私とは戦争の陰影が異なるからだろう、それらの感受性がかなり異なる。凶災だけでなく、梅雨時、暑さに陰りの見え始める初秋、そして晩秋、花の咲く春を待つ時。季節によって生老病死の感じ方・気分は変化する。「たなごころ」「梅雨のおとずれ」「その日のうちに」「野の末」「この道」「花の咲く頃には」「雨の果てから」「行方知れず」の8篇を味わいながら読んだ。
 「地域再生は『儲かる会社』作りから」が副題。題名と副題に尽きており、小出宗昭氏は年間相談件数4000超の企業支援拠点「エフビズ」の代表。他の自治体も共鳴し、全国約20か所にご当地ビズが誕生している。全国の成功事例を示しながら各ビズの奮闘ぶりを示している。
「地域再生は『儲かる会社』作りから」が副題。題名と副題に尽きており、小出宗昭氏は年間相談件数4000超の企業支援拠点「エフビズ」の代表。他の自治体も共鳴し、全国約20か所にご当地ビズが誕生している。全国の成功事例を示しながら各ビズの奮闘ぶりを示している。
上からの地方創生、単なる相談の受け手の官制の支援はなかなかうまくいかない。魂を入れ、具体的な生きた対策こそが重要。「儲かる会社」をどうつくるか。その通りだ。しかし、地方の企業は「ないないづくし」に苦しんでいる。「ないないづくし」の逆境に打ち勝ち、瀕死の企業をよみがえらせるには、必要な資質を備えたプロの人物が不可欠となる。企業支援のプロとして絶対不可欠なのは、「ビジネスセンス」「高いコミュニケーション力」「情熱」の3条件だという。仕事のできる政治家もそうだから納得する。成果を上げるには「セールスポイント(強み)を見つける」「ターゲットを絞る」「連携する」の3つの方法を示す。
「車いすスポーツのためのトレーニングマシン」「被災した学習経営者の再スタート支援」「自然薯ブランド化」「スポーツ弁当」「お掃除グッズ・ほこりんぼう」「防音防振製品」・・・・・・。具体的成果を示しつつ「商店街といっても"個店"から」「地域ビジネスのために金融機関は奮い立て」という。大事な働きを展開してくれている。
 足利尊氏によって京都に開設された室町幕府。「初代尊氏、三代義満、八代義政が有名だが、三代義詮、四代義持、六代義教といった面々もなかなかのもので、統治者として政治を推し進めた。義政の時代以降、室町幕府の力は衰えていくが、・・・・・・代々の将軍は、みな自身は王者であるという自尊心を持ち、勢力を伸ばそうと務めた」「ただ将軍(室町殿)が政治のすべてを仕切っていたわけではなく、細川氏をはじめとする有力な守護大名が並び立ち、将軍を支えながら政治に関与していた」・・・・・・。
足利尊氏によって京都に開設された室町幕府。「初代尊氏、三代義満、八代義政が有名だが、三代義詮、四代義持、六代義教といった面々もなかなかのもので、統治者として政治を推し進めた。義政の時代以降、室町幕府の力は衰えていくが、・・・・・・代々の将軍は、みな自身は王者であるという自尊心を持ち、勢力を伸ばそうと務めた」「ただ将軍(室町殿)が政治のすべてを仕切っていたわけではなく、細川氏をはじめとする有力な守護大名が並び立ち、将軍を支えながら政治に関与していた」・・・・・・。
「創世期の室町幕府と南北朝(鎌倉幕府討幕、建武の新政、南北朝の戦い、観応の擾乱)」「足利将軍の権威確立(上杉禅秀の乱、クジ引き将軍・六代義教)」「鎌倉公方と関東の争乱」「応仁の乱と室町幕府の動揺(無気力将軍・八代義政と日野富子、東山文化)」「足利将軍の衰退と室町幕府の滅亡(義輝・三好体制、信長の15代・義昭)」・・・・・・。まさに激動、動乱の室町時代の全貌をまとめてくれている。

