 長期の経済停滞から脱するための「戦略」を提示し、これまでとってきた経済政策を根本的に修正せよ、という。中野氏がこれまで思想的、経済理論的に論述してきたことを更に強く主張するとともに、最近のMMTについても解説する。当たり前のことだが、「デフレ時にはデフレ対策、インフレ時にはインフレ対策」が徹底されることがまず大事。日本はまず「財政支出を拡大して、デフレを脱却する。緊縮財政から積極財政へと転ぜよ」「ムチ型(企業利潤主導)(人件費削減)成長戦略をやめて、アメ型(賃金主導型)成長戦略へと転換せよ。賃金上昇や実体経済の需要拡大によって経済が成長するような経済構造へと改革せよ」という。平成が財政再建論、公共事業悪玉論、規制緩和の構造改革論によってデフレの悪循環に沈んだことを指摘する。
長期の経済停滞から脱するための「戦略」を提示し、これまでとってきた経済政策を根本的に修正せよ、という。中野氏がこれまで思想的、経済理論的に論述してきたことを更に強く主張するとともに、最近のMMTについても解説する。当たり前のことだが、「デフレ時にはデフレ対策、インフレ時にはインフレ対策」が徹底されることがまず大事。日本はまず「財政支出を拡大して、デフレを脱却する。緊縮財政から積極財政へと転ぜよ」「ムチ型(企業利潤主導)(人件費削減)成長戦略をやめて、アメ型(賃金主導型)成長戦略へと転換せよ。賃金上昇や実体経済の需要拡大によって経済が成長するような経済構造へと改革せよ」という。平成が財政再建論、公共事業悪玉論、規制緩和の構造改革論によってデフレの悪循環に沈んだことを指摘する。
「"インフレ恐怖症"は"商品貨幣論"の間違いに起因する。MMTは『通貨の価値を保証するのは、政府の徴税権力である』と説明する。その政府の徴税権力の根源は、民主政治にある」「成長と格差縮小の為には、需要対策として大きな政府、積極財政、減税、金融緩和。供給対策としてアメ型成長戦略、規制強化、労働者保護、グローバル化の抑制が必要」「デフレ時にムチ型成長戦略をとれば、企業は利潤を貯蓄に回し、人件費を切るからトリクルダウンは起きない」「デフレ時は縮小するパイを皆で奪い合うから、レントシーキング活動(自分の利益を増やすためにルールや規制の変更を政治・行政に働きかける)が活発化しやすい。規制緩和、競争促進の"改革"が煽られる」「現在の日本経済はデフレ。デフレは需要や財政赤字の"過剰"ではなく"過少"だ」「エリートが考え方を変えられないのは"認識共同体"だからだ」「グローバル化の徹底は、民主政治とは両立しない。グローバル化の徹底のために国際条約を使って、各国の民主政治を制限することになる」「一度決まったことは元に戻したり、変更できない "経路依存性"の現象が多くある」・・・・・・。
「平成の過ちを繰り返さないために!」という「基礎知識編」の続編。
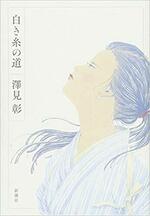 時は幕末。貧しい養蚕農家に生まれたお糸は手を抜かずに突き進む女性。数えで十歳のお糸は、歌川貞秀という旅絵師と、中村善右衛門という蚕種商に出会い、今までとは全く異なるものが世にあるのだと知る。ある時、医者が体温計を使って熱を計ることを知り、「体温計をお蚕飼いに使えないか」と思いつく。江戸に飛び出して、善右衛門と共に周りの助けを得て、苦労しながらも養蚕が量産し易いように、寒暖計を養蚕業用の蚕当計に作り上げていく。
時は幕末。貧しい養蚕農家に生まれたお糸は手を抜かずに突き進む女性。数えで十歳のお糸は、歌川貞秀という旅絵師と、中村善右衛門という蚕種商に出会い、今までとは全く異なるものが世にあるのだと知る。ある時、医者が体温計を使って熱を計ることを知り、「体温計をお蚕飼いに使えないか」と思いつく。江戸に飛び出して、善右衛門と共に周りの助けを得て、苦労しながらも養蚕が量産し易いように、寒暖計を養蚕業用の蚕当計に作り上げていく。
しかし、これはお糸の「寒暖計」「蚕当計」の成功物語ではない。江戸時代、しかも因習深き地方において、志をもって生き抜こうとした一人の女性の物語だ。江戸に何度も飛び出す。しかも親や自分の娘を村に置いて。「蚕当計」は作り上げたものの、少しも広まらないし、彼女自身への蔑みは繰り返される。とくに娘からの反発は凄まじい。しかし、何度も何度も体当たりで挑み、ついに「蚕当計」も村からの「信頼」も勝ち取る。何といっても娘と親子の会話ができるようになる。
私は、女性は男性よりも真剣で、一途で突っ込んで結果を出すと思っている。子供に対する愛情も深いし、仕事についてもやり切る力は凄い。お糸は決して良妻賢母でも、肝っ玉母さんでもない。"困った人"といえるかもしれないが、周囲とぶつかり、葛藤しながらも突き進む女性の姿が、黒船が浦賀沖に来る日本近代の黎明期を背景に見事に描かれる。
 「令和」制定の経緯を日テレ政治部がまとめたもの。「平成31年4月1日の発表の日のドキュメント」、さかのぼって「NHKのスクープ『生前退位』の衝撃と『恒久法か特例法か』の議論」、「官邸の動きと保守派の考え」「最終候補選定までの道のり」「考案者と国書」等々が、生々しく語られる。「極秘」で進められるものだけに、「取材される側」「取材する側」の緊張感が伝わってくる。さまざまな攻防はあるにしろ、「令和」がスタートを切った。
「令和」制定の経緯を日テレ政治部がまとめたもの。「平成31年4月1日の発表の日のドキュメント」、さかのぼって「NHKのスクープ『生前退位』の衝撃と『恒久法か特例法か』の議論」、「官邸の動きと保守派の考え」「最終候補選定までの道のり」「考案者と国書」等々が、生々しく語られる。「極秘」で進められるものだけに、「取材される側」「取材する側」の緊張感が伝わってくる。さまざまな攻防はあるにしろ、「令和」がスタートを切った。
本書はまた「元号と政治」の章で結ばれている。「始まりとなった水戸学」「光圀以来の"敬幕"の論理が、尊皇論が純化されることによって討幕論につながった」「明治より『一世一元』となったこと」「天皇親政と元号の結び付き」「敗戦によって天皇による"時間支配"の物語はピリオドを打つ」「法的根拠の喪失と元号廃止論の浮上」「保守勢力の"草の根"運動と元号法の成立(1979年6月)」・・・・・・。「権威と権力」「象徴天皇」「皇位継承」「内閣等による皇室の政治利用」など、国と社会の諸課題は考え続けなければならないことだ。
 面白い。殺人事件だが悪人はいない。運命に操られる家族。夫婦・親子の愛、思いが心に迫る。これも加賀恭一郎シリーズといえようが、主人公は加賀の従弟で刑事の松宮脩平。殺人事件をきっかけに、複数の家族の秘密があぶり出され、「人には家族にも言えないことがある」「言うべきか、言わざるべきか」が交錯する。"心の扉"という琴線に触れる作品。
面白い。殺人事件だが悪人はいない。運命に操られる家族。夫婦・親子の愛、思いが心に迫る。これも加賀恭一郎シリーズといえようが、主人公は加賀の従弟で刑事の松宮脩平。殺人事件をきっかけに、複数の家族の秘密があぶり出され、「人には家族にも言えないことがある」「言うべきか、言わざるべきか」が交錯する。"心の扉"という琴線に触れる作品。
目黒にあるカフェ「弥生茶屋」の経営者・花塚弥生が背中をナイフで刺され、店で殺害される。「あんないい人はいない」と誰もがいった。恨みを買うようなこともないように思われたが、捜査線上に二人の人物が浮かぶ。一人は綿貫哲彦、弥生の元夫。もう一人は汐見行伸、店の常連客で弥生に好意を寄せていたと思われた。捜査が進むと綿貫の家族(同棲する中屋多由子)、汐見の家族(妻・玲子が亡くなり、14歳の娘・萌奈と二人暮らし)がともに深い闇をかかえていることを知る。どうも証言がおかしい。秘密を抱え真実を心の内に隠しているとしか思えない。この二つの家族とともに、捜査を担当する松宮自身に、生まれてすぐに亡くなったとされる父親と名乗る者が現われ絡み合う。この家族にも人に明かせぬ秘密が隠されていた。
「あたしは、誰かの代わりに生まれてきたんじゃない」「そういえば、と克子が続けた。この糸は離さないっていっていたな。たとえ会えなくても、自分にとって大切な人間と見えない糸で繋がっていると思えたら、それだけで幸せだって。その糸がどんなに長くても希望をもてるって。だから死ぬまで、その糸は離さない」「素敵な巡り合いがあると思う(子どもができ)」・・・・・・。
殺人事件自体は解決するが、松宮は「解くべきは各家族に潜む親子の謎の糸だ」と奔走、苦悩する。家族の絆、親子の絆、血と育ての絆、運命をとことん感じさせる。
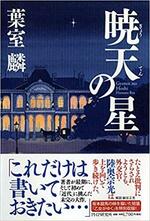 明治6年、征韓論で政府が分裂。明治10年、西南戦争で西郷隆盛が死ぬが、陸奥宗光は政府転覆計画に連座したとして、国事犯として5年の禁獄に処せられた。西郷、大久保が相次いで亡くなった後の明治10年代から日清戦争までの間、陸奥宗光は欧米列強と闘い、「不平等条約の改正」に命を懸けた。その心中は「明治になって初めて日本人は生まれたと陸奥は思っていた。それまではそれぞれの藩に住む者の集まりが日本人であったが、いまや誰もが日本人として平等であり、国家に対して、『義務あり、権利あり』と陸奥は主張している。......明治政府は、藩閥政府になりはてている。日本は日本人の日本である。薩長の日本ではない」と声を高くして言いたかったのだ。それは「日本を洗濯したく候、と唱えた坂本龍馬の理想とするところでもあった」と描かれる。
明治6年、征韓論で政府が分裂。明治10年、西南戦争で西郷隆盛が死ぬが、陸奥宗光は政府転覆計画に連座したとして、国事犯として5年の禁獄に処せられた。西郷、大久保が相次いで亡くなった後の明治10年代から日清戦争までの間、陸奥宗光は欧米列強と闘い、「不平等条約の改正」に命を懸けた。その心中は「明治になって初めて日本人は生まれたと陸奥は思っていた。それまではそれぞれの藩に住む者の集まりが日本人であったが、いまや誰もが日本人として平等であり、国家に対して、『義務あり、権利あり』と陸奥は主張している。......明治政府は、藩閥政府になりはてている。日本は日本人の日本である。薩長の日本ではない」と声を高くして言いたかったのだ。それは「日本を洗濯したく候、と唱えた坂本龍馬の理想とするところでもあった」と描かれる。
葉室麟の未完の遺稿。「作者は挫折や失敗を味わった人物を好んで主人公にする。ひとは生きていくことで、挫折や失敗の苦渋を味わう。そうなると、歴史を見つめてももはや『勝者』の視点は持ち得ないと作者(葉室麟)はいう」と解説の細谷正充さんは言っている。味わい深く、力むことのない葉室麟の逝去は残念だ。
「陸奥は剃刀と仇名されるほど鋭い頭脳をもっている」「紀州の出である」「藩閥政府を厳しく批判した」「伊藤博文に可愛がられ信頼された」「美しい女性・亮子を妻とした」「亮子は鹿鳴館の華と呼ばれたが夫婦とも鹿鳴館には違和感を持っていた」「機略縦横・坂本龍馬に魅かれ兄事していた(外交の才)」......。日清戦争をなぜ遂行したか。不平等条約を改正するためと苦悩する陸奥宗光。それに対する勝海舟の反対は、キレ味抜群。本書に特別収録された「乙女がゆく」も、龍馬とその姉・乙女の関係が活写され、とびきり良い。

