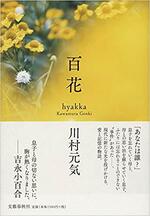 人生の生老病死――。不思議にも縁あってこの世に生を受け、人を愛し親ともなり、老いて死を迎える。命に刻まれた記憶の数々。花火は消えゆくがゆえに瞬時の鮮やかさ、百花繚乱の美が際立たせる。老いは"喪失"を伴なうが、消えざるものとは一体何か。母親と息子の生命の絆、思いの深さが、美しく、強く、感動的に描かれる。素晴らしい作品。
人生の生老病死――。不思議にも縁あってこの世に生を受け、人を愛し親ともなり、老いて死を迎える。命に刻まれた記憶の数々。花火は消えゆくがゆえに瞬時の鮮やかさ、百花繚乱の美が際立たせる。老いは"喪失"を伴なうが、消えざるものとは一体何か。母親と息子の生命の絆、思いの深さが、美しく、強く、感動的に描かれる。素晴らしい作品。
葛西泉。就職が決まり、家を出てからもう15年が経ち、結婚もした。大晦日、実家に帰ると母・百合子がいなかった。外に出て捜すと、公園の弱々しく光る外灯の下で、ブランコに乗った母を見つける。認知症と診断され、息子をも忘れていく母。母との思い出を募らせていく泉。しぼり込まれていく百合子の記憶に、泉は母の思いの深さを知っていく。二人には忘れることができない"事件"があった。突然、百合子が家を出て、泉を1年も置き去りにした。「泉の元に帰ってきた母は、それから自分の時間と心のすべてを息子のために捧げていた。・・・・・・百合子の熾烈な決意の源流を、泉はこの日記に見た。母は一生かけて、あの一年分の贖罪をしていくことに決めたのかもしれない」。
「半分の花火が見たい。半分の花火をあなたと見たいの」「言葉を失い、名前を忘れてしまったとしても、泉との思い出だけは残るのだろうか。いつか名前だけでなく泉そのものを忘れてしまったら、母のなかに自分のなにが残るのだろうか」「次々と打ち上がる半分の花火。泉と百合子が過ごした家で咲いていた数百の花のように、それが美しかったということだけを記憶に残し、やがて消えていく」・・・・・・。
 児童虐待、貧困の連鎖――。富井真紀さんは自らの壮絶な半生を赤裸々に語りながら、どうすれば「普通」になれるか。なぜ「普通」になれないのか。「貧困の連鎖を断ち切るために」(副題)今何ができるか。自ら立ち上げ格闘中の「居場所がない子のための読書・勉強Cafe」「食堂を持たない子ども食堂"プレミアム親子食堂"」「宮崎こども商店」「子ども貧困専門支援員養成通信講座」などを紹介する。本書のほとんどは、すさまじい家族と自らの半生記だ。
児童虐待、貧困の連鎖――。富井真紀さんは自らの壮絶な半生を赤裸々に語りながら、どうすれば「普通」になれるか。なぜ「普通」になれないのか。「貧困の連鎖を断ち切るために」(副題)今何ができるか。自ら立ち上げ格闘中の「居場所がない子のための読書・勉強Cafe」「食堂を持たない子ども食堂"プレミアム親子食堂"」「宮崎こども商店」「子ども貧困専門支援員養成通信講座」などを紹介する。本書のほとんどは、すさまじい家族と自らの半生記だ。
そりゃあ自暴自棄にもなるだろう。度を超えたアルコール依存症のひどい父親との地獄のような暮らし。借金とりは毎日来る。極貧。逃げても逃げても抜けられない。居場所はない。10代でも夜の街で働くしかない。結婚しても、相手もまた同じ境遇、育ち。ひどい自分の父親はまとわり付き、バラバラな家族。修羅場は続く。しかし、どこに相談したらいいかわからない。知識もない。「普通」が全く違うのだ。
全国で虐待事件は続いている。2017年に起きた大阪の子どもの置き去り死亡事件――男と外泊していたひどい母親だが、「この人、男に逃げたんだ。わかる」と思う。現実逃避だという。2015年川崎の中一男子暴行致死事件――母親は「昼夜問わず働いている。息子の行動を全ては把握できなかった」といい、「親の責任放棄」と大バッシングを受ける。一人で子どもを育てる母親は「どう追い込まれていたのか」「虐待する親たちはなぜそのような思考回路に陥るのか」・・・・・・。
「普通」ではない凄絶な世界で生きている人たちの「貧困の連鎖を断ち切るため」に格闘する実証の人生、実証の姿が記される。
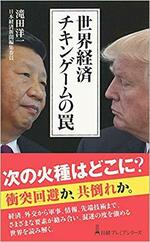 激変する世界。経済も政治も、情報、テクノロジーも・・・・・・。あらゆる所で、チキンゲームが行われている。「本書はニューヨーク、ワシントンからデトロイトを回り、ソウル、上海やモスクワを訪ねた取材の成果をもとに、世界経済のつばぜり合いを報告しようとした」とあるように、激変する世界の体温と緊張感が伝わってくる。そして、本書が報告しているのが、今年2月迄。その後の2回目の米朝首脳会談や最近の米中貿易の衝突など、世界の動きはますます激しく変化していることを実感する。チキンゲームは続くと把え、日本としての戦略をガッチリ打ち立てることこそが大切だと思う。
激変する世界。経済も政治も、情報、テクノロジーも・・・・・・。あらゆる所で、チキンゲームが行われている。「本書はニューヨーク、ワシントンからデトロイトを回り、ソウル、上海やモスクワを訪ねた取材の成果をもとに、世界経済のつばぜり合いを報告しようとした」とあるように、激変する世界の体温と緊張感が伝わってくる。そして、本書が報告しているのが、今年2月迄。その後の2回目の米朝首脳会談や最近の米中貿易の衝突など、世界の動きはますます激しく変化していることを実感する。チキンゲームは続くと把え、日本としての戦略をガッチリ打ち立てることこそが大切だと思う。
今年の世界地図――。「トランプが地球を振り回す(アメリカ・ファーストで国際的な約束事を次々とちゃぶ台返しを行っているが、トランプを後押しする草の根の支持層は堅固になっている)」「米中新冷戦 世界に暗雲(ペンス演説、米国の中国に対する構えの大変化、先端技術の覇権争い、テクノ冷戦)」「中国の夢と悪夢(シェア自転車の墓場、無人コンビニの弱点、中国の3つの過剰、中国製造2025の中国の意図、ファイブアイズの中国包囲網)」「欧州が壊れていく――3人のMの憂鬱(移民と難民にどう向き合うか、欧州議会選挙と右翼政党、スティーブ・バノンvsジョージ・ソロス)」「市場動乱再び(パウエルFRB議長解任説、新興国経済の不安定・もろさ)」「有権者の反乱はあるか(英国・仏などの若者の反乱)」「金というカナリアが鳴く中で(米国による資産の差し押さえを懸念した金購入)」・・・・・・。各章の中身は生々しい。
世界経済のつばぜり合い、米中のつばぜり合い、暗雲が次々とたれ込めるなか、日本はどう戦略を立てて動くか。
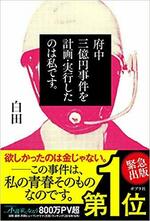 1968年12月10日、東京府中市で起きた三億円強奪事件。50年が経過し、犯人が告白文を発表する、という小説。
1968年12月10日、東京府中市で起きた三億円強奪事件。50年が経過し、犯人が告白文を発表する、という小説。
当時、大学2年だった実行犯の白田。計画を共に策謀する昔からの友人・省吾。そして恋人の橋本京子、三神千晶。60年安保が過ぎ、あの頃は再び大学は学生運動の渦中にあった。日本も1964年の東京オリンピックを終え、高度成長の勢いとともに、新しく迎える社会への希望と不安が交錯していた。若者はエネルギーもあり、"青春"を模索していた。
そんななか、「生きる証」「命を賭けても友情を貫こうとした意思」「奔流となる社会のなかでかき消される個人、それゆえの自らの決断」――府中三億円事件をそのように"金銭欲"ではないと想定して描いたもの。意表をついた"小説"。

 一高の紋章・橄欖と柏。橄欖は文の神・ミネルヴァで、柏が武の神・マルスで「文武両道を修めよ」との意味をもつ。岸は「やはり武よりは文、マルスよりはミネルヴァこそが先導しなけりゃならん」と椎名悦三郎にいう。「椎名は省内一仕事ができると見なされ、花道を歩いている岸をうらやんでいた。男の嫉妬ほど厄介なものはない――」「人にとって一番大事なのは、『人に遭う』ということなのかもしれんな」と先輩は椎名にいう。
一高の紋章・橄欖と柏。橄欖は文の神・ミネルヴァで、柏が武の神・マルスで「文武両道を修めよ」との意味をもつ。岸は「やはり武よりは文、マルスよりはミネルヴァこそが先導しなけりゃならん」と椎名悦三郎にいう。「椎名は省内一仕事ができると見なされ、花道を歩いている岸をうらやんでいた。男の嫉妬ほど厄介なものはない――」「人にとって一番大事なのは、『人に遭う』ということなのかもしれんな」と先輩は椎名にいう。
しかし、"花道を歩む"といっても一生は波瀾万丈。関東軍が支配する満洲に赴任、"二キ三スケ"と呼ばれるが、「岸は、清廉潔白だが仕事ができない者より、叩けば埃が出る身ながら天下国家のためになる仕事をする者の方が偉いのではないかと思っていた」。戦争は泥沼化し、昭和14年10月、日本に帰り、政変に次ぐ政変、激震のなか政治家として立つ。国家の死命を決する岐路。"喧嘩師"岸は激しくぶつかりながら闘いの日々、東條内閣が成立し、44歳の岸は商工大臣となる。激しい権力闘争、19年7月東條内閣総辞職。敗戦。巣鴨プリズン、A級戦犯、幽囚の日々。GHQ、憲法制定過程、吉田茂、朝鮮戦争、サンフランシスコ平和条約と欠陥多き日米安保条約。そして激しい政争と離合集散、保守合同。鳩山内閣の"北方領土問題"と米国・ダレス、訪米する岸。そして岸内閣、安保改定。池田内閣、佐藤内閣、田中内閣に対しての岸の思い。30年代初頭からは私の記憶に鮮明にあり、エピソードも聞いているものもあり、生々しい。
超絶の歴史大変動のなかで、「日本を背負う」政治リーダーが、心身ともに切り刻まれるなか何を思い、どう決断し行動したか――。さまざまな思いが交差し、乱反射する。

