
 「役に立たない人生相談」「好きなようにやればいい」――。94歳現役作家の佐藤愛子さんに、夫婦のこと、仕事のこと、腹の立つ友人・知人のこと、恋の悩みなどを相談する。「何を寝ぼけたこと、いってるの!」「『やーめた!』と叫べばいいんです」「よくよくヒマなんだねぇ、あなたは」「しっかりせえ!それでも男か!」「何もする必要なし!ほっときなさい」「人を変えるなんて無理な話。自分を変われば!」・・・・・・。ズバッと歯に衣着せぬ回答で気持ちがよい。まさに目の前(面の前)がパッと晴れて面白い。
「役に立たない人生相談」「好きなようにやればいい」――。94歳現役作家の佐藤愛子さんに、夫婦のこと、仕事のこと、腹の立つ友人・知人のこと、恋の悩みなどを相談する。「何を寝ぼけたこと、いってるの!」「『やーめた!』と叫べばいいんです」「よくよくヒマなんだねぇ、あなたは」「しっかりせえ!それでも男か!」「何もする必要なし!ほっときなさい」「人を変えるなんて無理な話。自分を変われば!」・・・・・・。ズバッと歯に衣着せぬ回答で気持ちがよい。まさに目の前(面の前)がパッと晴れて面白い。
若い頃は「こうなったらどうしよう」「真っ暗。絶望」などと思うが、年齢、苦労を重ねてくると、「何であんなことを悩んでいたんだろう」と思うものだ。ましてや波瀾万丈、苦労も経験も、人間洞察、教養も重ねてきた佐藤愛子さんの答えは凄い。それにしても、困っているだけで本当に悩まない。自分で考えない。周りばかり気にしてグズグズしている人のなんと多いことか。「生ぬるいこといっていないで、喧嘩してごらん!」といわれても、「それができないから悩んでいる」とグズグズ言う。「なに?それが出来ないから相談(母親の干渉から逃れたい)してるんだって? そんならお母さんのいいなりになって、そのうちに老衰して何もいわなくなる日を待つんだわね」と答えている。
 「政治制度から考える」が副題。「財政赤字が拡大している」「増税が必要でも政治家は先送りしている」「日本人の時間当たりの労働生産性は低い」「最低賃金の上昇は鈍い」「深刻化する人口減少・少子高齢化に手が打てていない(人災)」「賃金体系や税制が男性稼ぎ主世帯優遇のシステムになっている」――。日本の政治で問題視されることは多岐にわたるが、政治制度から改革の方途を考えようとしている。
「政治制度から考える」が副題。「財政赤字が拡大している」「増税が必要でも政治家は先送りしている」「日本人の時間当たりの労働生産性は低い」「最低賃金の上昇は鈍い」「深刻化する人口減少・少子高齢化に手が打てていない(人災)」「賃金体系や税制が男性稼ぎ主世帯優遇のシステムになっている」――。日本の政治で問題視されることは多岐にわたるが、政治制度から改革の方途を考えようとしている。
権力分立の大統領制と権力融合の議院内閣制――。大統領制は決して強くなく「政策決定は立法府の議会」「立ちはだかる議会」となり、日本では連立が安定していることもあり、議院内閣制による政権の安定が確立しているが、首相一強体制の死角もある。とりわけ強いリーダーとみなされてきたのが英首相だが今・・・・・・。仏の半大統領制。国会審議において「もっと議員立法を」「法案修正がほとんどないのは、与党の事前審査」「質疑と質問は違う」「衆議院解散の頻度が高く、落ち着きのない政治を生む」等が語られる。
第3章は「無能な議員が多すぎる?」だ。「投票率が低すぎる」「ネガティブ報道にさらされる議員」「世襲だらけ」「女性議員比率は世界最低レベル」などを指摘しているが、選挙制度自体の問題も大きい。第4章は「選挙が政治をダメにする?」だが、変える難しさはこの20数年、本当に味わい尽くしてきたことだ。
情報社会のなかでのメディア政治をどう生き抜くか。「政治は人が成すもの」であり、どう人間力を鍛えていくか。複雑化する社会、世界のなかで、どう識見・洞察力を磨くか。現場感覚、官僚とは別のリーダーシップをどう確立するか。「未来に責任」――どう時間軸をもった政治を築くか。政治制度ではないことに、課題はとてつもなく重く大きい。
 ふと遭遇した出来事に、「なぜ」と問いかけることが、問題の深淵を覗くことになる。高校2年生の図書委員仲間の松倉詩門と僕(堀川次郎)。二人には、いつも奇妙な謎めいた相談事が持ち込まれる。快活だが裏を疑い策略的思考をもつ松倉、性善説的な真に受けたまま思考を掘り下げていく堀川は、互いを刺激し合いつつも信頼のなかで問題を解決していく。全6編。
ふと遭遇した出来事に、「なぜ」と問いかけることが、問題の深淵を覗くことになる。高校2年生の図書委員仲間の松倉詩門と僕(堀川次郎)。二人には、いつも奇妙な謎めいた相談事が持ち込まれる。快活だが裏を疑い策略的思考をもつ松倉、性善説的な真に受けたまま思考を掘り下げていく堀川は、互いを刺激し合いつつも信頼のなかで問題を解決していく。全6編。
「913」――。「金庫をあけるのを手伝ってほしい」と浦上麻里先輩に依頼を受け意外な結末に。「ロックオンロッカー」――。二人である美容院に行くことになったが、ふとした店長の一言が引っかかる。「貴重品は、"必ず"、お手元にお持ち下さいね」・・・・・・。そこから事件がひも解かれてゆく。「金曜に彼は何をしたのか」――。金曜日の夜、学校の職員室の前の窓が割られた。犯人に仕立て上げられた男のアリバイはあるのか、何をしていたのか。
「ない本」――。3年生の香田が自殺した。彼から遺書を預かっていたのに止められなかった男の苦悩から発せられた行動は・・・・・・。「昔話を聞かせておくれよ」――。6年前に死んだという親父の残した宝物を探す。さわやかさを感ずる結果と思わせるが、次の「友よ知るなかれ」で、松倉の家庭の秘密が明らかにされる。
二人の距離感をもった心の交い合いは、大人のもの。
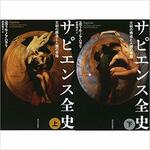 まさに壮大なサピエンス全史、人類が進化し文明が発展してきたという進歩史観等の楽観的な前提自体を覆すサピエンス全史となっている。7万年前、アフリカの片隅で生きていくのに精一杯の"取るに足りない動物"であったホモ・サピエンスが、全地球の主として"万物の霊長"を自称し、食物連鎖の頂点に立って環境を征服。いかに都市を築き、帝国を打ち立て、広大な交易ネットワークを築き上げてきたか。しかしヘブライ大学歴史学教授のユヴァル・ノア・ハラリ氏は歴史を俯瞰しつつ、最後に2つの痛烈な疑問を突きつける。「私たちは以前より幸福になっているのか」「正真正銘のサイボーグ、バイオニック生命体に変身する超ホモ・サピエンス時代に突入する瀬戸際にある」である。「人間の力は大幅に増したが、個々のサピエンスの幸福は必ずしも増進しなかったし、他の動物たちには甚大な災禍を及ぼした」「私たちは何を望みたいか、望んでいるかもわからない。不満で無責任な神々ほど危険なものがあるだろうか?」と結ぶ。
まさに壮大なサピエンス全史、人類が進化し文明が発展してきたという進歩史観等の楽観的な前提自体を覆すサピエンス全史となっている。7万年前、アフリカの片隅で生きていくのに精一杯の"取るに足りない動物"であったホモ・サピエンスが、全地球の主として"万物の霊長"を自称し、食物連鎖の頂点に立って環境を征服。いかに都市を築き、帝国を打ち立て、広大な交易ネットワークを築き上げてきたか。しかしヘブライ大学歴史学教授のユヴァル・ノア・ハラリ氏は歴史を俯瞰しつつ、最後に2つの痛烈な疑問を突きつける。「私たちは以前より幸福になっているのか」「正真正銘のサイボーグ、バイオニック生命体に変身する超ホモ・サピエンス時代に突入する瀬戸際にある」である。「人間の力は大幅に増したが、個々のサピエンスの幸福は必ずしも増進しなかったし、他の動物たちには甚大な災禍を及ぼした」「私たちは何を望みたいか、望んでいるかもわからない。不満で無責任な神々ほど危険なものがあるだろうか?」と結ぶ。
「20万年前東アフリカでホモ・サピエンスが進化する」「7万年前、認知革命が起こる。虚構の"言語"が出現し、歴史的現象が始まる」「虚構、架空の事物について語り、創作する能力、言語が拡大する」「7万年前の認知革命から、1万2千年前の農業革命の期間、狩猟採集民は豊かな暮らしだった。大型動物が死滅していく」「農業革命で大変化。定住、家畜化、栽培化、人口増、贅沢の罠、家畜化された動物の悲劇、空間の減少と季節等の時間軸、神話と法制度が導入される」「書記体系(記号を使っての情報保存)、文字・数の体系の衝撃、秩序としてヒエラルキーと差別が生ずる(人類の想像上の産物)(カーストも白人・黒人も男女も)」・・・・・・。そして「最強の征服者・貨幣を生む(BC3000年紀半ばにメソポタミアで銀のシェケル誕生)」「グローバル化を進める帝国のビジョン」――。ここまでが上巻だ。
下巻は「宗教という超人間的秩序」「無知の発見と近代科学の成立」「科学と帝国の融合(なぜヨーロッパは世界の覇権を握れたか)(19世紀のヨーロッパの支配は産業・科学・軍事複合体)(征服の精神構造)」「拡大するパイという資本主義のマジック(東インド会社のやったこと)(自由主義資本主義の強欲)」「国家と市場経済がもたらした世界平和」・・・・・・。サピエンスは「何をやってきたのか」「何を望むのか」――。副題は「文明の構造と人類の幸福」。
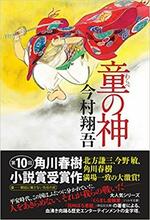 935年平将門の乱から1017年藤原道長が太政大臣になる平安時代後期。京、山城、大和、摂津、丹波の地域――。朝廷を背景にして源頼光、その配下の渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、さらには坂田金時らは、京人(みやこびと)として、周辺を「童」と蔑称(童は辛、目、重と分けられ、目の上に墨を入れられ重荷を担ぐ奴婢)し、制圧しようとした。摂津竜王山に移った滝夜叉、北に盤踞する丹波大江山の粛慎(鬼)、南に勢力を拡大する大和葛城山の畝火(土蜘蛛)らは三山同盟して立ち向かう。その中心に押し上げられたのが越後藩原郡の豪族の出の桜暁丸(おうぎまる)。花天狗とも酒呑童子とも呼ばれた桜暁丸は、皆が手をたずさえて生きられる人の世をひたすら求めて戦う。「京人は我らを鬼と呼ぶ。土蜘蛛と呼ぶ。そして童(わらわ)と呼び蔑む。理由などない。己が蔑まれたくないから誰かを貶める」「胸を張ってくれ。我らは何も汚れてなどいない。父母を想い、妻を想い、子を想い、仲間を想う。我らは誰よりも澄んだ心を持って生きたはずだ」「生きるのだ、何があろうと生き抜け。そして愛しき人と子を生し、我らの心を紡いでいこう」――。
935年平将門の乱から1017年藤原道長が太政大臣になる平安時代後期。京、山城、大和、摂津、丹波の地域――。朝廷を背景にして源頼光、その配下の渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、さらには坂田金時らは、京人(みやこびと)として、周辺を「童」と蔑称(童は辛、目、重と分けられ、目の上に墨を入れられ重荷を担ぐ奴婢)し、制圧しようとした。摂津竜王山に移った滝夜叉、北に盤踞する丹波大江山の粛慎(鬼)、南に勢力を拡大する大和葛城山の畝火(土蜘蛛)らは三山同盟して立ち向かう。その中心に押し上げられたのが越後藩原郡の豪族の出の桜暁丸(おうぎまる)。花天狗とも酒呑童子とも呼ばれた桜暁丸は、皆が手をたずさえて生きられる人の世をひたすら求めて戦う。「京人は我らを鬼と呼ぶ。土蜘蛛と呼ぶ。そして童(わらわ)と呼び蔑む。理由などない。己が蔑まれたくないから誰かを貶める」「胸を張ってくれ。我らは何も汚れてなどいない。父母を想い、妻を想い、子を想い、仲間を想う。我らは誰よりも澄んだ心を持って生きたはずだ」「生きるのだ、何があろうと生き抜け。そして愛しき人と子を生し、我らの心を紡いでいこう」――。
桜暁丸らの死闘は壮絶なものがあるが、朝廷側にも童(わらべ)と呼んだ渡辺綱、同じ抑圧された側から加わった相模足柄山出身の民・坂田金時らがおり、桜暁丸らとの心の交流が描かれる。大江山の酒呑童子の側から時代を剔抉する力作。

