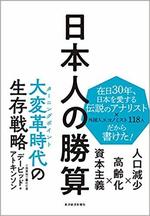 人口減少と少子高齢化のダブルパンチの日本。パラダイムシフトが緊急、不可欠だ。先進国最低水準の日本人の所得を上げること、生産性向上が必須条件となる。「日本は人材の評価は世界第4位なのに、生産性は第28位」「優秀な人材が山ほどいるのに、生産性・所得水準が低く、ポテンシャルを発揮できていない」と指摘し、とくに最低賃金の引き上げを強く訴える。「上手に最低賃金を引き上げる政策が、経済成長、女性活躍、格差の是正、福祉問題、財政問題など、ありとあらゆる分野における問題解決に大きく貢献する」といい、日本にはそれができる、勝算があるという。
人口減少と少子高齢化のダブルパンチの日本。パラダイムシフトが緊急、不可欠だ。先進国最低水準の日本人の所得を上げること、生産性向上が必須条件となる。「日本は人材の評価は世界第4位なのに、生産性は第28位」「優秀な人材が山ほどいるのに、生産性・所得水準が低く、ポテンシャルを発揮できていない」と指摘し、とくに最低賃金の引き上げを強く訴える。「上手に最低賃金を引き上げる政策が、経済成長、女性活躍、格差の是正、福祉問題、財政問題など、ありとあらゆる分野における問題解決に大きく貢献する」といい、日本にはそれができる、勝算があるという。
「人口減少と高齢化によって日本経済のデフレ圧力はこれから本格化する。必要なのは"賃上げ"によるインフレ誘導策だ」「福祉制度を維持するためにも、生産性向上を継続的に実現する経済モデルに切り替えよ。人口増加経済モデルから人口減少経済モデルである『高付加価値・高所得』資本主義へ転換せよ」「デフレ圧力緩和のためには供給過剰を調整するための輸出振興を」「企業の平均規模を大きくすることが生産性を高めるためには重要。"企業の統合促進"が不可欠だ」「最低賃金を引き上げて生産性を高めよ。"正当な評価"は人を動かす」「賃上げショックで生産性を高めよ。できなければ国が破綻する」「人材育成トレーニングを"強制"せよ。教育の基本的対象は大人だという新たなパラダイムを」――。各章でデータ・論文を用いて主張している。シンプルかつ明解で鋭い。
 登場するのはわずか3人。ビットコインの採掘(マイニング)を命ぜられる一人課長の中本哲史、その恋人で中絶と離婚のトラウマを抱えながら頻繁に海外に出かける外資系証券会社勤務の田久保紀子、「ニムロッド」と名乗り小説家の夢に挫折した同僚・荷室仁。
登場するのはわずか3人。ビットコインの採掘(マイニング)を命ぜられる一人課長の中本哲史、その恋人で中絶と離婚のトラウマを抱えながら頻繁に海外に出かける外資系証券会社勤務の田久保紀子、「ニムロッド」と名乗り小説家の夢に挫折した同僚・荷室仁。
人はかつても今も失敗、挫折やトラウマを抱え込みながら生きる。しかし、遭遇する社会は、AI・IT・ロボット、仮想通貨・ビットコインの世界が加速度的に押し寄せる。一方、「創世記」におけるニムロッドは「反逆する者」の意味をもちバベルの塔建造の企画発案者と見なされる。バベルの塔は人間の欲望の果てしなさ、文明の危うさを示すが、これからの社会は寿命すらも消し去られ地球の限界を突破するまでの人口増、情報技術の発展が生み出す並列と情報的重力の社会となりかねない。計算能力を飛躍的に向上させた人類はこの世の理すべてを知り尽くし、駄目な人間、失敗する人間を振り捨て、個が消え、倫理を超え、巨大な空虚に人間を放り出す。
「これ以上進んでいいのかどうか、首を傾げながらやっているんじゃないかな。何と言うか、全体的な不快感だけが漂っている」「君の願いももう完璧に叶ったのではないか?それでも君はまだ、人間でい続けることができるのかな?」「僕のビットコインは元々根拠が無に等しいからこそ・・・・・・膨れ上がった。・・・・・・子供の頃から思い描いていた高い塔を手にすることができた。だが、なぜだろう? その塔を手に入れてから、僕の右目からは涙が止まらなくなったのだ」――。バベルの塔、仮想通貨・ビットコインから文明の空虚と不快感・違和感を問いかけている。
 「0歳から100歳までの哲学入門」が副題。哲学とは人生、世界を自分で考えることだ。生老病死――命の終わり、人生のはかなさ、四苦八苦を考えることだが、この情報社会、教育が浸透し、仕事を余儀なくされている喧噪の社会ではなかなか難しい。自由に考えているかといえば、世の常識や軌範、人間関係、社会の通念や仕組み、場の空気を読むことを求められているゆえに、思考も発言も無意識的に自己規制している。「考えること」とは「自由になること」、考えることによって自由になる。自己を縛りつける制約から自らを解き放つことだ、という。そして「対話が哲学的になった瞬間」には「体が軽くなってふっと浮く感覚。一気に、あるいはゆったりと広がるような感覚。目の前が開け、明るくなる感覚」を体全体で感ずる。自由と責任をいっしょに取り戻す。自分自身を生きることなのだという。
「0歳から100歳までの哲学入門」が副題。哲学とは人生、世界を自分で考えることだ。生老病死――命の終わり、人生のはかなさ、四苦八苦を考えることだが、この情報社会、教育が浸透し、仕事を余儀なくされている喧噪の社会ではなかなか難しい。自由に考えているかといえば、世の常識や軌範、人間関係、社会の通念や仕組み、場の空気を読むことを求められているゆえに、思考も発言も無意識的に自己規制している。「考えること」とは「自由になること」、考えることによって自由になる。自己を縛りつける制約から自らを解き放つことだ、という。そして「対話が哲学的になった瞬間」には「体が軽くなってふっと浮く感覚。一気に、あるいはゆったりと広がるような感覚。目の前が開け、明るくなる感覚」を体全体で感ずる。自由と責任をいっしょに取り戻す。自分自身を生きることなのだという。
その哲学的対話の生きた場をどうつくるのか。哲学とは「問い、考え、悟り、聞くこと」だが、場をどうつくるか。座談会、修行の集いの場、対話と場づくりの重要性を考えさせられた。その意義とともに中身をもっと詰めなければと思う。「哲学対話」は最近とくに試みられているようだ。本書では、その「考える方法」が具体的に示される。
 「AI時代に活きる幼児教育」が副題。AI・IoT・ロボットの急進展するこれからの社会。仕事がそれらに取って代わられる社会。その真っ只中で人生を送ることになる今の子どもたち。それではどういう幼児教育が大切となるのか。いまや切実な重要問題だ。
「AI時代に活きる幼児教育」が副題。AI・IoT・ロボットの急進展するこれからの社会。仕事がそれらに取って代わられる社会。その真っ只中で人生を送ることになる今の子どもたち。それではどういう幼児教育が大切となるのか。いまや切実な重要問題だ。
日本の幼児教育は「遊び保育」が主流であった。またその対極の"お受験"のためのペーパー問題を解かせる「教え込み教育」も台頭した。しかし、AI時代では特に、「考える力」「管理されなくても与えられた問題を解決できる自律した人間」「柔軟性があり論理的な頭脳をつくり上げる就学前の"教科前基礎教育"」「IQに代表される認知能力だけでなく、忍耐力、協調性、計画力、表現力、意欲、発想力、自己制御力といった非認知能力が重要」だという。
そして「幼児期の早い段階から子どもが自分で本を読むことはお勧めしない」「幼児期は"聴く力"を育み、子どものもつ想像力を膨らませる時期」「読み・書き・計算は小学校に入ってからの課題。考える力・思考力を育てるのが幼児教育」「文章題ができない子が多い。論理的に意味を把握できないからだ」と言い、「モンテッソーリ教育」「課題を見つけて、夢中になって行う集中現象を起こして能力を獲得する」「遠山啓の"原数学"――数学的思考を育てる」「KUNOメソッド」「思考力をつけるために必要な10の力――ものごとの特徴をつかむ、比較する、順序づける、全体と部分の関係など」「"聴く・話す"をもっと大事に」などを紹介する。
「学力よりも意欲の時代へ」「認知能力を育てる過程で非認知能力も育てる」「幼児期の考える力は、主体的に参加し仲間と考えながら課題を解決する"アクティブ・ラーニング"でしか育たない」――。これまでの「教え込み教育」「知識の豊富さ、記憶の量獲得の教育」では、AI時代に通用しない。Educationとはラテン語で「引き出す」という意味だという。
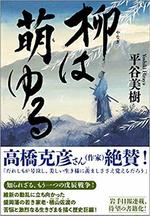 幕末の盛岡藩内――。京の都や江戸市中が、攘夷と開国、尊皇攘夷、勤皇だ佐幕だと激動するなか、盛岡藩では貧困と重税にあえぐ百姓が頻繁に一揆を起こしていた。藩財政の逼迫、一揆への弾圧、藩の重商主義対緊縮策の対立と反目、更なる不満の暴発と藩は揺れに揺れ、お家騒動を惹起した。百姓にも心を寄せた若き藩士・楢山茂太(後の佐渡)であったが、ペリー来航以来の日本の激動の渦に巻き込まれ、盛岡藩をカジ取りをする中心者に押し上げられていく。
幕末の盛岡藩内――。京の都や江戸市中が、攘夷と開国、尊皇攘夷、勤皇だ佐幕だと激動するなか、盛岡藩では貧困と重税にあえぐ百姓が頻繁に一揆を起こしていた。藩財政の逼迫、一揆への弾圧、藩の重商主義対緊縮策の対立と反目、更なる不満の暴発と藩は揺れに揺れ、お家騒動を惹起した。百姓にも心を寄せた若き藩士・楢山茂太(後の佐渡)であったが、ペリー来航以来の日本の激動の渦に巻き込まれ、盛岡藩をカジ取りをする中心者に押し上げられていく。
官軍に抗する奥羽越列藩同盟。「列藩同盟の諸藩はいずれも尊皇の心をもっております。同盟するは、薩長の横暴に抗するため。薩長こそが奸臣、朝敵である」――。しかし、次第に切り崩され、盛岡藩は秋田の久保田藩に攻め込み、賊軍の汚名を着せられることになる。最も危惧した薩長が牛耳る世の濁流に飲み込まれ、その責任を楢山佐渡は一身に負うことになる。大罪人となって盛岡に護送された楢山佐渡を鞭打ちどころか、侍・民百姓は手を合わせ涙をもってその駕籠を迎えた。
「花は咲く 柳は萌ゆる春の夜に うつらぬものは武士の道」――辞世の句である。時は移ろっても武士の道は変わらぬと読めるが、「時は移ろっていくのに、なにゆえ武士は変わらぬであろうという厭世の気持ちを歌いました」と佐渡に言わせている。政を司る者の時代の先を観る眼、高潔な心、決定する覚悟。そして戊辰戦争とは何であったのかを楢山佐渡の生死の様をもって突き付けている。

