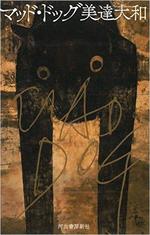「ネット炎上」――。有名人であっても無名人であっても、ツイッター、フェイスブック、SNSなどで、少々品の悪い、ふざけた、軽率な発言をする。それが広がり、突然、不特定多数の人から非難され、罵られ、袋叩きとなり、職を解雇されたり、恥と罪悪感から人生自体が崩壊する。原題は「だから君は公開羞恥刑に遭った」だ。著者は、そうした深刻な体験に遭った一人ひとりに会い話を聞いて考える。私たち自身もいつでも暴徒と化し、多くの人を晒し者にし、犠牲にする。「悪者を倒すのは正義」という面もあるが、現代の司法制度は歴史的に練り上げられ、被害者にも基本的人権があり、裁判もあり、罰の恐怖が罪を発生する抑止力となる。しかし、ネット上の被疑者にはそれがない。今、原則が覆され始め、新たな恐るべき時代が到来したのだ。
「ネット炎上」――。有名人であっても無名人であっても、ツイッター、フェイスブック、SNSなどで、少々品の悪い、ふざけた、軽率な発言をする。それが広がり、突然、不特定多数の人から非難され、罵られ、袋叩きとなり、職を解雇されたり、恥と罪悪感から人生自体が崩壊する。原題は「だから君は公開羞恥刑に遭った」だ。著者は、そうした深刻な体験に遭った一人ひとりに会い話を聞いて考える。私たち自身もいつでも暴徒と化し、多くの人を晒し者にし、犠牲にする。「悪者を倒すのは正義」という面もあるが、現代の司法制度は歴史的に練り上げられ、被害者にも基本的人権があり、裁判もあり、罰の恐怖が罪を発生する抑止力となる。しかし、ネット上の被疑者にはそれがない。今、原則が覆され始め、新たな恐るべき時代が到来したのだ。
ルポは多くにわたる。著者自身が直面した「ツイッターのなりすまし」「ボブ・ディランの発言を著書で捏造して非難を浴びたライター」「ある女性の冗談ツイッターが人種差別として大炎上した事件」「戦没者慰霊施設の前で不謹慎なポーズを取って、フェイスブックに載せて破滅した女性」「流出した売春婦の顧客リストに名前が載っていた牧師」「被告人にあえて羞恥刑を与えることで更生に導こうとする判事」・・・・・・。そしてルポを丁寧に続けながら、「ほとんど無傷で復活した人」やネット上で忘れられるように「グーグルの検索結果を変えることをサポートする新ビジネス」の姿まで紹介する。
焦点は、「恥辱」「懲罰としての恥辱」「公開羞恥刑=ネットリンチ」だ。「公開羞恥刑」は歴史初期からあり、日本でも「市中引き回し」や「三条河原」等で行われたことだが、今異なる位相で蘇ったのではないかとの問いかけだ。「恥と誇り」は人間の根源を成すものだ。それがズタズタにされた時、人は生きられない。このネットによる「公開羞恥刑」に対するシステムはどうすればいいのか。ますます過酷化する現代社会と人間は、なぜこうした残酷な結末を起こしてしまうのか、放置してしまうのか。著者は「群衆心理」「恥のない世界」「"恥を心の内側にとどめておくと、その恥は成長してしまう"という考えのもとでの講座の開催(恥ずかしいと感ずることからの脱却)」などにも肉薄する。たしかに「羞恥刑に関する議論もまだこれから」が現状だ。
「フィードバック・ループは、人間の行動を変えさせる有効な道具になる」「フィードバック・ルールのせいで、SNSは巨大なエコー・チェンバー(共鳴室)のようになっている。自分と考えが同じ人たちばかりと接することで、自分は正しいという信念を絶えず強化し、"称賛"というフィードバックがあったことで行動を継続する」「テクノロジー至上主義の人は民主主義の新しい形態とみなしているようだが、そうではない」「自分の作った世界に閉じ籠もり、異質なものを目にすることができなくなる。・・・・・・自分と別の考え方を持った人たちの別の世界が存在するという考えが、頭から抜け落ちる」「協調性のないのが人間である。だが今は、協調性があり、体制に順応する人にばかり居心地の良い、極端に保守的な世界ができつつあるように思う(同調)。"これが普通ですよ"と皆が始終言っている」「普通とそうでないものの間に境界線を引き、普通の外にいる人たちを除外して、世界を分断する――そんな時代になりつつあるのではないだろうか」――そう警告を発して結んでいる。
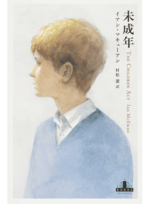 自らの責任で難問に断を下す裁判官の苦悩は、社会が複雑化してさらに深まる。「自らの夫婦関係にも悩む女性裁判官のもとに、信仰から輸血を拒む少年の審判が持ち込まれる」というテーマを、英国を代表する作家・マキューアンが描く。時間が切迫し、人命を急ぎ救えと主張する病院側。信仰で救われた家族はそれを拒む。少年は自らの判断をはたして持ち得るのか。裁判官は何に基づいて断を下せるのか。
自らの責任で難問に断を下す裁判官の苦悩は、社会が複雑化してさらに深まる。「自らの夫婦関係にも悩む女性裁判官のもとに、信仰から輸血を拒む少年の審判が持ち込まれる」というテーマを、英国を代表する作家・マキューアンが描く。時間が切迫し、人命を急ぎ救えと主張する病院側。信仰で救われた家族はそれを拒む。少年は自らの判断をはたして持ち得るのか。裁判官は何に基づいて断を下せるのか。
生命、倫理、社会条理、幸福、法、成年・未成年とは、生きる意味とは・・・・・・。人類永遠の課題にも、一瞬の結論を下さねばならない裁判官。緊迫した状況を深く抉りながら精緻に描き出す。煩悶の結果として、裁判の結論も物語の終結も予想どおりだが、生きたときに「信仰をなくしたとき、世界はどんなひらかれた、美しい、恐ろしい場所に見えたことだろう」「アダムは彼女に期待して来たが、彼女は宗教に代わるなにひとつ、なんの保障もあたえなかった」という更なる深渕に引き込まれる。
 我々の若い頃、難しいドストエフスキーの高い山に登攀することは誇りある挑戦だった。辻原登さんも同年代。しかも辻原さんは"ドストエフスキー嫌い"を公言し、あの「大審問官」にしても「いろいろな哲学者や批評家たちが、この大審問官の話というのを大袈裟に論じていますが、実はそんなに深い話ではないし、福音書を深く読んだ方がよほどいいと思う」という。ドストエフスキーの世界観、人物、作風、クセ、時代性等を含め、小説の中身を徹底的に読み込み、解き明かしているからこそ言える言葉だ。
我々の若い頃、難しいドストエフスキーの高い山に登攀することは誇りある挑戦だった。辻原登さんも同年代。しかも辻原さんは"ドストエフスキー嫌い"を公言し、あの「大審問官」にしても「いろいろな哲学者や批評家たちが、この大審問官の話というのを大袈裟に論じていますが、実はそんなに深い話ではないし、福音書を深く読んだ方がよほどいいと思う」という。ドストエフスキーの世界観、人物、作風、クセ、時代性等を含め、小説の中身を徹底的に読み込み、解き明かしているからこそ言える言葉だ。
難解であり、場面を心理も含めて立体的に建ち上げて詳細に語り、しかも未完であるがゆえに「カラマーゾフの兄弟」は重苦しいが、本書で暗雲を払うように解読してくれてきわめて面白い。「『カラマーゾフの兄弟』を『要約』する」「『カラマーゾフの兄弟』を深める」「亀山郁夫×辻原登 文学の『時代』と『時間』」「ドストエフスキーを貫く『斜めの光』」――。朝日カルチャーセンターでの「連続講義」。まさに「面白い(目の前がパッと開ける)」思いがした。
 「共生社会」が叫ばれるが、背景には中間層の凋落、分断社会の進行、コミュニティの崩れ、支え合いが難しくなっているからだ。「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、地域住民が支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティ形成は重要だが、難題だ。
「共生社会」が叫ばれるが、背景には中間層の凋落、分断社会の進行、コミュニティの崩れ、支え合いが難しくなっているからだ。「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、地域住民が支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティ形成は重要だが、難題だ。
今、「現役世代の低所得化と未婚化」「困窮の連鎖と子どもの貧困」「高齢世代の"再困窮化"」等が進行して、しかもこれらが複合して貧困と孤立が顕在化している。深刻な、かなり本質的事態だ。宮本さんのいう「生活保障」は「雇用と社会保障」を合わせて考える提言だが、従来の「支える側」と「支えられる側」を峻別してきた2分法的な日本の社会保障を、複合的に解決への道をつけるということだ。「強い個人」でいる間に「弱い個人」に転ずるリスクに備えるという20世紀型、2分法的な社会保障制度を変える試みだ。雇用と社会保障・福祉の連携は必須であるが、雇用の劣化、非正規問題、未婚化、孤立化の連鎖と困窮の三世代化に具体的に対応しなければならない。支える側の「強い個人」が標準となりえない時代、身体的には高齢者イコール「弱い個人」ではないといえる時代を迎えたのだ。
そこで提起される共生保障とは、「支える側」を支え直す。職業訓練や子育て支援、就学前教育等だ。「支えられる側」も社会参加、就労支援を促し、より多くの人が「支え合いの場」に参入できるようにする。まさに共生保障は、多様な困難を抱える多数の人々を、社会につなぎ能力を発揮することを可能にする仕組みである。
社会保障の普遍主義的改革が重要だが、現実には「財政的困難」「自治体の制度構造」「中間層の解体」の構造的ジレンマに制約されており、これを突破する具体的対策を進める必要がある。「強い個人」が中間層の縮小とともに減少し、「弱い個人」が増大する今日、中間層の不安や怒りをポピュリズムで対処するのではなく、断層をふさぐ共生保障の政治が期待されている。