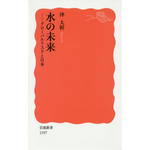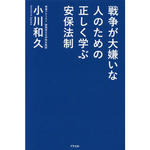 国家国民の安全をどう守るか。北朝鮮の昨今をはじめとして日本周辺の安全保障環境の変化にどう対処するか。国際社会の平和と安全にPKOをはじめとして、日本はどう関わるか。この2年余、国会で議論し、成立した平和安全法制。
国家国民の安全をどう守るか。北朝鮮の昨今をはじめとして日本周辺の安全保障環境の変化にどう対処するか。国際社会の平和と安全にPKOをはじめとして、日本はどう関わるか。この2年余、国会で議論し、成立した平和安全法制。
政治は、国際情勢にしても経済においても、どこまでもリアリズムが貫かれなければならないと思う。煽情的な政治、ポピュリズムの政治に陥ることを戒めなくてはならない。
小川さんは「集団的自衛権とはそもそも何か」「平和安全法制はどんな法律が含まれているか」「集団的自衛権と集団安全保障はどう違うか」「自衛隊の国連平和維持活動(PKO)参加の実情」「ROEとは何か」「自衛官が"戦死する"というデマ」「若者は徴兵されるのか」「平和安全法制と憲法9条」などを、軍事アナリストとして国際社会のリアリズムのなかで丁寧に整理して解説している。そして「安保法制で日本の平和と安全は高まる。"戦争法""戦争ができる国になる""自衛官が戦死する""アメリカの戦争に引きずり込まれる"などは誤りであり、デマである」と、安全保障の根幹と実態から指摘する。
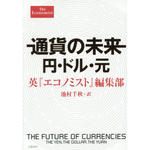 英「エコノミスト」誌が直近に執筆した、「通貨」に関する記事を集めて一冊に編んだもの。複雑化する世界経済を見通す鍵として「通貨」の角度から分析したものだ。
英「エコノミスト」誌が直近に執筆した、「通貨」に関する記事を集めて一冊に編んだもの。複雑化する世界経済を見通す鍵として「通貨」の角度から分析したものだ。
焦点は何といっても米国、ドル。次いで元だ。「この70年間、世界の金融・通貨システムに君臨してきた基軸通貨、ドルだが、その力を支えてきた米国の経済力は弱体化し、この覇権のぐらつきによって世界経済は急激に不安定化している」「米国はIMF、世界銀行、WTOといったグローバルな経済的枠組みに責任を果たさないようになっている。その原因は、国内の中流層の没落とリンクした国内政治での左右両極のポピュリストの台頭にある」「急速に拡大している米国外のドル資産、オフショアドルの世界。このドル資産をもとに米国以外の国は経済を運営しているが、そこには危機の際に国家や金融機関を救う『最後の貸し手』がいない」「世界各地に着々と人民元取引のネットワークを築いている中国だが、それは中国国内の完全自由化とトレードオフであり、習近平のジレンマだ」「通貨の未来――ビットコインとサイバー上におかれる改竄できない公開台帳『ブロックチェーン』の技術は、為替リスクのない信頼できる究極の基軸通貨にすることができるのか」・・・・・・。
米経済や中国の政治・経済をイギリスからの視点で語り、円についても「マイナス金利」「アベノミクス」について述べている。米国の「金利上げ」をとってみても、世界の経済全体がリンクして激震の波が伝播していることが実感させられる。
 2012年から3年余、雑誌「潮」や読売新聞等で発表してきた文章をまとめたもの。この間、世界も日本も政治・経済・社会の激動が続いたが、その激動の底流にある人間、人心、文化、文明の大きな変化から解き明かしている。まさに如実知見。哲学と教養が心奥に届き響く。掲載された都度、「『持続可能な成長』を脱却する」の定常型社会論をはじめとして、安倍総理とコピーをもとに話し合ったことも多々ある。現代社会の本質を剔り、その確たる動体視力が素晴らしい。
2012年から3年余、雑誌「潮」や読売新聞等で発表してきた文章をまとめたもの。この間、世界も日本も政治・経済・社会の激動が続いたが、その激動の底流にある人間、人心、文化、文明の大きな変化から解き明かしている。まさに如実知見。哲学と教養が心奥に届き響く。掲載された都度、「『持続可能な成長』を脱却する」の定常型社会論をはじめとして、安倍総理とコピーをもとに話し合ったことも多々ある。現代社会の本質を剔り、その確たる動体視力が素晴らしい。
「高学歴・低学力という病弊」「世は無常であることを痛感するがゆえに、今日を常の通りに生きようとする、という積極的無常観のすすめ(今日を深く味わう生き方)「混迷を極める"道徳感情"」「"介護の社会化"が家族を救う(新しい家族関係)」「(科学技術の進展のなか)だからこそ今必要なのは人間とは何かという哲学」「戦争を起こし、一転して再び平和な日常に回帰した日本人の"律儀"と呼ぶ倫理感覚」「目を覆う高学歴・低学力化を変えるには、まず義務教育の再構築」「教養と知的能力を備えた社会人を育てるに十分な教育を」「人生十年先延ばし論」「国立戦没者追悼施設のための議論を」「ポピュリズムとナショナリズム」「若者の労働観を抜本的に変える教育を」「18歳選挙権とそこに欠落している権利は勝ち取るものだという歴史の教訓」「戦争犯罪を詫び続ける理由」「知的エリートによる戦後復興」「人類史的大転換に知的に衰弱した日本社会は対応できるか」「煽情的な政治運動、ポピュリズム的な大衆感情をいかに賢明に防げるか」「政治に知性の安全弁を」――。この哲学不在の時代、いずれも改めて感銘を深くした。
地球環境と水問題――この問題の全貌と解決への方向性、メインストリームを真正面から示している。「水の悲観論者は間違っているが役に立つ。水の楽観論者は正しいが危険だ」――悲観論と楽観論は、水に限らず気候変動でも、エネルギーや食料でも、世界経済でも常に提起され、その過激さはイデオロギーとなり、現実的解決への行動を妨げる傾向にあるようだ。沖さんは「水と地球環境と人類の未来についての悲観論と楽観論の適切なバランス感覚を多くの方に得ていただければ幸甚である」と言っている。
「地球の水の何が問題か」「なぜ、どのように、水危機がグローバルリスクなのか」「グローバルリスクへの取り組み」「2014年に国際標準が発行されたウォーターフットプリント」「仮想水貿易――世界の水に頼る日本の暮らし」「水から見た食料問題」「気候変動と水の関係」「気温の上昇と豪雨の頻度」「未来可能性の構築へ向けて――危機感は重要だが、プラス方向の動機付けもまた有効」「千年科学技術をめざそう」「持続可能性の構築」――。「環境と経済の両立に悩んでいた時代はとうの昔に過ぎて、社会と経済と環境という三者の持続性をいかにバランスよく構築するかを構想し、その実現に向けて取り組む時代が来ている」と結んでいる。
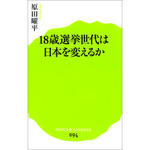 新たな有権者240万人は日本社会にどんな変化をもたらすか。若者と政治、若者と選挙、若者の意識の変化を現場から探っている。
新たな有権者240万人は日本社会にどんな変化をもたらすか。若者と政治、若者と選挙、若者の意識の変化を現場から探っている。
「若者は政治に興味がないというのは必ずしも正しくない」「(世界に比べて)日本の若者の政治離れが進んでいるのは、若者があえて政治に強い問題意識を持たずとも、失業率が高過ぎるヨーロッパの若者や、大学の学費が高過ぎるアメリカの若者と比べると、相対的に親の庇護や、そこそこの有形無形のセーフティーネットの下、それなりに安定して生活していける、ということを意味しているかもしれない」「現在の若者は、今の生活に満足度は高いものの、将来を非常に不安に思っている」「今の18、19歳は"脱ゆとり世代"で"さとり世代"。右肩上がりの景気感を全く知らない。物欲はあまりなく、車やブランド品、海外、お酒・・・・・・。無駄な消費や行動はできるだけ避け・・・・・・」「18歳選挙世代はラインというSNSアプリとともに青春時代を過ごしている」「将来は不安なので、無理をしないで今を楽しもう、という諦観の上に立った満足感を求める傾向」「不安のタネは、就職や結婚」「世界をゆるがす若者のパワー(各国)」「本来若者は生意気な生き物だったのに、"わからないのに投票に行っていいのか"と遠慮しがち」・・・・・・。
希望が持ちづらい低成長時代を生きた日本の若者は、世界に比べて相対的に恵まれ、優しい世代となっている。上昇志向を抱きにくく、現状維持志向となり、距離の遠いものではなく、身近なものに関心をもつ。国政の過剰な熱気と批判には、うさんくささを感じるようだ。高飛車な大上段の政策論より、地域や身辺の周りの子育て、雇用、保育所、学費等に関心をもつ。そして、「この人わかるわー」という共感、嘘はどんどん暴かれる時代だからオープン、正直さが大切となる。距離が近いことだ。何ごともそうだが、若者に寄り添って、いっしょに考える政治が求められている。いやそれは、世代を超えて日本社会がそうした方向に動いているのではないか。