 何ともジーンとくる小説4話だ。舞台は路地裏の地下にある狭い喫茶店・フニクリフニクラ。ところが、これが都市伝説ともなる不思議な「過去に戻れる喫茶店」だ。過去に戻るにはこの店の「ある席」に座った時で、しかも「コーヒーが冷めない間」だけで、「過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない」等のルールがある。
何ともジーンとくる小説4話だ。舞台は路地裏の地下にある狭い喫茶店・フニクリフニクラ。ところが、これが都市伝説ともなる不思議な「過去に戻れる喫茶店」だ。過去に戻るにはこの店の「ある席」に座った時で、しかも「コーヒーが冷めない間」だけで、「過去に戻ってどんな努力をしても現実は変わらない」等のルールがある。
心温まる4つの奇跡の物語。「恋人(結婚を考えていた才色兼備の清川二美子と恋人の賀田多五郎が別れる話)」「夫婦(記憶が消えていく男・戻木と妻の看護師・髙竹の話)」「姉妹(家出した姉・平井八絵子と旅館を継いでいた妹・平井久美の死)」「親子(この喫茶店で働いている華奢な妊婦・時田計とその子供・ミキの話)」――。
恋人、夫婦、姉妹、親子。いずれも最も近い存在であるゆえに、人は過剰な気づかいと安心ゆえの無関心の日常に覆われがちだ。長い間に蓄積された思い込みや誤解から抜け出せないでいる。その呪縛を解いてくれるのが非日常の極みの「過去に戻れる喫茶店」だ。4話とも「ありがと・・・」で締めくくられる。感動する。かつて映画「HANA-BI」で、一言もセリフを吐かなかった岸本加世子が北野武にたった一言「ありがとう」と言った感動的場面が再現されるかのようだ。何一つ現実は変わらなくとも心が変われば世の中は三変土田する。
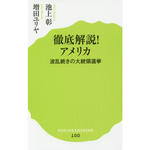 米大統領選挙を現地取材も含めて現場から徹底分析している。トランプ旋風、サンダース旋風とは何か。なぜヒラリーは思いのほか支持が上がらないか。
米大統領選挙を現地取材も含めて現場から徹底分析している。トランプ旋風、サンダース旋風とは何か。なぜヒラリーは思いのほか支持が上がらないか。
格差が拡大するアメリカ。"移民"に対する反発、民意の分断、決められない政治への苛立ち、ティーパーティーを生み出したもの、進む多言語・多文化、白人比率の急減とヒスパニック系の急増・・・・・・。若者をはじめとして不満・苛立ち、そして"怒り"がある。
また米大統領選挙の仕組み。そこに生ずる利権と中傷合戦とメディア。「センセーショナルな話」が受ける社会とトランプの"炎上商法"――。こうした選挙自体を現場取材のなかで、浮き彫りにする。
こうした動きは世界共通のものがある。「異質なものを排除し、自分たちだけの利益を追求する姿は"偉大なるアメリカを取り戻せ"というトランプの主張と重なる」「"炎上商法"に頼った人気取りは危う過ぎる」「世界中の国が内向きに、自分たちさえ良ければそれでいい、と考える勢力が強くなってきたのだろうか。世界中が感情的になり、冷静さを失っている」という。「世界が内向きになっていく中での大統領選挙」「分断され、格差が拡大するアメリカでの大統領選挙」「アメリカ社会の亀裂は、修復されることなく拡大していく」と、危惧を投げかける。
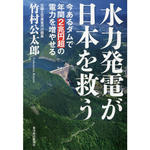 竹村さんは「黒部の太陽」がダムを造る土木技術者になる機縁となったというが、私もまた、小学生の頃に見た「佐久間ダム」建設の映画が、少なからず土木工学科に進む縁となっている。
竹村さんは「黒部の太陽」がダムを造る土木技術者になる機縁となったというが、私もまた、小学生の頃に見た「佐久間ダム」建設の映画が、少なからず土木工学科に進む縁となっている。
本書の主張はきわめて明確だ。日本のエネルギーの未来を考える時、石油・石炭の火力、原子力には限界と問題がある。再生エネルギーが重要だが、水力発電はきわめて有効だ。「現在、日本の総電力供給量に対する水力発電は9%だが、潜在力を引き出せば30%まで可能だ」という。そして方策を示す。「多目的ダムの運用を変更すること。河川法や多目的ダム法を改正して、ダムの運用法を変えれば、空き容量を活用できる」「既存ダムを嵩上げすること。新規ダム建設の3分の1以下のコストで、能力を倍近くに増大できる」「現在は発電に使われていない砂防ダム等に発電させる」「逆調整池ダム建設によるピーク需要への対応を図る」だ。そして「小水力発電」に水源地域の持続可能な活性化発電モデルを見る。そのためには「水源地域事業を支援する水力発電専門技術者集団の支援センターの設立」「事業を支える地銀と事業保証システム」「水資源地域が小水電発電の利益を一身に受けるための社会的合意」を提示する。議員立法だ。巨大ダムの新設ではなく、環境破壊もない水力発電は大きな可能性があることを、技術も含めて示している。
「彼らの思い出には補償できない。俺たちダム屋にはどうすることもできない。それが辛い」――ダム屋の心の声も響いた。
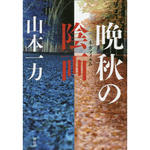 「掛け値なしの面白さ 著者初の現代ミステリー」と帯にあるが、ミステリーというよりも蓄積された心の奥がにじみ出る4篇の小説。
「掛け値なしの面白さ 著者初の現代ミステリー」と帯にあるが、ミステリーというよりも蓄積された心の奥がにじみ出る4篇の小説。
尊敬する高名なグラフィック・デザイナーの叔父から、死後に日記が届く。その意味するものを探る「晩秋の陰画」。飛行機恐怖症の男が、人の余命日数が見えてしまう特殊能力をもつようになり、その結末を描く「秒読み」。アラン・ドロン、リノ・バンチュラの「冒険者たち」に魅せられた人たちを描く「冒険者たち」。そして音楽評論、オーディオ評論、音にかけた男たちの人生の終章「内なる響き」。
これまで抱いてきた山本一力さんの世界が一変し、フランスへ、アメリカへ、音へ、ハーレーへ、深層心理へと時空を乱反射する。
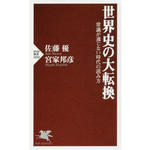 国際情勢は想定外の出来事も含めて激動の渦中にあるが、その背後の因果・相関関係を見抜く歴史的大局観が必要――その観点から二人が転換期の核心を語り合っている。
国際情勢は想定外の出来事も含めて激動の渦中にあるが、その背後の因果・相関関係を見抜く歴史的大局観が必要――その観点から二人が転換期の核心を語り合っている。
激流を象徴する事件の1つが、2014年3月のロシアによるクリミア併合(ウクライナ危機)。それは世界が再びナショナリズムの時代に回帰しはじめた、「力による領土不拡張」という戦後国際社会のルールを変えたことだ。もう1つは、世界中で経済格差の広がりがあり、貧困が固定化される。中層階級が直撃され、移民や既存のエリートに強烈な"怒り"をぶつける「ダークサイド」の社会現象があるという。こうしたダークサイドのマグマが噴出する世界の大きなうねりに、各国は今、その対策に苦慮している。
そうしたなか、中東、中央アジア、欧州、アメリカ、中国、そしてイスラム、IS、トランプ現象、中国の戦略等々・・・・・・。世界を一周して、歴史的大局観から解き明かす。

