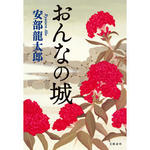 「霧の城」「満月の城」「湖上の城」の三編――。いずれも戦国の世を城を守るために仁王立ちして戦う女城主の姿、大事なものを守り抜く姿を描いている。
「霧の城」「満月の城」「湖上の城」の三編――。いずれも戦国の世を城を守るために仁王立ちして戦う女城主の姿、大事なものを守り抜く姿を描いている。
信長に逆らった女――岩村城主・遠山左衛門尉景任に嫁ぎ、後に飯田城主の秋山虎繁と夫婦として共に戦う珠子。戦乱に翻弄され、織田信長に振り回された珠子が、決然と自らの意志で立つ。「この霧が晴れた時には、織田勢も戦の世も消え失せていればいい」・・・・・・。
「満月の城」は、加賀、越中、能登を舞台に、畠山義綱の側室であった佐代が、上杉謙信、織田信長の狭間でわが子・義隆を守り毅然と立つ。
そして「湖上の城」。2017年のNHK大河ドラマ「おんな城主・直虎」の奈美(次郎法師直虎)。奈美は井伊家22代直盛の長女として天文3年(1534)に生まれた。直盛の従弟直親(亀之丞)を婿に迎えて家を継ぐはずであったが、直満(父)、直親らが今川義元から謀叛の疑いありとされ、直親は信州に身を隠す。奈美は髪を下ろす。井伊領を狙う武田、今川、徳川の攻めぎ合い。井伊家の男たちが次々死ぬなかで、直親の嫡男・虎松の後見人として奈美は還俗。次郎法師直虎として男として生きる姿を描く。
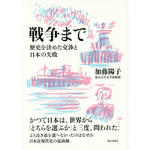 副題は「歴史を決めた交渉と日本の失敗」。まさに戦争に至るまで、「かつて日本は、世界から『どちらを選ぶか』と三度、問われた」として、「リットン調査団と報告書」「日独伊三国同盟」「戦争前夜である日米交渉」の三つの交渉、「選択」を浮き彫りにし、詳説する。そしてこの歴史の転換点において、問題の本質が正しいかたちで選択肢に反映されていたかを問いかける。
副題は「歴史を決めた交渉と日本の失敗」。まさに戦争に至るまで、「かつて日本は、世界から『どちらを選ぶか』と三度、問われた」として、「リットン調査団と報告書」「日独伊三国同盟」「戦争前夜である日米交渉」の三つの交渉、「選択」を浮き彫りにし、詳説する。そしてこの歴史の転換点において、問題の本質が正しいかたちで選択肢に反映されていたかを問いかける。
リットン報告書は、当時の報道でいう「中国側の主張を全面的に支持していた」ものではなく、「世界への道」を提示し、日本にも配慮したものであったこと。「その時、為政者はなにを考えていたのか」を示す。三国軍事同盟は「なぜ、ドイツも日本も急いだのか」「"バスに乗り遅れる"から結んだのではない」「日本が牽制したかったのはアメリカではなく、アジアへ回帰してくるドイツ。戦勝国ドイツを封じ、敗戦国の植民地を獲得するため」等々、分析する。日米交渉では「日米交渉の裏にある厚み」「ハル・ノートで罠にはめられた?」「駐米日本大使館員の勤務怠慢による対米通告の遅れという神話」「日本はなぜアメリカの制裁を予測できなかったか」「アメリカの失敗」などが示される。
そして、「相手国の社会の基本を成り立たせている基本的秩序=憲法にまで手を突っ込んで、書き換えるのが戦争」「戦争に賭けた日本は、何に敗けたのか」「日本が望んでいた社会の基本秩序と、アメリカが望んでいた社会の基本秩序の差違」等が示され、「GHQ憲法草案、日本側草案段階にも『平和』は、入っていなかった」ことを明らかにする。
「選択」はきわめて難しい決断であることは私自身感じていることだが、そのためには問題が正しく提起されることが重要だ。改めてそのことを感じさせてくれた本だ。
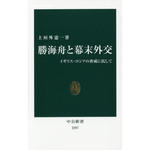 1853年のペリー浦賀来航から幕末――。日本を取り巻く外交環境は激しかった。アヘン戦争(1840~42年)を起こしたイギリスは1857年のインド大反乱(セポイの乱)に苦闘しながらもインドでの覇権を確定、1860年にはアロー戦争(第二次アヘン戦争とも。1856~60年)で北京を占領、その勢いは日本を震撼させていた。ペリー来航以来、アメリカは開国への強い行動を起こしていたが、1861年には南北戦争に突入する。イギリス・フランスとロシアの戦いであったクリミア戦争(1853~56年)は、極東においてもロシア艦隊とイギリス艦隊がぶつかり合い、アロー戦争では清とイギリス・フランスの講和にロシアは介入、広大な領土を清国から得た。当然オランダの力もある。米、露、蘭、英――攘夷・開国高まる日本のなかで、どの国と結び外交を展開するか、幕府内でも主張は乱れ、親米一辺倒の井伊直弼など親英・親米・親露が激しく対立した。
1853年のペリー浦賀来航から幕末――。日本を取り巻く外交環境は激しかった。アヘン戦争(1840~42年)を起こしたイギリスは1857年のインド大反乱(セポイの乱)に苦闘しながらもインドでの覇権を確定、1860年にはアロー戦争(第二次アヘン戦争とも。1856~60年)で北京を占領、その勢いは日本を震撼させていた。ペリー来航以来、アメリカは開国への強い行動を起こしていたが、1861年には南北戦争に突入する。イギリス・フランスとロシアの戦いであったクリミア戦争(1853~56年)は、極東においてもロシア艦隊とイギリス艦隊がぶつかり合い、アロー戦争では清とイギリス・フランスの講和にロシアは介入、広大な領土を清国から得た。当然オランダの力もある。米、露、蘭、英――攘夷・開国高まる日本のなかで、どの国と結び外交を展開するか、幕府内でも主張は乱れ、親米一辺倒の井伊直弼など親英・親米・親露が激しく対立した。
そして1861年、ロシア艦隊・ポサドニック号の対馬占領事件が起きる。小栗忠順の日露同盟論に対し、老中安藤信正は親英路線を立て対立する。安藤信正、水野忠徳ラインが指名したのが勝海舟だと著者は見る。勝海舟、横井小楠は、道義を説き、かつ全島民を失うともどちらの国にも対馬は渡さないとの断固たる覚悟に立っての外交を行う。
列強のバランス・オブ・パワーを利用して、イギリスにもロシアにも対馬を取らせない――。「外交の極意は、誠心正意にある」と言う勝海舟のギリギリの攻防を、文献を精査して浮き彫りにする。
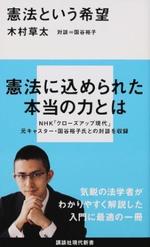 憲法論議は重厚な論議でなくてはならない。2000年、国会に憲法調査会ができた時、「憲法を論ずることは国の形を論ずること」という共通の思いがあった。
憲法論議は重厚な論議でなくてはならない。2000年、国会に憲法調査会ができた時、「憲法を論ずることは国の形を論ずること」という共通の思いがあった。
本書の帯には、「気鋭の法学者がわかりやすく解説した入門に最適の一冊」とある。「さまざまな法律がある中で、憲法は、国家の失敗を防ぐための法律だ。・・・・・・今こそ、憲法に記された先人たちの知恵に学ぶべきだろう」という。
「日本国憲法と立憲主義」「人権条項を活かす」「『地方自治』は誰のものか」の各章と対談がある。憲法も時代の進展・変化のなかで見ていかなければならないのは当然だが、地盤の動きやすい上層を削り、確固たる固い岩盤がどういうものか。それを常に考え続ける憲法論議でなくてはならないことを感ずる。
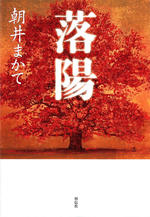 明治天皇は明治元年(1868)10月、東京に入り江戸城は皇城と改称された。その時17歳。そして明治45年(1912)7月、崩御される。渋沢栄一、阪谷芳郎市長ら東京の政財界の人々は「神宮を帝都に創建すべし」と動き始め、またたく間に巨大なうねりとなった。しかし、東京には針葉樹は育たない。
明治天皇は明治元年(1868)10月、東京に入り江戸城は皇城と改称された。その時17歳。そして明治45年(1912)7月、崩御される。渋沢栄一、阪谷芳郎市長ら東京の政財界の人々は「神宮を帝都に創建すべし」と動き始め、またたく間に巨大なうねりとなった。しかし、東京には針葉樹は育たない。
林学者として反対していた本郷高徳らは、造営が決まるや胆を決める。「かくなる上は、己が為すべきことを全うするだけだ。明治を生きた人間として」「天皇の徳を懐ひ 天皇の恩を憶ひ(漱石の奉悼の言葉)」・・・・・・。全国からの献木10万本、勤労奉仕のべ11万人、完成は150年後。大事業が始まった。
"明治を生きた人間"は何を考えたか。人々は何ゆえに天皇を尊崇し、神宮を造営しようとしたのか。東京の落胆、焦慮、そして万謝の念。武士の城と日本の求心力。絶対的支配とは異なる万民への「まなざし」と人々の受容と安堵。
「明治という時代は大正になって、ようやく完成したのかもしれない」とのつぶやきが、心奥に伝わる。自らを厳然と律しながら、常に心は民衆に開かれていた天皇――主人公の東都タイムスの瀬尾亮一の思いと行動が描かれる。

