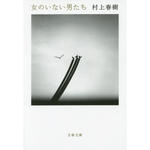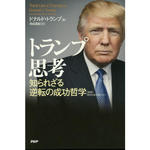 トランプ大統領が誕生するや、批評・解説のトランプ本が多数出ている。本書はトランプの肉声、しかも最近のものではないから大統領選挙用に脚色されていない。トランプ自身のウェブサイトに書いた記事を中心に49篇がまとめられたエッセイ集であり、2010年9月にPHP研究所より刊行された「明日の成功者たちへ」を改題し、再編集したものだ。
トランプ大統領が誕生するや、批評・解説のトランプ本が多数出ている。本書はトランプの肉声、しかも最近のものではないから大統領選挙用に脚色されていない。トランプ自身のウェブサイトに書いた記事を中心に49篇がまとめられたエッセイ集であり、2010年9月にPHP研究所より刊行された「明日の成功者たちへ」を改題し、再編集したものだ。
「自分自身と自分の仕事に噓をつくな」「人生で成功するには常識とハードワークが必要だ。大事なのは新しい刺激に目をとめること、頭と五感を開かれた状態にしておくことだ」「即断力を養うために学ぼう。即断力は訓練と自己鍛錬によって身につく」「環境の変化はめまぐるしい。ついていけなければ脱落する。何をするにせよ、成長を止めてはならない。現状に満足してはならない。学び続ける癖をつけよう」「挑戦。高次元の自己にチャンスを与えよ」「成功者には、経験、人格、知識の共通項がある」「チャンピオンには、耐えてきた練習量、払ってきた犠牲・勇気がある。発想のスケールが大きい」「人生はアート、仕事はアートだ。私の仕事は、職人技と芸術の両方を兼ね備えており、絶対に妥協はしない」「物事を関連づけて考えられるようになろう」「恐怖心を忍び込ませるな。問題に対処し解決する姿勢を身につければ、成功の可能性は広がる」「ビジネスの成功は、適正、努力、運の総和だ」「短く、早く、単刀直入に事を成せ」「自分のエネルギーの流れを維持するには、勢いに気持ちを注げ」「打たれ強く、意志を強く持ち、学ぶことに貪欲であれ」「最高の人間を集めよ」「ポジティブに考えるとともに、現実も忘れるな」「目的を見出し、目的に生きよ」「用心を怠るな」「チームワーク。好きな人たちと仕事をしよう」・・・・・・。
トランプのエネルギー、アクティブ、合理性、不屈、スピード、学びへの貪欲、妥協しない、挑戦、チームワーク――いずれもすさまじい。
 世界の戦乱・事件・災害等の生死を背景に、人間の実存と存在に迫り、問い続ける希有の作品。主人公のアイはシリアで生まれ、子どものいないアメリカ人のダニエルと日本人の綾子夫妻の養子となり、日本で何不自由なく暮らす。しかし、恵まれた環境に育つなかで、「なぜ私が?」「世界で起きる不幸のなか、自分のみ免れ、幸せでいいのか」「他の幸せを奪っているのではないか」「血のつながりのない自分のアイデンティティーへの不安」「恵まれていることへの罪悪感」に常に襲われる。そして高校1年生の数学の授業で教師の放った「この世界にアイは存在しません。」の一言がずっと心に突き刺さる。アイは自身の名であり、「私」であり、「愛」であり、「数学の"虚数"(実在しない数)(i×i=-1)」でもある。考え抜かれた題名自体に驚く。
世界の戦乱・事件・災害等の生死を背景に、人間の実存と存在に迫り、問い続ける希有の作品。主人公のアイはシリアで生まれ、子どものいないアメリカ人のダニエルと日本人の綾子夫妻の養子となり、日本で何不自由なく暮らす。しかし、恵まれた環境に育つなかで、「なぜ私が?」「世界で起きる不幸のなか、自分のみ免れ、幸せでいいのか」「他の幸せを奪っているのではないか」「血のつながりのない自分のアイデンティティーへの不安」「恵まれていることへの罪悪感」に常に襲われる。そして高校1年生の数学の授業で教師の放った「この世界にアイは存在しません。」の一言がずっと心に突き刺さる。アイは自身の名であり、「私」であり、「愛」であり、「数学の"虚数"(実在しない数)(i×i=-1)」でもある。考え抜かれた題名自体に驚く。
アイは世界の戦乱・事件、9・11テロ、東日本大震災、自身に関係するシリアやハイチの危機に敏感に反応し、自身の宿命、存在、アイデンティティー、そして血縁、家族、愛を考え続ける。ピュアな妥協なき求道ともとれる追求の姿に引き込まれる。そして生老病死の追求とアイデンティティー崩落の危機を、アイを全的に肯定する家族・友人の心と愛情によって救い出される。「この世界にアイは、存在する。」「世界には間違いなく、アイが存在する」「私はここにいてもいい存在、いなくてはいけない存在だ」とベクトルを健やかに反転させていく。
 「地方再生に挑戦する人々」と副題にあるように、全国各地で防災・減災や地域の活性化に頑張っている建設業や政治家の現場の姿を、くっきりと紹介している。
「地方再生に挑戦する人々」と副題にあるように、全国各地で防災・減災や地域の活性化に頑張っている建設業や政治家の現場の姿を、くっきりと紹介している。
「『稲むらの火』と国土強靭化」では二階自民党幹事長のこの数年の仕事、防災・減災・国土強靭化がいかに大事か。雨の降り方が変化し、巨大地震に見舞われた「災害列島・日本」にどう対応するか。大都市で、地方で、離島で格闘する人々。「世のため人のためにつくせ」との精神で「公共事業悪玉論」を振り払いながら黙々と志をもって取り組む人々。インフラのストック効果を凝視して日本の経済成長を支え、推進する人々。
「技術はうそをつかない」「B/Cという考え方は都市部ほど有利に働くのではないか」「熊本城復興のために"国民の一人一枚瓦寄付"運動」「電気商会の"24時間365日いつでも飛んでいきます"のキャッチフレーズ」「下水道のSPR工法の衝撃」・・・・・・。「国民・政府・自治体の皆さん、建設業の現場の声を聴いてください!」とまで現場の声を伝えてくれている。
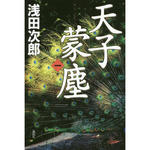 「蒼穹の昴」「珍妃の井戸」「中原の虹」「マンチュリアン・リポート」に続く第5部「天子蒙塵」の第一巻。待望の書だ。天子蒙塵とは「天子が塵をかぶって逃げ出す」こと。
「蒼穹の昴」「珍妃の井戸」「中原の虹」「マンチュリアン・リポート」に続く第5部「天子蒙塵」の第一巻。待望の書だ。天子蒙塵とは「天子が塵をかぶって逃げ出す」こと。
張作霖爆破事件をはさみ、宣統帝溥儀と皇后・婉容、淑妃・文繡、そしてその側近たち、更には張学良らが何を思い、どう動いたか。溥儀と文繡の離婚劇の真相から、日本がかかわった天津から満洲建国への道のりを、文繡姉妹の静かな語りによって描いている。
巨大な時代の荒波に吞み込まれながらも、自由をめざした女性の物語でもあり、同じ荒波のなかで大清の復辟を秘めつつも楽園的日常に浸るラストエンペラー・溥儀の姿など、悲哀が滲む。1930年代の中国大陸への序章がこの第1巻だ。