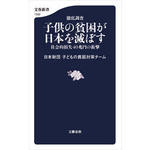 「子どもの貧困を放置してしまうと、社会の支え手が減ると同時に支えられる人が増える。そのコストは社会全体で負担しなければならない」「家庭の経済格差が子どもの教育格差を生み、将来の所得格差につながる貧困の連鎖が問題となっている。その貧困の連鎖が及ぼす経済的・社会的影響を具体的な金額として示す。子どもの貧困の社会的損失推計を示す」――。「子供の貧困」は他人事ではない。ジブンゴトとしてできることをやろうと、日本財団 子どもの貧困対策チームがやっていることを紹介しつつ訴える。
「子どもの貧困を放置してしまうと、社会の支え手が減ると同時に支えられる人が増える。そのコストは社会全体で負担しなければならない」「家庭の経済格差が子どもの教育格差を生み、将来の所得格差につながる貧困の連鎖が問題となっている。その貧困の連鎖が及ぼす経済的・社会的影響を具体的な金額として示す。子どもの貧困の社会的損失推計を示す」――。「子供の貧困」は他人事ではない。ジブンゴトとしてできることをやろうと、日本財団 子どもの貧困対策チームがやっていることを紹介しつつ訴える。
OECD諸国における日本の子どもの貧困率(相対的貧困)は、34か国のうち上から10番目と高く、ひとり親家庭の貧困率はワースト一位だ。ひとり親、とくに母子世帯の収入は低く、子どもとの接触も少ない。放置すると「大卒は半減し、中卒は4倍増」「非正規社員や無業者が一割増加」「1人当たりの生涯所得が1600万円減少」「1人当たりの財政収入が600万円減少」「全体で所得が40兆円超、財政収入が16兆円失われる」という社会的損失をもたらすと推計する。1年当たりで換算すると「所得の減少数は約1兆円、財政収入の減少数は約3500億円」という。
「進学率や中退率を改善することで所得が向上する」ということだが、より本質的な子どもの貧困問題は「社会的相続(自立する力の伝達行為)」が歪められることだ。その内容を「金」「学力」「非認知能力(学力等以外の自制心、やり抜く力など)」等を分析し、エリクソンの発達段階的なライフサイクル論を示す。とくに非認知能力の重視、重要性だ。
国の取り組み、足立区など各自治体の取り組みとともに、NPO等の取り組みを紹介している。待ったなし、今やるべき重大問題だ。
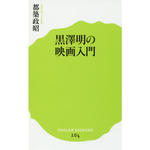 「黒澤明 全作品と全生涯(2010年 東京書籍)」など、黒澤明の実像を紹介してきた都築政昭さんが、その人間像と「黒澤映画」の真髄を語っている。改めて、その凄さに感心する。
「黒澤明 全作品と全生涯(2010年 東京書籍)」など、黒澤明の実像を紹介してきた都築政昭さんが、その人間像と「黒澤映画」の真髄を語っている。改めて、その凄さに感心する。
私自身、「姿三四郎」に始まり、「素晴らしき日曜日」「羅生門」「生きる」「七人の侍」「隠し砦の三悪人」「悪い奴ほどよく眠る」「用心棒」「椿三十郎」「天国と地獄」「赤ひげ」「影武者」「乱」など、生涯で30本作った映画のかなりを見てきたことに驚いた。「黒澤は『映画という美しくて素晴らしいもの』の奴隷なのである」「生きる勇気と元気を与える映画を!」「人間は仲良く善意をもって」「人間は自然の一部」「闘う――男たちの世界」「笑わせ、泣かせ、怒らせて」「人間の尊厳、そこにある確固とした人生肯定」「愛とヒューマニズムの体現」「トルストイとドストエフスキーとバルザック」「テーマが骨太で、話がおもしろくて、映像がダイナミックで、俳優が持ち味を出しきって」「イプセンのように最初に盤石な布石をする」「演技に助太刀はせず、自分で絞り出せ」「名うての完璧主義者」「悪い、いいの見極めがつかないでどうして監督がやれるか(ニセモノとホンモノの区別)」・・・・・・。
映画を芸術の高みに押しあげた黒澤明の人と作品が躍動的に語られる。
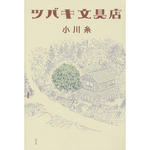 温かく優しい物語だ。鎌倉市のとある小学校の近くにあるツバキ文具店。先代(祖母)が亡くなって、反抗的で海外に逃げていた雨宮鳩子(ポッポちゃん)が帰って代書屋を継ぐ。
温かく優しい物語だ。鎌倉市のとある小学校の近くにあるツバキ文具店。先代(祖母)が亡くなって、反抗的で海外に逃げていた雨宮鳩子(ポッポちゃん)が帰って代書屋を継ぐ。
隣りに住むバーバラ婦人、男爵、パンティー、マダムカルピス、守景とその子陽菜(QP)など、登場人物はいずれも幸せそうだ。代書屋に持ち込まれる仕事は「お悔み状」「恋文」「離婚報告の手紙」「かつての恋人に元気であることを伝えるだけの普通の手紙」「借金を断る手紙」「汚文字の人の代筆」「天国からの妻への手紙」「先代が文通相手で本心を吐露している手紙」「QPちゃんの鏡文字」「絶縁状」・・・・・・。
夏、秋、冬、春と経験を経て、鳩子はわだかまりを乗り越えて「亡き祖母(先代)への長い手紙」を書く。感動作。人生を丁寧に生きていく、幸せを見つけて生きていくことが心に浸み入るようだ。
 教育基本法の第1条には、「教育は、人格の完成を目指し・・・」とある。「人間教育」に全てを注いできた梶田先生の教育哲学と実践が集約された書だ。副題には「人間としての成長・成熟を目指して」とある。「教育の深さが日本の未来を決定する」と、教育基本法改正案の衆院本会議に立った私は発言したが、その中核が本書で述べられている。感銘する。
教育基本法の第1条には、「教育は、人格の完成を目指し・・・」とある。「人間教育」に全てを注いできた梶田先生の教育哲学と実践が集約された書だ。副題には「人間としての成長・成熟を目指して」とある。「教育の深さが日本の未来を決定する」と、教育基本法改正案の衆院本会議に立った私は発言したが、その中核が本書で述べられている。感銘する。
「『人間としての尊厳』を具体化していく教育を――『我の世界』を生きる力を育てる」というプロローグから始まる。生きる力には「我々の世界」を生きる力と「我の世界」を生きる力の2つの面があると、梶田先生の世界が開示される。そして「有能な『駒』でなく賢明な『指し手』に」「『内的な促し』のために――本源的自己の錬成と意識世界での動機づけ」「『やる気』の育成を考える」「自己統制における現実適応性と価値志向性――主体形成のために」が示される。哲学不在の時代における「我々の世界」「我の世界」をどう生きるかという生きる力の人間教育の本源に実践面を含めて迫っている。
「『こころ』の教育を考える」「道徳教育の新たな充実・発展のために」「自己を語ることとアイデンティティと」で左右からの浅薄な批判を砕き、人間形成の中道を示すとともに、教育実践における「開・示・悟・入の教育思想」を提示する。教育界のなかでの実践研究を語っているが、その奥行きの深さに感じ入る。
「学校教育」の具体的実践を踏まえての「人間教育」、そして現代社会のなかでの「生涯教育」のあり方をいかに模索してきたか――その崇高な「人間教育」の哲学と実践が滲み出ている。私との対談も紹介されている。
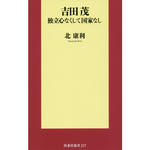 「吉田茂 ポピュリズムに背を向けて」で、北康利さんは、吉田茂がいかに「独立国家の完成」に強い信念をもっていたかを示した。本書はその後、サンフランシスコ講和条約後を描いている。
「吉田茂 ポピュリズムに背を向けて」で、北康利さんは、吉田茂がいかに「独立国家の完成」に強い信念をもっていたかを示した。本書はその後、サンフランシスコ講和条約後を描いている。
「ポピュリズムに背を向けた男(吉田茂)とポピュリズムを上手に利用した男(鳩山一郎)。好対照の二人ではあるが、共通するのは強い信念をもっていたことである。・・・・・・ともに『独立国の完成』を目指すというものだった」「吉田茂という政治家にとって、国民は自分たちが指導して幸せにするべき対象であり、世論の動向に従って政治を進めていくなどということを、彼は微塵も考えていなかった」「岸信介の最大の政治目標は、吉田が果たせなかった対等な日米関係の構築と自主外交路線の確立にあった。まさにそれは吉田の思い描いた『独立国の完成』そのものである」――。
吉田茂、鳩山一郎、三木武吉、石橋湛山、重光葵、大野伴睦、松野鶴平、広川弘禅、緒方竹虎、岸信介、河野一郎、佐藤栄作、池田勇人・・・・・・。苦難の日本、激しい政局のなかで闘う政治家の姿が活写される。

