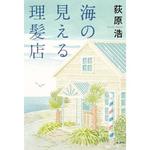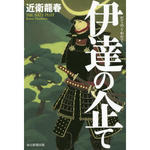 伊達政宗――。永禄十年(1567)8月、出羽の米沢城で生まれ、寛永13年(1636)5月、70歳で亡くなった。「政宗は死に至るまで天下を夢見ての往生であった」「政宗の五度目(の挑戦)もあと一歩届かなかった」「儂は天下を狙っておる」「豊臣を討つ戦いになるか。家康を討つ戦いになるか。四度目は明確にしたいものじゃ。(大坂冬の陣の参陣)」・・・・・・。
伊達政宗――。永禄十年(1567)8月、出羽の米沢城で生まれ、寛永13年(1636)5月、70歳で亡くなった。「政宗は死に至るまで天下を夢見ての往生であった」「政宗の五度目(の挑戦)もあと一歩届かなかった」「儂は天下を狙っておる」「豊臣を討つ戦いになるか。家康を討つ戦いになるか。四度目は明確にしたいものじゃ。(大坂冬の陣の参陣)」・・・・・・。
しかし、世に出る時が遅かった。「20年、いやあと数年早く生まれておれば、太閤に頭を下げることもなかったがのう。思い出すと腸(はらわた)が煮え繰り返る」。天正13年(1585)に秀吉は天下を掌握するための領地拡大阻止・私戦禁止の惣無事令を出した。奥州の大半を手にしながらも天正18年(1590)の小田原での死装束を纏っての秀吉下での屈辱に始まり、常に秀吉に押さえられ、その死後は家康に抗いながらも下らざるを得ず、大坂冬の陣、夏の陣に至る。その怒り、苦衷、天下取りの野望が描かれるが、終章「新たな企て」において、腹臣片倉景綱の死、家康の死、乱世の終止符への志、北上川改修、新田開発、そして家光の後見役の姿が、短く描かれる。
 2025年まで――時間はそうない。団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、要介護や認知症の人の割合が高い75歳以上が約2200万人となる。高齢化率は30%を超える。2012年に約462万人といわれる認知症患者は2025年には約700万人(高齢者の5人に1人)と見込まれている。介護給付費は発足時(2000年度)の3.6兆円が15年には10.1兆円、25年には約20兆円に到達するという。急性期医療とその後の社会復帰のための効率的なこれまでの医療体制は、完治が難しい慢性疾患を複数抱えた高齢者への対応にシフトせざるを得ない。そこで、「地域包括ケアシステム」と「コンパクト+ネットワーク(国土のグランドデザイン2050)」を含めた「ケア・コンパクトシティ」という選択をする以外ない、という。それなしに、「2025年、高齢者が医療・介護難民」という惨状を脱することができない。
2025年まで――時間はそうない。団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、要介護や認知症の人の割合が高い75歳以上が約2200万人となる。高齢化率は30%を超える。2012年に約462万人といわれる認知症患者は2025年には約700万人(高齢者の5人に1人)と見込まれている。介護給付費は発足時(2000年度)の3.6兆円が15年には10.1兆円、25年には約20兆円に到達するという。急性期医療とその後の社会復帰のための効率的なこれまでの医療体制は、完治が難しい慢性疾患を複数抱えた高齢者への対応にシフトせざるを得ない。そこで、「地域包括ケアシステム」と「コンパクト+ネットワーク(国土のグランドデザイン2050)」を含めた「ケア・コンパクトシティ」という選択をする以外ない、という。それなしに、「2025年、高齢者が医療・介護難民」という惨状を脱することができない。
これからの日本は「都市部で急増する後期高齢者と介護難民」「社会保障費の膨張に伴う財政危機」「人口減少に伴う地方消滅」という3つの問題に直面する。人口減少、少子高齢社会が加速する今、「空間選択や時間軸を重視した政策に切り替え、スマートシュリンクの時代に向けて舵を切れ」「"まちづくり"や"エリアマネジメント"の視点を盛り込みつつ、医療・介護など必要なサービスをコンパクトシティという地域の空間の中で効率的・効果的に提供すること」「"まちづくり"はヒューマンスケールで」「地域の共同体マインドを共有することが大事で、規範的統合が重要だ」・・・・・・。
全国の市町村での先駆的取り組みを紹介しつつ、数々の具体的提言を行っている。私も同じ問題意識をもって「コンパクトシティ+ネットワーク」「対流促進型国土の形成」を進めている。「ケア・コンパクトシティ」――同感。実行の時だ。
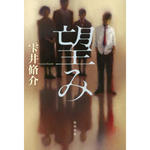 最近もあった少年たちがリンチで殺害する事件――。その事件に突然、わが子が巻き込まれた時、父親は、母親は、娘は、関係のあった人々は、狼狽のなかで何を思い、考えたか。辛い。
最近もあった少年たちがリンチで殺害する事件――。その事件に突然、わが子が巻き込まれた時、父親は、母親は、娘は、関係のあった人々は、狼狽のなかで何を思い、考えたか。辛い。
サッカー少年であった石川規士が高校初の夏休み直後、2日も帰って来ず、父・一登と母・貴代美は胸騒ぎを覚える。そして息子の友人が遺体となって発見され、犯人と思われる少年2人の逃亡が目撃される。しかし、行方不明者は3人。息子は加害者か、被害者か。犯人であっても生きていてほしいと思う母・貴代美。加害者のはずがない、被害者であれと思う父・一登。無事であってほしい、いや無実であってほしい・・・・・・。
「望み」は絶望のなかのせめてもの望みでしかない。望みなき望みだ。父と母、男性と女性、親と子、現在と今をはらむ未来。日常と死。死の現実のなかに「怨」が消える。交錯し、相反する思いが、生死の現実のなかで融け、定置する。
 「心こそ大切なれ」という仏典にある心は生命のことである。森羅万象の生命・こころが滲み出て、日本語がいかに美しいか、味わい深いものか、生命の真髄に迫るものであるか。感動した。本書は本であって本ではない。境地の現われだ。
「心こそ大切なれ」という仏典にある心は生命のことである。森羅万象の生命・こころが滲み出て、日本語がいかに美しいか、味わい深いものか、生命の真髄に迫るものであるか。感動した。本書は本であって本ではない。境地の現われだ。
「はじめに」で「万象への深い認識を示す日本語に、わたしは脱帽しつづけている」という。「あとがき」で「動作とはすべてことばのこころを演じるものなのか。・・・・・・もうこうなると、ことばはほとんどこころにひとしい。こころは、言語となり動作ということばによって現されているのだった」と語る。本書の後ろから抜き書きすると「しかし当時の現実主義者・定家が主張する丈の高さを、丈の暗みに引きずり降ろした珠光の、冷えや痩せの心が滲み出た陰翳の美学は、大きく日本美を深化させる、勇敢な発言だったというべきだろう」「日本人はつねに常識、偽制、権威といったものの正体への絶望と、それへの断念を表明してきたように思える」「しかし、正反対に、古典人の山川草木は人間とあい融和し、ともども在る物であった。お互いに魂を持つ者としてまなざしを交わす物だったことを、古典は教えてくれる(自然と人間)」「あいまいさも、ごまかしも、すべてがそぎ落とされて、それこそ冴えざえとした物の輪郭を鏡として自分を発見できる季節が、冬であった。心の季節といったものを古典から汲みとることもまた、大事であろう」・・・・・・。うなってしまう。
日本の歴史と文化、ことばのこころを受けて、「丁寧に生きていこう」「いちだんと深い人生の味わいを尊重しよう」と思う。