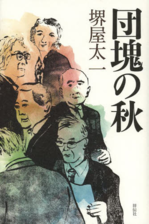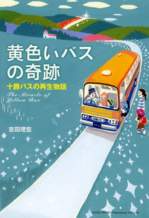人生は長いようで短い。「時は流れない。積み重なっていくのだ」――カナダ、アメリカ15日間の旅を学生時代(卒業寸前)いっしょにした団塊の世代の男6人、女1人の7人のエリート。いずれも順風万帆どころか波瀾万丈。それは自ら数々の流行と需要をつくり、自ら時代をつくってきた団塊の世代自身の善悪を越えた宿命ともいうべき帰着点でもある。
その時代の風景とは何か。「2015年 さまよえる活力」「2019年 年金プラス10万円」「2020年 孫に会いたい!」「2022年 孫の進路」「2025年 養護センターまで2316歩」「2028年 電気守」とその特徴を予測して描く。団塊の世代と団塊ジュニア、そして孫――時代をつくる(つくってしまう)これら3世代へのエールとも感じる。未来の新聞記事が各章に付いている。
いずれも世界最高の知性の6人が率直に語る。視点が高く、深い。そして科学的、哲学的、真実へのあくなき追求姿勢、しかも謙虚さに感動する。吉成さんの卓越したインタビュー、まとめる力に、感謝したいほどだ。
「人生に意味などというものはない。われわれはただ存在するというだけのことだ」「西欧の覇権は民族の能力の違いによるものではなく、単なる地域的優位性の結果だ」という生物学・生理学のジャレド・ダイアモンド。「全ての言語にはその深層に共通する文法が存在し、人間は言語の基本文法を生得的な器官として持って生まれてくる」と語る言語学者ノーム・チョムスキーは、市場主義や覇権主義を批判する。
脳神経学・精神医学のオリバー・サックスは、「教育で大事なことは、先生と生徒のポジティブな関係であり、教えている内容への先生の情熱である」といい、音楽と言語に言及しつつ、人間存在の究極に迫る。人工知能分野を開拓したマービン・ミンスキーは「なぜ福島にロボットを送れなかったか」と科学の方向性の転換を語る。数学者トム・レイトンはインターネットの最先端で繰り広げられるサイバー戦争等を語り、世界の変容や危険性、その解決方法について自らの起業にもふれつつ語っている。分子生物学者、DNA二重らせん構造の発見者ジェームズ・ワトソンは、「最もエキサイトしている事柄は何か」と問われ、「ガンを治すことです」と即答する。
いずれも生命、哲学、宗教が語られ、推薦図書まで上げている。刺激的な書だ。
うれしい話だ。倒産寸前だった十勝バスが、若社長の「お客さんのために」という熱気によって息を吹き返した。社員を愛し、地域を愛したチーム十勝バスは、奇跡を起こした。それも各地方でバス事業や鉄道事業が苦戦をしているなかでの話だ。中心者の一念、社員との結束と意欲、バス停近くで営業をかけるという奇抜なアイデア。国土交通省でも話を直接伺っている。また十勝バスは数々の賞を受賞している。
驚くべきは輸送人員の増加だ。地方でバス利用者の減少が続くなかで、十勝バスは平成20年度294万人が24年度には337万人となった。本書をもとにミュージカル「KACHI BUS(カチバス)」(でっかい北海道で起こった、ちっちゃなバス会社の奇跡)が上演されている。現在は東京公演中(下北沢本多劇場 1月5日~13日)。今後、札幌や帯広でも公演予定だという。
元大関・琴風、尾車親方。現役時代は大関への期待がかかった時に左ヒザじん帯断裂の大ケガで幕下まで陥落、再起を果たしてまた関脇で左ヒザ半月板損傷。再び立ち上がり初優勝して大関へ。また右ヒザじん帯損傷で引退――。尾車親方となって苦節13年、ついに関取を誕生させるが、昨年4月4日、巡業先で転倒して頸髄捻挫の重傷。首から下が全く動かせない全身麻痺の状況から奇跡の復活をついに果たす。
逆境、試練、苦難の連続、一寸先は闇、波乱万丈――。「勝つまでやることを、頑張ったというんだ」「何度転んでも起き上がるんだ」「ピンチを乗り越える力を持っている者にしか、試練は与えられない。自分は認められた男だと思って頑張れ」と自身に言い聞かせながらの人生が、琴風の人生だが、「琴の音が、風に乗って響く」琴風らしく、ものすごく謙虚に静かに語っている印象的な本だ。