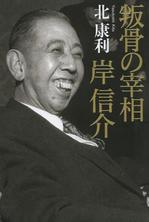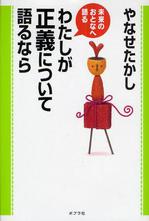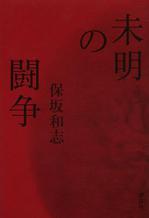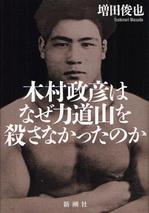「国民に媚びることなく、国家を真の独立へと導こうとした岸信介。彼が思い描いた理想に、この国はまだ遠い」と本書は結ばれている。昭和2年3月の昭和恐慌(岸31歳)から昭和30年の保守合同(自由民主党結成)(岸59歳)、そして60年安保改定。まさに激動の日本。北さんは岸が戦い続けた吉田茂を「吉田茂 ポピュリズムに背を向けて」の名著を出しているが、国を背負った「自ら反(かえ)りみて縮(なお)くんば、千万人といえども吾往かん(孟子)」を貫いた叛骨の宰相として岸信介を描いている。そして「歴代総理のなかで、辞任後もっとも評価が高くなったのは岸信介ではあるまいか」という。あの昭和の戦争、そして占領下の日本、そして保守合同への"自民党戦国史"――そのなかで、日本を背負うとはどういうことか。保守政治とは何か。そのなかで突き上げる情念とは何かを、描き出してくれている。
 「21世紀の対話」(池田大作・トインビー対談)が刊行されて約40年。世界で28言語に翻訳出版されたこの対談を、佐藤優さんが今こそ必要な哲学として鮮やかに解き明かす。本書にあるのは生命の尊厳の人間哲学だ。
「21世紀の対話」(池田大作・トインビー対談)が刊行されて約40年。世界で28言語に翻訳出版されたこの対談を、佐藤優さんが今こそ必要な哲学として鮮やかに解き明かす。本書にあるのは生命の尊厳の人間哲学だ。
佐藤さんは現代社会の迷妄はリーダーたちの「思想の欠如」にあると見る。現代社会の浅薄さは「哲学の不在」にあることは間違いないが、その哲学は現実に根ざし、行動を伴なって初めて意味をもつ。本書は「価値を創り出す理性的直観の力」「宗教と科学」「ニヒリズムの超克」「正義について」「労働の哲学」「一神教と汎神教への考察」「愛と慈悲」「生命の尊厳」など、佐藤さんが対談のなかから抽出して、21世紀の今こそ、この対談がその光を放つと解説する。
やなせたかしさんが今年亡くなった。「手のひらを太陽に」は今も歌われ、「それいけ!アンパンマン」は毎日、朝のBSで放映されている。いばらず、自慢せず、「人生の楽しみの中で最大最高のものは、やはり人を喜ばせることでしょう。すべての芸術、文化は人を喜ばせたいということが原点で、喜ばせごっこをしながら、原則的には愛別離苦、さよならだけの寂しげな人生をごまかしながら生きている」「ぼくは怒るよりも笑いたい」「愛と勇気だけが友達さ、とアンパンマンのマーチでいっている」と語る。
キャラクターをつくる大変さと工夫。スーパーマンと違ってアンパンマンは弱点をもったヒーローだ。しかし、少し優等生。一方ばいきんまんは結構人気がある。どこかガキ大将とか、不良とか、片目の海賊とか愛嬌のある悪人も素適だとウケることがある。
本書の第一章は「正義の味方って本当にかっこいい?」と、?から始まっている。
小説は物語、ストーリーの面白さと思っていたが、この「未明の闘争」は全く違う。あるのは生命の流れだ。その生命の流れが次々と絵巻物のように、しかも時空を飛んで連続する。記憶をエピソードとしてまとめず、自由に生命のおもむくまま飛ばす。思ったのは仏法の法概念。「法とは水(サンズイ)が去ると書くが、目の前の水は既に今あった水ではなく去っていく。しかし目の前の水は常に厳然と絶え間なく流れゆく。無常と常住の十字路に今の瞬間を位置づける。それが中道の生命である」――。その諸法実相の世界を時空を越えて描いたのだと思う。死んだ友人が目の前に現われたり、子供の頃の思い出が突然出てきたり、音楽や哲学がサッと現われたり、家族同然の猫の生老病死が語られたりする。しかもどれも温かい。
「人生の時間の流れに出遭いや出来事が点在するのではなく、出遭いや出来事が起きるそのつどそのつど人生の時間の流れが起こる」「現在とは何十年前であろうと、それを現在状態たらしめようとする記憶装置なんだ」「ジョジョは突然、"アオーン!アオーン!"とカン高い声で激しく鳴きながら、二階に向かって階段を駆け上がった。いまボッコの魂が去ってゆくのがジョジョにわかってそれを追いかけた」・・・・・・。「私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた」という冒頭の一節から、定番とは違う世界にいきなり誘い込まれた。
木村政彦と力道山の試合は私の記憶に明確にある。伝説の男・木村政彦とはどういう人物であったのか。
「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」「戦前・戦後、15年間も負けなし、不敗のまま引退した男」「柔道で化物のように強い選手4人をあげれば、木村政彦、ヘーシング、ルスカ、山下泰裕だが、最強は木村」「鬼の牛島がつくった芸術品・木村」「昭和29年12月22日、巌流島の決戦、木村政彦対力道山戦の真実とは」「プロ柔道の旗揚げ」「エリオ・グレイシーを粉砕」「プロレスの夜明けと木村の悲哀」――不器用で荒くれ、ムチャ丸出しの若者・木村の生々しい生涯が活写され、悲しくもなる。
本書は、木村政彦とその師・鬼の牛島辰熊が主役だが、そこに嘉納治五郎、力道山、大山倍達、岩釣兼生らが交差する。いや時代自体が渦のように木村に襲いかかる。
正直面白い。興味深いのは一つに「柔道とは何か」「講道館柔道とは何か」を抉り出していることだ。嘉納治五郎は、古流柔術が廃れゆくのを嘆き、実践的武術、真剣勝負を志向し、たんなるスポーツになってしまうことを憂えたという。しかし、戦後、GHQの下で講道館は「柔道は武道ではない。スポーツである」として生き抜く道を探った。「柔道は1本。最近はレスリングのようになってしまった」というのは違う。元来、武道として真剣勝負としての柔道は"殺し合い""寝技も打撃も"であり、たんなるスポーツではない。それゆえにプロ柔道が立ち上がったという。
もう一つ、興味深いのは牛島と木村の師弟間における違いを描いていることだ。「東條や三船は"政治"をにらみ、石原(莞爾)や牛島は"思想"を見ていた」と増田さんは語っている。日本人、サムライ牛島だ。そして戦後、自らの堕落を絶対に許さぬ牛島と、坂口安吾の「堕落論」「救われるために墜ちよ」という言葉以上に、飲み、喧嘩し、自然体のなかで決定的に"堕落"を生きた木村の戦後という生き様の差異。力道山戦も、その後の失意と放浪もその帰結だと語っている。本書は徹底した取材で描きあげた戦中、戦後の歴史書でもある。