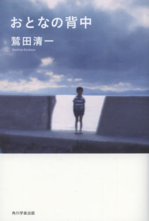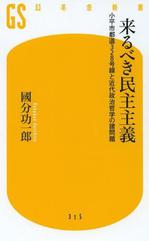幕末以前の民衆――それは「自分たちの生活領域こそ信ずべき実体であり、その上に聳え立つ上部構造は自分たちの実質的な幸福とは何の関係もないとする、下積みの民衆の信念」であり、「天下国家を論ずる上の方の人たちの、生活現場に関する無知を笑う」という民衆世界であった。そして、そうした民衆世界の自立性を撃滅し、国民国家を創立する、そして民衆を国民に改造する――それが近代である。さらにそれとセットになるのは「知識人の出現(近代知識人とは国民国家の創造をその任務とする)」だという。そして本書では「反国家主義の不可能性」と「国民国家における"人間の条件"」に踏み込んで語っている。
幕末以前の民衆――それは「自分たちの生活領域こそ信ずべき実体であり、その上に聳え立つ上部構造は自分たちの実質的な幸福とは何の関係もないとする、下積みの民衆の信念」であり、「天下国家を論ずる上の方の人たちの、生活現場に関する無知を笑う」という民衆世界であった。そして、そうした民衆世界の自立性を撃滅し、国民国家を創立する、そして民衆を国民に改造する――それが近代である。さらにそれとセットになるのは「知識人の出現(近代知識人とは国民国家の創造をその任務とする)」だという。そして本書では「反国家主義の不可能性」と「国民国家における"人間の条件"」に踏み込んで語っている。
一方、「西洋化としての近代とその魅力」や「フランス革命再考」を示しながら、生活の豊かさや快適さとともに近代へのアンビヴァレントな思いは常にあり、それは「民族国家の拘束力がますます強化される」という呪いと「世界の人工化(自然との平常の交感を失う)」の呪いが痛切な問題として残ることを指摘する。
「近代とは何か」は「民衆とは何か」「グローバリズムとリージョナリズムとは何か」「国民国家とは何か」「進歩の帰結として何を失い、何に呪縛されることになったのか」等々の根本的問題を問いかける。深い。
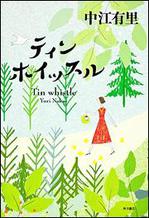 人生はままならぬものだ。ましてや厳しく激しい魔性の芸能界ではなおのことだ。さらに経験のない若い女性がそこで生き抜き続けることは、仏典に説く「一眼の亀が浮木に遭う」が如き至難さであろう。凋落を感じながらも再起をかける女優、情熱を失いつつも今の仕事に向き合う女性マネージャー、ロケ地で偶然にも再び映画への道へ誘われる元女優。この三人の心象風景が見事に描かれる。
人生はままならぬものだ。ましてや厳しく激しい魔性の芸能界ではなおのことだ。さらに経験のない若い女性がそこで生き抜き続けることは、仏典に説く「一眼の亀が浮木に遭う」が如き至難さであろう。凋落を感じながらも再起をかける女優、情熱を失いつつも今の仕事に向き合う女性マネージャー、ロケ地で偶然にも再び映画への道へ誘われる元女優。この三人の心象風景が見事に描かれる。
元女優の小学生の娘が、言葉を発せられずにティンホイッスルを吹く。人生の転機と再生、そしてその決断。自己存在の意味と証明。そして言葉と心。自分は何をしたいのか、自分の本心は自分でもわからない。しかし生命は知っている。それが噴き出すには、何かのキッカケがいる。"運と運命""縁と逡巡""有と無と空の世界"のなかで、自己肯定の決断がティンホイッスルの音として跳躍する。