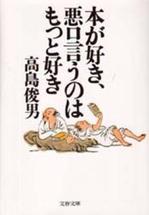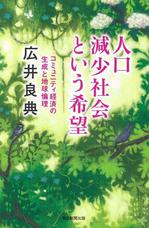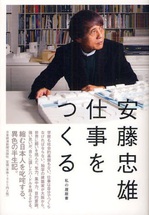3.11の衝撃と安倍政権の一年――。「保守に品格が求められるように、リベラルには歴史を前に進める矜持が不可欠です。貧相で矮小なリベラルであってはならない。リベラルであれ保守であれ、それぞれの立ち位置からどういう次代のシナリオが描けるのか。ある問題に立ち向かうため、冷静に議論できる磁場を構築していくことが、知の役割であり、我々の務めだと思う」――。
問題にしているのは、21世紀を主導するビジョンも構想も描けず、思考停止状態の日本だ。世界の潮流から取り残された「内向する日本」。「株価が上がってめでたい」という内輪の祭に興じ、「近隣の国にはなめられるな」という次元での安手のナショナリズムに吸い込まれた思考停止、鬱々とする日本だ。
なぜこの国が簡単に「国家主義への誘惑」に吸い込まれるのか。なぜ古い高度成長志向型経済観しかもてないのか。寺島さんは「近代を正視せよ」「世界の潮流に気付け」といい、対談の中で中島岳志さんは「リベラルとは近代の毒をも含めて、そこを踏み固めて前に進むこだわりだ」という。「構造的矛盾を見抜き、創造的未来へと運動論に高めていく視座が求められる。それはリベラル再生への探求だ。私は単なる時代の解説者などではいられない」と寺島さんはいう。
経済成長、拡大路線をひたすら走ってきた単線的、一本道の日本。しかし今、ポスト成長、成熟化、定常化の時代に入ったことを認識し、「(単線ではなく)根底にある自然観や生命観、人間観とともに、また実現されるべき"豊かさ"のビジョンとともに、複数のものが存在する」という視点に立って、意識変革、社会の転換を図ろう――それはローカルな地域に根ざしたコミュニティ経済の生成と「地球倫理」とも呼ぶべき価値原理の確立だ。人口減少社会は、そうした意味からチャンスであり、希望である。「地域からの離陸」の時代であった高度成長期とは反対に、人口減少社会は「地域への着陸」の時代になっていく。それはコミュニティや自然への着陸でもある。そう広井さんはいう。
グローバルな競争のなかで、"強い国""猛々しい国"をめざしがちだが、じつは社会の底流では、"安らかな国""安心・安定の国"への志向が確実に始まっている。「人間―自然の切断」「帰納的・合理的な要素還元主義」――そこから生じた工業化・市場化。アトミズム的な社会観ではなく、多様性(生き方も都市それぞれも多様性を評価)、関係性(人間と自然、個人とコミュニティ社会)、幸福(福祉)思想を重視する。それを重層的に「ポスト成長時代の価値と幸福」「コミュニティ経済の生成と展開」「ローカル化が日本を救う」「情報とコミュニティの進化(つなぐこと)」「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」「緑の福祉国家」「人間の顔をした環境都市」「もうひとつの科学」「日本の福祉思想――喪失と再構築」など、意欲的に提示している。
「いまはもう経済成長なんかにしがみついているときではない。文明の書き換え作業にしっかり取りかかるときなんじゃないでしょうか」「経済力や軍事力で競い合うような国じゃない、文化力を大切にする『別品』の国です」「3.11で成長社会から成熟社会への転換が始まると思ったが......3.11以前の日本を再生しようとしているように思う」――。マクルーハンから藻谷浩介さんの「里山資本主義」、浜矩子さんの「老楽(おいらく)国家」、広井良典さんの「人口減少社会という希望――コミュニティ経済の生成と地球倫理」などをも引きつつ語っている。
日本は米国の大量生産・大量消費・大量廃棄に裏付けされた「豊かな社会」をめざして"経済大国行きの超特急"に乗ってきた。欲望のビックバンだが、若者文化、テレビ時代とテレビ人間、適当に壊れるようにつくる品質や機能の廃品化、使い捨て計画的廃品化、浪費の誘発は、次第に歪みを生み脱線する。そうした世の中の空気や気分は三面記事と広告に表現される。「フル回転していた大量生産・大量消費の歯車がきしみ始め、需要の創出がお手上げ(手詰まり)になった。その壁を強引に突き破ろうとすれば、広告は強引になり、暴力的にならざるをえません」――。まさに広告は時代のきしみから生ずる叫びだ。
「成長から成熟へ」も「経済大国かつ生活大国」もいわれ続けてきた。3.11を経て、この国を今、未来を見つめてどうするか、マイルドな成長は勿論必要だが、どういう質を求めてグランドデザインを描くか、そして行程をどう進めるか、を問いかけている。
すごいし、すさまじい。「安藤というやつは、抜き身で走ってきたおもしろいやつや。近寄らん方がいい」「一人、裸で刀持って走っているようなやつや、危ない」と言われたという。気迫、気力、集中力、目的意識、強い思いを持つことが、自らに課したハードルを越えさせる。エネルギッシュな、野生をもった、知的好奇心の旺盛な若者達よ出でよ。それが日本を元気にする。
「甘え」などは勿論のこと、「ゆとり」などというのではない。不安と隣り合せ、緊張感に包まれた世界に突き放す。外国でも、仕事でも、一人で突き放す。その体験が、社会を生きていく上で大きな糧となり、人間を強くするという。
やり遂げた仕事も素晴らしいが、人生に迫る創造の迫力は異次元だ。
土木工学は安全、堅固を追求する。建築工学の美、文化、躍動、アートのための空間、美しい風景、街づくり、デザインの世界に触れることができた。