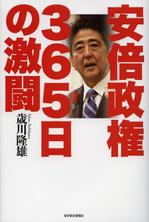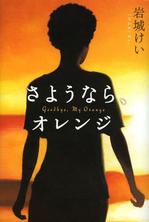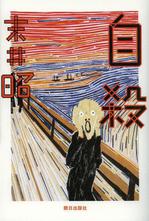「景気・経済の再生」「東北の復興」「防災・減災・危機管理」を三本の柱として、とにかく遮二無二走った一年。本当に激闘の一年だった。リスクを負ってもやり抜く政治だったと思う。歳川さんは「挫折を通じて辛酸を舐めた安倍氏はリスクを取る政治家に変身したのは間違いない」「現在の安倍首相は、従前の安倍首相ではない。別人格である」という。
自然現象を想定外とするのは、過去の事象を直視しない(したくない)人間の性もあるが、政治は人が成すものだけに、より変数が多い。それだけに政局観には、多くの変数、キーマンに直接ふれて得る皮膚感覚、動態視力、人間観が不可欠だ。本書はその時々の政局を、そのまま載せている。当たりもはずれも当然あるが、むしろそれだけにどう観たかという視点があらわで面白い。それは「どういう人間か」「どういう人材の布陣か」「どう考えて決断したか」という人間観・人物観をもって"チーム安倍"に迫っているからだと思う。その人物観は世界に及んでいる。
まさに海外の小説のよう。アフリカの戦火によって親・兄弟を失って難民となりオーストラリアに逃げてきた主人公。それ自体が新しいが、そのきめ細かな心象の描写は卓越したものがある。「シャワーの中で彼女(サリマ)はよく泣いた」「右も左もわからない。頼りになる親戚もいない。友人の支えも望めない。そしてなにより、言葉が伝わらない」「必死の思いでここにともに逃れてきたというのに、夫はいともあっさり妻と子供を捨ててしまった」――。一方、その友人となる日本人女性・佐藤サユリ。大学の研究員の夫についてオーストラリアに渡ってきたが、最愛の娘を託児所で失い、哀しみと喪失感にさいなまれる。
娘のいない色彩のない世界、光の先に追いやられた憂鬱やその下に広がる陰影を見てしまう二人だが、滲み出るような慈愛の交流によって「生きて死ぬということがただならぬことだ」ということを感じるようになる。幸せとは○○を獲得するものではない。幸せとはそこにあるものだ。自分を受け入れること、そして走り出すことなのだ。働き体に覚え込ませ、自分で素直にその場から立ち上がるしかないのだ。そこに苦しさをため込んだゆえに涙して見た夢や希望、夕陽、オレンジ色は消え、新たな境地がスタートする――そんな世界を描く。祖国とは、母国とは、母国語とは、人間とは、生きることとは、幸福とは、そうしたことを語りかけている。
「現在・過去・未来の視点から考える」と副題にあり、1980年代半ばからのプラザ合意以降の円高不況、バブルとバブル景気、バブル崩壊と長期停滞・デフレの始まり、デフレの本格化、デフレと円高の持続とリーマンショックを整理・分析する。また、本書が発刊されたのは昨年4月、アベノミクスのスタートしたあとで、期待をもちつつ、冷静に成功への課題を提起している。
「デフレと円高は、フロー市場とストック市場に作用しつつ、総需要を停滞させることで長期停滞をもたらした」「デフレと円高という貨幣的現象に大きく影響したのは政策のミスだが、金融政策は大した効果をもたらさないという"デフレレジーム"が、政策担当者・メディアをも巻き込んで失敗が失敗の連鎖をもたらした」「三本の矢は"大胆な"金融政策という一本の矢あってのことだ」――。本書は3つのステージ、3つの政策手段、3つの時点という3×3のフレームワークの視点から、これまでの日本経済とアベノミクスを分析し、それぞれについて好循環を生み出すことの必要性を精緻な分析によって説く。
「金融と世界経済――リーマンショック、ソブリンリスクを踏まえて」というテーマで、「金融拡大の30年間を振り返る」(池尾和人)、「グリーンスパンの金融政策」(翁邦雄)、「世界的バランス調整がもたらす"日本化現象"」(高田創)、「グローバル・インバランス」(後藤康雄)、「アベノミクスと日本財政を巡る課題」(小黒一正)の5人が、きわめて明確に本質と現実を述べている。
全体の流れは、投資ブームの終焉から金融政策へ、それも証券化やデリバティブに関連して新しい金融、そして常に中心となった米国、そしてグリーンスパンの狙いと政策、更にリーマンショック後の世界経済へと連なる。日本の経済を学び「デフレになるならバブルに目をつぶる」というグリーンスパン。日本が90年代以降、民間債務が政府債務に置きかわって"身代わり地蔵"となって国債残高の積み上がりが起きたこと。日本の債務調整の出口が米欧のバブル崩壊と重なった不運。今、アベノミクスが米国の終了段階と重なった幸運。金融危機の背景を探るインバランス仮説と流動性仮説(日本は危機を促したのか、巻き込まれたのか)。日本の財政危機の厳しい現実(2%インフレでも消費税25%必要)を直視した財政・社会保障の抜本改革――などの問題を分析している。「戦略ミスは戦術では挽回できない」という言葉が身にしみる。重要なのは改革の哲学、そして将来構想ということだ。
生きづらさを感じている人が多い。会社や学校にも行きづらい。しかし一方で、生と死も希薄になってしまっているのが今の社会でもある。自分自身、いろいろ経験してきたように思うが、「すぐ興味をもつ」「平気でだまされる」「無一物の人に弱い」「人に優しい」「敗者に魅せられる」――そんな末井さんの世界にふれてみると、人生の半分位しか見ていないと思えてくる。
「自殺していく人がいとおしく可哀想でなりません」「自殺する人は真面目で優しい人です。真面目だから考え込んでしまって、深い悩みにはまり込んでしまうのです。感性が鋭くて、それゆえに生きづらい人です。生きづらいから世の中から身を引くという謙虚な人です。そういう人が少なくなっていくと、厚かましい人ばかりが残ってしまいます」「生きづらさを感じている人こそ死なないで欲しい。社会に必要な人です」――。そして「みんな死なないでくださいね。生きてて良かったということはいっぱいあるんだから」と結んでいる。
「孤独と自殺」「いじめと自殺」「世間サマ(良き人であることを期待する)と自殺」「(両親が自殺し)残された者の話」「抗議の自殺と自死」「二人のホームレス」「青木ヶ原樹海に行く」「うつと自殺」「人に良く思われたい。過剰に。そして絶望して自殺未遂」「自分を捨てて他者のことを真剣に考える愛。相手の中に自分自身を見ること」――。率直なだけにより心に迫ってくる。