 「自由とセキュリティの相剋」という命題は、「多元主義と一元主義」「多様性の重視か安全への渇望か」「人権か覇権か」という複雑かつ広範な問題であり、現在世界を覆っているポピュリズムの問題でもある。「ポピュリズムの定義は定まってないが、多元性、多様性を否定し、一元的・集権的な政治を求めるものであることは間違いない。真の人民を代表するのは自分たちだけである、それ以外は『人民の敵』などとして排除するところにポピュリズムの特徴がある」「これが出てくる背景には、経済のグローバル化によって、雇用の安定性が脅かされたり、外国人が増えてなんとなく不安であるとか、文化的な一体性が損なわれるといったセキュリティ低下の意識があるといえる」と言う。コロナ禍やロシアのウクライナ侵略、欧米の選挙における右派ポピュリズム政党の跋扈、世界における専制主義の台頭・・・・・・。「強い指導者を求めるというより、むしろ誰でもいいから、社会をまとめてもらいたい」という空気のなか、「自由と多様性」が脅かされる現在への警告を、政治思想の名著6作から提示する。ミル、ホッブス、ルソー、バーリン、シュミット、フーコーの6人だ。
「自由とセキュリティの相剋」という命題は、「多元主義と一元主義」「多様性の重視か安全への渇望か」「人権か覇権か」という複雑かつ広範な問題であり、現在世界を覆っているポピュリズムの問題でもある。「ポピュリズムの定義は定まってないが、多元性、多様性を否定し、一元的・集権的な政治を求めるものであることは間違いない。真の人民を代表するのは自分たちだけである、それ以外は『人民の敵』などとして排除するところにポピュリズムの特徴がある」「これが出てくる背景には、経済のグローバル化によって、雇用の安定性が脅かされたり、外国人が増えてなんとなく不安であるとか、文化的な一体性が損なわれるといったセキュリティ低下の意識があるといえる」と言う。コロナ禍やロシアのウクライナ侵略、欧米の選挙における右派ポピュリズム政党の跋扈、世界における専制主義の台頭・・・・・・。「強い指導者を求めるというより、むしろ誰でもいいから、社会をまとめてもらいたい」という空気のなか、「自由と多様性」が脅かされる現在への警告を、政治思想の名著6作から提示する。ミル、ホッブス、ルソー、バーリン、シュミット、フーコーの6人だ。
「自由とセキュリティの相剋」は本質的問題だ。生命や生活の安全、セキュリティを考えれば、人々が力を合わせ、意志を統一させ、現存秩序を維持することが重要となる。自由を重視する政治理論は、「どう生きるべきかは人それぞれであり、どの生き方が正しいという確証がない以上、一つにまとまることはできないという考え方」であり、「絶対的に正しい秩序というものが保障されないとすれば、秩序への異議申し立ての余地は常に必要だという考え方」だ。「セキュリティ重視の政治理論からすれば、秩序対抗的な動きはセキュリティの低下につながる撹乱要因に過ぎないが、自由重視の政治理論からすれば、秩序を一元化し、それを固定化しようとすることこそが、秩序を牢獄に変え、人々の生活のセキュリティをかえって低下させかねない」と言うのだ。コロナ禍、戦争、経済の不安定、社会の不安と分断、フェイクの暴走など、セキュリティへの危機意識が高まれば、秩序の再構築と一元化への誘惑は高まるが、少数意見を封じ込めた自由軽視のいずれの専制も、歴史の中で脆弱さをさらけ出したと改めて思う。
人も思想も時代の中にある。自国の政治的危機に翻弄されたホッブスは、人間を自由のままにすれば、セキュリティは低下するということから「秩序志向」「国家(リヴァイアサン)」を示す。そして、ワイマール共和国の危機に身を置いたシュミットは、「政治とは戦争である」「政治は緊急事態、例外状態にこそ現れる」「政治的多元主義批判」「セキュリティを確保するためには個々人が自由を放棄して、集団として力を合わせる以外にはない」と発想する。シュミットの影響を受けた丸山眞男の「(日本の戦争主体の)無責任の体系」について、著者は「戦前の日本の失敗の本質はむしろ、価値の多元性を否定した点にあったと考える」と言っている。
ミルは「少数意見擁護論」「個人の自由の領域を幅広く認めようとするには、社会に多様性が必要。多様な意見が確保されることで、社会の知的発展が期待できる」とする。著者は「現在の自由論は、あまりにセキュリティー論の方に傾きすぎている」とし、「自由の条件として、平等や貧困の克服が重要であるとしても、それは充分条件ではない。自由論というのは、それ自体として論じられるべきだ」と言う。
ルソーは「一般意志」による統一を構想する。しかも「一般意志への服従は、共同体全体によって強制される。これは『自由への強制』に過ぎない」と言う。しかしその後、「フランス革命期に『人民の敵』と名指しされた人々が、次々にギロチンにかけられる」ことになる。偉大な人も思想も時代の中にあるということか。
20世紀に入り、バーリンは「ニつの自由概念」を示す。消極的自由と積極的自由の概念だ。「個人に許される範囲と社会によって統制される範囲との境界線に関わるのが消極的自由であり、そこでは個人の内面は問題にならない。他方で積極的自由は、まさにその個人の内面で起きていることを問題している」「消極的自由で特に強力なのは政府による統制」「バーリンは、多元主義の立場から、人々にとっての価値選択が一つにはならないこと、そして一つの理念によって社会をまとめようとすれば無理が生じる」ことを主張する。
フーコーは、「継続する戦争状態というものを国家間戦争の局面でなく、内戦の局面において、つまり国内の征服者と被征服者との関係において見ていく」「ホッブスの戦争状態とは、実際の力の激突としての戦争とは異なり、相手を攻撃するぞという『表象のゲーム』であるとする。血の匂いはしない」「眼目は主権批判」など、「権力のあり方」を論じている。これらの著作を通じ、著者の考えが随所に述べられる。短い新書だが中身は深大。
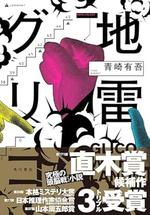 都立頰白高校1年の射守矢真兎(いもりやまと)は、勝負事に桁はずれに強い女子高校生。親友の同級生・鉱田とともに、次々と持ち込まれる勝負に挑む。スリリングな5つの勝負が描かれる。風変わりなゲームの数々、究極の頭脳戦、鮮やかな解決策、その切れ味、達人ぶりに引き込まれる。
都立頰白高校1年の射守矢真兎(いもりやまと)は、勝負事に桁はずれに強い女子高校生。親友の同級生・鉱田とともに、次々と持ち込まれる勝負に挑む。スリリングな5つの勝負が描かれる。風変わりなゲームの数々、究極の頭脳戦、鮮やかな解決策、その切れ味、達人ぶりに引き込まれる。
「地雷グリコ」――ジャンケンで勝ったら階段を登る。対戦相手と互いに3つの段に地雷を仕掛け、被弾を避けながら昇る心理戦。あっと驚く理詰めの戦略を真兎は仕掛ける。
「坊主衰弱」――百人一首の絵札を使った神経衰弱。「男」と「姫」と「坊主」の3種類あるが、「坊主」をめくってしまった時は一発アウト。勝負の途中に「鉱田ちゃんへ」という不思議なLINEが真兎から届く。"イカサマ"を見抜く鮮やかな眼力。
「自由律ジャンケン」――生徒会の佐分利会長が真兎に興味を持ち、グー・チョキ・パーの3種に両プレイヤーが考案した<独自手>を加えた計5種でジャンケン対決を仕掛けてくる。佐分利会長は<蝸牛>、真兎は親指を立てた<銃>の形で対戦が始まる。
「だるまさんがかぞえた」――屋外で距離をとって行う「だるまさんがころんだじゃなくて、かぞえた?」のゲーム。標的(オニ)が、暗殺者をいつ振り向くかは<入札>しだい。進むか止まるかの心理戦。いろいろな条件を確認して、真兎が考え抜いた作戦とは・・・・・・。これはとんちの「一休さん」のよう。
「フォールーム・ポーカー」――真兎と鉱田を置いてけぼりにした雨季田絵空との戦い。約6000万円を賭けて、ポーカーを3枚で行う。4部屋に伏せられた52枚のトランプ。真兎と絵空は互いに相手を知ってるが故に、探り仕掛け合う。そして決着、和解へ。
痛快な青春の頭脳バトル小説。よくぞこういうゲームを考え出すものだ、そしてその解決策を。仕掛け合いを、行ったり戻ったりして考えた。
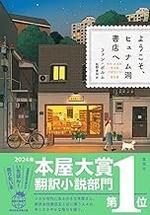 2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位。会社を辞め、ソウル市内の住宅街にカフェ付きの書店を始めたヨンジュ。緊張とストレスで疲れ果て、会社を辞めるだけでなく、離婚までして追い詰められた彼女が、子供の頃からの夢だった本屋を開いたのだ。ヒュナム洞の「ヒュ」は「休」という字。アルバイトで手伝うようになったバリスタのミンジュン、夫の愚痴をこぼすコーヒー業者のジミ、無気力な男子高校生ミンチョル、その母のヒジュ(ミンチョルオンマ)、兼業作家のスンウ・・・・・・。社会や家族との関係に悩み、孤独を抱える人や傷ついた人たちが、この本屋に来て癒されていく。
2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位。会社を辞め、ソウル市内の住宅街にカフェ付きの書店を始めたヨンジュ。緊張とストレスで疲れ果て、会社を辞めるだけでなく、離婚までして追い詰められた彼女が、子供の頃からの夢だった本屋を開いたのだ。ヒュナム洞の「ヒュ」は「休」という字。アルバイトで手伝うようになったバリスタのミンジュン、夫の愚痴をこぼすコーヒー業者のジミ、無気力な男子高校生ミンチョル、その母のヒジュ(ミンチョルオンマ)、兼業作家のスンウ・・・・・・。社会や家族との関係に悩み、孤独を抱える人や傷ついた人たちが、この本屋に来て癒されていく。
「自分が本を愛し、書店のスタッフが本を愛するなら、その愛は逆にも伝わるのではないだろうか。・・・・・・本でコミュニケーションし、本で冗談を言い、本で友情を深め、本で愛をつないでいくなら、客も自分たちの思いをわかってくれるのではないだろうか」「一日を豊かに過ごすことは、人生を豊かに過ごすことだと、どこかで読んだ一節について考えながら眠りにつくのだろう」・・・・・・。
著者のファン・ボルムは言う。「息つく間もなく流れていく怒涛の日常から抜け出した空間。もっと有能になれ、もっとスピードを上げろと急き立てる社会の声から逃れた空間。その空間で穏やかにたゆたう一日。それは私たちからエネルギーを奪っていく一日ではなく、満たしてくれる一日だ」「私は自分が読みたいと思う物語を書きたかった。自分だけのペースや方向を見つけていく人たちの物語を。悩み、揺らぎ、挫折しながらも、自分自身を信じて待ってあげる人たちの物語を。・・・・・・もっと頑張らねばと自分を追い詰めて日常の楽しさをなくしてしまった私の肩を、温かく包んでくれる物語を」――。まさにこの本は、その通りの「優しく慰められる」本になっている。「~しなければならない」「~すべきだ」でがんじがらめになっている社会。「本当に、好きなことをしないといけないのか?でも、自分には好きなことなんてないのに」という生の世界を、このヒュナム洞書店は受け入れている。「彼の言う幸福とは、最後の瞬間のために、長い人生を人質にとられているのと同じだ。最後の瞬間の一度きりの幸福のために、生涯、努力の指導士で不幸に生きていかないといけないんだ。そう考えると、幸福っていうものがなんだか恐ろしくなったんです。だから、私は幸福ではなく、幸福感を求めて生きようって、考えを変えたんです」と言うくだりがある。
ヒュナム洞書店、この空間が人々の身近な存在となり、力を湧出させる場となっていく。悩みの背景に、燃え尽き症候群や不安定な非正規雇用、激しい競争があるのは日韓共通のものだが、大学卒の就職難は韓国の大変さを物語っている。また、ヒュナム洞書店は「多様性のためにベストセラーは排除した」と言っている。「ヨンジュは大型書店のベストセラーコーナーに行くと、出版市場の歪んだ自画像を見る思いがした。数冊のベストセラーに依存する悲しい現実。本を読まない文化のあらゆる側面が反映された結果に過ぎない。このような現実のなか書店を運営するものがなすべきは、それでも小さな努力を積み重ね、読者に多様な本を紹介することであるはずだ」と言っている。このような本屋が地域にあることは意義深く嬉しいことだ。
 「世界は経営でできている」「人生は経営でできている」――企業だけでなく、全てが経営による。経営とは「価値創造する」「価値創造へのマネージメント」だ。人類史における本来の経営は「価値創造という究極の目的に向かい、中間目標と手段の本質・意義・有効性を問い直し、究極の目的の実現を妨げる対立を解消しながら豊かな共同体を作り上げる知恵と実践」だ。
「世界は経営でできている」「人生は経営でできている」――企業だけでなく、全てが経営による。経営とは「価値創造する」「価値創造へのマネージメント」だ。人類史における本来の経営は「価値創造という究極の目的に向かい、中間目標と手段の本質・意義・有効性を問い直し、究極の目的の実現を妨げる対立を解消しながら豊かな共同体を作り上げる知恵と実践」だ。
しかし、世界から経営が失われている。「人生の様々な場面において、経営の欠如は、目的と手段の転倒、手段の過大化、手段による目的の阻害・・・・・・など数多くの陥穽をもたらす」と言う。それは「あらゆるものが創造できる」という視点を持たないと、手段に振り回されるからだ。「人生における金銭、時間、歓心、名声などの悲喜劇は『何かの奪い合い』から生まれる。そして奪い合いは、限りある価値に対して発生する」「価値を有限だと錯覚すれば、顧客に粗悪品を掴ませ、従業員を搾取し、他者を蹴落とすことになる。価値有限思考を、経営によって価値は創造できると考える価値無限思考への転換が重要となる」「価値が無限に創造できるものならば、他者は奪い合いの相手ではなく、価値の創りあいの仲間になれるのだ」と言う。
本書は、「日常」「貧乏」「家庭」「恋愛」「勉強」「虚栄」「仕事」「健康」「老後」「歴史」「人生」など17項目を上げ、いずれも「経営でできている」ことを示す。一見経営と無関係なことに経営を見いだすことで、世界の見方ががらりと変わる。今、日本に足りない「経営」「価値創造」の世界を開示する。国家の運営も、「経営」の知恵と実践が重要となるということだ。
 「女性とマイノリティの100年」が副題。シベリア抑留体験のある父を持ち、アナキスト伊藤野枝の壮絶な生涯を描いた「風よ あらしよ」の作者・村山由佳。祖父が関東大震災で殺されかけ、在日韓国・朝鮮人として様々な差別を経験してきた朴慶南。1923年9月1日に発生した関東大震災、そこで起きた民間人らによる朝鮮人虐殺や憲兵による無政府主義者殺害。それから100年たった今、2人の対談が行われた。「関東大震災で、なぜ普通の人間が同じ人間に対し、かくもむごいことができたのか」「民族差別の背景に何があったのか」「当時の差別と排除の濁流は、今の時代へそのままつながっているのではないか」――。女性とマイノリティの100年を率直に語り合っている。
「女性とマイノリティの100年」が副題。シベリア抑留体験のある父を持ち、アナキスト伊藤野枝の壮絶な生涯を描いた「風よ あらしよ」の作者・村山由佳。祖父が関東大震災で殺されかけ、在日韓国・朝鮮人として様々な差別を経験してきた朴慶南。1923年9月1日に発生した関東大震災、そこで起きた民間人らによる朝鮮人虐殺や憲兵による無政府主義者殺害。それから100年たった今、2人の対談が行われた。「関東大震災で、なぜ普通の人間が同じ人間に対し、かくもむごいことができたのか」「民族差別の背景に何があったのか」「当時の差別と排除の濁流は、今の時代へそのままつながっているのではないか」――。女性とマイノリティの100年を率直に語り合っている。
「大震災での朝鮮人虐殺の事実」――朝鮮人、中国人、間違えられ日本人も含めて6000人もの"大虐殺"。「姜徳相による虐殺のメカニズム解明(暴力が支配する戒厳令下の虐殺) (日本による過酷な植民地支配に対して、1919年の朝鮮半島での3.1独立運動など、大規模な反日運動が各地で起き、日本政府や軍警察当局は危機的な事態とみなし恐れていた)」などが示される。「朝鮮人なら殺してもいいという時代があった」「関東大震災時の自警団は東京1145、神奈川634・・・・・・。組織の中核は、各町村の青年団、在郷軍人会、消防組で、警察が上から組織したものが多い」と言う。「植民地支配、官民どちらにもある朝鮮人への差別意識と仕返しを恐れる感情、戒厳令を背景にした官製弾圧」を指摘する。
「男社会は同性愛を忌避する」――。「ホモソーシャルな社会の中では、ホモセクシャルである人間はまず排除される。ホモセクシャルを嫌うホモソーシャルから、ホモフォビア(同性愛嫌悪症)が出てくる」「自分に自信がない人ほど持ち物で人と張り合ったり他人を見下したりする。自分に自信がないから、変に理論武装して『論破』に快感を見出したりマウンティングしたがる」とし、価値はそれぞれに独自のものであると言う。また、「相手の心に響く謝罪」「物語は他者の『痛み』を伝える」「被害を受けた側への想像力」の大事さを語り合っている。
「抵抗者たちの近現代史」であるとともに、「人間の原点」を感じさせる対談。

