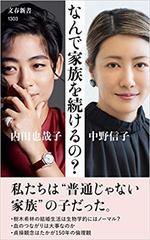 「選択的夫婦別姓」「同性婚」などが問題提起される今、「家族」についての対話は見逃せない。「私たちは"普通じゃない家族"の子だった」という二人。内田也哉子さんは樹木希林と内田裕也の娘であり、希林と裕也は同居していたのは最初の1~2か月、45年間はほぼ別居だが、娘のお宮参りなど、ことあるごとに写真館で家族写真を撮ったという。19歳で本木雅弘さんと結婚、三児の母として家族を最優先に生きてきたという。中野さんも大変裕福なエリートと思いきや、ご両親は離婚、親との葛藤を抱え込んできたという。
「選択的夫婦別姓」「同性婚」などが問題提起される今、「家族」についての対話は見逃せない。「私たちは"普通じゃない家族"の子だった」という二人。内田也哉子さんは樹木希林と内田裕也の娘であり、希林と裕也は同居していたのは最初の1~2か月、45年間はほぼ別居だが、娘のお宮参りなど、ことあるごとに写真館で家族写真を撮ったという。19歳で本木雅弘さんと結婚、三児の母として家族を最優先に生きてきたという。中野さんも大変裕福なエリートと思いきや、ご両親は離婚、親との葛藤を抱え込んできたという。
「2040年、日本人の半分が結婚を選択しなくなる」「アホウドリのカップルの3分の1はレズビアン(その時だけオスと浮気をし、子育てはメス2羽でする)(子育てと生殖行動は別)」「貞操観念はたかが150年の倫理観。本来、人間の性のあり方はもっと多様だった」「産みの親と育ての親はどっちの影響が大きいか(育ての親)」「知性は母から、情動は父から受け継ぐ」「脳科学は生理学の延長で自然科学、心理学は哲学の延長で考え方の仕組み」「生物にとっての最重要課題は、自身の生命の維持(集団のメリットと利己機能を削るストレス)」・・・・・・。
「家族のあり方というのは、一意に定まるようなものではなく、歴史的、民俗学的に見れば多彩な様式が存在した。その柔軟性が私たちにとっての生存戦略的な武器であった」「社会的な機能を十全に果たしていれば、家族というのは決して現在の私たちが刷り込まれているようなステレオタイプなものである必要はないはず」と中野さんはいう。「普通の家族とは何なのか」「家族ってこれでいいのか」と問いかけながら生きてきた二人の実感こもる対談。
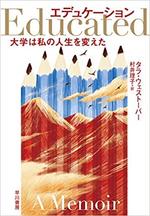 凄まじい壮絶な人生の回顧録。タラ・ウェストーバーさんは、米国アイダホ州生まれ。ブリガム・ヤング大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学で研究者となった歴史家・エッセイストの女性。1986年、アイダホ州クリフトンでモルモン教サバイバリストの両親のもと、7人兄姉の末っ子として生まれ育つ。父親の極端な思想的呪縛の影響は強く、政府を目の敵とし、子供たちを学校に通わせない。科学や医療を否定し、民間療法を盲信、社会から孤立した暮らしをする。父親の廃品回収とスクラップの仕事は乱暴なもので、子供は命にもかかわる危険な作業を強制される。現実に爆発事故、落下事故、交通事故・・・・・・。親も子供も瀕死の大事故は、よくぞ何とか死を免れたと思うほどだが、身体に残った後遺症は大きい。父親だけでなく次男ショーンによる熾烈な暴力もタラを極限まで追い詰める。
凄まじい壮絶な人生の回顧録。タラ・ウェストーバーさんは、米国アイダホ州生まれ。ブリガム・ヤング大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学で研究者となった歴史家・エッセイストの女性。1986年、アイダホ州クリフトンでモルモン教サバイバリストの両親のもと、7人兄姉の末っ子として生まれ育つ。父親の極端な思想的呪縛の影響は強く、政府を目の敵とし、子供たちを学校に通わせない。科学や医療を否定し、民間療法を盲信、社会から孤立した暮らしをする。父親の廃品回収とスクラップの仕事は乱暴なもので、子供は命にもかかわる危険な作業を強制される。現実に爆発事故、落下事故、交通事故・・・・・・。親も子供も瀕死の大事故は、よくぞ何とか死を免れたと思うほどだが、身体に残った後遺症は大きい。父親だけでなく次男ショーンによる熾烈な暴力もタラを極限まで追い詰める。
あまりにも残酷、あまりにも過酷、深い絶望のなかで、タラは大学に行くことを決意する。学校に全く行っていない子供たちだが、絶望のなかで救いを求める光となったのが、彼女の強靭な意志、美しい歌声、凄い知力。「大学は私の人生を変えた」が副題だが、呪縛から離れて大学に行ったのではない。父母、兄弟の呪縛は、その後も間歇泉のように随時、噴き上がる。「あの場所は私に取り憑いていて、もしかしたら一生逃れられないかもしれない」と思う。ところが父は「結果から見れば、お母さんとお父さんが学校に行かせなかったのは正しかったんだ。ホームスクールのおかげだとなんで言わなかったんだ」「神の魂が歓迎されない場所(ケンブリッジ大)だったら、行くことはない」とまでいうのだ。愛憎のアンビバレント的関係に宗教思想原理の実践が加わったなかでも、家族の絆は放擲することができないのだ。最後の最後まで胸が締め付けられた。全米で大きな話題となったベストセラー。
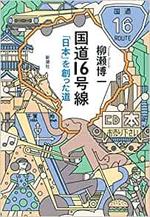 ユニーク、かつ面白い。「地形」は人間の生存にとって最も本質的であるからだ。首都圏をぐるりと囲む330キロの環状道路国道16号線。三浦半島の付け根から横須賀、横浜の海辺を走り、東京に入って町田、八王子、福生を抜け、埼玉の入間、狭山、川越、さいたま、春日部を過ぎ、千葉の野田、柏、千葉、市原から再び東京湾岸の木更津、富津に至る馬蹄形の国道16号線。ここには今、1100万人もの人が住んでいる。
ユニーク、かつ面白い。「地形」は人間の生存にとって最も本質的であるからだ。首都圏をぐるりと囲む330キロの環状道路国道16号線。三浦半島の付け根から横須賀、横浜の海辺を走り、東京に入って町田、八王子、福生を抜け、埼玉の入間、狭山、川越、さいたま、春日部を過ぎ、千葉の野田、柏、千葉、市原から再び東京湾岸の木更津、富津に至る馬蹄形の国道16号線。ここには今、1100万人もの人が住んでいる。
縄文時代の「遺跡や貝塚」が多い。中世の「城」が多い。江戸幕府の頃から明治にかけて、日本の殖産興業と富国強兵の要となる生糸(八王子・富岡そして横浜の港)や軍事施設(それが戦後は米軍施設になる)、ユーミンやサザンに至るジャズやニューミュージックの音楽・文化、モータリゼーションのなかでの大団地やショッピングモール、大学の集積・・・・・・。そして今、大団地の疲弊(ニュータウンがオールドタウン)と高齢者の集積、環境を視野に置いたテレワークの新たな若者向け街づくり・・・・・・。日本そのものを映し出し、時代をくっきりと具現する日本・首都圏の文明の栄枯盛衰の国道16号線だ。
背景には「地形」がある。「4つのプレートがぶつかる世界でも稀な場所、黒潮の流れに突き出た2つの半島、急峻な丘陵地といくつもの台地、大きな河川が注ぐ巨大な内海の東京湾(利根川も家康以前は東京湾に注いでいた)、後背部に広い低地の関東平野、そして台地と丘陵地の縁に無数の小流域――。それを馬蹄形につなぐと16号線になる」という。大型平野そのものは、太古以来、大水害と高潮等で住みづらく、家康以来の利根川の東遷、荒川の西遷で変わり、戦後は高度成長や人口急増、土地バブル、公害等々の影響がそのまま現れたのだ。
「なにしろ日本最強の郊外道路(生糸が殖産興業を、軍港が富国強兵を、リゾートホテルと米軍とショッピングモールが同居、少子高齢化がもたらすゴーストタウン)」「16号線は地形である(船と馬と飛行機の基地となる、大学と城と貝塚が同じ場所で見つかる)」「戦後日本音楽のゆりかご(矢沢永吉とユーミン、ルート16を歌う、ジャズもカントリーも進駐軍に育てられた)」「消された16号線――日本史の教科書と家康の罠(16号線の関東武士が頼朝の鎌倉幕府を支える、太田道灌が拓いた豊かな水の都、"江戸は寒村だった"は家康伝説の強化策の面も)」「カイコとモスラと皇后の16号線(皇后が引き継ぐ宮中養蚕の伝統、八王子と横浜を結ぶシルクロードと鑓水商人、天皇家の蚕と渋沢栄一)」「未来の子供とポケモンが育つ道(定年ゴジラが踏み潰す老いたニュータウン、コロナとバイオフィリア=生物愛が16号線を再発見させる)」・・・・・・。
こうして見ると時代の変化は16号線に現われる。変化を見ようとするなら国道16号線から目を離すな、ということだろう。
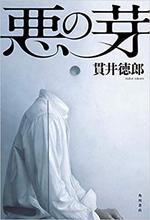 3日間で10万人もの人が集う大規模なアニメコンベンション――。突然、一人の男が火炎瓶を次々に投げ、8名が死亡し重軽傷30数名という無差別大量殺人事件が発生した。犯人・斎木均は現場で焼身自殺。マスコミは少年期に受けた"いじめ"を機に小・中・高と学校に行けず、就職もままならなくなった斎木の転落の半生を容赦なく暴き続けた。一流銀行に勤務し、幸せな家庭を築いていた安達周は、この犯人の名に驚愕する。じつは"いじめ"の発端となる"斎木菌(細菌)"呼ばわりの"あだ名"を付けたのが安達だったのだ。斎木の人生を狂わせた罪の意識に苛まれ、ネットで報じられることへの怯えで、安達はパニック障害を起こし会社を休職する。なぜ斎木は無差別大量殺人事件を起こしたのか。斎木は何に怒ったのか。「社会に対する恨み」と決めつけていいものなのか。安達は、動機・真実に迫ろうと苦しみもがく。「悪の芽」は一体どこで生じたのか。
3日間で10万人もの人が集う大規模なアニメコンベンション――。突然、一人の男が火炎瓶を次々に投げ、8名が死亡し重軽傷30数名という無差別大量殺人事件が発生した。犯人・斎木均は現場で焼身自殺。マスコミは少年期に受けた"いじめ"を機に小・中・高と学校に行けず、就職もままならなくなった斎木の転落の半生を容赦なく暴き続けた。一流銀行に勤務し、幸せな家庭を築いていた安達周は、この犯人の名に驚愕する。じつは"いじめ"の発端となる"斎木菌(細菌)"呼ばわりの"あだ名"を付けたのが安達だったのだ。斎木の人生を狂わせた罪の意識に苛まれ、ネットで報じられることへの怯えで、安達はパニック障害を起こし会社を休職する。なぜ斎木は無差別大量殺人事件を起こしたのか。斎木は何に怒ったのか。「社会に対する恨み」と決めつけていいものなのか。安達は、動機・真実に迫ろうと苦しみもがく。「悪の芽」は一体どこで生じたのか。
"いじめ"はいじめた方も生涯、心に傷を負う。"ネット社会"の悪口は、人の人生を根っこから崩壊させることがある。「こうなったのは全部、社会が悪い、他人が悪いというのは努力が足りない人間のいうことだ」というのは、弱肉強食の理屈ではないか。斎木は懸命に働き、心を通わせた"キャバ嬢"に「人間はまだ進化が充分じゃないんだ。・・・・・・見下したり、攻撃したり、人間はおかしな生き物ですよ。ネットでの悪口だけでなく、キャバ嬢とか風俗嬢を見下してるから、それで萌愛のために寄付する気がなくなったんでしょ。立派な生き物の振りして生きている人も、ホントは他人を見下す気持ちを心の中に持っているんです。人間がもっともっと進化して、みんなが優しい生き物になってたら萌愛はきっと死なずに済んだんです」と語り合ったという。人間であることの放棄、優しい生物になれない人間への絶望。世界にも、人間にも、自分にも、もういいやって思ってしまう絶望。「人間はなぜ、自分の周囲に向ける分しか優しさを持っていないのだろうか」と問いかける。無差別大量殺人事件まで至らなくても、現代のありうる問題を剔抉する傑作。
 「関ヶ原の戦い(慶長5年9月15日)」を一次史料を駆使して新進気鋭の執筆陣が最新の研究成果を示す。すると、「家康の小山評定」や「小早川秀秋への問鉄砲」などが、どうも怪しいことがわかる。歴史文書を残すということが、自らの人生や一族にとって不利か有利か、二次資料等は"勝者の歴史"となりがちだということだ。歴史研究はそうしたこともあって難しいし、面白いといえるだろう。
「関ヶ原の戦い(慶長5年9月15日)」を一次史料を駆使して新進気鋭の執筆陣が最新の研究成果を示す。すると、「家康の小山評定」や「小早川秀秋への問鉄砲」などが、どうも怪しいことがわかる。歴史文書を残すということが、自らの人生や一族にとって不利か有利か、二次資料等は"勝者の歴史"となりがちだということだ。歴史研究はそうしたこともあって難しいし、面白いといえるだろう。
徳川家康(水野伍貴著)、上杉景勝(本間宏)、伊達政宗(佐藤貴浩)、最上義光(菅原義勝)、毛利輝元(浅野友輔)、石田三成(太田浩司)、宇喜多秀家(大西泰正)、大谷吉継(外岡慎一郎)、前田利長(大西泰正)、長宗我部盛親(中脇聖)、鍋島直茂(中西豪)、小早川秀秋・黒田長政・福島正則(渡邊大門)、そして「関ヶ原の戦いの従来のイメージの打破」「近衛前久書状」について白峰旬氏。14武将が描かれる。「関ヶ原」については、越後から会津へ移封された上杉景勝に対して最上・伊達との"北の関ヶ原"である「慶長出羽合戦」があること、そして家康と西軍の三成、大谷吉継、さらに宇喜多秀家、長宗我部盛親は勝敗がはっきりしているが、他の武将も関ヶ原の後、大変な激震に見舞われたことがよくわかる。「東軍が最終的に勝利をつかんだのは、小早川秀秋、黒田長政、福島正則の力なくして語れない。しかし、その後の命運は大きく違ったのである」と結ばれているが、小早川秀秋などは1602年には"酒の飲みすぎ"で20才で死亡している。
「豊臣七将による三成襲撃事件も一次史料にはない」「小山評定における福島正則の大演説は作り話」「石田三成と大谷吉継の"友情物語"は根拠がない」「小早川秀秋への"問鉄砲"はフィクション」「直江状はあったが"家康への挑戦状"と評される内容ではなかった」「政宗は秀吉への思いをもちつつ、家康の時代を認めた」「輝元は"お飾り"にはほど遠い独自の思惑で戦いに加担する"野心家"だった」「三成は福島正則が味方すると想定したことが誤算で敗因」「鍋島直茂の処世術」「抜け駆けを許した正則(井伊直政、松平忠吉)」・・・・・・。
イメージが先行、定着している「関ヶ原の戦い」も、史料に即してみると今も動いている。

