 「命の経済」への転換を訴える。昨年10月の出版だから、「コロナ」のデータは7月頃までが中心だと思う。2021年3月の現在、欧州では「変異株が急増」、日本では「首都圏の緊急事態宣言が21日まで延長、下げ止まらない」「コロナのダメージが長期となり、観光・飲食・航空等の交通機関、そして医療体制と、持ちこたえられない所(倒産等)が出ている」「年内の完全終息は見込めない、重傷者も時々は出る(尾身茂会長)」と厳しい状況にある。アタリ氏は、昨年夏頃までのデータを使ってだが、その本質と未来を観ようとしている。その背後にある分析は「現在のパンデミックが過ぎ去っても別のパンデミックが訪れるだろう」「今回のパンデミックを外出禁止措置等で乗り切ろうとしても、疲弊した企業や医療等は、元に戻らないことがある」ということだ。だからこそ「命の経済」への転換を図ろうというのだ。
「命の経済」への転換を訴える。昨年10月の出版だから、「コロナ」のデータは7月頃までが中心だと思う。2021年3月の現在、欧州では「変異株が急増」、日本では「首都圏の緊急事態宣言が21日まで延長、下げ止まらない」「コロナのダメージが長期となり、観光・飲食・航空等の交通機関、そして医療体制と、持ちこたえられない所(倒産等)が出ている」「年内の完全終息は見込めない、重傷者も時々は出る(尾身茂会長)」と厳しい状況にある。アタリ氏は、昨年夏頃までのデータを使ってだが、その本質と未来を観ようとしている。その背後にある分析は「現在のパンデミックが過ぎ去っても別のパンデミックが訪れるだろう」「今回のパンデミックを外出禁止措置等で乗り切ろうとしても、疲弊した企業や医療等は、元に戻らないことがある」ということだ。だからこそ「命の経済」への転換を図ろうというのだ。
パンデミックの歴史を語り、今回の未曾有のパンデミックに対して、中国には厳しく、ロックダウンの欧米のやり方を批判、"三密""マスク""手洗い"等の韓国・台湾等を褒める。そして、今後の世界は「米中両国が衰退し、覇権国なき世界に向かう変化が加速する」とし、EUの使命に言及する。そして、今回のことで「自己と向き合う貴重な機会を得た」「テレワークの増大」「非営利活動の発展」「情報リテラシー」「心地よい時間こそ大切」など、新しい動き、価値観が生まれていることを指摘する。
そして「命の経済」――。「我々は、組織構造、消費、生産の形態を抜本的に見直す必要がある。経済活動を新たな方向に誘導しなければならない」という。優先課題は「治療薬とワクチン開発」「医療、予防、健康増進のヘルスケアの強化」「新たな対話の形、食生活を改める(少肉多菜、少糖多果、地産地消)」「密集型都市からの脱却」「医療とともに教育に力を入れる(遠隔教育、再就職の職業訓練、生涯学習、遠隔授業、失う社会性やグループ活動、スポーツ、社会活動への支援)」「文化と娯楽の未来」・・・・・・。パンデミック後の成長分野、健康・食糧・住宅・文化・スポーツ・教育等々、そして環境も国土保全も視野に入れた市場では満たせない莫大な需要へのシフト。それが「命の経済」だという。そして「自動車、航空機、工作機械、ファッション、化学、プラスチック、化石燃料、ぜいたく品、観光などの企業が過去の市場を取り戻すことはない」と指摘する。別のサービスへの移行を模索する一方で、「観光業を救え」「持続可能な観光を模索せよ、一部の観光地への過剰観光ではなく、近場の観光も」と提唱する。さらに地球温暖化が人類に危機を及ぼす一方で、それがパンデミックを引き起こす、リンクしていることを指摘する。こうしたパンデミックが100年に1回でなく、たびたび起きるとすると、全くその通りだ。警告と提唱の本。
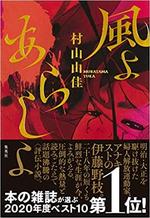 「吹けよ あれよ 風よ あらしよ。強い風こそが好きだ。逆風であればもっといい。吹けば吹くだけ凧は高く上がり、トンビは悠々と舞うだろう。その年、大正2年9月20日――祝いどころか用意もしてやれない困窮の中で、野枝は長男・一を産み落とす」――。明治・大正を激しく駆け抜け、手塚らいてうの「青鞜」に参画し、アナキスト大杉栄とともに憲兵に連れ去られ殺害された婦人解放運動家・作家の伊藤野枝の28年の生涯(1895年~1923年)。
「吹けよ あれよ 風よ あらしよ。強い風こそが好きだ。逆風であればもっといい。吹けば吹くだけ凧は高く上がり、トンビは悠々と舞うだろう。その年、大正2年9月20日――祝いどころか用意もしてやれない困窮の中で、野枝は長男・一を産み落とす」――。明治・大正を激しく駆け抜け、手塚らいてうの「青鞜」に参画し、アナキスト大杉栄とともに憲兵に連れ去られ殺害された婦人解放運動家・作家の伊藤野枝の28年の生涯(1895年~1923年)。
福岡の糸島郡今宿村の貧しい家に育つ。色は浅黒く、小柄で、黒々とした眼光は強いが澄んでいる。野育ち少年のようで、激しく、これほどまでというほどの負けず嫌いで、頭脳明晰。出て来た東京は、近代化・産業化の轟音、日清・日露の戦争を経て、政治・思想闘争は過激を究めていた。幸徳秋水らが処刑された大逆事件が1910年(明治43年)、平塚らいてうの「青鞜」創刊は1911年(明治44年)。10代後半の伊藤ノエはそのど真ん中を疾走した。教師の辻潤と恋愛関係になり、2度目の結婚。そして大杉栄をめぐって妻・堀保子、神近市子、野枝との四角関係は泥沼化し、神近が大杉を刺す日陰茶屋事件に行き着くが、結局は大杉と野枝が結ばれていく。赤貧洗うがごとくの生活で、家賃も払えず家も転々、同志も変転するが、大杉との間では同志的絆も強く、相性も良く、毎年のように5人もの子を成す。そして関東大震災後の混乱のなかで、官憲に捕われ共に殺される。
明治維新から50年――世界も第一次世界大戦、ロシア革命。日本の近代化、労働運動や女性解放・人権運動の勃興期。社会も人間も荒削り、欲望むき出しの時代であったことが、伊藤野枝の激しい生涯(たった28年)を通じてよくわかる。「叔父夫婦をはじめ野枝には苦労のかけられ通しだったろう」「もとより大杉は、行動・実行にこそ重きを置いている。思想を広めるだけで呑気に満足している連中を横目に見ながら・・・・・・」「世の多くの人々は大杉栄を無鉄砲だと思っている。近藤の見る大杉はそうではない。何をするにも計画は細心にして緻密、ただし、いざ心を決めたら算盤を捨てて立ち上がる。計画と実行の間が人より短いだけだ」・・・・・・。どんな思いで死んでいったのだろう。「これでもう失わなくていいのだ。与り知らぬところでひとの命が奪われ、自分ひとり遺されて生きながらえる恐怖に、二度と怯えなくていい。追い求める理想と、炉辺の幸福の間で板挟みになる必要もない」「あらしの時は去っていった。ここには風すら吹かない。この穴よりもなお深い、安堵」・・・・・・。凄まじい評伝小説。
 このコロナ禍で、食料危機は世界最大級、しかも喫緊の課題であることは、2020年10月、国連WFP(国連世界食糧計画)がノーベル平和賞を受賞したことからも窺える。現在、世界では十分に食料を確保できない人は9億4000万人、なかでも極度の食料不安を抱える人は約2憶7000万人で、コロナ禍以前より急増しているという。アフリカでの食料危機は厳しく、日本でも食品ロスが大きな課題となっているように、「大手コンビニ1店舗で、1日1万円以上の食料を捨てている」現状がある。
このコロナ禍で、食料危機は世界最大級、しかも喫緊の課題であることは、2020年10月、国連WFP(国連世界食糧計画)がノーベル平和賞を受賞したことからも窺える。現在、世界では十分に食料を確保できない人は9億4000万人、なかでも極度の食料不安を抱える人は約2憶7000万人で、コロナ禍以前より急増しているという。アフリカでの食料危機は厳しく、日本でも食品ロスが大きな課題となっているように、「大手コンビニ1店舗で、1日1万円以上の食料を捨てている」現状がある。
その原因は単なる「人口増」などで片づけられるものではない。本書ではまず「分配の不平等」をあげる。貧困(経済力がなければ食料が購入できない)、紛争、自然災害、経済の停滞で食料が入手できないことは、イエメンやコンゴ等でも明らかで、そこからまた暴動・紛争が起きている。次に「搾取主義の食料システムとヒエラルキー(高所得国が低所得国から搾取する構図、強者が独占し弱者に分配されない)」「食品ロス(食べ物の3分の1が捨てられている)」が指摘される。そして生産面や利用面から考えると「気候変動(水不足や高温での旱魃)」「ミツバチやその仲間の減少」「バッタの害」「バイオ燃料・バイオエタノール(バイオマスがカーボンニュートラルであっても可食部まで使われている)」「肉食の増加(牛1キロあたり11~13キロの穀物が必要)」がある。そして「新型コロナが脆弱な国に打撃を与えること」「人口が2050年には97億人まで増加すること」など10の原因をあげている。
その対処方法は、それらの原因を減少させることに尽きる訳だが、「食品ロス削減(賞味期限を延ばす技術革新、30・10運動、食べ残しへのペナルティ)」「食料安全保障の『利用可能性』」「消費者啓発」「昆虫食」「省資源化の取り組み、培養肉の開発」「食のシェア(フードバンク、家庭で余った食べ物を必要な人に渡すフードドライブ、おてらおやつクラブ)」「生ごみの資源化(リサイクル)」等、きわめて生活の身近なことまでの具体例をあげる。そして最後に「食への危機感も敬意も足りない日本人」「貧困、飢餓を1、2とするSDGsについて日本は周回遅れだ」と厳しく指摘、意識改革を促し、「私たちができる100のこと(アクション100)」を例示する。
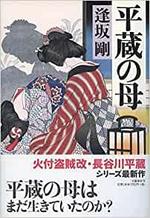 「本所のテツサブロウに、会わせておくれ」――。心臓発作で倒れた老女がそればかり言う。銕三郎はたしかに長谷川平蔵の幼名。与力筆頭・柳井誠一郎、同心・俵井小源太。手先を務める「清澄楼」の仲居・美於らが動くが、平蔵はそれが母親になりすました盗賊仲間による復讐劇であることを見破る。一網打尽。この「平蔵の母」を含む6つの短篇集。
「本所のテツサブロウに、会わせておくれ」――。心臓発作で倒れた老女がそればかり言う。銕三郎はたしかに長谷川平蔵の幼名。与力筆頭・柳井誠一郎、同心・俵井小源太。手先を務める「清澄楼」の仲居・美於らが動くが、平蔵はそれが母親になりすました盗賊仲間による復讐劇であることを見破る。一網打尽。この「平蔵の母」を含む6つの短篇集。
「せせりの辨介」――。神楽坂の古物商「壺天楽」の主人は、かつて盗っ人の「ばってらの徳三」。その店を、色褪せた風呂敷を抱えた30前後に見える小柄な女がたずねる。その中には黒い薬師如来の立像があり、脚の部分をえぐった奥の空洞から30両もの小判が姿を現わした。裏の裏、そのまた裏をかく辮介と平蔵の戦いが始まる。
「旧恩」――。寒風が吹き荒れる日、大店のあるじとぶつかった女が、何かをすり取った。その女はすれ違った若手の同心・今永仁兵衛の顔をまじまじと見つめる。仁兵衛の手先で浅草の「矢場一」で働く可久が追うと・・・・・・。なかなかのしゃれたいい話。
「陰徳」――。浅草田原町の料理屋「鈴善」のご新造・あやのが、渡し船に乗ろうと急ぐ井原進十郎を呼び止める。その船は沈没して皆死亡し、乗りそこねた進十郎は命拾いするが・・・・・・。その裏には陰徳陽報と因果があったことを平蔵が見抜く。善意だけでない人間心理の奥の奥がのぞかれる。「深川油堀」――。恵覚寺の貞道和尚にはめられた潜竜と、賭場で知り合った「梵天の善三」による仕返し。それに可久がからむ。「かわほりお仙」――。盗っ人稼業をしていた歌吉と仙は、今は堅気。歌吉は長谷川組の手先だ。"のすりの三次"に滝野川村の正受院の山門に来いと仙は呼び出される。石神井川沿いの茂み裏側の崖に小さな洞穴。そこで仙と歌吉は三次を倒すが・・・・・・。
人間の業と悲哀、怨念と人情、事件の裏と仕掛け・・・・・・。逢坂「平蔵」の世界が滲み出る。
 「コロナ危機におけるリーダーシップと民意」「英のEU離脱、トランプ現象と格差」「ポピュリズムと政治」「SNS、デジタル社会と政治」等々、「民主主義」の問われる課題は常に重い。本書は世界における民主主義の思想と歴史を再検討する。「民主主義とは『参加と責任のシステム』である」との軸で、民主主義を巡る諸問題とその解決の方向性を示す。当然、民主主義を巡ってのギリシャ以来の論調を凝縮して解説し、自由・平等・議会・政党・議院内閣制など、全方位から、また時間軸から論述する。前著「未来をはじめる」とともに、膨大な人類の思考・営為をきわめて明確、わかりやすく語る。大変面白く有意義、納得の著書だ。
「コロナ危機におけるリーダーシップと民意」「英のEU離脱、トランプ現象と格差」「ポピュリズムと政治」「SNS、デジタル社会と政治」等々、「民主主義」の問われる課題は常に重い。本書は世界における民主主義の思想と歴史を再検討する。「民主主義とは『参加と責任のシステム』である」との軸で、民主主義を巡る諸問題とその解決の方向性を示す。当然、民主主義を巡ってのギリシャ以来の論調を凝縮して解説し、自由・平等・議会・政党・議院内閣制など、全方位から、また時間軸から論述する。前著「未来をはじめる」とともに、膨大な人類の思考・営為をきわめて明確、わかりやすく語る。大変面白く有意義、納得の著書だ。
今日の民主主義の危機として「ポピュリズムの台頭」「独裁的指導者の増加」「第四次産業革命とも呼ばれる技術革新」「コロナ危機」の4つを提起する。そして「参加と責任のシステム」である民主主義を、今後も"試行錯誤"を続け、具体的な制度化を充実させていく必要を説く。ダールの「民主主義という理想と、現実とのギャップを直視する」「政治的平等、有効な参加、知識や情報の普及」「決定すべき事項の選択権、そして包括性の民主主義の基準」や、ロールズの「人々が自らの道徳的判断と突き合わせ、繰り返し検証していくこと」「人々が正義感覚、すなわち、他者に配慮して行為することへの感覚・能力を涵養していくこと」などを紹介する。自由・平等・民主との緊張感、参加と責任への意志、動体視力を共にすることの重要性だ。
歴史上で繰り広げられた民主主義への思想闘争の紹介は柔らかで痛快だ。民主主義を否定的に把えることがギリシャ以来、多かった。「プラトンは師であるソクラテスが民衆裁判にかけられ刑死する。『ソクラテスの弁明』に詳細があるように、多数者の決定に疑問をもつ。行き着いたのが、『哲人王』の構想だ」「アリストテレスは、堕落形態を論ずる。僭主政、寡頭政、衆愚政だ」「古代ローマの共和政は、民主主義が"多数の横暴""貧しい人々の欲望の追求"と否定的意味合いであったものを"公共の利益の支配"として始めた」「マグナカルタ(1215年)で貴族たちは自らの自由と権利を王に承認させ、王権に制限をかけた。これがイングランドの政治制度が発展する礎になった」「ホッブスは『リヴァイアサン』(1651年)を著し、個人の自由と安全を守るためには、無秩序を克服する強力な国家(リヴァイアサン)が必要だとした」「ロックは『統治二論』(1689年)で、リヴァイアサンを打ち立てる一方で、それを制約し、枠付ける議会の力もイングランドに確立しようとした」「1776年、北米の13植民地が独立を宣言、1787年の合衆国憲法は国家連合ではなく連邦国家としてアメリカ合衆国を打ち立てようとした"妥協の産物"」「単一不可分の共和国を掲げるルソーと、分権的な社会と地方自治を理想とするトクヴィルとは180度違うが、市民の主体的参加とそれに基づく当事者意識を重視する点で、同じ民主主義論の系譜に立つ」「ルソーは私的所有権制度こそが、貧富の不平等拡大の原因だと考え、相互に自由で平等な個人による社会契約によって国家を打ち立てることを主張した」「近代の民主主義は議会制を中心に発展、議論の焦点は、議会をいかに民主的にするかに向かった。そこに政党が生まれる。バークは政党とは単なる党派ではなく、政治的意見を同じくする政治家が政権の獲得を目指して結集したものと主張した」「ルソーの人民主権論に対し、コンスタンはあくまで個人の自由が大切だとした。政治参加に魅力があるより、自由とは何よりも自分の私的な生活を平穏に享受できること。民主主義と自由主義は矛盾、緊張関係にあるとした」「トクヴィルは青年貴族であったが、アメリカを訪問し、名もなき一般の人々の政治的見識の高さに感銘を受けた。ヒントは自治や結社の活動だった。生き方、考え方、生活様式としてのデモクラシーだ」「トクヴィルによって再び積極的な意味に転じた民主主義だが、これをより本格的な代議制民主主義の理論として構築したのは盟友・ミルだった(「アメリカのデモクラシー<1835年>」の書評をミルが執筆した)」「ミルは自由論に続いて1861年に代議制統治論を刊行、代議制民主主義こそが最善の政治体制だと指摘した」「20世紀に入り、ウェーバーは有能なビスマルクの負の政治的遺産を見て『完全に無力な議会』『政治教育のひとかけらも受けていない国民』を目の当たりにし、執行権が統治の中心機能だと看取し、大統領制に期待した」。そして「政治は結果責任、責任倫理を指摘した」・・・・・・。そして、ダールの「多元主義」、アーレントの「政治とは単なる利害調整ではなく、相互に異なる多様な諸個人が言葉を交わすことによって、自由で公共的な空間を創出することにある」というメッセージ、ロールズの「正義論」、日本の吉野作造の「民主主義」、丸山眞男等の"戦後民主主義"に論及する。
民主主義は時代とともに、風雪を経て、未来も試行錯誤しつつ発展していくし、させていかなければならない。「参加と責任のシステム」と宇野さんはいう。納得する。「参加」のシステムは当然だが、「責任」についてこそ古代ギリシャ以来の人類の思考と試行があったことを本書からひしひしと感じた。アリストテレスの「衆愚政への懸念」、プラトンの「多数者の決定への疑問と哲人王」、公共の利益を考える「ローマ共和制」、ルソーの「一般意志」、トクヴィルがアメリカで見た「自治や結社の活動」、ダールの「多元主義」、ロールズの「正義論」等々は、参加する人々の「責任」の中身、社会全体の質的中身を問うことなしに民主主義を語れないということではないか。「政治は結果責任」を主張したウェーバーは、ナチス後であればどう発言したであろうか。そして「無力な議会」「政治家の劣化」「ポピュリズム」の今であれば、どう発言したであろうか。

