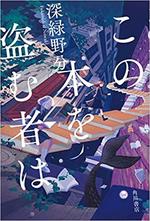 本好きや本の蒐集家が集まる"本の町"の読長町。その書店街の核心となるのが御倉館。書物の蒐集家で街の名士であった御倉嘉市を曾祖父に持つ高校生の御倉深冬が主人公。嘉市の娘・御倉たまきも優れた蒐集家であったが、所蔵の書約200冊が書架から消え去る"事件"に激昂し、館を閉館し、一族以外は誰ひとり立ち入りも、本の貸し出しもできなくなった。たまきが息を引き取った後、「愛する本を守ろうとして、読長町と縁の深い狐神に頼んで、25万9122冊という膨大な書物一つひとつに"魔術"をかけた」という噂が流れた。たまきの子である御倉あゆむ(深冬の父)と叔母ひるねが現在の御倉館を管理している。そんなある日、御倉館から蔵書が盗まれる。御倉館にとっては大事件。しかも館内にいてほとんど眠り続けるひるねの手に「この本を盗む者は、魔術的現実主義の旗に追われる」と書かれた紙を発見する。御札とも護符ともいえるものだ。魔術的現実主義のブック・カース。物語を盗んだ者は、物語の檻に閉じ込められる。魔術的現実主義の世界に、泥棒が閉じ込められるという呪いは、街自体を一変させてしまう。
本好きや本の蒐集家が集まる"本の町"の読長町。その書店街の核心となるのが御倉館。書物の蒐集家で街の名士であった御倉嘉市を曾祖父に持つ高校生の御倉深冬が主人公。嘉市の娘・御倉たまきも優れた蒐集家であったが、所蔵の書約200冊が書架から消え去る"事件"に激昂し、館を閉館し、一族以外は誰ひとり立ち入りも、本の貸し出しもできなくなった。たまきが息を引き取った後、「愛する本を守ろうとして、読長町と縁の深い狐神に頼んで、25万9122冊という膨大な書物一つひとつに"魔術"をかけた」という噂が流れた。たまきの子である御倉あゆむ(深冬の父)と叔母ひるねが現在の御倉館を管理している。そんなある日、御倉館から蔵書が盗まれる。御倉館にとっては大事件。しかも館内にいてほとんど眠り続けるひるねの手に「この本を盗む者は、魔術的現実主義の旗に追われる」と書かれた紙を発見する。御札とも護符ともいえるものだ。魔術的現実主義のブック・カース。物語を盗んだ者は、物語の檻に閉じ込められる。魔術的現実主義の世界に、泥棒が閉じ込められるという呪いは、街自体を一変させてしまう。
次々に蔵書が盗まれる。その都度、街は一変し、人ひとりいないという場面まで生ずる。「この本を盗む者は、固ゆで玉子に閉じ込められる」(固ゆで玉子のハードボイルドの街に)、「この本を盗む者は・・・・・・幻想と蒸気の靄(もや)に包まれる」(巨大ゲートを構えた工場街、銀の獣の世界)、「この本を盗む者は、寂しい街に取り残される」(人が忽然と姿を消す『人ぎらいの街』)。まさに驚天動地、本の世界が街を一変させて深冬に迫ってくるのだ。
深冬を助ける不思議な少女・真白とともに、"本嫌い"であった深冬は、祖母の"呪い"の真実、本が好きだった頃のことにたどり着く。
 女子高時代に少女バンドを組んでメジャーデビューをした三人の女性。厳しい校則の学校で放校処分になるが、短くとも輝いた時代を忘れられない。それから約20年――。イラストレーターの井出ちづるは、夫は若い女性と浮気をし、夜遅くまで帰ってこない。放っておかれて、「ほとんど一人暮らし」の状態。しかし、「嫉妬を感じない、そのことにちづるは戸惑っている」のだ。帰国子女で独身の草部伊都子は、著名な翻訳家で"ヤリ手"で美人、輝く母・芙巳子をもつ。母との確執、愛憎のアンビバレントのなかで、各地で撮った写真集を出そうとするが、なかなかうまくいかない。早々と結婚して母となった岡野麻友美。自分のできなかったことを娘のルナに託そうとタレントをめざそうとしても、娘の性格、志向は違うようで思うようにいかない。
女子高時代に少女バンドを組んでメジャーデビューをした三人の女性。厳しい校則の学校で放校処分になるが、短くとも輝いた時代を忘れられない。それから約20年――。イラストレーターの井出ちづるは、夫は若い女性と浮気をし、夜遅くまで帰ってこない。放っておかれて、「ほとんど一人暮らし」の状態。しかし、「嫉妬を感じない、そのことにちづるは戸惑っている」のだ。帰国子女で独身の草部伊都子は、著名な翻訳家で"ヤリ手"で美人、輝く母・芙巳子をもつ。母との確執、愛憎のアンビバレントのなかで、各地で撮った写真集を出そうとするが、なかなかうまくいかない。早々と結婚して母となった岡野麻友美。自分のできなかったことを娘のルナに託そうとタレントをめざそうとしても、娘の性格、志向は違うようで思うようにいかない。
三人とも「日々の雑事に追われるだけで時間がどんどんたっていく」「ふりかえっても自分の足跡が見つけられないように思う」「40歳になるまで、充実感や達成感というか、そういう心底実感できることがないかしら」「何がしたいか。自分は何がしたいのか」「浮き輪にのって漂っているような気がする」と思い、漠たる不安のなかで悩むのだ。そして、ふと現れた男性に心を奪われたり、感情が爆発して顰蹙を買ったりしてしまうのだ。そこには間違いなく"執着"があるのだろう。あの高校時代の"満足感"への執着、娘への執着、浮気する夫を見返したいと思う執着、愛憎を乗り越えたいと常に母親に敵対心をもつ執着・・・・・・。それは"業"というべきものだろう。そして伊都子にとって倒そうとしても倒れない、不死身のような母・芙巳子が末期癌を宣告される・・・・・・。何よりも強いつながりを持つ三人は結集して、驚くべき行動に出る。死直前の母に海を見せようとするのだ。
最後に大きなテーマとして出てくるのが海・・・・・・。「あなたはひとりでも大丈夫だから」と芙巳子は言っていた。「自分としてやり切ることはやり切る」という命からの決断を生老病死の砌で三人は実行・体験するのだ。「自己自身に生きよ」「海よりも空よりも広い宇宙に抱かれた生命を止観する」ことに通ずるのだろう。角田さんがこの小説を書いたのは直木賞受賞の頃で、14年間埋もれていたのを今回出版したのだという。ぜひ、この三人が50歳の今、どう人生に向きあってきたかを書いてほしいと思う。
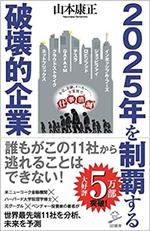 「2025年はどうなっているか?」「5年後の未来はこの11社が決定づける」「5年後に破壊される企業、台頭する企業」「5年後、あなたの仕事はこう変わる」――。5年後というのはすぐだ。もう11社の驀進、加速は止まることはない。「会議でもホロレンズでバーチャル場面が投影され、AIが翻訳する」「通勤は電車の200%コスパのいい"ロボタクシー"」「ウーバーは瞬く間にロボタクシーに市場を奪われる」「出張先はアップルホテル、割引率の高いアップルカード」「AI先生、小学2年生に九九を教える。リモート授業でもホロレンズが活躍」「調理はアマゾンのロボット・アレクサクッキングシェフご用達の大豆肉のステーキ」「映画、ドラマでも視聴者100万人なら100万通り」・・・・・・。
「2025年はどうなっているか?」「5年後の未来はこの11社が決定づける」「5年後に破壊される企業、台頭する企業」「5年後、あなたの仕事はこう変わる」――。5年後というのはすぐだ。もう11社の驀進、加速は止まることはない。「会議でもホロレンズでバーチャル場面が投影され、AIが翻訳する」「通勤は電車の200%コスパのいい"ロボタクシー"」「ウーバーは瞬く間にロボタクシーに市場を奪われる」「出張先はアップルホテル、割引率の高いアップルカード」「AI先生、小学2年生に九九を教える。リモート授業でもホロレンズが活躍」「調理はアマゾンのロボット・アレクサクッキングシェフご用達の大豆肉のステーキ」「映画、ドラマでも視聴者100万人なら100万通り」・・・・・・。
11社とは グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト、ネットフリックス、テスラ、クラウドストライク、ロビンフッド、インポッシブル・フーズ、ショッピファイの世界最先端企業。これら企業は、「検索後の世界から『検索前』の世界へ(グーグル)」「アレクサ君、屋外に進出。ついに街全体を食いに来る(アマゾン)」「2万km離れた人と目の前で会話ができる世界へ(フェイスブック)」「視覚、聴覚、嗅覚、五感すべてを占拠(アップル)」「2億人以上の嗜好に合わせた映像を届ける(ネットフリックス)」「スマートシティのOSの覇者になる(マイクロソフト)」「テスラのイーロン・マスクはリニアで結ぶハイパーループ構想」「ベジタリアンだって肉の食感(インポッシブル・フーズ)」「"売買手数料0"の投資が当たり前の世界をつくる(ロビンフッド)」「全企業が在宅勤務社会のトリガー(クラウドストライク)」「企業のECサイト開発・運営の10兆円ベンチャー(ショッピファイ)」――。いずれも「業種の壁を崩壊」させ、買収・吸収・戦線拡大でコングロマリット化を図る。それがメガトレンドの①。「②はハードでもソフトでもなく、体験が軸となる」「③はデータを制するものが未来を制す」だ。その大波は 全ての業種、カード・金融、運輸、映像、農業、セキュリティ、モビリティ(自動運転、ロボタクシー)、建設、医療・ヘルスケア、物流など全分野に襲いかかる。
激動・激震の世界の様子を山本康正さんが現場から緊迫感をもって語る。
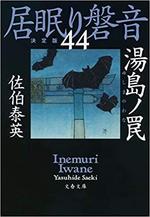 直心影流尚武館坂崎道場は改築の最中。坂崎磐音は木挽町にあった江戸起倒流の鈴木清兵衛を打ち破る。「坂崎磐音、予は迂闊にも江戸起倒流の背後に老中・田中意次、意知父子があることを知らなんだ」と、訪ねてきた白河藩主・松平定信がいい、竹刀を交える。定信は田沼意次の政治手法を「賄賂政治」と批判し、意次によって白河藩へと遠ざけられていた。読売屋の和蔵が来て、「佐野善左衛門政言が、田沼父子を告発する闇読売をばら撒こうとしている」という。佐野の暴発を心配した磐音は、毒矢から回復した忍びの霧子と密偵の弥助を岩槻宿に向かわせる。幕政中枢の老中・若年寄の田沼父子に対し、徳川家基、佐々木玲圓、おえいの仇を己の手で決したいと思っている磐音。そんな時、佐々木道場からの住み込みの門弟・松平辰平が失踪する。「こたびの一件はいよいよ田沼父子がなりふりかまわず牙を剥き出しにした結果と思える。倅の田沼意知様を己の跡継ぎにするために、尚武館を消滅させる決意をしたのだ」と、南町奉行所の笹塚孫一、木下一郎太が語る。磐音らが辰平の救出に動く。後に「瓦版」という名称になる「読売」(江戸のゴシップ誌)が、あたかも現代のように江戸の権力攻防に影響を与える。
直心影流尚武館坂崎道場は改築の最中。坂崎磐音は木挽町にあった江戸起倒流の鈴木清兵衛を打ち破る。「坂崎磐音、予は迂闊にも江戸起倒流の背後に老中・田中意次、意知父子があることを知らなんだ」と、訪ねてきた白河藩主・松平定信がいい、竹刀を交える。定信は田沼意次の政治手法を「賄賂政治」と批判し、意次によって白河藩へと遠ざけられていた。読売屋の和蔵が来て、「佐野善左衛門政言が、田沼父子を告発する闇読売をばら撒こうとしている」という。佐野の暴発を心配した磐音は、毒矢から回復した忍びの霧子と密偵の弥助を岩槻宿に向かわせる。幕政中枢の老中・若年寄の田沼父子に対し、徳川家基、佐々木玲圓、おえいの仇を己の手で決したいと思っている磐音。そんな時、佐々木道場からの住み込みの門弟・松平辰平が失踪する。「こたびの一件はいよいよ田沼父子がなりふりかまわず牙を剥き出しにした結果と思える。倅の田沼意知様を己の跡継ぎにするために、尚武館を消滅させる決意をしたのだ」と、南町奉行所の笹塚孫一、木下一郎太が語る。磐音らが辰平の救出に動く。後に「瓦版」という名称になる「読売」(江戸のゴシップ誌)が、あたかも現代のように江戸の権力攻防に影響を与える。
 乃公出でずんば蒼生を如何せん――俺がやらねば誰がやるとの心意気で、明治・日本に資本主義革命を起こし、その近代化を一気に加速させた渋沢栄一。2024年からの新一万円札の肖像が決まり、2月からNHK大河ドラマ「青天を衝け」が始まる。私の地元・北区の飛鳥山に長く住み、そこで没した。1840年(天保11年)に生まれ、1931年(昭和6年)までの91歳の生涯であった。北康利さんが書いてくれることを待ち望んでいたが、渋沢の生きざまや思考、「論語と算盤」の信念に肉薄した期待どおりの素晴らしい作品。とくに、日本では西郷や大久保、伊藤、板垣等々の政治分野の国づくりが主流で語られるが、渋沢もたんなる「経済人」というのではなく、大蔵省や日銀や殖産産業、企業システムなど、まさに国づくりの骨格を築き上げた人物であったということが鮮明になる。
乃公出でずんば蒼生を如何せん――俺がやらねば誰がやるとの心意気で、明治・日本に資本主義革命を起こし、その近代化を一気に加速させた渋沢栄一。2024年からの新一万円札の肖像が決まり、2月からNHK大河ドラマ「青天を衝け」が始まる。私の地元・北区の飛鳥山に長く住み、そこで没した。1840年(天保11年)に生まれ、1931年(昭和6年)までの91歳の生涯であった。北康利さんが書いてくれることを待ち望んでいたが、渋沢の生きざまや思考、「論語と算盤」の信念に肉薄した期待どおりの素晴らしい作品。とくに、日本では西郷や大久保、伊藤、板垣等々の政治分野の国づくりが主流で語られるが、渋沢もたんなる「経済人」というのではなく、大蔵省や日銀や殖産産業、企業システムなど、まさに国づくりの骨格を築き上げた人物であったということが鮮明になる。
「論語と算盤」とは何であったのか――。商売は儒学では"金儲けの下賤な策"としてきた江戸以来のメンタリティーを渋沢は変えようとした。「魂を入れなければ資本主義は金儲けの道具になり、まさに下賤な業に堕ちてしまう」と考え、その最高の経典である「論語」を使って反転させ、公益につながるものであることの信念を貫き通した。「士魂商才」「道徳経済合一説」「社会的責任を忘れないリーダーの高い志」を唱え続けた。水戸学のプラグマティズム、朱子学批判。伊藤仁斎・会沢正志斎からのプラグマティズムとナショナリズムを継承しつつ、経済学的にも市場の"見えざる手"ではなく、「国家のため」「社会のため」といった公共精神、ナショナリズムが渋沢の思想と行動に現われる。経営の社会的責任について、P・F・ドラッカーは「彼(渋沢)は世界のだれよりも早く、経営の本質は『責任』にほかならないことを見抜いていたのである」と激賞したという。それが、岩崎弥太郎など同時代財界人との対立の根っ子にあることや並走した井上馨との距離感が鮮やかに浮き彫りにされる。政府にすりよって利益を得る政商の道を決して歩まず、社会・福祉事業にも力を入れ、戦争に反対し、財政規律を無視した国家経営にも異を唱え、行動した。
「人並み外れた行動の人」「強情っぱり」「強い意志と情をあわせもった人」であり、「常識や国境にとらわれないスケールの大きい人」であり、「誰の話も聞いて、即行動する"お節介"の人」であった渋沢の姿が活写される。大倉喜八郎、安田善次郎、古河市兵衛、浅野統一郎、佐々木勇之助、大川平三郎、中上川彦次郎、娘婿の穂積陳重や阪谷芳郎・・・・・・。明治から大正、昭和初期に至る間のあらゆる政治家、経済人との深い交わりと思想と行動。その結果の結実が驚嘆するほど見えてくる。

