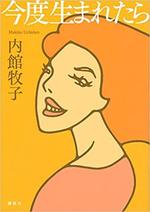 「終わった人」「すぐ死ぬんだから」に続き、"人生100年"「長寿社会」であるがゆえに考えさせる本。「人生をやり直したい」「あの時、あっちの道を選んでいれば・・・・・・」というのは、人によって悔恨もあれば、ごく普通に感情を伴うことなく思うこともあろう。自分自身にとってみると「回り道は真っすぐ道」だったということだ。誰しもターニングポイントは何回かある。いい時も悪い時も人生には4回位あるというが、迷った時は積極策をとる。悔いのない方を選ぶことだろう。「我慢して人生を無駄にしちゃダメ。・・・・・・他人に気を遣って生き続けて、何が楽しい」「昭和40年代は野蛮な時代だった(結婚して当然。オールドミスなどという言葉が平然と社会で通った)」「時代の風潮に合わせすぎるな。それらはすぐに変わっていく」「人間は死ぬ日まで、何が起きるかわからない。とにかく楽しんで生きるためには、自分から動く。何かを始める」「自分に与えられた人生を元気に、弾んで歩いて行く。佐保子にとっても私にとっても"今度生まれたら"より今なのだ」と本書にある通りだ。「私自身が『年を召した方』になってみると、口当たりがよく『人間に年齢は関係ない』とは言い難い。ただし、たとえ70を過ぎても、一生の一部分を、また生活の一部分を、やり直すことはできる」という。老境に入って、体も頭も若いが、仕事はない、社会も必要としてくれない、結局趣味に生きるしかないのか・・・・・・。「俺の人生、私の人生とは何だったのか」は「今度生まれたら」と同じ位相にある。
「終わった人」「すぐ死ぬんだから」に続き、"人生100年"「長寿社会」であるがゆえに考えさせる本。「人生をやり直したい」「あの時、あっちの道を選んでいれば・・・・・・」というのは、人によって悔恨もあれば、ごく普通に感情を伴うことなく思うこともあろう。自分自身にとってみると「回り道は真っすぐ道」だったということだ。誰しもターニングポイントは何回かある。いい時も悪い時も人生には4回位あるというが、迷った時は積極策をとる。悔いのない方を選ぶことだろう。「我慢して人生を無駄にしちゃダメ。・・・・・・他人に気を遣って生き続けて、何が楽しい」「昭和40年代は野蛮な時代だった(結婚して当然。オールドミスなどという言葉が平然と社会で通った)」「時代の風潮に合わせすぎるな。それらはすぐに変わっていく」「人間は死ぬ日まで、何が起きるかわからない。とにかく楽しんで生きるためには、自分から動く。何かを始める」「自分に与えられた人生を元気に、弾んで歩いて行く。佐保子にとっても私にとっても"今度生まれたら"より今なのだ」と本書にある通りだ。「私自身が『年を召した方』になってみると、口当たりがよく『人間に年齢は関係ない』とは言い難い。ただし、たとえ70を過ぎても、一生の一部分を、また生活の一部分を、やり直すことはできる」という。老境に入って、体も頭も若いが、仕事はない、社会も必要としてくれない、結局趣味に生きるしかないのか・・・・・・。「俺の人生、私の人生とは何だったのか」は「今度生まれたら」と同じ位相にある。
主人公は70歳になった佐川夏江。老境の夫婦、そして息子たちの家庭と人生、姉夫婦やかつて職場の同僚であった人の人生を描く。70代以降の人生をどうするか、長寿社会ゆえの大変な問題を、軽妙にテンポよく、ズバっと描く。さすが内館牧子さんとうなってしまうほどだ。
 明治維新とは何だったのか。「絶対主義の確立」とか「ブルジョワ革命」などと捉える論調もあったが、「マルクス主義のカテゴリーにあてはまらない民族革命であり、西洋の脅威に直面した日本が、近代化を遂げなければ独立を維持できないと考えて行った革命であった」(吉野作造の継承者・岡義武)を引きつつ、北岡さんは「要するに維新から内閣制度の創設、憲法の制定、議会の開設に至る変革は、既得権益を持つ特権層を打破し、様々な制約を取り除いた民主化革命。自由化革命であり、人材登用革命であった」という。さらに「明治維新のキーワードは公議輿論だった。江戸時代に発言できなかった者が発言し、‥‥‥私的な利益は度外視して国益だけを考えて、ベストの議論を取る。それが大久保の言う公議輿論だった」「明治維新以来の政治で最も驚くべきことは、日本が直面した最重要課題に政治が取り組み、ベストの人材を起用して、驚くべきスピードで決定と実行を進めていることである」という。政治が「制度化」され、リーダーが「セクショナル・インタレスト」に陥り、政治のダイナミズムを失っているとの現代政治への眼は鋭く、本質を剔る。そこに「明治維新の意味を問う」という"意味"があると思う。
明治維新とは何だったのか。「絶対主義の確立」とか「ブルジョワ革命」などと捉える論調もあったが、「マルクス主義のカテゴリーにあてはまらない民族革命であり、西洋の脅威に直面した日本が、近代化を遂げなければ独立を維持できないと考えて行った革命であった」(吉野作造の継承者・岡義武)を引きつつ、北岡さんは「要するに維新から内閣制度の創設、憲法の制定、議会の開設に至る変革は、既得権益を持つ特権層を打破し、様々な制約を取り除いた民主化革命。自由化革命であり、人材登用革命であった」という。さらに「明治維新のキーワードは公議輿論だった。江戸時代に発言できなかった者が発言し、‥‥‥私的な利益は度外視して国益だけを考えて、ベストの議論を取る。それが大久保の言う公議輿論だった」「明治維新以来の政治で最も驚くべきことは、日本が直面した最重要課題に政治が取り組み、ベストの人材を起用して、驚くべきスピードで決定と実行を進めていることである」という。政治が「制度化」され、リーダーが「セクショナル・インタレスト」に陥り、政治のダイナミズムを失っているとの現代政治への眼は鋭く、本質を剔る。そこに「明治維新の意味を問う」という"意味"があると思う。
ペリー来航、阿部正弘の開明官僚の抜擢、桜田門外の変と公武合体路線、大政奉還、公議政体と王政復古、五箇条の御誓文、版籍奉還、廃藩置県‥‥‥。「明治4年に断行された廃藩置県こそは、維新革命の性格を決定づけ、またその後の方向を決める最も重要な決定であった」「島津久光は激怒する。西郷の引き出しと久光の説得は難題だった。(大久保は)この問題のために、実に渾身の努力をしていたのである」と大久保の志をもった戦いを讃える。公議輿論、明治の精神だ。
大村益次郎の抜擢と徴兵制度、地租改正、電信・電話・鉄道や教育の整備、岩倉使節団、そして征韓論‥‥‥。「自分を慕う仲間を裏切ることなく、しかし同志である大久保の国家建設を妨害することもなく、戦士の同胞の思い出のなかに死んでいくことが、西郷の希望であったと私は考える。これは政治的人間である大久保と、非政治的・宗教的人間である西郷の決定的に違うところであった」という。征韓論から西南戦争に至る難局。大久保は「行詰りとなったならば、万難を排して踏破するなり、または迂回するなり、臨機に適当な手段を用いなければならぬ。其処で静定の工夫を回らしたならば、必ず何処にか活路が見出されるものである‥‥‥」と語ったという。そして大久保の死、自由民権運動と明治14年政変、朝鮮問題と条約改正、明治憲法の制定、官僚制度の整備、天皇大権の強大、超然演説と議会政治の定着、元老から政党へ、政治の制度化と合理化‥‥‥。
「明治維新を再検討してみて、もっとも印象的なのは‥‥‥日本が直面した最も重要な課題に、最も優れた才能が全力で取り組んでいたということである。‥‥‥その国が直面する最も重大な課題に、最も優れた才能が全力で取り組んでいるかどうかが、決定的に重要だと痛感している」と結び、現代政治への警告を発している。
 「コロナと潜水服」をはじめとする5つの短篇集。いずれも不思議なことが起きるが、ファンタジック。人間の深層心理をきわめて柔らかく、すっきりと描く。人生が肯定的、時々シニカルで塩をきかせるようで、心持よい。
「コロナと潜水服」をはじめとする5つの短篇集。いずれも不思議なことが起きるが、ファンタジック。人間の深層心理をきわめて柔らかく、すっきりと描く。人生が肯定的、時々シニカルで塩をきかせるようで、心持よい。
「海の家」――妻の不倫にショックを受けた小説家が、葉山の古民家に一人で住む。誰もいないはずの家だが、子供の足音が聞こえる。海岸で不良たちに暴行されるが、助けに来た子供が・・・・・・。夫の優柔不断、妻の甘え上手、したたかさとズルさ。
「ファイトクラブ」――早期退職の勧告に抵抗し、"追い出し部屋"的な警備員の仕事につかされた中年の男たち。仕事が終わった後、ボクシングを始めると、コーチが現われ、面白くなってのめり込む。そして事件が起きる。
「占い師」――プロ野球選手と付き合うフリー女性アナウンサー。好調でブレイクすればうれしいが、モテモテで自分から離れそう。悩んで"占い師"に相談する。「鏡子」と名乗る"占い師"は、自分を映す"鏡"だったのか。
「コロナと潜水服」――5歳になる息子はどうも不思議な能力を持っているらしい。「バアバ、今日はお出かけしちゃダメ」「パパ、そこに座っちゃダメ」などと突然言うと、コロナ感染者が出る。パパは防護のためになんと"潜水服"を着る。
「パンダに乗って」――会社を興して20年、社長として頑張ってきた自分へのご褒美として念願の初代フィアット・パンダを新潟で手に入れた男。パンダに乗ると、次々に元の持ち主の友人たちの所に車が案内し連れていくのだった。
「海の家」の子供、「ファイトクラブ」のコーチ、「占い師」の鏡子、「コロナと潜水服」の5歳の息子、「パンダに乗って」のパンダの元持ち主・・・・・・。いずれもあり得ないものだが、どこか100%ないかといえば「?」・・・・・・。心を映す"鏡"かも知れぬ。
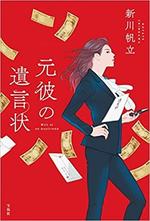 2021年「このミステリーがすごい!」大賞受賞作。主人公は、おカネ大好きの敏腕の若手弁護士・剣持麗子。「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という前代未聞の遺言状を残して、大手製薬会社・森川製薬の御曹司・森川栄治が死去する。栄治はわずか3か月だけだが、麗子の元カレだった。
2021年「このミステリーがすごい!」大賞受賞作。主人公は、おカネ大好きの敏腕の若手弁護士・剣持麗子。「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という前代未聞の遺言状を残して、大手製薬会社・森川製薬の御曹司・森川栄治が死去する。栄治はわずか3か月だけだが、麗子の元カレだった。
数百億円とも思われる遺産目当てに何人もが"犯人"として手を上げる。そして名乗り出た栄治の友人・篠田から麗子は代理人を頼まれる。栄治は重度のうつ病で体力も低下、インフルエンザで死んだというが、本当はどうなのか。森川家でいったい何が起きているのか。「完璧な殺害計画をたてよう。あなたを犯人にしてあげる」と麗子は意気込み、軽井沢の現場に乗り込んでいく。奇想天外の展開、キャラの立つ女性弁護士はじつに面白い。著者自身が若き弁護士であればこその魅力あふれる作品。
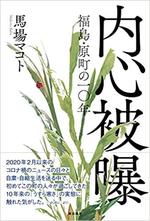 東日本大震災から10年になる。福島原発事故で放射能に怯え続けた相双地域。南相馬市は、原発の20km内の小高区、30km内の原町区、その外の鹿島区に分かれ、「警戒区域」「緊急時避難準備区域」「非避難区域」として3区域別々の原発被害対策をとらざるを得ず、退避も補償も別々となった。それぞれの地域住民の不安・戸惑い・不満は想像を絶するものがある。本書の副題は「福島・原町の10年」――。この間、原町区の人々はどう生きたか、4つの家族を取り上げたドキュメント。「懸命に生きる」「一所懸命に生きる」「皆で力を合わせて共に生きる」姿には感動する。それに比して「政府とか東電とかのいかにも遠い」こと。この10年も今も放射能に怯え続けた苦悩が胸に迫る。「コロナ禍の東日本大震災から10年」は、その心からまず考えるべきだと思う。
東日本大震災から10年になる。福島原発事故で放射能に怯え続けた相双地域。南相馬市は、原発の20km内の小高区、30km内の原町区、その外の鹿島区に分かれ、「警戒区域」「緊急時避難準備区域」「非避難区域」として3区域別々の原発被害対策をとらざるを得ず、退避も補償も別々となった。それぞれの地域住民の不安・戸惑い・不満は想像を絶するものがある。本書の副題は「福島・原町の10年」――。この間、原町区の人々はどう生きたか、4つの家族を取り上げたドキュメント。「懸命に生きる」「一所懸命に生きる」「皆で力を合わせて共に生きる」姿には感動する。それに比して「政府とか東電とかのいかにも遠い」こと。この10年も今も放射能に怯え続けた苦悩が胸に迫る。「コロナ禍の東日本大震災から10年」は、その心からまず考えるべきだと思う。
第一章「終戦記念日」は、相馬地域の創価学会婦人部のリーダー松本優子さん。「"自主避難""屋内退避"と言われてもどうすればいいのか」「学校の再開もできない現実」「放射能の危険と圧倒的情報不足」などの大混乱のなかでの闘いの実態。「外部被曝と内部被曝という言葉があるが、南相馬の人間はみんな一人ひとりがあの原発事故が深い"内心被曝"を受けたと思う」という。第二章の「未来の扉」では、㈱北洋舎クリーニング社長・高橋美加子さん(中小同友会相双地区会長)の闘いを紹介する。「南相馬からの便り」を発行し、「"ありがとう"から始めよう! つながろう南相馬」の運動、「鎌田實講演会(歌・さだまさし)」「ファシリテーション運動」「世界一のエコシティの建設」など走り回る。第三章「ほめ日記」は卒寿を迎えた羽根田ヨシさん、息子の妻・民子の看護師(鹿島厚生病院)としての"野戦病院"さながらの闘いを描く。原発事故で医療現場は大混乱、高齢者が亡くなっていく姿は深刻。放射能に怯え、ストレスの重なる浜通りで、6年間も住居を転々とし帰還した羽根田ヨシさんの「ほめ日記」は元気を与えた。復興はこうした庶民一人ひとりの "負けまいとする心" あってのことだ。上がやったのではない。
第四章は「新築開店」――。幕末からの魚屋「てつ魚店」を苦難のなか復活させ、最初は新潟からの魚、そして片道7時間の大回りしての小名浜からの魚の仕入れ、2019年に新築開店した「てつ魚店」の奮闘と福島の漁業、再生エネルギーの問題を抉る。

