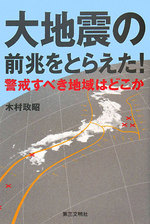事件、それもおかしな事件が多い。「暴走老人」ではないが、皆どうもキレやすい。時代の波にさらされ、さらわれているようだ。
事件、それもおかしな事件が多い。「暴走老人」ではないが、皆どうもキレやすい。時代の波にさらされ、さらわれているようだ。
一方、事件のたびにニュースが拡大して流され、まことしやかな解説がされ、簡単に納得してしまうことも、困ったことだ。
最近の事件・ニュースを「三面記事の奥にあるものを、その心理に分け入り、角田さんがキメ細かく描く。
「不倫相手の妻の殺害を依頼」「介護の母親を殺害」「担任教師の給食に毒物を混ぜる」「妹を殺してしまう姉」――何年にもわたる心理描写が、追い詰められていく様子が、角田さんの手でキメ細かく描かれる。悲しく、寂しく、いたたまれない。しかも現実を想起させるだけに、胸がしめつけられる。
 これは自伝。秘書官の上塚司が記録したもの。明治44年(1911年)に日本銀行総裁に57歳で就任、大蔵大臣に59歳。内閣総理大臣に2度、それも大正10年(1921年)の原敬暗殺のあとと、昭和7年(1932年)の5・15事件の直後。日本きっての財政金融通として、82歳で没する{昭和11年(1936年)の2・26事件}まで大蔵大臣には7度もついた。
これは自伝。秘書官の上塚司が記録したもの。明治44年(1911年)に日本銀行総裁に57歳で就任、大蔵大臣に59歳。内閣総理大臣に2度、それも大正10年(1921年)の原敬暗殺のあとと、昭和7年(1932年)の5・15事件の直後。日本きっての財政金融通として、82歳で没する{昭和11年(1936年)の2・26事件}まで大蔵大臣には7度もついた。
どうしようもない経済的難局の時には、最後は「高橋是清に頼む」といわんばかりだ。
この自伝は、それ以前の話だ。血気盛ん、無頼の行動力と意志強き直言と交渉力が、明治初期から地球をまたいで発揮される。仙台藩の武家の養子として育ち、14歳で渡米。奴隷となったり、放蕩したり、ペルー銀山発掘の失敗、日露戦争での外債募集など、まさに波乱万丈。
昭和恐慌をモラトリアム(支払猶予措置)で、世界恐慌を金輸出禁止、積極財政などで日本経済を脱出させた彼の手腕には経世済民の意志と経済への動体視力があった。