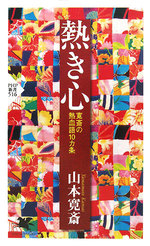 山本寛斎さんが、身体をこわして、残しておきたいと思った言葉、考え方、生き方。熱血語10ヵ条だ。
山本寛斎さんが、身体をこわして、残しておきたいと思った言葉、考え方、生き方。熱血語10ヵ条だ。
思いを、夢を、やりたい事を、ピュアにストレートに、言語、身体、行動を全部使ってぶつける「熱血語」10ヵ条だ。「外見こそが最も重要な自己表現だ」「夢を叶えるコツは、狂ったように欲しがること」「未来に前例などない。迷ったら新しいほうを選ぼう」「最後まであきらめない人に未来は開かれる」「好きなことに没頭しよう!そうすれば辛いことも苦にならない」「戦いの前に"勝つべき理由"を明確にせよ」――など。
朝5時に起床して、木々にふれ、青空にふれ、大地にふれて、細胞が目ざめて、一気に1日をスパートする。日本人が世界の舞台でド肝を抜く。今日本で最も必要なエネルギーあふれる、元気になる書。
 グリーンスパンの存在感が、司令塔の役割を担って世界経済の安定に寄与してきたことはまぎれもない事実だ。グリーンスパンがここで今回の金融危機が「100年に1度か50年に1度の事態」と言い、「危機が解決したときにあらわれてくる世界は、経済という面でみて、私たちが慣れ親しむようになってきた世界とは大きく違っているのではないか」といっていることは、今、世界の識者の枕詞のようになっている。また一方で、彼が政策金利を下げすぎたことが、今回の一因となったとする批判もある。
グリーンスパンの存在感が、司令塔の役割を担って世界経済の安定に寄与してきたことはまぎれもない事実だ。グリーンスパンがここで今回の金融危機が「100年に1度か50年に1度の事態」と言い、「危機が解決したときにあらわれてくる世界は、経済という面でみて、私たちが慣れ親しむようになってきた世界とは大きく違っているのではないか」といっていることは、今、世界の識者の枕詞のようになっている。また一方で、彼が政策金利を下げすぎたことが、今回の一因となったとする批判もある。
本書を読むと、現在を予想しながらも、より悪いシナリオとなっていることを感ずる。そのなかで、「陶酔感と恐怖心」というキーワードが出てくる。「信用と景気の拡大局面には陶酔感がゆっくり積み上がっていく」「信用と景気の循環の収縮局面は、恐怖心に動かされる」「市場は事実上、一夜にして陶酔感から恐怖心に振れ、恐怖心は陶酔感よりはるかに強い力をもち、暴落は突然に起こる」という。
だからこそ、途中の制御は難しく、まただからこそ、制御装置を市場の制度のなかに慎重に埋め込むことが必要となる。「市場の規制に反対」という基本に立つグリーンスパンは、今、どう考えているのか。
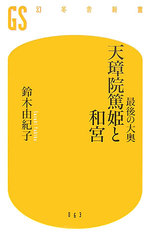 大河ドラマ「篤姫」は大人気のようだ。なぜか。
大河ドラマ「篤姫」は大人気のようだ。なぜか。
「女性が主人公」「篤姫と和宮のからみをはじめ、橋田壽賀子の"渡る世間は鬼ばかり"的な家族的世界」「歴史ものにありがちな戦闘場面がない」「しかし、歴史の激しい動きを女性の生き方のなかでかいま見る」「俳優がキラ星で、二世も話題をつくっている」「宮崎あおいが親しみやすく好感度抜群」など。私の近くではテレビ関係者など、とにかく分析するだけでも盛り上がっている。
たしかに魅かれるものがある。
幕末に、政略のために徳川将軍家に嫁いだ二人の女性、篤姫と和宮。最初は立場の違いから対立するが、二人とも短い結婚生活で夫に先立たれる。似たような運命が二人の心を通わせたか、幕末の動乱の中、篤姫と和宮はともに徳川の人間として、命がけの行動で江戸城を無血開城に導く。封建時代の中で、二人はゆるぎない信念と行動力の持ち主だったようだ。こんな生き方が、多くの支持を得て、テレビの高視聴率をはじき出しているのかもしれない。
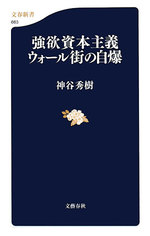 「日本もアメリカも、経済社会がバブルにまみれ、強欲と拝金主義に席捲されたときに、人の心から大事なものが失われてしまった。なんでもデジタル志向で、「0か1」しかない。その中間を配慮できない。この思考法が社会を大きく分裂させてしまった。最悪のものが、お金を基準とした『勝ち組・負け組』の分類だった」と神谷さんはいう。
「日本もアメリカも、経済社会がバブルにまみれ、強欲と拝金主義に席捲されたときに、人の心から大事なものが失われてしまった。なんでもデジタル志向で、「0か1」しかない。その中間を配慮できない。この思考法が社会を大きく分裂させてしまった。最悪のものが、お金を基準とした『勝ち組・負け組』の分類だった」と神谷さんはいう。
司馬遼太郎が亡くなる前、最後の対談を思い出す。「日本はこれからどうなりますか」という質問に「未来はない。ダメだと思う」と答えていたという記憶がある。
たしか96年の2月位の話だ。理由は「バブルによって日本人がダメになった」だった。今のアメリカをはじめとする先進諸国、そして世界。借金と消費ならず浪費社会、浪費に頼った成長政策。「借りた金で今日を愉しむ」「借りた金で投機する」「ノンリコースで借りた金は、返せなくなったら担保物権の鍵を渡せば終わり」――金融が収益の4割を占めてしまった米国、そのなかで強欲資本主義の先頭を走り続けたウォール街の自爆。
社会を構成する人間社会自体の反省と再建というのがまさに今の課題。社会の劣化、人間の劣化をどう立て直すかを問いかけている今の金融危機だ。暴走を食い止めるためにルールをどうつくるか、それは限度を知り、節度を守るという哲学的な人間の総合力が底流になくして成しうるものではない。


