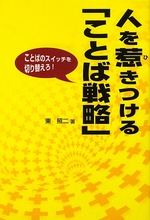水野さんがずっと言ってきた1995年以降の「強いドルは国益」の米戦略。その米モデルを「アメリカ投資銀行株式会社」と呼ぶなら、日本のモデルは「日本輸出株式会社」と呼ぶことができ、しかもそれは連結会社のように裏側ではくっついている。グリーンスパンに「100年に1度」などと"傍観的"に言われたくないと水野さんが思うのは、バブルを生み出し、ローンと消費、金融商品化等々を駆使して世界のカネを呼び込んだ米国戦略とそれに結局、協調してきた日本という構造をハッキリ見ているからだ。
水野さんがずっと言ってきた1995年以降の「強いドルは国益」の米戦略。その米モデルを「アメリカ投資銀行株式会社」と呼ぶなら、日本のモデルは「日本輸出株式会社」と呼ぶことができ、しかもそれは連結会社のように裏側ではくっついている。グリーンスパンに「100年に1度」などと"傍観的"に言われたくないと水野さんが思うのは、バブルを生み出し、ローンと消費、金融商品化等々を駆使して世界のカネを呼び込んだ米国戦略とそれに結局、協調してきた日本という構造をハッキリ見ているからだ。
しかし、このモデルは破綻し、金融にこのところ振り回される存在となった実体経済は低迷し、G7からBRICSも含めたG20の時代となり、ドル基軸から無極化への方向が始まり、世界の資本主義経済が次のステージに突入した。
この書は12月発刊だが、今再び、現時点の明確な発言を聞きたいところだ。大企業たたきとか、内需主導へ、などではなく、「日本新興国向け企業株式会社」へ、大企業向け法人税下げ、下請け垂直構造を脱して知識組替えの必要性、不安を取り除く社会保障や人材教育などを本書では示しているが、新たな時代へのスタートを急がねばならない。
 イー・アクセスの会長、イー・モバイルの会長兼CEOである千本さん。いやそれだけでなく、83年に第2電電(DDI、現KDDI)を創業、最初の民間の通信事業者の設立をしたのも千本さんだ。次々と通信革命を自ら、一人で切り拓いてきた千本さんは、モバイルブロードバンドという時代の要請にいちはやく着手し、挑戦している。
イー・アクセスの会長、イー・モバイルの会長兼CEOである千本さん。いやそれだけでなく、83年に第2電電(DDI、現KDDI)を創業、最初の民間の通信事業者の設立をしたのも千本さんだ。次々と通信革命を自ら、一人で切り拓いてきた千本さんは、モバイルブロードバンドという時代の要請にいちはやく着手し、挑戦している。
この書はベンチャーかくあるべしという評論ではない。波乱万丈、千本さんが自ら荒波に向かって突き進んでいく"わが闘争"ともいうべき挑戦者の軌跡だ。
「ベンチャーは金儲けではない。真のベンチャーとは国家と国民が必要とすることを自らリスクを取って行うことだ」と語るその姿勢と行動のなかに、人生の芯ともいうべき鍛え抜かれた哲学が生まれている。挑戦のなかに、常に「一人立つ精神」「前にひたすら進むたくましい精神力」と、その姿に共鳴する「人こそ財産・人に恵まれる人生」という人間("人の生命"の姿勢と"人と人との間"の人間学)の哲学がみなぎっている。
 二人の対談、そして、農業では「日本の食と農」(NTT出版)の神門善久氏が加わる。
二人の対談、そして、農業では「日本の食と農」(NTT出版)の神門善久氏が加わる。
「答えを求めず、『ものの見方』を身につけよ」「日本の教育は『見る目』を養おうとしない。先に正しいやり方があり、正しい文字があり、正しい発音があると思っている。これでは話が逆だ」「概念で世界を作り上げるのは楽だ。頭が固い。要するに抽象的で現実を単調に見ているだけ」「モノから考える考え方が大切。具体的なモノ、データに則って考えれば本質が見えてくる」
人類史はエネルギー争奪史――木材がエネルギーであった昔と今の石油。
温暖化対策に金をかけるな。温暖化がもたらす最大の問題――雪がなくなる、水の問題。少子化万歳。浮上するアメリカ問題、中国問題と現代文明。
平場の優良農地がなぜ耕作放棄されるのか。「困窮ではなく、贅沢ゆえの耕作放棄だ。日本の米作は完全自由化でも強い(神門氏)」など、概念のベールをはいで、モノから、データから、現実、現場から見る「見方」を語っている。
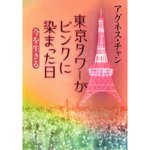 10月は「乳がん月間」、10月1日は乳がん検診の日(ピンクリボンデー)。それが表題、そして副題に「今を生きる」とある。2~3時間の睡眠時間で走り回ったアイドル時代。学業、結婚、仕事、ボランティア、家庭――その間の「アグネス論争」。そして、唾液腺腫瘍、乳がん。想像を絶する不安と家族愛、そして人民大会堂のコンサート。
10月は「乳がん月間」、10月1日は乳がん検診の日(ピンクリボンデー)。それが表題、そして副題に「今を生きる」とある。2~3時間の睡眠時間で走り回ったアイドル時代。学業、結婚、仕事、ボランティア、家庭――その間の「アグネス論争」。そして、唾液腺腫瘍、乳がん。想像を絶する不安と家族愛、そして人民大会堂のコンサート。
仕事と家庭とボランティア(社会貢献)の三本柱の生活を生き抜くアグネス・チャンさんとは、ここ3年ぐらい何度もお会いした。日中友好で、そして児童ポルノ問題で。ピュアで、自然で、現実からけっして目をそらさないで、一生懸命に、世界を舞台に強く生きている。「感謝」「有難う」「人の生命を大事に」「心の孤独な人に、病んでいる人に、優しさの輪を広げる」「命の輝きを求めて」ひたむきに生き抜こうとしているアグネス・チャンさんが生きる意味を語ってくれている。