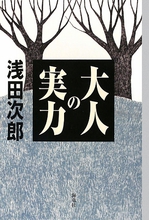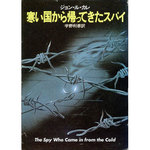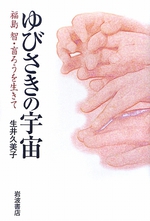 今年5月、全国の自治体で初めて、東京都に盲ろう者のための支援センターが発足した。都議会公明党が福島智さんと会って実現させたものだ。5月末、その支援センターを私は訪れ、福島さんにお会いした。
今年5月、全国の自治体で初めて、東京都に盲ろう者のための支援センターが発足した。都議会公明党が福島智さんと会って実現させたものだ。5月末、その支援センターを私は訪れ、福島さんにお会いした。
目が見えず、耳も聞こえない。その無音漆黒の世界にたった一人、地球からひきはがされ、果てしない真空の宇宙に放り出されたような、心の芯が凍りつくような魂の孤独と不安のなかで、福島さんは生き抜いている。「不便なことと不幸は違う。
障がいの有無と幸、不幸とは本来関係ない」「フランクルの愛、かけがえのない愛について」「能力は本質でなく属性だ。否定すべきは、能力の差とその人の存在の価値を連動させることだ」「私たち障がい者がなすべき"最も重要な仕事"は、生きることだ。そしてよりよく生きることだ。そして支え合うことだ」「セーフティ・ネットは安全網ではなく、落下しないようにネットを架け橋として張ることだ」「応益負担は益だから利用料を払えということだ。益を求めているのではない。
人間らしく生きる最低限の支援がほしいだけだ」