 米国発の金融危機・経済危機の原因を述べているが、最近のそうした分析の書とは全く違う。大武さんは、税のプロ中のプロであるとともに、産業界の実体・経済政策にくわしいエコノミストだが、ベトナムで日本語で複式簿記を教える学校を立ち上げるなど世界を飛び回っている。
米国発の金融危機・経済危機の原因を述べているが、最近のそうした分析の書とは全く違う。大武さんは、税のプロ中のプロであるとともに、産業界の実体・経済政策にくわしいエコノミストだが、ベトナムで日本語で複式簿記を教える学校を立ち上げるなど世界を飛び回っている。
世界の大変な時代はもう1990年代初頭から始まっている。為替レートを使った米の対日攻略に日本はさらされ、グローバル化、超高齢社会化、環境制約・資源制約の顕在化の大きな変化の渦中にある。
今後を考えればまず、日本はジャパン・クールのモノづくり大国であることをより生かしていく必要がある。そして日米協力も大切だ。米国発の金融破綻が世界に拡散したが、米国はあくまで基軸通貨国であり、アメリカドルが安定していなければ日本経済の安定も発展もない。
さらに、とくにアジアだ。アジアの人口は増え続ける。日本は人口減少社会を迎える。だからアジアとの連携・協力のなかで日本経済を活性化させることが不可欠だ。大武さんが、「日本の税理士による未来会計を活用せよ」「複式簿記をベトナムに、アジアに普及せよ」「アジア活性化のために日本語を」「日本の発展の大前提は平和であり、戦争回避に努力せよ」と行動するのは、この「大変」のなかで日本はどう生き抜くかを模索し、切り拓こうとしているからだ。
まさに、大武さんは世界の新たなグローバル・ステージのなかで、日本がどう生き抜くか。「大変」を踏まえたうえでアジアと世界の上に立ってどう頑張るかを示しているわけだ。また、企業のあり方、働き方、相続税制のあり方等に専門家として提言をしている。受け止めたい。
 堺屋太一さんの本は「油断」「団塊の世代」「峠の群像」にはじまり、ずっと読んできた。この本は今、時代の変わり目の大激震にあたり、近代工業社会から知価社会への転換を改めて語っている。物財の豊富が幸せという社会から満足が大きい主観の世界に変わったということを、本当に認識しなければダメだと繰り返し述べている。
堺屋太一さんの本は「油断」「団塊の世代」「峠の群像」にはじまり、ずっと読んできた。この本は今、時代の変わり目の大激震にあたり、近代工業社会から知価社会への転換を改めて語っている。物財の豊富が幸せという社会から満足が大きい主観の世界に変わったということを、本当に認識しなければダメだと繰り返し述べている。
1つは明治維新とは何であったか。(1)開国(2)武士の身分を廃止(3)廃藩置県(4)新貸令(5)教育制度と軍事体制――それはグローバリゼーション、公務員改革、道州制・・・などとなる。
もう1つはチンギス・ハンはなぜ世界を制覇できたか。その強さとは何か。
そうした例を引きつつ、この20年にわたって指摘し続けている知価社会に本格的に対応できる国をつくらねばならない。
 想像を絶するネットいじめの息苦しさを感じてしまう。
想像を絶するネットいじめの息苦しさを感じてしまう。
メールで友人とつながり、インターネットを活用して楽しむものが、掲示板やメールでの「相互性」や「匿名性」をもって、裏サイトなどで悪用されたりする。ネットいじめの横行だ。
ネット社会を生きる子供は疲弊している。児童買春・児童ポルノ禁止法改正に動いているが(G8でポルノ写真の単純所持を禁止していないのは日本とロシアだけ)、性的いじめなどは生涯にわたってその子どもを苦しめ続ける。
ネットいじめ問題の大本は「いじめ」そのものだ。悪いのは「いじめている側」だ。これまでのいじめ対策は被害者に「頑張れ」とか「親・教師に勇気をもって言え」といったピントはずれが多かった。加害者の側への対応こそが大切で、いじめている子には、自分が認められたいという「承認欲求」が満たされていないといういらだちがある。それを被害者にぶつけ、相手が苦しむ姿が面白い。人を傷つけないようにする心の教育、情報モラル教育が大事だし、いのちの大切さを教えること、すぐ「死ね」とか「死にたい」と書き込まないようにする教育が大切となる。
それにしても、メディアの暴力を笑いにする番組。漫才ブームというが、すぐ頭を叩いたり、「ブタ」とか「デブ」「薄毛」など軽薄な「優越型」ネタの多さは何だ。
渡辺さんは諸外国の対応も含めて、丁寧な取材によって実態を浮き彫りにし、提言している。
 「日本」再生への提言であり、改革派の一翼を担った中谷さんの話題の自戒、懺悔の書である。
「日本」再生への提言であり、改革派の一翼を担った中谷さんの話題の自戒、懺悔の書である。
読みやすい。それは心情を吐露して率直に書いているから、そしてもう一つ、私自身が「日本という国とは、日本人とは、日本の文化と文明とは」を問いかけ続け、政治の場では常に庶民や中小企業の現場から考えてきたということによると思う。グローバル資本主義はモンスターへと変貌した。そして「世界経済の不安定化」「所得や富の格差拡大」「地球環境破壊」などの負の効果をもたらした。
それを、ケインズ、サミュエルソン、クルーグマン、スティグリッツ。そしてポランニーの警告(労働、土地、貨幣そのものを取引することで市場経済はおかしくなった)、トクヴィル、カルヴァン、理念国家・宗教国家アメリカ、縄文と弥生の融合、日本文化と思想・・・・・・。人物と思想を悟りつつ、日本再生への提言を述べている。
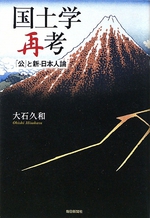 「公」と新・日本人論という副題がついている。「国土学事始め」に続く第2弾。
「公」と新・日本人論という副題がついている。「国土学事始め」に続く第2弾。
「城壁を必要とした国」と日本のように「城壁を全く必要としなかった国」とが、繰り返し、分析され、解説される。
どうしてこんなに経済も社会も世界に比して競争力を失い劣化しているのに、日本はあいまいな、不正確な、情緒的な論議しかできないのか。
国土への働きかけによって人類は今日の生存と生活を確保してきたのに、日本は公共事業悪玉論、道路やダムはムダといったひずんだ言論がまかり通るのか。どうして空港も港湾もハブが逃げているのに危機感をもたずにいられるのか。脆弱な国土である日本を治山、治水、耐震事業のなかで、まさに国土に働きかけることによって守ってきたのに、その営為がなぜ平然と無視されてしまうのか。
「文明の生態史観」「文明の環境史観」「泥の文明、砂の文明、石の文明」「縮み志向の日本人」「人生地理学」――今日まで私は多くの書と人に接し、日本と日本人と日本国土と文明と文化を考えてきたが、大石さんは、これらに真正面から正確に問いかけをしている。そして日本人の情緒主義・臨機主義・円満主義の思考癖を十分認識しつつ、新しさを尊び、喜ぶ文化、人間中心ではないエコロジカルな人間主義、他との共生など日本人のアイデンティティを世界に発信しようと訴える。同感である。

