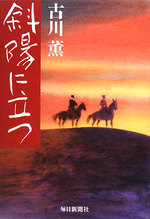
福田恆存氏は「乃木将軍と旅順攻略戦」で、「歴史家が最も自戒せねばならぬ事は、過去に対する現在の優位である。吾々は二つの道を同時に辿る事は出来ない。・・・・・・当事者はすべて博打を打ってゐたのである。丁と出るか半と出るか一寸先は闇であった。それを現在の『見える目』で裁いてはならぬ。歴史家は当事者と同じ『見えぬ目』を先ず持たねばならない」といっている。
乃木希典と児玉源太郎という双曲線となって明治を生きた二人の軍人の人生。それをたどるのが本書「斜陽に立つ」の物語だと、古川薫氏はいう。そして司馬遼太郎氏の「殉死」「坂の上の雲」でいう乃木愚将論は史実と違い、誤りであり、理不尽という。
「弾丸は回せない、旅順は肉弾でやれ」――そこに生じた悲惨な犠牲は乃木愚将論に帰すものではなく、海軍が陸軍の作戦に介入してまで旅順攻撃を急がせたことをはじめ、数々の要因がある。現代の安全地帯にいる者が、観覧席から嘲笑するがごとき言動を痛烈に批判している。
乃木希典の生と死、生い立ちと生きざまのなかに、「斜陽」「落日」などの萎れた類語が乃木詩に目立つのは、残照のなかに悵然とたたずむ自分を風景化させているのだ、と古川氏は描いている。
本書は次の言葉で結ばれている。
「憂い顔のままに乃木希典は、斜陽に立つ孤高の像を今の世に遺した。自敬に徹したこの最後のサムライにとって、世上の毀誉褒貶は無縁のざわめきでしかなかった」
そして「あとがき」で、本書の執筆について「不幸感を背負って、ナンバー2の座位を生き抜いた19世紀生まれの児玉源太郎、憂い顔で斜陽に立つ乃木希典の寡黙な生きざまへの共感である」と古川氏は述べている。
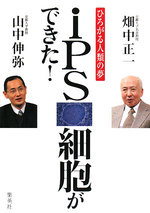
「人の皮膚細胞から、様々な細胞になれるiPS細胞ができた!」というニュースが昨年11月世界を駆け巡った。倫理的にも問題なく拒否反応も無い。再生医療に画期的な変化が予想され、心筋梗塞、糖尿病、筋ジストロフィー、大ヤケド・・・。病を持つ人にとっては夢のような細胞だと言われている。iPS細胞ができた時の様子を語るページは喜びで文字が踊っているようだ。
発表するまでの険しい道のりと、今後の可能性と課題にも言及するが、「私の研究は人の役に立っていないんじゃないかという思いが常にあり、医療の現場に役立てる研究であることが嬉しい!」と何度も繰り返す山中教授。
エアポートの売店にサイエンス雑誌があるというアメリカに比べ科学への関心が低いと言われる日本。国際間の熾烈な競争のなかで、文科省も力を入れているが、米の研究体制を「政治家の方に見てほしい」と山中教授は言っている。
 「起きるかどうかではない。いつ起こるかだ」――感染症対策の専門家はそういう。「鳥インフルエンザウイルスH5N1」。すでにヒトの世界に入り込み始めて、2003年以降、世界14カ国で380人が感染し、240人が死亡。致死率はなんと60%だ。2006年4月24日、インドネシアのスマトラ島北部のクブシンブラン村で女性の死から恐るべき事件が起きる。走り回るWTOや医師、対策班。まさに時間との戦い、どう封じ込めるかの緊迫した闘いだ。もうそうしたことが始まっている。
「起きるかどうかではない。いつ起こるかだ」――感染症対策の専門家はそういう。「鳥インフルエンザウイルスH5N1」。すでにヒトの世界に入り込み始めて、2003年以降、世界14カ国で380人が感染し、240人が死亡。致死率はなんと60%だ。2006年4月24日、インドネシアのスマトラ島北部のクブシンブラン村で女性の死から恐るべき事件が起きる。走り回るWTOや医師、対策班。まさに時間との戦い、どう封じ込めるかの緊迫した闘いだ。もうそうしたことが始まっている。
(1)抗ウイルス薬(タミフル)の大量投与
(2)国民のワクチン接種(パンデミックワクチン、プレパンデミックワクチン)
(3)学校の閉鎖
(4)感染者の社会的な隔離や強制的な旅行制限――など、大事なのはまず(2)。
医療機関から金融機関に至るまでの緊急対応。そして大量であるがゆえの治療、命の優先順位。プレパンデミックワクチンの備蓄。米国で行われている大規模な実践的演習。
日本の戦略を早く進めなければならない。
 地方が疲弊しているから、どう活性化するのか、という知恵を得る本ではない。高松さんはドイツのバイエルン州、フランケン地方の10万人都市、エアランゲンに住むジャーナリストだ。都市に統一感がある。10万人都市は田舎ではなく賑わいがある。景観はきわめて高い優先順位をもつ。文化の充実は目を見張る。静寂はきわめて重視される価値観である。環境立国・ドイツというが、それは結局、生活の質や歴史・文化を重視するという志向性が全てにあるからだ。
地方が疲弊しているから、どう活性化するのか、という知恵を得る本ではない。高松さんはドイツのバイエルン州、フランケン地方の10万人都市、エアランゲンに住むジャーナリストだ。都市に統一感がある。10万人都市は田舎ではなく賑わいがある。景観はきわめて高い優先順位をもつ。文化の充実は目を見張る。静寂はきわめて重視される価値観である。環境立国・ドイツというが、それは結局、生活の質や歴史・文化を重視するという志向性が全てにあるからだ。
自然発生というより、都市は人工空間。中央には広場がある。人はその都市の生存・生活空間のなかでどう質の高い生活を築いていくか。
「何でも揃う小さな大都市」ということ自体、これらのことと密接な関係性がある。人材も揃っている。職住近接でもある。公共財は利便性・経済効果という切り口ではなく、自らの住む生活圏の生活の質ということから考えるということだ。
森も静寂と憩いをもたらすものだからこそ重視される。
グローバリゼーションと喧騒のなか、日本人の生活の拠点をどう獲得するのか。考えること大である。それにしても日本社会に大きな影響をもつメディアやテレビはドイツではどうなっているのだろうか。


