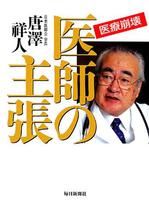昭和的価値観が20項目列記されている。その昭和的価値観に、皆とらわているが、時代は変わっており、若者に平成的価値観をもって生きよと呼びかけている。そのキーワードは多様化。
昭和的価値観が20項目列記されている。その昭和的価値観に、皆とらわているが、時代は変わっており、若者に平成的価値観をもって生きよと呼びかけている。そのキーワードは多様化。
人の生き方は違う。競争してバリバリ働くことを望む人もおり、かたやボチボチ働いて、そこそこの暮らしを楽しむ人もよし。しかし、少なくとも、現在の日本社会が、若者にとって苦しいものとなっている(それは前著の「若者はなぜ3年で辞めるのか?」で明らか)ことは事実だ。
その雇用の最大の問題は、非正規雇用などが、既得権益をもつ先行世代によって、企業の生き残りということから若者などにシワ寄せされるということにある。しかもそれは野党などのうらみ節、単純な切り文ではなく、新たな成長を生むシステムへどう切り替えていくかという視点に立てと城さんはいう。
学歴偏重、大企業、終身雇用の一本線の昭和的価値から多様な生き方の平成的価値観へと社会が変わっていることをしっかり見すえ、21世紀の新しい日本の成長と成熟と改革を成しとげることをスタートせよと城さんは指摘している。
現状維持では日本の、そして若者の、未来はない。
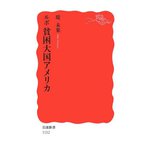 新自由主義政策、経済重視型の民主主義、市場原理主義。
新自由主義政策、経済重視型の民主主義、市場原理主義。
こうした米国の政策が、中流を急速度に貧困層へ転落させ、貧困層を最貧困層へ突き落としていく。
それらを、「貧困が肥満国民を生む」「民営化の極端な進展が、FEMAまでもつぶし(格下げ)、ハリケーン・カトリーナのニューオリンズの悲劇を生む」
「学校の民営化(チャータースクール)は立派な先進モデルではない」「病気になれば、たちまち貧困層に転落する世界一高い医療費、そして日帰り出産妊婦や医療過誤の多発」「戦争が派遣ビジネスとなっており、日本人も米州兵となっていること」「その徴兵自体が貧困層や貧困高校生、カード地獄に陥った学生たちをターゲットにしていること」などのルポを通じて明らかにしている。
読む時にずっと、日本のことを考えながら読んだ。
 日本と暮らして45年、この本には日本を愛し、日本を心配してくれているカーティス先生の温かい心があふれている。ごく自然に、そして良識をもって、現場から、そして、日本を米や世界から客観視しているカーティス先生は、95年から2015年までが日本を変える最重要の「20年のデケード」であり、今の日本は自信を失いすぎている。日本文化には粘り強さと日本人の順応性と対応能力があり、ダイナミズムがあるんだから、良い方向にもっていけるとエールを送ってくれている。
日本と暮らして45年、この本には日本を愛し、日本を心配してくれているカーティス先生の温かい心があふれている。ごく自然に、そして良識をもって、現場から、そして、日本を米や世界から客観視しているカーティス先生は、95年から2015年までが日本を変える最重要の「20年のデケード」であり、今の日本は自信を失いすぎている。日本文化には粘り強さと日本人の順応性と対応能力があり、ダイナミズムがあるんだから、良い方向にもっていけるとエールを送ってくれている。
そのためには「有権者を説得する『説得する政治』が大事」「非タテ社会の様相が強まり、自慢したり、カネを重視したりする人が多くなり、謙虚な美徳がこわれ始めている」「平等社会から競争社会、実力主義社会となる大きな変化があり、公平の価値が重要となる」「しかし、日本はまだ勤勉であり、前向きという強さがある」「日本社会は今も美しい」「今、日本政治のなかにあった政治家と官僚、官邸と自民党、自民党と野党の間の"非公式な調整メカニズム"がこわれてきた。
働かなくなっている」「マナーからルールへ」「政策通より政治通に」――公明党についても、そうしたことをチェックし、バランスをとり、政策をうながす役割を期待していると感じた。
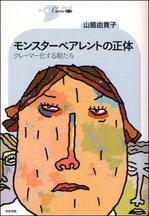 クレーマー化する親たちは、余裕がなく、いっぱいいっぱいで、不満もストレスも不安もたまりにたまっている。
クレーマー化する親たちは、余裕がなく、いっぱいいっぱいで、不満もストレスも不安もたまりにたまっている。
そして不幸を嘆き、少しでも幸せそうな人に鬱積したものをぶちまけたいというマグマがたまっている。しかも、コミュニケーションの減少と不全があり、この国の人間関係は希薄化しているうえに、IT、携帯が仮想空間に拍車をかけている。そのうえ、教師(それは議員も役人も医者も)は、サービスするのが当然という店員扱いをされるという社会の大きな変化がある。
お医者様でも先生でもなく、保護者様、患者様意識はそうしたことからでき上がっている。山脇さんの「教室の悪魔」は攻撃的だったが、この本もまた見事に実態を見せてくれ、解決策を示してくれている。
「幸せになること、自分の力で幸せになるのだ」「人生とは勝ち負けなのだろうか。幸せか幸せではないかではないのだろうか」との締めくくりの言葉はズシッと心に響く。