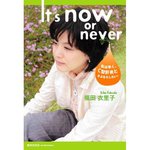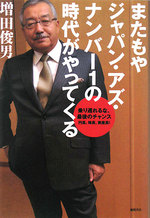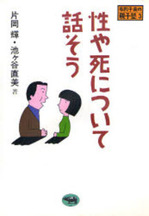 現在、東京家政大学学長の片岡先生の20年前の著作。池ヶ谷直美さんとの対談と各テーマについて語った本だ。「グリーン、グリーン」や「飛んでったバナナ」などの作詞もしている片岡先生は、子どもの教育は勿論、地域との交流、学長の立場など活動は幅広い。
現在、東京家政大学学長の片岡先生の20年前の著作。池ヶ谷直美さんとの対談と各テーマについて語った本だ。「グリーン、グリーン」や「飛んでったバナナ」などの作詞もしている片岡先生は、子どもの教育は勿論、地域との交流、学長の立場など活動は幅広い。
しかし、背景には、「性と死」「生と死」という哲学があり、深い。そしてやさしさ、温かさがある。先日、対談をさせていただいた。「性や死をどのように子どもたちに伝えるか」「現代の社会は死をかくし、悪をかくす。
しかし、子ども達は、"こわい"ものに魅かれ、見たい欲求がある。その全てをいかにして見せていくか。その丁寧な発達過程における学習を助ける忍耐と許容が親には必要だ」「"飛んでったバナナ"も船長さんに最後食べられてしまう。ハッピーエンドではない。そうした物語性と哲学性を入れた」「民話、伝統文化、そうしたなかに人間の智慧がある」「"いないいないばー""鬼ごっこ""かくれんぼ"などの遊びにも智慧がある」――など、蓄積された言葉に感動がヤマほどあった。本書はその思想・哲学的源流だ。