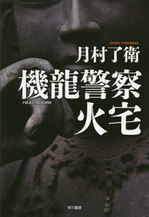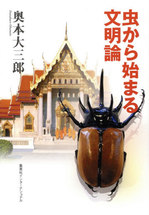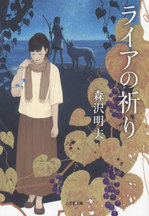月村了衛さんの短篇集。火宅、焼相、輪廻、済度、雪娘、沙弥、勤行、化生が収録されている。警視庁に新設された特捜部SIPDは、「龍機兵」と呼ばれる最新鋭の装備を持つ突入要員の他に、刑事部、公安部などの既存の部署に属さない専従捜査員を擁している。トップダウンで創設されたがゆえに他からの反発もある。
「悪の顕われたる者は禍い浅くして、隠れたる者は禍い深し」(洪自誠「菜根譚」)、そして短篇の表題が仏教用語にあるように、対象とする犯罪は深山幽谷を思わす深い闇の中にある。
「よく聞き、よく見ろ。捜査はそれに尽きるんだ。どんなときでも耳と目をよく使え。頭は放っておいても耳と目についてくる」――由起谷志郎主任が元上司に教えられた捜査の基本。「機龍警察」の登場人物の過去や至る過程にもふれている。ハードボイルド警察小説。
驚嘆すべき本だ。きわめて易しく、目の前がパッと開ける面白い本だが、その思考は、虫の世界から世界各地へ及び、日本の文明から世界の文明へ、日本文化から欧米文化へ及び、微小の生命空間は宇宙生命空間へと広がる。
私も思えば子供の頃、春はつくしんぼを採り、野イチゴを摘み、夏休みは昆虫採集、川で魚をとった。近所の仲間といつも広場で遊んだ。生活は季節のなかに、自然とともにあった。奥本さんは、それが大事なのだ。日本人はそうして小さなものを細かく見る眼、いわば接写レンズの眼を磨いてきたのだという。
「第一部 虫の世界」「第二部 人の世界」を通じ、次から次へと風土と人間と文化(あるいは宗教)が開示され、展開する。ヴェルレーヌ作の詩「落葉」(上田敏訳)について、穏やかで晴天が多く、そぞろに寂しくもある日本の秋と、フランスの厳しい冬を前にしたつかの間の重苦しい凄絶ともいえる秋の違いを示す。虫や自然、詩や絵画を例示しつつ、「日本に風景画はあったのか」「ルイ・ヴィトンはなぜ日本でよく売れるか」などで結ぶ。面白くて心が躍った。
13,000年前から2300年前くらいの1万年以上も続いた縄文時代――。きれいな水と空気、大地から実をとり、狩りをする。食べ物も豊富にあって、天変地異が起こらず、他人と仲良く暮らすことを願った縄文人。人は、自然と対決では勿論なく、共生というよりも、自然に抱かれて生きてきたようだ。ゆったりとした時空のなかで、人は自然の声を聞き、人の心に敏感。本書には「泣く」「祈る」「人と自然との交流」が、文明の夾雑物を一切排除して描かれる。全ての過剰を除去したシンプル、原点、原風景の心持良さだ。
ライアの"ラ"は「五」を意味する。天・地・火・水・神。この世の全てを表わす。"イ"は「朗らか」、"ア"は「結ばれる」――。縄文時代のライアと、現代の大森桃子が結びついて主人公となる。縄文の魅力とロマンが感動的に流れ出る。
森沢明夫さんの「津軽百年食堂」「青森ドロップキッカーズ」に続く青森三部作。鈴木杏樹主演で映画化され、近く公開される。楽しみだ。

全盛を誇った日本マクドナルドが苦戦していることを分析・レポートしている。マクドナルドを日本化しようとした藤田田氏(1971年~2003年)と、米国式経営を志向した原田泳幸氏の経営(2004年)だが、不思議にもほぼ同じような結果、一致をもたらしている――それを分析している。
1993年、バブル崩壊後の消費低迷で売り上げが急減したことに対し、ディスカウント路線と店舗拡大戦略で対応した藤田氏。ブランドイメージが低下したところにBSE問題(2001年)が追い討ちをかけた。米国式経営を持ち込み新商品をヒットさせた原田氏だが、商品の値頃感の失墜やほかの外食チェーンやコンビニに顧客を奪われていく。マクドナルドの経営理念(QSC+V)(品質Q、サービスS、清潔度C+お値打ち感V)、サービスのトライアングル(企業・従業員・顧客の満足、感動と満足の三角形)は現場の人間の努力があって成立するものだが、それが崩れてきた。また、イノベーションの不足もめだつと指摘する。
欧米人が19世紀から20世紀にかけて発明した最強の3つのビジネスモデル。百貨店、食品スーパー、FCシステムはいずれも、苦戦を強いられている。変化激しい社会、構造的な変化のなかで、定見を保持、鍛えつつ、短期的収益だけにとらわれない経営は至難のことだと思われるが、あらゆる組織が問われていることだ。真正面から問いかけられた思いだ。
21世紀の全体主義――問題意識は同じだ。「思考停止」が「凡庸」な人々を生み出し、巨大な悪魔「全体主義」を生む。1951年、ハンナ・アーレントの「全体主義の起原」は「反ユダヤ主義」「帝国主義」「全体主義」の三部から成る。そして大衆の出現なくして全体主義は成立することはなかったと指摘する。フランクフルト学派、ホイジンガ、フロム、オルテガ等々、私の20代は大衆社会化状況のなかで全体の中への個の埋没現象、ファシズム論を学び、書き、語ったが、今はない。事態は逆にそこまで進んでいるといってよい。
藤井さんは、21世紀の「凡庸」という大罪、思考停止の病理を具体的に示す。「いじめ」「リセット願望」「俗情に結びつく構造改革」「米経済界を席巻した新自由主義」「グローバリズム全体主義」「大衆迎合的プロパガンダの横行」「全体主義的テロル」・・・・・・。そして、人間は人間である以上、思考停止してはならない責務があるという。