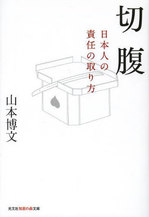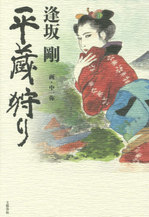江戸時代特有でもある「切腹」は、「武士の身分的矜持」と、それを支える「主君の絶対性」による。「殿中刃傷事件――大石内蔵助ら46人の切腹など」「宝暦木曽川治水工事 薩摩藩・平田靱負の切腹」「刑罰としての切腹」「御家騒動と切腹」など、具体的実例をあげながら、日本のいわゆる"武士道"といわれるものと、江戸時代を浮き彫りにする。
「武士は失敗があれば腹を切るものという観念があったので、不祥事があれば進んで切腹する者もあり、上から強要された場合でも潔く腹を切った。個々の武士の倫理観は日本人の責任感の強さを示すものとして高く評価できる。しかし、上に立つ者がその倫理観を利用して、自らの責任を逃れようとした事例が目立つ。現在でもそうした傾向はあるが・・・・・・」「江戸時代、切腹に追い込まれた武士を見ていると、本当に悪い事をしている者はそれほど多くない」という。「葉隠」の冒頭「武士道と云(いふ)は死ぬ事と見付けたり」とは、「常住死身」の覚悟、心構えを述べたものだと指摘している。
いわゆる"詰め腹"――現代社会の責任のとり方を再度考えさせてくれる。
農山村の集落は基本的には強靭で強い持続性をもっている。「地方消滅などといわれるが、現実には「ここに生きる」意志と努力は強く深い。しかし、他方で集落には「臨界点」もあり、安易な"地方消滅論"はそれを加速させると警鐘を鳴らす。
小田切さんは現場を歩きに歩き、その強さ、靭さ、意欲、懸命さ、若者などの田園回帰などの変化を凝視する。そして示された地域づくりへの挑戦は、過疎化・超高齢化の難問を突破するカギとなり、その体系を明らかにする。力づけられる。
さらにそこにとどまらない。都市・農村共生社会の方向性を提起する。「成長路線を掲げ、"農村たたみ"を進めながら、グローバリゼーションにふさわしい"世界都市TOKYO"を中心とする社会を形成するのか。そうではなく、国内戦略地域(食料、エネルギー、水、森林等)である農山村を低密度居住地域として位置づけ、再生を図りながら、国民の田園回帰を促進しつつ、どの地域も個性を持つ都市・農村共生社会を構築するか。こうした分かれ道が私たちの目の前にある」とする。あの東京オリンピックから50年、「これまでの50年、これからの50年」という視野での国民的議論が、いま必要である」という。本当にそう思う。
「出生前診断、生殖医療、生みの親・育ての親」と副題にある。共同通信社の連載記事の単行本化だが、「子どもを産み、育てることの意味」を現場から問いかける。晩婚化、出産年齢の高齢化、少子化社会、医療技術の飛躍的進歩、そのなかでの生命倫理、情報量の多いセンシティブ社会、社会的養護の子どもの増加、支える制度の不備・・・・・・。今、国内の体外受精で生まれた赤ちゃんの累計30万人(12年には約3万8千人)。
こうしたなかで、苦しみ、悩み、もがき、決断し、乗り越える当事者の言葉は、言葉をはるかに越えている。「子どもを産み、育てるとは」「親子とは」「親になるとは」「子になるとは」「生まれた人たちの出自を知る権利とは」「生みの親が育てられない子どもをどう育てるか」――。目の前のきわめて重い現実を突き付けている。
「その顔を、いつも、太陽のほうに向けていなさい。あなたは、影を見る必要などない人だから」(ヘレン・ケラー)――。
ヘレン・ケラーとアン・サリバンの物語を、明治時代の青森に移し変え、弱視をかかえた去場安(さりばあん)と三重苦の介良(けら)れんの物語として描く。それにれんの初めての幼な友だちとなる盲目の津軽三味線・人間国宝となる狼野キワが加わる。何とも言えない感動が広がり、涙した。
原初的な感覚――生きるということ、人間に備わった無限の可能性、生の肯定から噴出する愛の力、最初に教えた「祈り」、差し込む光、生きる希望・・・・・・。見えざる世界を知り、感ずるところに人生が始まり、そこを開示悟入するには師弟がいる。思考が垂直に心に迫ってくる。