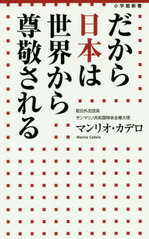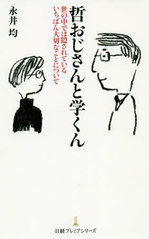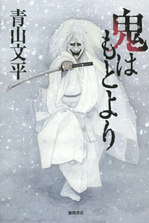「公衆衛生学から見た不況対策」という副題がついている。著者は公衆衛生学・政治社会学のオックスフォード大学教授と同大学の疫学者。
テーマとしているのは不況下において、財政緊縮策か財政刺激策のどちらがいいか。その選択はどのような影響を健康に及ぼすか、ということだ。それを膨大な実証研究によって示している。
1930年代の米国のニューディール政策からソ連崩壊と市場経済移行後のロシアとベラルーシ、さらに昨今のリーマンショック後のアイスランドとギリシャ、そしてイギリスのキャメロン政権やオバマ政権の対応等を検証する。
結論は「不況下での緊縮財政は景気にも健康にも有害」ということだ。「不況時には財政赤字と債務増加の悪循環を招くから緊縮財政を」というエコノミストやIMFのいう通りにして、公共住宅予算や医療費を削減、失業対策費などの削減を行った国は、社会は混乱、病気や自殺も増える。逆にそれを保持する努力をして社会政策を拡充した国は、健康も社会も経済も財政も回復する、としている。
不況下での政策決定は「緊縮政策から距離を置き、もっと健康的なボディ・エコノミックを目指すべきだ」という。そしてその柱とすべきは「有害な方法は決してとらない」「人々を職場に戻す」「公衆衛生に投資する」の3つだと指摘する。「どの社会でも、最も大事な資源はその構成員、つまり人間である。したがって健康への投資は、好況時においては賢い選択であり、不況時には緊急かつ不可欠な選択となる」と結んでいる。
サンマリノ共和国特命全権大使のマンリオ・カデロ氏は、駐日大使の代表である「駐日外交団長」の重責を務める。1975年に来日して約40年、日本の文化を外国人の目から分析。「なぜ日本人は日本の魅力を知らないのか」「日本がいかに素晴らしい伝統、文化、精神性を持つ、世界から憧憬の眼差しを向けられていることを日本人に自覚してほしい」「日本は戦後の荒廃の中から不死鳥のごとく蘇り、世界のトップに比肩するまでに駆け上がった。しかも、近隣のアジア諸国を様々な方法で支援してきた」「日本人は、礼儀正しく、環境に優しく、平和的な民族だ。きれい好きで周囲に迷惑をかけない、慎ましい国民だ」などを、さまざまな例を示して語る。
冒頭と第4章に16世紀後半、九州のキリシタン大名がローマに派遣した伊東マンショらの「天正遣欧少年使節」が紹介される。時は「大航海時代」。長崎の港を出港したのが天正10年2月20日、まさに本能寺の変のあった年だ。ルネッサンス文化と遭遇し、羅針盤、火薬、印刷機の発明発見に立ち会い、地図や航海図、地球儀、測量機械、時計、楽器、建築、美術を伝え、「コロンブスやマルコ・ポーロよりも凄い大偉業だ」という。しかも、伊東マンショたちのみならず、伊達政宗が主宰した「支倉常長らの慶長遣欧使節団」や豊後のペトロ・カスイ・岐部らの勇敢・強さへの感動を語る。
表題からすると子どもに哲学を語るように思われるが、解説書などではない。哲学そのものを真正面から示す哲学書だ。
「本当の重要な問題は現在諸科学が扱っているような問題ではない。例えば、一回しかないこの人生とはそもそも何であり、それをどのように生きるべきなのか、という問題こそ重要だろう。科学はそれに答えず、宗教がそれに答えるが、残念ながら宗教の主張することは嘘(根拠なき独断、作り話)だ」「生の苦しみを無くし生に意味を与えるために作り出されたその種の作り話を、どんな種類のものであれ一切認めないというのが、宗教と対立する側面での哲学の根本前提なのだ(哲学は、祈りを拒否する祈りだ)」――。宗教と科学のみならず、宗教との違いを述べる。「常識や教義によって独断的に答えたくなるようなところで、どこまでも論理的に、理詰めに考えていくことが最も価値ある行為であるという信仰」、それが哲学だという。通俗的思考に堕すのではない、哲学に固有の議論の仕方を随伴して示してくれる。
「君の人生は一回性の、他と比較不可能な、無理由になぜか存在しているだけのもので、それが何であるかは決して分からない何かなのだから、他とも比較可能な意味での幸福な人生など求めたりしたら、台無しになってしまう。・・・・・・人生は、本質的に空しく、根本的にその意味が分からないという意味で無意味なものだからだ。それが本質なのだから、それを味わい尽くしたほうが、生まれて生きた甲斐があるというものではないか」――。世界、生命、実存の究極に妥協なく迫る哲学の深淵にふれさせてもらった。
槍働きが生きていた慶長から150年が経った宝暦の、最大の敵は貧しさだ。その敵と戦いうるのは、死と寄り添う武家しかありえない。己の死に場処は御馬廻りではなく、藩札掛にあると信じた――。
カネも気力もなくなった東北の極貧の小藩の経済の立て直しに挑む家老・梶原清明と、それを助ける藩札万指南の奥脇抄一郎。鬼となることを覚悟する清明。
「己の軀を死の淵に投げ出すことで清明は鬼になる。だから常に、一人でいなければならない。(護衛に囲まれていては、清明は鬼になれないのだ)この男は執政に就いてからずっと、死と生の際を歩み続けている」「誰よりも鬼には向かぬ者が、誰よりも厳然と鬼をやっている」「自分の父に死を命じ、多くの藩士の禄を剥ぎ取り、そして国の礎である百姓の血を流させた」・・・・・・。
鬼となって極貧の国を救う――。覚悟、命懸けで初めて事は成ずる。命に迫る素晴らしい直木賞候補作。同じ直木賞候補作に万城目学氏の「悟浄出立」があるが、これも「悟浄出立」「父司馬遷」など読みごたえがある。
パリ経済学校教授のトマ・ピケティ氏の「21世紀の資本」が、世界的なベストセラーになっている。これを「60分でわかる『21世紀の資本』のポイント」として、池田信夫さんが整理してくれている。
所得格差の拡大は重要課題だが、経済成長には一定の格差は不可避の部分があり、ピケティは「成長の持続にはインセンティブが必要で格差も生まれる」「過去200年の成長と富の歴史を見ると、資本の収益は一国の成長率を上回る。労働収入より資産からの収入が伸びる」「資本収益率rが成長率gを上回り、今後もその傾向が続く(資本主義の根本矛盾r>gに集約)」――。池田さんは、「ピケティは"資本"を"資産"と同じ意味に使い、賃金以外のすべての所得を"資本所得"としている」という。
格差拡大、中間層の脱落は世界的な問題だ。しかし、先進国は所得格差が拡大しているが、世界全体では新興国の工業化で縮小している。またコンピュータなどテクノロジーの変化が格差拡大の要因に間違いなくなっている。ピケティは「グローバルな累進資本課税と、世界の政府による金融情報の共有」「中間層の労働収入への課税を減らして、高所得者に対する資産課税の拡大」などを提案するが、見通しは暗い。「日本の格差は、米のように上位1%と残り99%の格差ではなく、正社員と非正社員の格差」(池田)だ。グローバル化のなかで、各国がそれぞれどう取り組むか。池田さんの解説はありがたい。