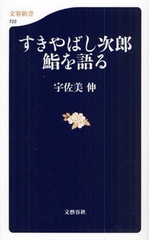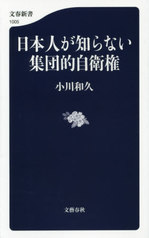正直、こんな丹念に、精魂込めた、心の行き届いた達人・凄腕の職人技の鮨を食べてみたい。そう思った。
小野二郎さん。生まれは大正14年(1925年)、静岡県の佐久間村。7歳になって間もなくの正月に、親元を離れて二俣町の割烹旅館「福田屋」へ奉公に出る。休みは元日と盆の2日のみ。隣町まで三輪の自転車をこいで出張料理までした。16歳で横浜の軍需工場に徴用され、20歳で豊橋の工兵隊。26歳で東京・京橋の鮨店「与志乃」へ弟子入り・・・・・・。40歳で「すきやばし次郎」を開業する。
生半可ではない苦労をしている。理不尽なことも山ほどある。しかし、それを生命力と根性で平然(のように見える)と、真っすぐにやりとげている。辛いといわない。常に全力、手を抜かない。そして今も全力、常に現役。「なんでも十年はしがみつかなきゃ、物事の本質なんてつかめっこない」「ワタシは7歳から働き詰めに働いて、それをちっとも辛いとも苦しいとも悲しいとも思わず普通にやって来た」――。
宇佐美さんは「現代とは職人不在の時代だ。職人とは、いついかなる場合でも同じものを同じレベルでこしらえる、あるいは表現する腕の確かさだ」「そのレベルをどこまで高みに引き上げられるかが職人の力量であり、腕の冴えだ。二郎さんは、まさに凄腕の職人である」という。
日本を取り巻く安全保障環境が変わるなかで、隙間のない安保体制をどう整備するか――これがテーマとなり、2014年7月1日の閣議決定が行われた。小川和久さんは「閣議決定は安定した仕上がりとなった。公明党が『平和』という立脚的を外さず、憲法との規範性、政府解釈との論理的整合性などを厳格に問い続けてきた結果だ」とインタビューでも発言している。
本書は、そもそも集団的自衛権とはいかなるものか。世界ではどう考えているか。実態はどうか。日本の政治家、官僚、マスコミ世論にいかに誤解が多いか、などに触れている。そして、小川さんは集団的自衛権に限らず、日本の議論は「賛成か反対か?」から始められる傾向があるが、集団的自衛権を考える上で押えるべきポイントは(1)「そもそも国家の平和と安全をどう確保するのか」を考えること(2)日本の防衛力の現状を直視すること――の2点だ、と指摘する。安全保障のスペシャリストが、解説してくれる。
「地方創生」を考える時に大切なのは、たんなるアイデア勝負ではなく、構造的な視点を持つことだ。人口減少、超高齢社会、大地震や大災害の切迫性、世界の都市間競争の激化、ICTなどの激変・・・・・・。こうしたなかで、我が市は我がまちはどう生き抜くか。コンパクト+ネットワーク、都市間連携による対流促進型の国土形成というのが、昨年7月にまとめた国土交通省の「国土のグランドデザイン2050」だ。もう1つ大切なことがある。それはイデオロギーではなく、冷静なデータ、数字に基づくことだ。
本書はデータ、数字に基づいている。全国を俯瞰し、歴史的な時間軸を物差しとして、いかに市町村に違いがあるか、浮沈を繰り返しているかを示している。大変参考になる。「地方消滅の虚実」「極端化する地域」「人口が減ると何が問題なのか」「新潟県に見る地域社会の現実」「地方再生は本当に可能か」「東京一人勝ちは是正すべきか」などを検証し、提言を行っている。
「他人を攻撃せずにはいられない人」に続いての著作。誰でも「プライドが高くて迷惑な人」になりうる。「かつては、家庭、学校、社会の中で、自己愛的イメージを徐々に断念させて、現実の自分を受け入れさせる、つまり"身の程を知る"ようにさせるシステムが働いていた。・・・・・・ところが、いまやそれが機能しなくなりつつある」「結局のところ、"経験によって強化された全能感"もしくは"対象リビドーの満足"を大人になってから持てるように、経験を積み重ねたり、良好な人間関係を築いたりすることができるかどうかにつきる。・・・・・・今いる場所で、地道な努力を続けて自然に認められるようになるのが、"プライドが高くて迷惑な人"にならないための最善の方法なのである」という。
現状を受け容れるには、時間も経験もいる。「暴走○○」などとよく言われるストレス社会・・・・・・。仏法では「諦めるは、諦観(明らかに観る)」と説くが、これも相当の修行がいる。
「深代惇郎と新聞の時代」と副題にある。「天声人語」執筆者の伝説のコラムニスト・深代惇郎を描くとともに、その仲間たち、先輩・後輩のなかに横溢するジャーナリストの魂を描き出している。力ある言葉の紡ぎ手は、心のなかにどれだけの蓄えをもっているかによることを感じさせる。
「深代惇郎にあった特徴のひとつは目線の低さである。権力や権威というものに伏する志向はまるでなかったし、地位や肩書きというもので人を見ることもなかった」「深代はファナティックなものを嫌い、排した。均衡を測ることにおいて精巧なセンサーを体内に宿していた」「深代は、モノを至上とする"進歩史観"への深刻な懐疑主義者であった」「リベラル、柔らかい視線、バランス感覚、正義感、博学多識、ウィット・・・・・・。深い眼差しをもったヒューマニスト像が浮かんでくる」「人と会うこと、本を読むこと、深く考察すること・・・・・・。聞き、話し、感じる。それを文に生かす」「世の中に名文家と呼ばれる人は幾人もいた・・・・・・(深代は)その背後に人生論的なフィロソフィーがあった。人間のもつ深い情感というか、存在の哀しみというのか、天人にもその種のものがどこかに込められていた」・・・・・・。また天声人語を継いだ辰濃和男について「彼は常に弱者、恵まれない人、運の悪い人、死者に温かい眼をむける。おごりたかぶった権力者が嫌いで、この道一筋、地道に、黙々とがんばる人たちに声援を送る」という松山幸雄の言葉も付け加えられている。
「天声人語」は「天に声あり、人をして語らしむ」だ。深代惇郎は自ら「この欄を、人を導く『天の声』であるべしといわれる方がいるが本意ではない。民の声を天の声とせよ、というのが先人の心であったが、その至らざるの嘆きはつきない」と書いている。私がよく使う「民の欲する所 天必ず是れに従う」という言葉に通じよう。
それにしても、そうした心の蓄えから発せられた言葉。三島由紀夫の割腹自殺、田中内閣を怒らせた"架空閣議"、「なんという残酷な社会だろう。親に『謝罪のことば』をいわせ、カメラの前で頭を下げさせる・・・・・・」という痛烈なマスコミ批判・・・・・・。深代惇郎が投げたのは常に選び抜かれた直球だったと思う。