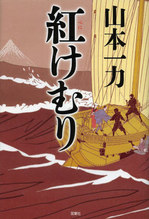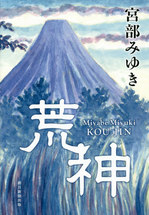師父とは武智鉄二。「私の前に立ちはだかった相手は武智鉄二という、変わりすぎるほど変わった人物だった。・・・・・・通りいっぺんの道徳や、権威や、規範や、体制を蹴散らしながら歩き続けたこの人物を、私は一生の師と仰いだ」「武智師と私を結びつけたのは歌舞伎を主とした日本の伝統文化だった」――。
「『あんたはそうやって人に余計な気ィばっかりつかっているから疲れるんだっ』 文字通り雷電に打たれたごとく全身が硬直して棒立ちとなり、私は真っ赤に熾った師の顔を呆然と見ていた。・・・・・・そして本気の怒りは、長い年月をかけて私の人格をつるんと覆っていた硬質の膜のようなものを、みごとに突き破ったのである」――。まさに自己そのものをぶっ壊してくれるのが師だと思う。
武智鉄二、木下順二、中村扇雀。松井さんはこの3人をはじめとして、多くの人に恵まれ、歌舞伎などの芸術の世界でもまれにもまれ、格闘してきたことを、静かに語り続けている。師弟愛に生きるということは中道を歩むということだ。だから格闘しても根本的には、迷いがない。私とは全く異次元の話に圧倒されるが、武智鉄二の父・正次郎が京大土木工学科の先輩であったり、芸能好きのゆえの接点も時折り、交差する。
「武智鉄二との出会いをひと口で締めくくるのは難しいが、世間を相手に戦い続けてきた人は、他人様にどう思われようが、自分の殻を打ち破って全開で生きることの必要を私に説いたのだった」――師父の遺言だ。
森羅万象の現象を如実知見するのは、宗教・哲学の究極だが、まさにその生命・世界を科学によって迫り、解明する。世界はリズムの動的世界だ。胸の鼓動、呼吸、体内時計、歩行、鳥のはばたき、ホタルの明滅、虫の鳴き声、時計の刻みと音、バイオリンの弦の震えと音、季節の移り変わり、潮の干満、昼夜のサイクル、天空の動き・・・・・・。命あるものも無いものも、リズムがある。そして、リズムとリズムが出会う。そこに、不思議な歩調を合わせるリズムが刻まれる。それが「同期現象」「シンクロ現象」であり、「引きこみ」が起きる。
学生時代、耐震工学を専攻し、「地盤と構造物」全体の力と変位が比例しない「非線形振動(震動)論」を研究した。本書はとにかく幅広く、まさに森羅万象の諸現象を「身辺に見る同期」「集団同期」「生理現象と同期」「自律分散システムと同期」などで分析してくれる。
「ミレニアム・ブリッジの騒動(歩行の同期)」「電力ネットワーク」「結合振動子系としての交通信号機ネットワーク」など、現在、関わっている問題も開示してくれている。
冒頭の「そう、これは個人的な復讐ではない・・・・・・むしろ善意の告発というべきだ・・・・・・カタストロフィを引き起こすには二つの条件が必要だ・・・・・・ひとつは対象の本質に精通していること・・・・・・いまひとつは現象を再現する手段があること・・・・・・私は今、その両方を手にしている」――。読み終えればここに全てがあることがわかる。
防衛省技術研究本部が開発し、四星工業が設計、製造したTF-1が、侵入機にスクランブルをかけている途中、墜落する。それも2度、そして3度とそれぞれ別の要因で墜落、あるいは危機にさらされる。当初、パイロットの操縦ミスとされたことに疑問をもった四星工業の空力制御班主任・永田昌彦、そしてその部下の元気で探究心旺盛な女性・沢本由佳(主人公)。四星を去った永田の同期・倉崎、元自衛隊員・山岸光昭、そして自衛隊の後藤、岩谷、井口、事故当事者の波江一尉・・・・・・。真相に迫るこれらの人の連携、技術的知見は現場感覚もあって、臨場感、緊迫感が横溢する。面白い。本当に悪い奴は犯罪者となることを免れるようだ。
航空機の専門家でなければ到底書けない作品。興味深かった。第21回松本清張賞受賞作品。